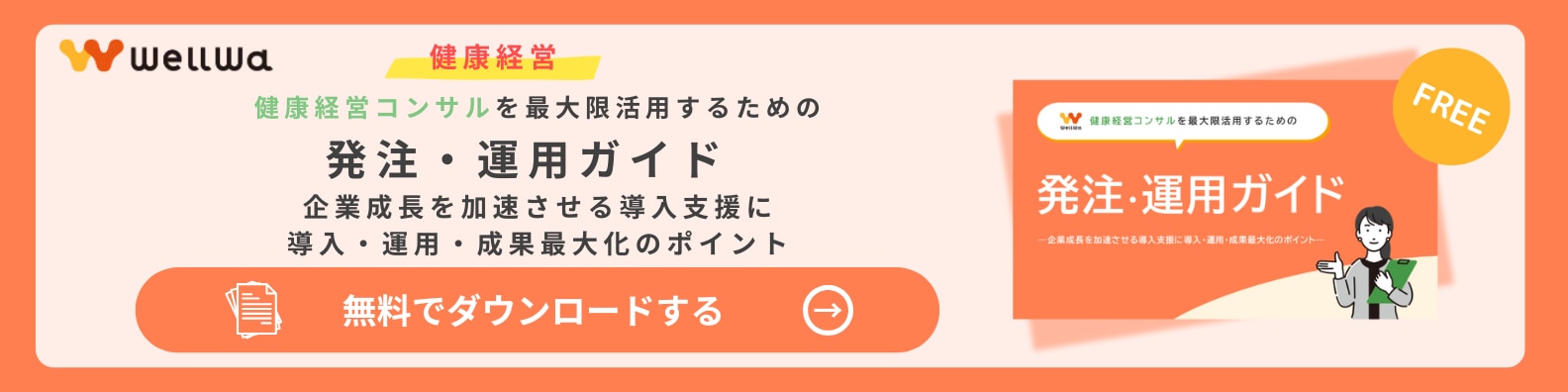職場の空気が変わる!コミュニケーション活性化の取り組み改善ポイントとは
職場の人間関係に「なんとなく壁を感じる」といった声を耳にすることはありませんか?
コロナ禍以降、リモートワークの普及や働き方の多様化により、以前のような自然な会話や雑談が減少し、コミュニケーション不全を訴える企業が増えています。職場でのコミュニケーションは、単なる円滑な業務遂行のためだけでなく、従業員のメンタルヘルスや生産性、エンゲージメントにも直結する重要な要素です。
本記事では、企業の健康経営推進担当者や福利厚生担当者に向けて、職場のコミュニケーション改善のポイントと具体的な取り組みをご紹介します。
目次[非表示]
なぜ職場のコミュニケーションが課題になるのか?
コロナ以降で変わった職場の人間関係
コロナ禍をきっかけに急速に広がったリモートワークや時差出勤、会議のオンライン化は、感染症対策として一定の成果を上げましたが、その裏側で職場のつながりが希薄化する副作用も生んでいます。
- 「顔を合わせる機会が激減した」
- 「雑談のタイミングがつかめない」
- 「仕事以外の会話がないので関係性が浅い」
こうした声は、多くの職場で日常的に聞かれるようになりました。一見、業務に支障がないように見えても、心の距離がチーム力に影響を与えていることに注意が必要です。
働き方の多様化がもたらす「雑談の減少」
リモートワーク、フレックスタイム制度、副業、短時間勤務──こうした多様な働き方は個人の生産性向上やライフスタイルの尊重には有効ですが、偶発的な接点を減らすという課題も抱えています。
従来であれば、朝の出勤時や休憩時間、会議前の数分といった「すき間時間」に生まれていた雑談が減ることで、職場の空気が必要最小限のやり取りだけになる傾向があります。
この「雑談の欠落」は、チームの心理的安全性や信頼関係の構築を妨げ、孤立感や疎外感の温床になりかねません。
健康経営との関連:つながりが生むメンタルと生産性
職場コミュニケーションの問題は、単なる「雰囲気の良し悪し」ではありません。従業員のメンタルヘルスや生産性に直結する「健康経営の根幹」でもあります。
厚生労働省も「職場における心の健康づくり」指針の中で、良好な人間関係の構築を一次予防として位置づけており、「会話がしやすい環境=メンタル不調の早期発見と予防に寄与する」とされています。
つまり、職場コミュニケーションの改善は、組織のパフォーマンスと健康を底上げする土台づくりといえるのです。
出典:厚生労働省「職場における心の健康づくり」
社内コミュニケーションを促進するメリットとは?
プレゼンティーズム・エンゲージメントへの好影響
職場の会話量が増えると、業務効率だけでなくなんとなく体調が悪いという状態=プレゼンティーズムの改善にもつながることが各種調査で明らかになっています。
また、「自分が職場で認められている」「困ったときに相談できる人がいる」と感じられることで、エンゲージメント(職務への熱意と集中度)も高まります。
社員同士の自然なつながりは、結果的に「働きやすさ」と「パフォーマンス」の両方を向上させる要素となります。
離職率の低下と職場満足度の向上
「辞めた理由は人間関係」といった声は珍しくありません。いくら仕事のやりがいがあっても、相談しにくい・孤立感がある・仲間意識が薄い――こうした要因は離職を早めるトリガーとなります。
一方で、「職場の雰囲気がいい」「チームに相談しやすい文化がある」といった環境は、中長期的な定着と満足度の向上に直結します。
採用競争が激化する今、職場のコミュニケーションは定着率を左右する経営戦略の一部といえるでしょう。
チーム力の強化とイノベーションの土壌づくり
コミュニケーションが活性化した職場では、「アイデアが共有されやすくなる」「助け合いが自然に生まれる」「部署間の連携がスムーズになる」といったイノベーションの土壌が育ちます。
日常的な雑談や情報共有の中から、気づきや新しい視点が生まれ、それが組織としての創造性を高めるサイクルを生むのです。
今すぐ試せる!職場コミュニケーション活性化の取り組み
朝礼・ランチ・1on1を見直す「時間共有」施策
決まった時間を共有する機会は、コミュニケーション活性化の第一歩です。とくに朝礼やランチ、1on1ミーティングは「話す場」ではなく「関係を築く場」として再設計することで、社員同士の信頼構築に大きく貢献します。
具体的には、
- 朝礼で「ひとこと雑談テーマ」を設ける
- 月1回は上司と雑談中心の1on1を行う
- 昼休みに「雑談ルーム」を開放する
といった工夫で、業務外の自然な会話が増えていきます。
全社イベントや部門横断型プロジェクトの活用
運動会・ボウリング大会・ハッカソン・勉強会などの全社イベントや、複数部署合同のプロジェクト活動は、日常では接点の少ない社員同士をつなぐ「交流のブリッジ」になります。
特に30代〜40代の中堅層やリモートワーカーは孤立しやすいため、「チーム横断で目的に向かって動く」経験は、心理的安全性やチームビルディングにも好影響を与えます。
雑談・非業務会話のきっかけを意図的に設ける
いきなり「雑談しよう」と言っても自然には生まれません。そこで効果的なのが、雑談のきっかけとなる仕掛けです。
- オンラインで使える「雑談トピックカード」
- 社内SNSで「#週末どうだった?」タグを定期投稿
- WellWa(ウェルワ)のような健康チャレンジで「話題のきっかけ」を演出
こうしたきっかけ提供により、非業務の会話が当たり前になる空気づくりが可能になります。
成功する企業が実践する「コミュニケーションの設計」
共通言語をつくる「健康」や「趣味」のテーマ化
コミュニケーションの活性化を図る上で最も大切なのは、「話すきっかけ」をつくることです。特に世代や部署を越えて話題を共有するには、立場や役職に関係なく語れる「共通言語」が必要です。
そこで効果的なのが、「健康」や「趣味」をテーマとした取り組みです。
- 「1日6,000歩達成したらスタンプ」
- 「好きな朝食を紹介し合うSlack投稿」
- 「業務時間中の昼ストレッチ会」
といった取り組みは、気軽に話しかけられる雰囲気を生み出し、上下関係の垣根を取り払うきっかけになります。
仕組みによる継続:ゲーミフィケーションと可視化
「一度きりのイベント」で終わらせず、日常的な行動へと落とし込むには、仕組みとして続けられる設計が欠かせません。
特に、ポイント制やランキング、バッジ獲得などのゲーミフィケーション要素を取り入れることで、楽しみながら継続できる環境が整います。
また、コミュニケーションの頻度や参加状況を可視化することで、取り組みの成果を社員自身が実感でき、「頑張っている姿が見える」ことがやる気の持続にもつながります。
キリンのWellWaに学ぶ!健康×つながりで職場を変えるアプローチ
雑談を生む「チャレ活」「健康選手権」の仕掛け
WellWaは、キリンビバレッジが提供する企業向け健康支援ツールで、チームで健康行動に取り組む「チャレ活」や、部署対抗の「健康選手権」といったイベント設計が特長です。
これらは、「健康」というテーマを通じて自然に会話が生まれる設計になっており、社員同士の共通話題を創出する仕組みとして優れています。
自然な交流を生む「WellStock」「ミッション」
WellWaでは、日々の健康行動を達成することでポイントが貯まり、社内用ウェルネスストア「WellStock」でドリンクと交換可能。この「ごほうび」が健康行動のきっかけとなり、ミッション達成を報告し合う文化も自然と生まれます。
1日ごとのミッションも「今日の睡眠をチェックしよう」「昼休みに背伸びチャレンジ」など、ハードルが低く共感されやすい内容なのも特長です。
部署横断型の「つながり」がエンゲージメントを高める
WellWaでは、部署間のランキング形式やスタンプの送り合いなど、組織横断的な交流を促す機能が豊富に搭載されています。
これにより、「普段話したことのない他部署の人とも、健康をきっかけにつながることができる」という声が多数寄せられており、エンゲージメントや職場満足度の向上にも寄与しています。
コミュニケーション促進の失敗を防ぐためのポイント
取り組みの「目的」を明確にする
「なぜこの取り組みをするのか?」が社内で共有されていないと、コミュニケーション施策はただのノリで終わってしまいます。
- 「働きがいのある職場づくりのため」
- 「部署間の連携を強化するため」
- 「心理的安全性を高めるため」
など、目的を明示し、共通のゴールとして位置づけることで、社員の納得感と参加率が向上します。
定量指標とフィードバックで効果を見える化
施策の成果は「雰囲気」で判断されがちですが、数値で効果を見える化することが、上層部への報告や改善サイクルには不可欠です。
- ミッション参加率
- スタンプ送信数
- 健康施策に対する満足度調査
などの定量・定性データを活用し、フィードバックを取り入れる運用体制が成功の鍵となります。
まとめ
健康は誰もが共感できる普遍的なテーマです。それをきっかけに、会話が生まれ、信頼が生まれ、心理的安全性とエンゲージメントが高まる職場の土壌が整っていきます。企業が本気で健康経営に取り組むなら、コミュニケーションという視点を外すことはできません。いきなり全社的な施策を導入するのではなく、少人数・短期間・トライアル形式からスタートし、現場の声を吸い上げながら改善することが、継続の秘訣です。
まずはやってみるという小さなアクションが、部署全体・企業全体へと広がる道筋をつくります。
WellWaなどツールを活用して「輪」を生み出そう
コミュニケーションは育てるものです。そして、育てるためには土壌(文化)と水(仕組み)が必要です。WellWaのようなツールは、その両方を支える「健康×つながり」の実践プラットフォームとして、多くの企業で成果をあげています。
皆様の職場にも、心地よいつながりの輪を広げる第一歩を。今こそ、健康と対話を軸にしたコミュニケーション改革を始めましょう。