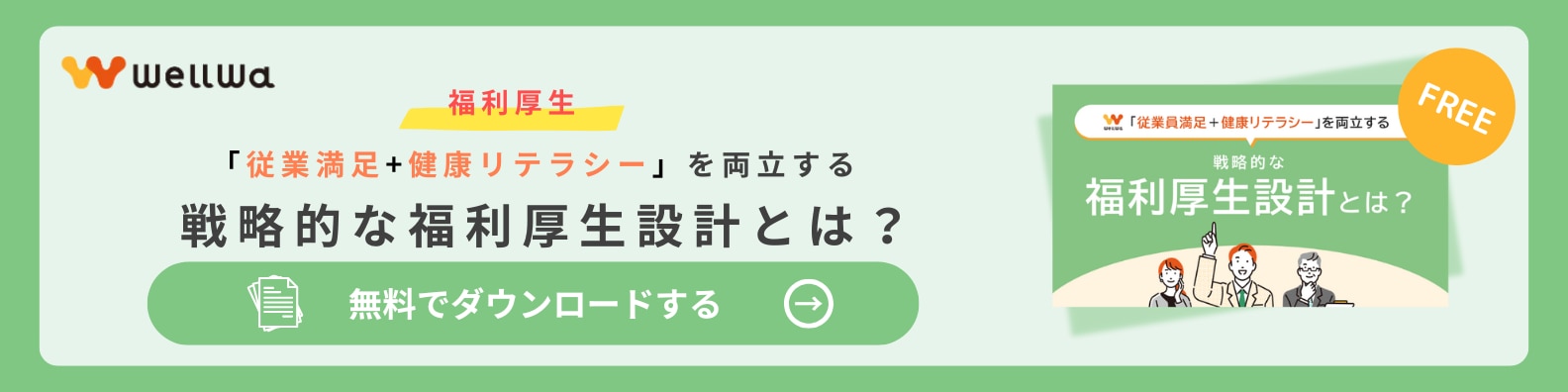福利厚生でメンタルヘルス対策!コミュニケーション活性化で職場の健康を守る方法
近年、職場のストレスや人間関係の課題により、メンタルヘルスの重要性がますます高まっています。本記事では、企業が福利厚生を通じて実現できる効果的なメンタルヘルス対策と、職場のコミュニケーション活性化による相乗効果について、具体的な施策とともに紹介します。
目次[非表示]
- 1.メンタルヘルス対策が企業に与える影響
- 2.メンタルヘルスと職場コミュニケーションの関係
- 3.福利厚生として導入できるメンタルヘルス対策
- 3.1.1ストレスチェック制度(法定福利厚生)
- 3.2.2外部EAP(従業員支援プログラム)や相談窓口の設置
- 3.3.3休養・リフレッシュ支援
- 3.4.4ハラスメント防止と心理的安全性の確保
- 4.コミュニケーションを活性化する福利厚生制度
- 4.1.1社員同士の交流促進イベント
- 4.2.2デジタルツールを活用した交流促進
- 4.3.3オフィス環境の工夫によるコミュニケーション促進
- 5.健康経営と連動したコミュニケーション活性化
- 6.メンタルヘルス対策と社内コミュニケーション活性化の成功ポイント
- 7.まとめ
メンタルヘルス対策が企業に与える影響
現代社会では、納期プレッシャー、業務量の多さ、対人関係の悩みなど、精神的に不安定になりやすい状況が職場に日常的に存在します。厚生労働省のデータによれば、ストレスが原因でメンタルヘルス不調を訴える労働者の割合は年々増加傾向にあり、「令和5年雇用動向調査結果の概況」によると、離職者の内、男性の9.1%、女性の13.0%が「職場の人間関係が好ましくなかった」を離職理由に挙げています。
出典:厚生労働省「令和5年雇用動向調査結果の概況」
福利厚生を通じたメンタルヘルス対策は、これらの課題を解決するだけでなく、「企業は自分たちの健康を大切にしてくれている」という安心感を従業員に与えます。特に注目すべきは、メンタル面でのサポートが日々のコミュニケーションを活性化させ、職場全体の風通しをよくする効果があることです。
メンタルヘルスと職場コミュニケーションの関係
メンタルヘルス不調の原因を調査すると、「職場の人間関係」が上位に挙がることが多いことをご存知でしょうか。特に上司との関係性や同僚との意思疎通がうまくいかないケースでは、高いストレスを感じやすく、気づかないうちに心の不調につながりやすくなります。
一般社団法人 日本経営協会の調査報告書によると、職場でのメンタルヘルス問題の約60%が「人間関係」に起因しているというデータもあります。
出典:一般社団法人 日本経営協会「NOMA News Release(2017/04/14)」
このことから、コミュニケーションの質を高めることがメンタルヘルス対策の第一歩といえるでしょう。
オープンなコミュニケーションが可能な環境では、悩みや不安を早期に共有できるため、深刻な問題に発展する前に対処できます。また「誰かとつながっている」という安心感は孤立を防ぎ、ストレス耐性を高める効果もあります。リモートワークが普及した現代だからこそ、意図的に「つながり」を設計することが求められているのです。
福利厚生として導入できるメンタルヘルス対策
1ストレスチェック制度(法定福利厚生)
ストレスチェック制度は、従業員50名以上の事業所に義務付けられている法定福利厚生ですが、最近では小規模企業でも自主的に導入する企業が増えています。(※2025年3月14日、50人未満の小規模事業場でのストレスチェック義務化が盛り込まれた「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました)
出典:厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案の概要(PDF)」
結果を活かす工夫:
- 部署ごとのストレス傾向を可視化し、職場環境改善につなげる
- 高ストレス者には産業医面談を促し、早期ケアを実施
- 経年変化を追跡し、施策の効果を測定
2外部EAP(従業員支援プログラム)や相談窓口の設置
EAP(Employee Assistance Program)は、外部の専門機関と提携し、従業員がメンタル不調や人間関係の悩みについて相談できる仕組みです。
導入のポイント:
- 臨床心理士や産業カウンセラーなど専門家による相談体制
- 対面・電話・オンラインなど選べる相談方法
- 匿名相談制度による心理的安全性の確保
- 上司向けのマネジメント相談も含めた総合的サポート
3休養・リフレッシュ支援
心身のリフレッシュを促す福利厚生制度も、メンタルヘルス対策として大きな役割を果たします。
効果的な施策例:
- リフレッシュ休暇やメンタルヘルス休暇の導入
- ヨガ・マインドフルネス研修の実施
- フィットネスジムやスパ施設の利用補助
4ハラスメント防止と心理的安全性の確保
ハラスメントはメンタルヘルス不調の大きな要因です。防止策として、以下の取り組みが効果的です。
具体的な対策:
- ハラスメント防止研修の定期実施
- 外部通報制度(ホットライン)の導入
- 定期的な1on1ミーティングによる上司と部下の対話促進
特に1on1ミーティングは、問題の早期発見と信頼関係構築に有効です。
コミュニケーションを活性化する福利厚生制度
1社員同士の交流促進イベント
実践例:
- 社員旅行・社内イベントへの費用補助
- 部署を超えたプロジェクトや勉強会の開催
- チームビルディング研修の導入
2デジタルツールを活用した交流促進
リモートワーク環境でも効果的なコミュニケーション施策として、以下のようなデジタルツールの活用が挙げられます。
導入例:
- Slack等のチャットツールに雑談専用チャンネルを設置
- バーチャルオフィスによるカジュアルな対話環境の構築
- オンライン朝会や終礼での近況共有
3オフィス環境の工夫によるコミュニケーション促進
物理的な空間設計も、従業員のコミュニケーション活性化に大きく影響します。
効果的な施策:
- フリーアドレス制の導入による部署間交流の促進
- カフェスペースや休憩エリアの充実
- 立ち話ができるハイテーブルの設置
健康経営と連動したコミュニケーション活性化
健康経営の視点からメンタルヘルスとコミュニケーションを同時に支援する取り組みも注目されています。
健康習慣の共有によるコミュニケーション促進
具体的な取り組み例:
- 部署対抗ウォーキングイベントの実施
- 健康レシピの社内共有会
- ヘルスリテラシー向上セミナーの開催
これらの取り組みは、健康という共通のテーマを通じて社内の会話が生まれるきっかけとなります。
キリンビバレッジによる健康経営×コミュニケーション活性化ソリューション
福利厚生と社内コミュニケーションを同時にサポートできるソリューション「WellWa」が注目されています。健康イベント機能やミッション達成によるKIRINの美味しい健康飲料が購入できるポイント付与など、「楽しい健康」を体験できる健康支援アプリを提供しています。
KIRINの健康飲料による職場環境改善
オフィス内に置き型のスムージーやKIRINの健康飲料自販機を設置することで、従業員の栄養補給を手軽にサポートできます。気軽にドリンクを接種できる空間をつくることで、従業員の健康意識を自然と高めるだけでなく、スタンド周辺での会話や雑談のきっかけにもなり、社内コミュニケーションの活性化にも寄与します。
健康行動を促進するポイントアプリの活用
WellWaのアプリでは、健康行動を促進するポイント制度と連携した健康プログラムが利用できます。毎日の歩数記録や食事管理、睡眠ログなどを入力することでポイントが貯まり、社内キャンペーンや報酬制度と組み合わせることも可能です。
このポイント付与型の健康アプリは、自販機の利用や社内イベントへの参加と連動させることで、楽しみながら健康を意識できる環境をつくれます。「ウォーキングキャンペーン」や「朝活イベント」などと組み合わせることで、社員同士が楽しく関わりながら健康を目指せる風土が醸成されていきます。
〈詳細はこちら〉
メンタルヘルス対策と社内コミュニケーション活性化の成功ポイント
経営層のコミットメントと継続的な取り組み
メンタルヘルス対策やコミュニケーション活性化は、一度きりのイベントではなく継続的な取り組みが重要です。特に経営層が率先して参加することで、「会社として本気で取り組んでいる」というメッセージを従業員に伝えることができます。
多様なニーズに対応できる選択肢の提供
従業員によって、コミュニケーションスタイルや健康ニーズは異なります。一律の施策ではなく、選択できるオプションを用意することで、より多くの従業員が参加しやすくなります。
効果測定と改善のサイクル
導入した施策の効果を定期的に測定し、必要に応じて改善していくことも大切です。従業員の声を取り入れながら、PDCAサイクルを回していくことで、より効果的な取り組みになっていきます。
まとめ
メンタルヘルス対策と職場のコミュニケーション活性化は、企業の持続的な成長の土台となる重要な取り組みです。従業員一人ひとりの心の健康を守るためには、制度や環境の整備だけではなく、日常的な人とのつながりや安心感を育む文化づくりが欠かせません。
福利厚生として導入するストレスチェックやEAP、リフレッシュ支援などの制度は、単独でも効果がありますが、コミュニケーションを促進する取り組みと組み合わせることで、さらに大きな効果を発揮します。
自社の課題や文化に合った施策を選び、継続的に取り組むことで、従業員が心身ともに健康で、いきいきと働ける職場環境が実現できるでしょう。それは結果として、生産性の向上や優秀な人材の定着、企業ブランドの向上にもつながっていきます。