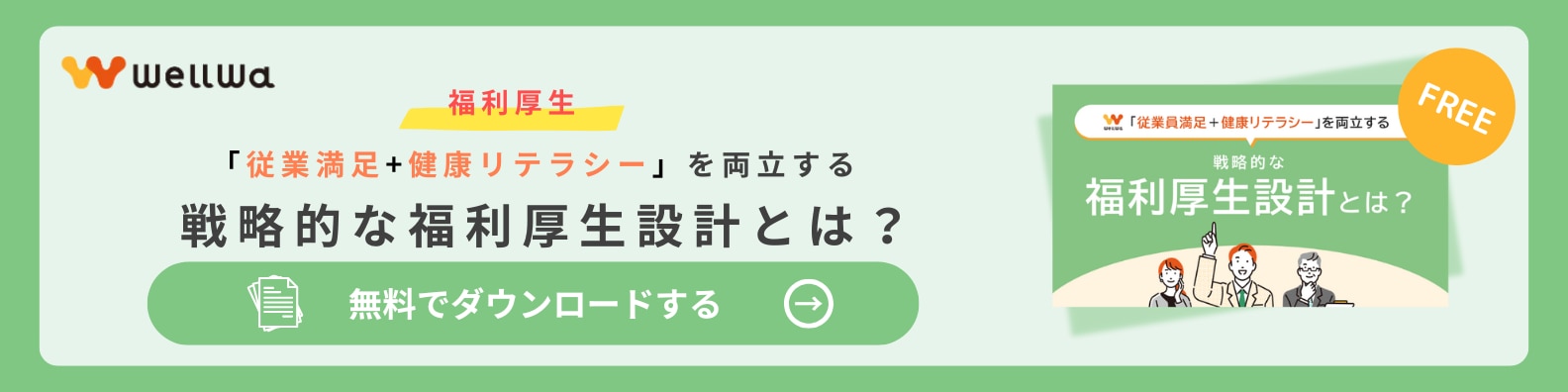導入した福利厚生の利用率を向上させるには?利用率改善のコツを解説
多くの企業が福利厚生制度を整備しているものの、十分に活用されておらず、本来の効果が得られていないことがあります。本記事では、その原因を明らかにし、利用率向上に向けた具体的な改善策を解説します。従業員の満足度向上や健康経営の推進に向けて、 “活用される制度設計”を目指しましょう。
目次[非表示]
福利厚生の利用率が低いのはなぜ?
福利厚生を導入しても思うように活用されない背景には、いくつかの共通した課題があります。ここでは、利用率が低くなってしまう主な要因を整理し、改善へのヒントを探っていきます。
企業が充実した福利厚生を導入しても、実際の利用率が低いことが多い
企業は従業員満足度や定着率の向上を目的に、さまざまな福利厚生サービスを導入しています。しかし、実際には思うように成果が得られないケースが散見されます。制度を設けただけでは従業員に活用されず、費用対効果が得られないリスクもあるため、利用率を高める取り組みが求められます。
福利厚生の利用率が低い主な原因
福利厚生の利用が進まない背景には、制度自体の設計や周知方法に課題があることがよく見られます。以下では、代表的な4つの原因について詳しく見ていきます。
認知不足:社員が制度の存在を知らない・詳細を理解していない
福利厚生制度が存在していても、その内容が従業員に十分に伝わっていないケースが多く見受けられます。社内報やメールで簡単に紹介されただけでは、忙しい日々の中で記憶に残りにくく、利用にはつながりません。特に新入社員や異動したばかりの社員は、制度の情報にアクセスしづらく、知らないままスルーしてしまうこともあります。
手続きが複雑:申請方法に手間がかり利用を避ける
申請に紙の書類提出や承認プロセスが必要な場合、手間がかかることで利用が敬遠されがちです。たとえば、出張精算のように先送りしているうちに申請し忘れる、というパターンもあります。利用するたびに煩雑なステップを踏まなければならない設計では、せっかくの制度も宝の持ち腐れになってしまいます。
魅力不足:社員のニーズと合っていないサービスが多い
導入している福利厚生が、実際の従業員のライフスタイルや価値観とマッチしていない場合も、利用率は伸びません。たとえば独身の若手が多い職場で育児支援制度ばかり充実していても、活用には結びつきません。年齢や家族構成、働き方の多様性に応じた制度設計が重要です。
利用条件が厳しい:対象者が限定されているため活用しにくい
制度によっては、「勤続年数3年以上」「扶養家族あり」など、細かい条件が設定されていることもあります。対象者が限定されすぎると、多くの従業員が「自分には関係ない」と感じてしまい、利用意欲が湧きません。せっかくの制度を広く活用してもらうには、柔軟な対応が求められます。
福利厚生の利用率を上げるメリットとは?
福利厚生制度の利用率を高めることは、制度の活用そのものだけでなく、その先の行動変容や意識改革につながる点に意味があります。企業と従業員双方に多くのメリットがあるため、さらなる成果を生み出す可能性を秘めています。
従業員満足度の向上:福利厚生の活用で働きやすさが向上
福利厚生制度が従業員にとって利用しやすく、個々のニーズに合った制度が整っていれば、日々の働きやすさが向上し、モチベーションアップにも寄与します。結果として、社内の雰囲気や職場の満足度が向上する効果が期待できます。
企業のエンゲージメント向上:従業員の会社への愛着が強まり、定着率がアップ
「制度があるだけでなく、しっかり活用できる」という体験は、会社への信頼や愛着を深める要因となります。特にライフイベントや体調不良など、困ったときに役立つ福利厚生は、従業員の心理的安全性を高め、離職防止にもつながります。エンゲージメントの向上は、企業文化の安定にも寄与します。
採用力の強化:福利厚生の充実は、求職者にとって魅力的なポイント
求人市場では、給与だけでなく福利厚生の内容も重要な検討のポイントとなっています。自社の制度が積極的に活用されている実績があれば、求職者へのアピール材料になります。とくに働き方改革やワークライフバランスが重視される今、制度の「見せ方」だけでなく、「使われ方」が重要視されています。
健康経営の推進:健康支援系の福利厚生を積極的に活用してもらうことで、社員の健康増進につながる
スポーツジム補助や健康診断のオプション、メンタルヘルス支援などの福利厚生は、社員の健康行動を後押しします。利用率が上がれば、企業全体の健康意識も向上し、医療費の削減や生産性の向上といった副次的なメリットも生まれます。まさに「攻めの健康経営」を実現する基盤となります。
福利厚生の利用率を向上させる4つの改善策
福利厚生を「導入しただけ」で終わらせないためには、利用しやすい環境づくりが不可欠です。ここでは、実際に多くの企業で効果が出ている4つの改善アプローチを紹介します。
1社内への周知を徹底する
制度の存在を知ってもらわなければ、利用にはつながりません。まずは「制度の周知」を最優先に取り組みましょう。
多様なコミュニケーション手段を活用
情報は、繰り返し・多方面から伝えることが重要です。部署や職種によって伝わりやすいチャネルは異なるため、メールはもとより、口頭での案内や動画配信なども検討しましょう。
社内ポータルサイト・SlackやTeamsでの通知
制度の概要や申請方法をまとめたページを社内ポータルサイトに用意し、アクセスしやすくする工夫も有効です。新しい制度の追加時は、SlackやTeamsなどのビジネスチャットツールを活用し、即時に情報が届く仕組みを整えましょう。
福利厚生ガイドブックを作成し、新人社員研修で活用
社員が福利厚生の内容を正しく理解し、有効に活用できるよう、制度の概要や利用手順を分かりやすくまとめた「福利厚生ガイドブック」を作成します。このガイドブックは、新入社員研修の一環として配布・説明を行い、入社初期から福利厚生の活用意識を高めることを目的としています。紙面やデジタル形式での配布に加え、定期的な内容更新を通じて、全社員にとって常に最新で信頼性のある情報源となるよう運用します。
2申請・利用方法を簡素化する
制度があっても、手間や時間がかかる印象を与えると利用は進みません。申請の工数を減らす工夫が、利用率アップのカギになります。
手続きのデジタル化・アプリ活用
紙での申請や対面の承認フローは、現代の働き方にはそぐわない面があります。福利厚生の利用申請をオンライン化すれば、申請者と承認者の省力化、業務効率の向上にもつながります。特にリモートワークが普及した今、場所を問わず手続きできる仕組みが求められています。
福利厚生専用アプリや社内システムでワンクリック申請を実現
最近では、福利厚生制度専用のアプリやプラットフォームが登場しています。これらを活用すれば、申請や利用が“ワンクリック”で完結し、利用ハードルが大きく下がります。社員にとって「使いやすい」と感じられることが、利用継続のポイントです。
紙ベースの手続きを廃止し、スマホ・PCで手軽に申し込み可能にする
スマートフォンやパソコンで完結する申し込みフローを設けることで、社員が空き時間に気軽に利用できるようになります。業務中に申請する時間が確保できない従業員にも配慮し、「いつでもどこでも申請できる」環境を整えることが重要です。
3従業員のニーズに合ったサービスを導入する
福利厚生は「多ければ良い」わけではなく、実際のニーズに合っていることが肝心です。従業員の声を反映した制度設計が、利用率の底上げに直結します。
定期的なアンケートで希望を把握する
「どの福利厚生が魅力的か」「導入してほしい制度は何か」といった意見を定期的にアンケートで収集しましょう。従業員の本音を知ることで、実際に求められているサービスを把握できます。
利用率が低いサービスを廃止し、予算をニーズの高い福利厚生に振り分ける
コストに見合わない制度は見直しが必要です。限られた予算を最大限に活用するためには、不要な制度は整理し、人気のあるサービスに集中投資する判断も重要です。
世代・ライフスタイルに合わせた選択肢を用意する
若年層にはレジャーや旅行補助、中高年には医療支援や介護支援といったように、世代やライフステージに応じて複数の選択肢を提供することで、より幅広い従業員が自分ごととして利用しやすくなります。
4 インセンティブ制度を導入する
利用を「推奨する」だけでなく、楽しみながら取り組める仕組みにすることで、制度がより浸透します。
利用に応じてポイントを付与し、特典と交換できる仕組みを導入
福利厚生の利用に応じてポイントが付与され、一定のポイントを貯めると商品やサービスと交換できる仕組みを取り入れることで、社員の利用意欲が高まります。健康促進や学び直し支援といった制度と組み合わせると、相乗効果が生まれます。
ランキングや表彰制度を活用し、利用促進を図る
部署ごとの利用率ランキングや、積極的に制度を活用した社員の表彰制度などを導入することで、制度利用が社内で“見える化”されます。ゲーム感覚で参加できるようにすれば、おのずと制度が浸透します。
従業員の健康行動でポイントがたまる健康特化型のアプリとは?

近年注目されているのが、従業員の健康行動に応じてポイントが貯まる“健康特化型”のアプリです。たとえば、ウォーキングやストレスチェックへの回答など、健康行動を起こすたびにインセンティブが付与され、貯まったポイントを商品や食事券と交換できる仕組みです。
こうした仕組みは、利用するほど健康になれるという“好循環”を生み出し、企業の健康経営推進にも大きく寄与します。導入企業の多くで従業員の健康意識が高まり、欠勤率や医療費の削減にもつながっていることから、今後ますます導入が広がると見込まれています。
〈キリンビバレッジが提供しているウェルビーイングソリューションとは〉
まとめ
福利厚生は「整備するだけ」では効果を発揮しません。社員にとって魅力的で、使いやすく、そして実際に活用される制度であることが重要です。制度の周知から申請の簡素化、ニーズに合ったサービス設計、そしてインセンティブの導入まで、総合的に取り組むことで、福利厚生の利用率は確実に改善できます。健康経営や人材定着にも大きな効果をもたらすため、今こそ制度の見直しと活用促進を進めましょう。