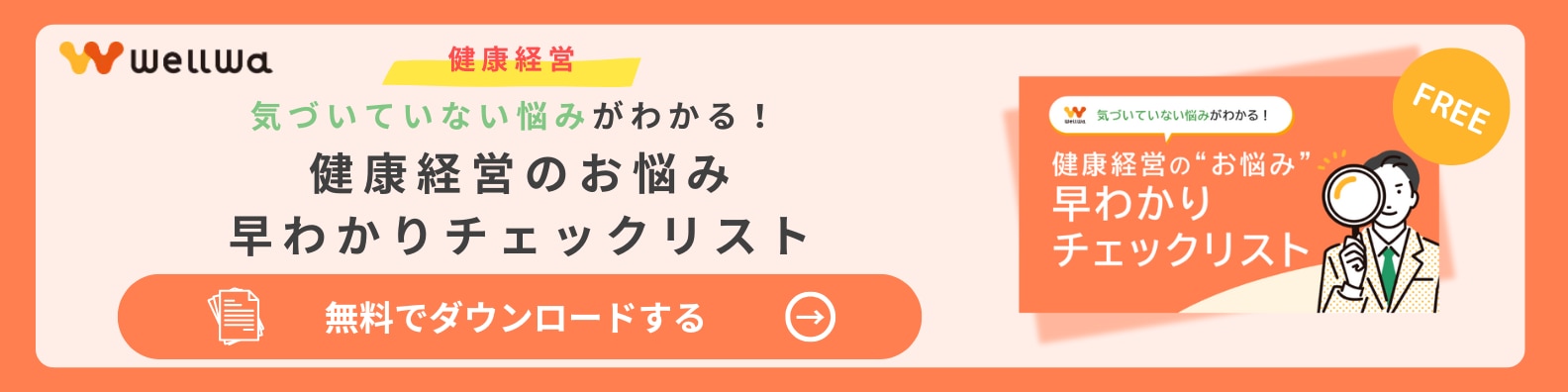エンゲージメントが低い…その原因、アンケートで見えていますか?
「最近、なんとなく社員の元気がない」「離職が続いているけれど、はっきりした原因がわからない」そんな悩みを抱えるマネージャーや人事担当者は少なくありません。この記事では、表面化しにくいエンゲージメント低下のサインを、アンケートを活用してどう可視化・予防するかを解説します。
目次[非表示]
社員が静かに辞めていく組織の共通点
表面的には問題がないように見えても、実は社員の離職予兆が進行している組織には共通する特徴があります。それは、小さな違和感やモヤモヤが放置され、本人も周囲もそれに気づかないまま蓄積していくことです。業績指標や表面的な満足度スコアでは読み取れない、感情レベルの"揺らぎ"が、離職の最初のサインとなります。
離職者インタビューでは、表向きには"キャリアアップ"や"家庭の事情"といった前向きな理由が語られます。しかし、その裏には評価への不満、上司との関係悪化、将来への不安など、より感情的で微妙な要因が隠れていることが少なくありません。この"本当の理由"に早期に気づけるかどうかが、離職防止の分かれ道になります。
退職が相次ぐ組織には、見逃されがちなサインがあります。
- ちょっとした雑談や相談の頻度が減る
- チームミーティングでの発言数が減る
- 意見に対して建設的な反応が減る
こうした小さな変化を察知できる組織力が、人財流出を防ぐ鍵となります。
エンゲージメント低下のサインをアンケートで可視化する方法
エンゲージメントが低下している社員は、明確な不満を訴えるとは限りません。むしろ、漠然とした"モヤモヤ"や"違和感"を抱えながら、表面的には問題なく働いていることが多いものです。この感情のサインを捉えずにいると、気づいたときには離職という結果を招いてしまいます。
効果的なアンケート設計のポイント
モヤモヤや不安、不満を可視化するには、単に満足度を5段階で聞くだけでは不十分です。以下のような工夫が効果的です。
- 感情の温度を測る設問を盛り込む
「最近、仕事に対して前向きな気持ちになれていますか?」 「チームで意見を自由に言えると感じますか?」 - 自由記述欄を設け、社員自身の言葉で今の気持ちを表現してもらう
- 前回調査からの「変化」に注目する
「やりがい」「人間関係」「将来性」に対するスコアの微妙な低下を追跡
このように、数値だけでなく質的な変化を捉えることで、問題が深刻化する前に手を打つことができます。
心理的安全性とエンゲージメントアンケートの関係
心理的安全性とエンゲージメントは密接な関係にあります。チーム内で自分の意見や感情を安心して表現できる環境があるかどうかは、エンゲージメントレベルに大きな影響を与えます。心理的安全性が高い職場では、課題も建設的に話し合われ、モチベーションが維持されやすくなります。
一方、組織の閉塞感を示す兆候には注意が必要です。
- 「ミスを恐れて発言しにくい」と感じる社員の増加
- 「提案しても受け止められない」という認識の広がり
こうした兆候を放置すれば、やがて静かな離職の波となって現れる可能性が高まります。
チームの健全度を測るためには、心理的安全性に関する設問をアンケートに組み込むことが重要です。
- 「あなたの意見はチームで尊重されていると感じますか?」
- 「失敗を共有できる雰囲気がありますか?」
こうした問いかけを通じて、職場の空気感を定量・定性の両面から把握することができます。
エンゲージメントアンケートで本音を引き出す工夫
匿名性と信頼性の確保
エンゲージメントアンケートで本音を引き出すには、社員が安心して回答できる環境づくりが不可欠です。匿名性を確保することで、社員は忖度や報復を恐れず、正直な声を届けやすくなります。特に評価や上司へのフィードバックに関する設問では、匿名性の確保が回答率と回答の質に直結します。
自由記述の効果的な活用法
自由記述設問を設ける際は、単なる「不満のはけ口」に終わらせない工夫が必要です。
- 回答後に「どう改善したか」を必ずフィードバックする
- 「社員の声をもとにどんなアクションを取ったか」を共有する
こうした仕組みを組み込むことで、社員は「言っても無駄」という諦めを感じることなく、建設的な意見を出すようになります。
アンケート実施の配慮事項
アンケート設計においては、回答者の信頼を得るための配慮が求められます。
- 設問数を過剰に増やさない
- 設問の意図を明確に伝える
- 回収後の扱い方を事前に説明する
これらの配慮が積み重なることで、社員との信頼関係が育まれ、より質の高い回答を得ることができます。
エンゲージメントアンケートの回答率を高める方法
アンケートの回答率には組織風土が色濃く反映されます。回答率が低い組織には、「どうせ何も変わらない」という諦めムード、「誰が書いたかバレるのでは」という不安、「忙しくて答える時間がない」という優先順位の低さ、といった共通する特徴が見られます。
回答率を高めるためには、配信タイミングにも注意が必要です。繁忙期や直近に不祥事・大きなトラブルがあった直後は避けた方が無難です。理想的なのは、組織に大きな変化があった直後(新施策導入後、組織再編後)や、業務が比較的落ち着いている時期に実施することです。
また、「このアンケートが今後どう活用されるか」を事前に明確に伝えることで、社員の参加意欲を高め、回答率向上につなげることができます。
エンゲージメントアンケートのスコア分析ポイント
エンゲージメントアンケートの結果を分析する際は、単なる数値としてのスコアだけでなく、以下の3つの視点が重要です。
1.時系列の変化傾向
時間の経過に伴う変化を捉えることが重要です。例えば「やりがい」スコアが半年でじわじわと低下している場合、表面的には問題が見えなくても、深刻な課題が進行している可能性があります。
2.部署別・属性別の比較
部署別・属性別にデータを細分化して、「偏り」や「沈黙」を見つける視点が欠かせません。特定の部署だけスコアが異常に低い、特定世代だけ満足度が低い、といった傾向は、ピンポイントで施策を打つべきサインです。また全体的にスコアが高くても、自由記述でネガティブな声が多い場合は注意が必要です。
3.未説明の低下要因の分析
スコアが下がった理由が明確でない場合、その背後には「言いづらい課題」や「構造的な問題」が潜んでいる可能性があります。表面に現れない理由に目を向け、仮説を立てて深掘りすることが、人事担当者の重要な役割となります。
エンゲージメントを測定・改善するツール「WellWa」

エンゲージメント可視化と改善サイクルを効率的に回すツールとして、キリンの「WellWa」があります。WellWaでは、25問の設問でエンゲージメント指標や心理的安全性指標、メンタル指標等を包括的に測定し、業界比較や経年推移も可視化できます。
部署対抗チャレンジやランキング機能を通じて、アンケート結果を施策につなげる仕掛けも標準装備されています。測定だけではなく、具体的な行動変容までサポートできる点が、WellWaの大きな強みです。
まとめ
エンゲージメントアンケートは単なる調査ではなく、社員の本音を引き出し、組織の未来をつくるための重要な対話の場です。効果的に活用するためには、設問設計、実施タイミング、分析視点、施策連動のすべてに細やかな工夫と配慮が必要です。
小さな変化を丁寧に拾い上げながら、社員と組織の成長を支えるアンケート文化を育てていきましょう。