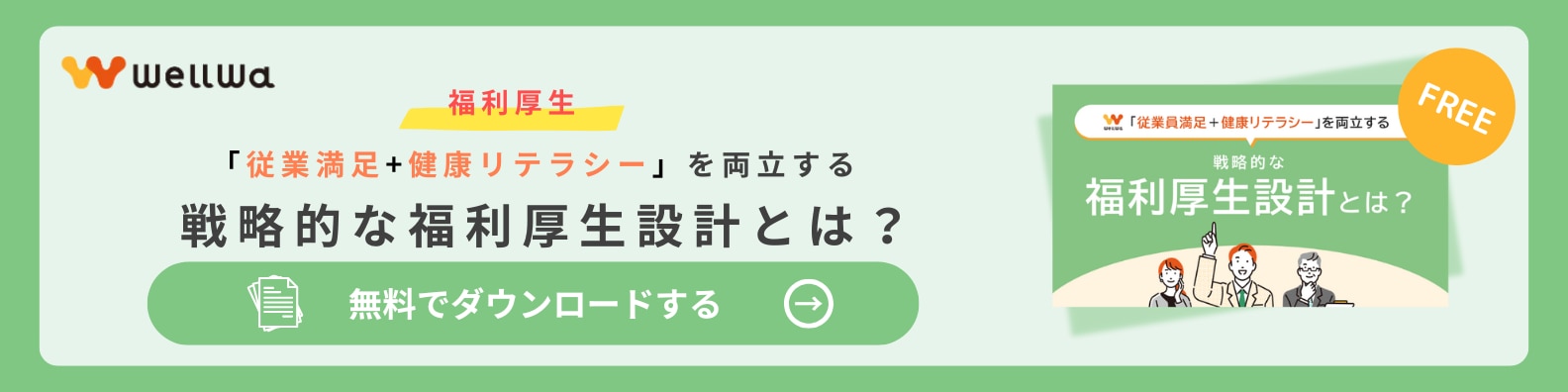従業員エンゲージメント向上施策の重要性と特徴
従業員エンゲージメントの向上は、組織の生産性や定着率に直結する重要課題です。この記事では、従業員エンゲージメントの基礎知識から、企業成果に直結する施策のポイント、成功に導く実践ステップまでを詳しく解説します。
目次[非表示]
「従業員エンゲージメント」とは何か?
従業員エンゲージメントとは、単なる満足度とは異なり、社員が組織の目標に共感し、自ら積極的に貢献しようとする心理的な状態を指します。仕事にやりがいを感じ、組織への誇りを持ち、自発的に行動する力が高い状態がエンゲージメントの高い状態です。
従業員満足度が"受け身"の指標であるのに対し、エンゲージメントは"能動的"な指標であることが大きな違いです。満足していても、組織に貢献しようとしない社員は多く存在します。一方で、エンゲージメントが高い社員は、多少の不満があっても組織のために力を尽くす傾向があります。
エンゲージメントが企業成果に与える影響は大きく、生産性向上、離職率低下、顧客満足度向上、イノベーション創出にも直結することが多くの調査で示されています。逆にエンゲージメントが低い組織では、モチベーション低下、離職率上昇、業績悪化という負のサイクルに陥りやすくなります。
近年、日本の従業員エンゲージメントは世界的に見ても低水準で、2022年のGallup社の調査では日本の社員で仕事に熱意を持って取り組んでいる人はわずか5%にとどまり、全球平均(23%)を大きく下回りました。
参照元:Gallup,Inc
こうした背景から、社員の働きがいやモチベーションを高める「エンゲージメント向上施策」が多くの企業で注目されています。
施策がうまく機能しない現場の本当の課題
多くの企業では、エンゲージメント向上を目指して数値目標を設定します。しかし、目標を掲げただけでは現場は動きません。その背景には、エンゲージメント向上が"やらされ感"で捉えられていたり、現場のリアルな課題感に寄り添った施策設計ができていなかったりする問題があります。
"社員のために"と意図して設計した施策も、現場にとっては押し付けや負担と受け取られることがあります。このズレが施策の空回りを招き、せっかくの取り組みが逆効果になってしまうケースも少なくありません。
また、施策を"やった感"だけで終わらせてしまうのもよくある失敗パターンです。イベント開催やアンケート実施といった単発の取り組みはできても、その後のアクションや改善に結びつかないと、社員の期待に応えるどころか、むしろ不信感を生む結果になります。
本当の“エンゲージメント課題”の所在
エンゲージメント向上を目指す上で、まず注意すべきは、社員の声を"誤読"していないかという点です。表面的な不満や要望に振り回されるのではなく、その背後にある本質的なニーズを捉えることが重要です。
例えば、"福利厚生を充実してほしい"という声の背景には、"会社に大切にされていると感じたい"という心理が隠れている可能性があります。
課題の本質は制度の有無ではなく、組織内にどれだけ"信頼"が育まれているかにあります。上司との信頼関係、同僚との協力関係、会社への信頼。この信頼の有無が、エンゲージメントを大きく左右します。制度を整えることも大切ですが、それ以上に"人と人"の関係性をどう育てるかが問われています。
さらに、"満足度が高い=エンゲージメントが高い"という誤解も根強くあります。満足している社員が必ずしも主体的に貢献しているとは限りません。本当にエンゲージメントを高めるには、満足度調査だけに頼らず、"働きがい"や"貢献意欲"を測る指標も取り入れるべきです。
課題を読み解くための“可視化”のステップ
エンゲージメント向上に取り組む際、最初に行うべきは現状の"可視化"です。しかし、単にスコアを見るだけでは本質的な課題は掴めません。エンゲージメントサーベイで数値が良くても、現場にはモヤモヤが溜まっていることがあります。逆に数値が低くても、成長意欲に溢れた健全な危機感が存在する場合もあります。だからこそ、"定量"だけではなく、"定性"、つまり社員の生の声にも耳を傾けることが重要です。
スコアと自由記述、インタビューや対話型ワークショップなどを組み合わせ、社員の本音を多面的に読み解いていく。そこから、施策の方向性や優先順位を明確にしていくのが、成功するエンゲージメント施策設計の第一歩です。また、小さな変化を捉える仕組みも大切です。月次の簡易サーベイや、1on1の振り返りを活用して、日常の中に"変化の兆し"を拾う習慣を組み込むと、機動的な対応が可能になります。
成果に繋がるエンゲージメント向上施策の特徴
エンゲージメント向上施策で成果を出すためには、トップダウンとボトムアップの理想的なバランスが不可欠です。経営層からの強いメッセージと、現場からの自発的なアイデアや行動。この両輪を噛み合わせることで、施策は組織文化の一部として根づいていきます。
制度設計に力を入れるのも重要ですが、それ以上に大切なのは、日々の"行動"をどう変えていくかです。マネージャーが定期的に1on1を実施する、感謝を言葉にして伝える、フィードバック文化を育むといった"日常の積み重ね"がエンゲージメントの土台になります。
特にマネージャーの役割は重要です。大げさな施策でなく、普段の何気ないコミュニケーション、部下の小さな成功を認める姿勢、困ったときにすぐ相談できる空気づくりといった関わり方が、組織全体のエンゲージメントレベルを底上げします。
「誰と組むか」で決まる。巻き込み力と社内推進チームの作り方
エンゲージメント向上は、人事だけで成し遂げられるものではありません。むしろ、人事が単独で抱え込もうとすると、途中で行き詰まるリスクが高まります。経営層、管理職、現場リーダーを早い段階から巻き込んだ推進体制を整えることがカギです。
経営層には、エンゲージメントが業績に直結することをロジックで訴え、リーダーシップを発揮してもらいます。管理職には、現場に寄り添いながら施策を日常に根付かせる役割を担ってもらい、現場社員には、小さな成功体験を積み重ね、仲間を巻き込む力を発揮してもらいます。この三層を有機的につなげていくことが、組織全体を動かす推進力になります。
成功体験を単発で終わらせず、仕組み化して横展開していく視点も重要です。"うまくいった事例"を可視化し、他部門にも広げていくことで、エンゲージメント向上の好循環を生み出せます。
従業員の行動を促すアプリ「WellWa」とは

こうしたエンゲージメント施策の推進を後押しするツールとして、キリンが提供するアプリ"WellWa(ウェルワ)があります。WellWaは、部署対抗チャレンジやランキング機能など、全社員が個人でもチームでも楽しめる仕掛けを多数搭載しています。ゲーム感覚で自然に健康行動やコミュニケーション促進ができ、組織に前向きな一体感をもたらします。
また、健康行動で貯めたポイントをキリンの商品と交換できる「食の福利厚生」制度も導入されています。楽しみながら継続できる仕組みが、社員のモチベーションを高め、施策の定着をサポートします。
実践ポイント|エンゲージメント向上施策を成功させる3つのステップ
- 現状把握と課題特定:定量・定性両面から社員の声を集め、本質的な課題を特定する
- 全員参加型の推進体制構築:経営層・管理職・現場を巻き込み、三位一体で推進する
- 小さな成功の積み重ねと仕組み化:日常の中で実践できる小さな行動変容を促し、成功事例を横展開する
エンゲージメント施策に絶対的な正解はありません。組織ごとに課題も文化も異なるため、試行錯誤しながら"自社に合った形"を見つけていくことが必要です。表面的な数値だけに惑わされず、本質的な課題を見極め、焦らず諦めず、小さな変化を積み重ねる。この地道な努力によって、確かな組織の変化と、社員一人ひとりのいきいきとした働き方が実現するでしょう。