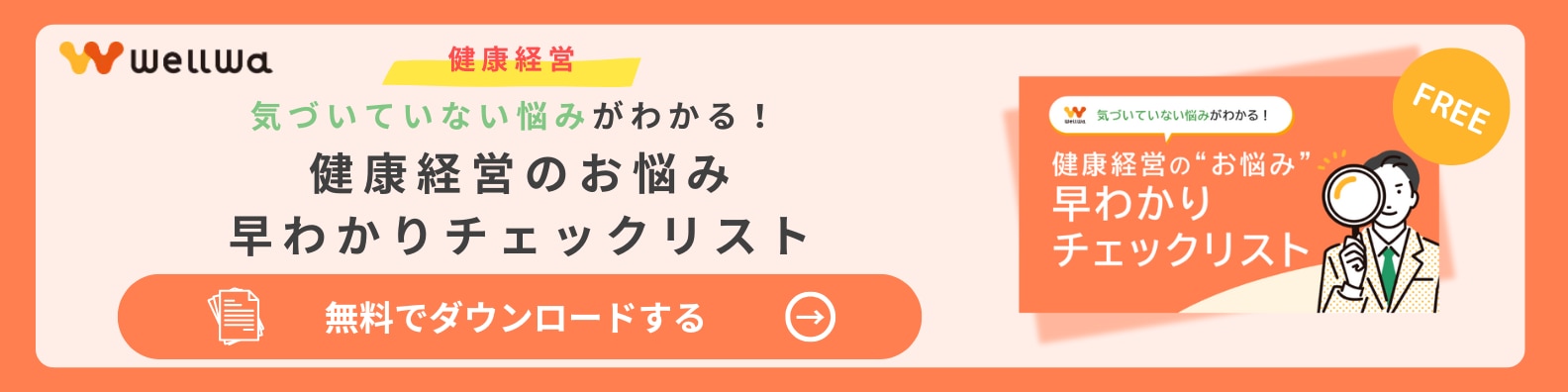従業員の健康課題は「見えないリスク」?健康経営と人的資本経営で高める企業価値
リモートワークや働き方の多様化が進むいま、従業員の健康リスクは目に見えにくく、かつ複雑化しています。
「運動不足や孤立感、睡眠障害、メンタル不調」これらは企業にとって生産性の低下や人財流出を招く“隠れたリスク”です。
本記事では、健康課題が経営に与える影響と、企業が取るべき実践的な対策を解説します。
目次[非表示]
- 1.なぜ今、健康経営が企業に求められているのか?経営課題としての従業員の健康
- 2.企業が直面する健康課題の全体像と人的資本経営への影響
- 2.1.身体的健康問題:生活習慣病・腰痛・睡眠障害など
- 2.2.メンタルヘルス問題:ストレス・不安・うつ状態
- 2.3.デジタル・リモート時代特有の課題:孤立・眼精疲労・情報過多
- 2.4.健康課題の複雑化・慢性化による見落としのリスク
- 3.健康課題の「見えにくさ」が企業にもたらす3つの経営リスク
- 4.健康課題を「可視化・定量化」するメリットと実践方法
- 5.実践事例に学ぶ:企業が取り組むべき健康課題への対応策
- 5.1.ケース1 メンタル不調の早期発見と相談体制の整備
- 5.2.ケース2 生活習慣改善を促す健康支援プログラム
- 5.3.ケース3 リモートワーク社員向けの健康管理施策
- 5.4.成功の鍵は「従業員の自発的参加と信頼関係構築」
- 6.WellWaに学ぶ「楽しさ」で広げるチーム・ウェルビーイングの可能性
- 6.1.WellWaとは何か? ― 健康を「自分ごと」に変える新発想のアプリ
- 6.2.WellWaの3大特徴:「たのしい健康」「おいしい健康」「健康のROI」
- 6.3.導入メリットと活用法:WellWaがもたらす組織変革のリアル
- 7.まとめ
なぜ今、健康経営が企業に求められているのか?経営課題としての従業員の健康
近年、企業を取り巻く環境は大きく変化し、従業員の健康が単なる福利厚生ではなく、経営課題として重要視されています。特に、リモートワークの普及や働き方の多様化が進む中で、企業が従業員の健康に戦略的に取り組む健康経営が注目されています。
働き方の多様化で顕在化する新たな健康リスク
リモートワークやフレックスタイム制、副業の解禁といった働き方の多様化により、従業員の自由度は高まった一方で、健康管理の難しさという新たなリスクが浮き彫りになっています。
オフィス勤務であれば自然と確保できていた「運動機会」や「他者との交流」が減少し、運動不足・孤立感・生活リズムの乱れといった課題が顕在化。企業にとっては、従業員の健康状態が見えにくくなることで、潜在的なリスクの把握が困難になっています。
健康経営が注目される社会的背景と政策動向
このような課題に対し、経済産業省は「健康経営」という概念を推進しています。これは、従業員の健康を経営視点でとらえ、戦略的に取り組むことで企業価値向上につなげる考え方です。
「健康経営優良法人認定制度」の導入や、企業の人的資本情報開示への政策誘導など、国としても企業の健康施策への取り組みを後押しする動きが加速しています。
健康経営は単なる福利厚生から、経営戦略に組み込むべき領域へと格上げされつつあります。
健康課題がもたらす“見えない損失”
従業員の健康課題が放置された場合、最も大きな影響は「生産性の低下」です。欠勤や休職といった直接的な損失だけでなく、「プレゼンティーズム(出勤しているものの、生産性が低い状態)」という見えにくい損失も深刻です。
ある調査によれば、プレゼンティーズムによる経済損失は、アブセンティーズム(欠勤)よりも数倍の規模になるといわれています。日々の体調不良やストレスが蓄積することで、企業全体のアウトプットや雰囲気に目に見えないダメージを与えているのです。
従業員の健康課題は、経営課題の根幹に位置すると言っても過言ではありません。
企業が直面する健康課題の全体像と人的資本経営への影響
身体的健康問題:生活習慣病・腰痛・睡眠障害など
多くの企業で見られるのが、身体的な不調の慢性化です。長時間労働や運動不足、栄養バランスの乱れによって、生活習慣病や肥満、腰痛、肩こりといった問題が蔓延しています。
特に座りっぱなしのデスクワークでは、筋骨格系への影響が大きく、生産性低下の要因にもなります。さらに、睡眠不足や質の低い睡眠は、集中力や判断力の低下につながり、事故やミスのリスクを高める要素ともなっています。
メンタルヘルス問題:ストレス・不安・うつ状態
次に深刻なのがメンタルヘルスの問題です。人間関係、業務負荷、将来への不安、家庭と仕事の両立ストレスなど、さまざまな要因が複雑に絡み合い、うつ症状や不安障害、燃え尽き症候群といった症状が増加しています。
こうした問題は、本人がSOSを発信しづらく、周囲が気づきにくいことから、対応が遅れやすい傾向にあります。メンタル不調による休職や離職は、本人のみならずチーム全体に波及するリスクをはらんでいます。
デジタル・リモート時代特有の課題:孤立・眼精疲労・情報過多
リモートワークの常態化に伴い、対面での雑談やちょっとした相談機会の消失がもたらす「孤立感」も重要な課題です。特に若手社員においては、成長実感や帰属意識の欠如という形で現れやすくなっています。
また、オンライン会議の連続や画面の長時間視聴による眼精疲労・頭痛・脳疲労も無視できない問題です。さらに、チャット・メール・通知などによる情報過多・常時接続ストレスも、メンタルとフィジカルの両面に影響を与えています。
健康課題の複雑化・慢性化による見落としのリスク
現代の健康課題は、単一ではなく「複雑に絡み合い、かつ慢性的に続く」という特性があります。例えば、ストレスが睡眠を妨げ、それがさらに身体的疲労を招き、結果としてモチベーションの低下やミスの増加へとつながる……といったように、複数の課題が連鎖的に悪化していくケースが珍しくありません。
このような複雑性を前にすると、企業は「健康診断だけでは把握できない」「定量化が難しい」といった壁に直面します。だからこそ、全体像を俯瞰し、相互に関連する課題を早期に捉える視点が不可欠です。
健康課題の「見えにくさ」が企業にもたらす3つの経営リスク
パフォーマンスの低下とプレゼンティーズムの増加
健康課題の「見えにくさ」が最も深刻な影響を及ぼすのは、生産性の低下です。社員が不調を抱えたまま働き続ける「プレゼンティーズム」は、企業にとって気づかぬまま損失を拡大させる隠れたリスクとなります。
不眠や肩こり、メンタル不調など、一見業務に直接関係なさそうな問題が、実はパフォーマンスを大きく左右することは少なくありません。従業員一人ひとりの状態に目を向ける姿勢こそが、全体のアウトプットを押し上げる鍵となります。
離職・人財流出の要因としての健康課題
健康問題は、離職の誘因にもなり得ます。不調が長引いて相談できず、フォローがないままに退職を選ぶケースも存在します。特にメンタルヘルス関連では、表面化する前に深刻化し、復帰困難な状況に至ることもあります。
中長期的に見れば、社員の健康を守ることは優秀な人財の定着と組織力の維持に直結する投資です。
健康配慮の欠如が企業ブランドを毀損する可能性
近年では、従業員に対する企業の姿勢が採用や取引、レピュテーションに影響する時代です。社内外から「従業員を大切にしない会社」と見られることは、ブランディングや採用競争力に深刻なダメージを与えかねません。
逆に言えば、健康経営に真摯に取り組む姿勢は、「信頼できる企業」としてのブランド強化につながるのです。
健康課題を「可視化・定量化」するメリットと実践方法
健康診断・ストレスチェックなどのデータ活用
健康状態の可視化には、既存の仕組みを活用するのが現実的です。健康診断結果やストレスチェックの集計を活用することで、組織全体の健康傾向を把握する第一歩が踏み出せます。
ただし、個人情報の取り扱いには十分な配慮が必要です。統計的に処理されたデータを集団単位で活用することが前提となります。
組織・部署ごとの健康傾向を数値で把握する手法
部署別の健康リスクやエンゲージメントの傾向を数値で把握することにより、ピンポイントでの施策設計が可能になります。たとえば「A部署では運動不足が顕著」「B部署ではメンタル不調が多い」などの傾向がわかれば、打ち手を最適化できます。
このような分析には、簡易サーベイやアプリ活用による自動集計が効果的です。
定量化によって「属人的対応」から脱却する効果
定量データを活用すれば、「あの人は元気そう」「この部署は雰囲気が良い」といった主観的な判断から脱却できます。これにより、客観的な健康経営の意思決定が可能になります。
定量化は、「やっているつもり」の施策から脱却し、経営視点での施策評価と改善の循環を生み出す起点となります。
実践事例に学ぶ:企業が取り組むべき健康課題への対応策
ケース1 メンタル不調の早期発見と相談体制の整備
あるIT企業では、週次の簡易ストレスチェックと社内チャット相談窓口の導入により、メンタル不調の早期発見と予防に成功しました。相談件数が可視化されたことで、人事部の対応リソースも最適化できたといいます。
ケース2 生活習慣改善を促す健康支援プログラム
製造業の企業では、食事・運動・睡眠のセルフチェックとフィードバック機能を持つアプリを活用し、生活習慣病予備群の減少につなげました。
「指導」ではなく「気づき」を与える設計が、従業員の自律的行動変容を促す要因となっています。
ケース3 リモートワーク社員向けの健康管理施策
フルリモート体制を取る企業では、「歩数・水分補給・昼食報告などをオンラインで共有するチャレンジ型イベント」を実施。部署を超えたつながりが生まれ、健康への意識とエンゲージメントの向上が見られました。
成功の鍵は「従業員の自発的参加と信頼関係構築」
いずれのケースにも共通する成功要因は、「強制しない」「楽しく参加できる仕掛けがある」「信頼されている制度設計」です。トップダウンではなく、従業員自らの意思で関われる健康施策こそが、継続と成果を生み出す鍵となります。
WellWaに学ぶ「楽しさ」で広げるチーム・ウェルビーイングの可能性
WellWaとは何か? ― 健康を「自分ごと」に変える新発想のアプリ
WellWa(ウェルワ)は、健康経営を「たのしく・おいしく・つながる」体験に変えることで、従業員の自発的参加とエンゲージメントを高める健康アプリです。単なるヘルスチェックではなく、日常の中での行動変容を促す工夫が随所に施されています。
WellWaの3大特徴:「たのしい健康」「おいしい健康」「健康のROI」
- つながり、楽しむ健康アクション:部署対抗戦、ランキング、スタンプ等、ゲーム感覚で取り組める要素が満載です。
- 嬉しい、おいしい健康アクション:健康行動に応じてポイントを貯め、飲食物と交換可能。行動変容のインセンティブとして機能します。
- 健康のROI:25問のサーベイにより、健康施策の効果を「見える化」し、人的資本開示にも応用可能です。
導入メリットと活用法:WellWaがもたらす組織変革のリアル
WellWa導入企業では、「部署間の関係性が良くなった」「健康行動が習慣化した」「施策の効果が数値で見えるようになった」といったポジティブな変化が報告されています。
健康が「会社の文化」として根付いた時、はじめて人的資本経営の土台が完成するのです。
まとめ
従業員の健康課題は、いまや経営課題の中核をなす存在です。身体的・精神的な不調、リモートワークによる孤立など、企業を取り巻くリスクは複雑化・潜在化しています。しかし、これらを可視化・定量化し、楽しさと信頼を持って対処すれば、企業文化を根本から変えるきっかけになります。
WellWaのようなツールを活用し、「楽しく健康に働ける職場」を組織の当たり前にすることこそが、持続可能な健康経営、そして人的資本経営への第一歩です。従業員の健康への投資は、企業の生産性向上、人財定着、そして企業ブランドの強化に直結します。