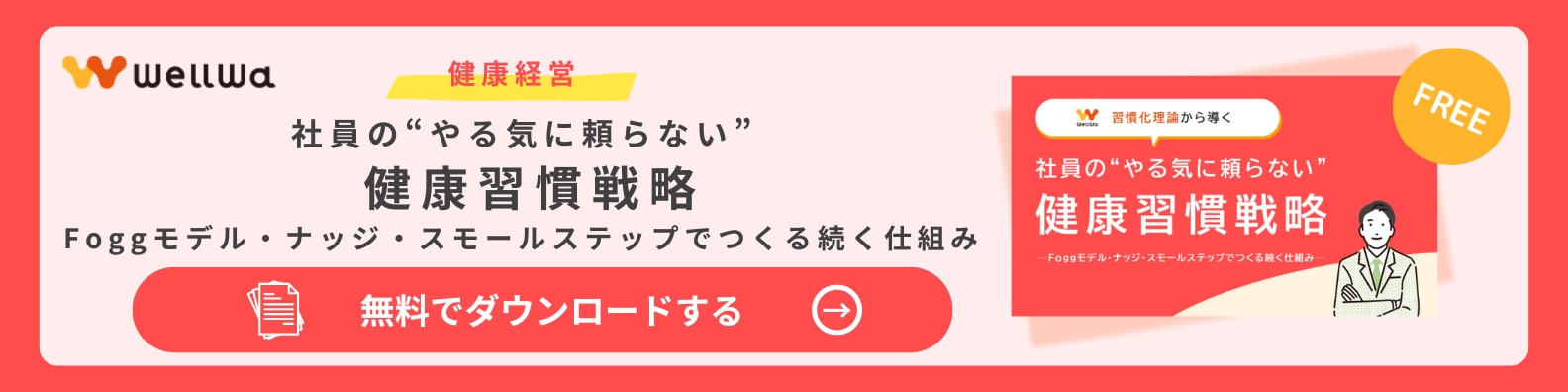社員が自然と続ける!職場で定着する5つの健康習慣
働き方改革やウェルビーイングが注目される今、企業にとって欠かせないのが「職場での健康習慣」です。社員が自然と続けられる習慣づくりは、生活習慣病の予防や生産性向上につながるだけでなく、組織全体のエンゲージメント強化にも直結します。
本記事では、健康経営を成功させるために企業が取り入れるべき5つの健康習慣と、定着させるための仕組みづくりをわかりやすく解説します。
目次[非表示]
- 1.なぜ「職場の健康習慣」が今、求められているのか
- 2.健康習慣を“定着”させるための3つの前提条件
- 2.1.「やらされ感」を排除する仕組み
- 2.2.継続しやすい“心理的ハードルの低さ”
- 2.3.個人任せにしない「組織の関与」
- 3.社員が自発的に続けたくなる!職場で実践すべき5つの健康習慣
- 3.1.朝のストレッチ習慣化:1日をスッキリ始める環境づくり
- 3.2.歩くミーティング:運動×コミュニケーションの相乗効果
- 3.3.スタンディングデスク活用:座りっぱなしを防ぐ工夫
- 3.4.健康ドリンクの設置:“選択肢”から変える食習慣
- 3.5.マインドフルネス時間の導入:メンタルのセルフケア支援
- 4.チームで取り組む健康習慣の新常識:WellWaが生み出す職場のウェルビーイング
- 4.1.“やらされ感”を払拭する共創型アプローチ
- 4.2.「たのしい健康」イベントでチームの一体感を育む
- 4.3.「おいしい健康」×福利厚生で継続意欲を向上
- 4.4.健康のROIを可視化するサーベイと分析モデル
- 5.健康習慣を社内に根づかせるための導入・運用ステップ
- 5.1.Step1:課題とニーズの明確化
- 5.2.Step2:小さく始める→効果検証のサイクル化
- 5.3.Step3:健康リーダー・巻き込み型仕組みの活用
- 5.4.Step4:継続を後押しする評価・インセンティブ設計
- 6.まとめ:小さな健康習慣が大きな成果を生む理由
なぜ「職場の健康習慣」が今、求められているのか
働き方改革とウェルビーイングの潮流
昨今の働き方改革の流れとともに、企業が重視すべきテーマとして注目を集めているのが「ウェルビーイング」です。これは、従業員が身体的・精神的・社会的に良好な状態であることを目指す考え方であり、単なる“働きやすさ”の提供にとどまらず、“働きがい”や“人生の充実”にも踏み込む視点が求められています。
こうした潮流の中で、健康管理は本人の責任だけではなく、職場全体で支えるものへと変化しています。中長期的な企業の成長には、従業員一人ひとりが健康を習慣化し、自然に良い行動を選べる職場づくりが不可欠なのです。
健康経営が注目される理由とは
経済産業省が推進する「健康経営」は、従業員の健康を重要な経営資源と位置づけ、戦略的に投資する考え方です。いまや多くの企業が健康経営優良法人認定を目指し、健康施策の充実に取り組んでいます。
その中で明確になってきたのが、“一過性の施策では効果が出にくい”という事実です。健康診断や講習会などの単発的な取り組みでは、従業員の行動に変化は生まれません。鍵を握るのは、日常に根づく「健康習慣」の定着です。
メンタル・フィジカル不調の放置がもたらす損失
企業が健康習慣を重視する背景には、健康問題がもたらす損失の大きさもあります。欠勤や休職といったアブセンティーズム(不在による損失)だけでなく、体調が万全でないまま働くプレゼンティーズム(生産性の低下)による影響も深刻です。
さらに、メンタル面の不調は本人だけでなくチーム全体のモチベーションや士気を下げるリスクも抱えています。こうした状況を防ぐためにも、早期の予防と日々の習慣による維持管理が重要といえるでしょう。
健康習慣を“定着”させるための3つの前提条件
「やらされ感」を排除する仕組み
健康習慣が続かない最大の原因は、“やらされている感”にあります。会社からの指示や義務感によって始めた取り組みは、形骸化しやすく、自主性が育ちません。
そこで必要なのが、楽しさや共感を伴った仕掛けです。例えば、ポイント制や部署対抗戦などのゲーム性を取り入れたり、実際に参加している社員の声を共有したりすることで、「やってみたい」「続けたい」という気持ちを生み出すことが可能です。
継続しやすい“心理的ハードルの低さ”
「毎日30分の運動をしましょう」と言われても、忙しいビジネスパーソンにとっては大きな負担です。重要なのは、誰でも無理なく始められる“入り口の低さ”です。
「階段を使う」「水をこまめに飲む」「昼食の写真を共有する」といったような、5秒でできる健康行動を促すことで、習慣化へのハードルを大幅に下げることができます。こうした“小さな行動”の積み重ねが、大きな成果につながります。
個人任せにしない「組織の関与」
習慣を個人任せにしていては、モチベーションの維持が難しくなります。そこで重要になるのが、組織としての関与と支援体制です。
例えば、上司が率先して健康活動に参加したり、社内コミュニケーションツールで健康行動を共有・称賛する文化を育てたりといった仕組みが、「一人で頑張らない」環境をつくります。組織全体で支え合うことで、健康習慣は定着しやすくなります。
社員が自発的に続けたくなる!職場で実践すべき5つの健康習慣
朝のストレッチ習慣化:1日をスッキリ始める環境づくり
朝の始業前やチームミーティングの冒頭に簡単なストレッチを取り入れることで、身体と気持ちのスイッチを切り替えることができます。座りっぱなしになりがちなオフィスワークでは、血行促進や集中力アップに効果的です。動画や社内インストラクターを活用し、習慣化しやすい仕組み作りが鍵となります。
歩くミーティング:運動×コミュニケーションの相乗効果
「ウォーキング・ミーティング」は、近くの公園や社内の廊下を歩きながら行う打ち合わせ形式です。歩くことで思考が柔軟になり、アイデアが出やすくなる効果も報告されています。気分転換にもなり、実用性の高い健康習慣といえるでしょう。
厚生労働省の「健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023」では、生活習慣病予防のために「1日60分以上の身体活動(1日約8,000歩)」を行うことを推奨しています。
出典:厚生労働省 健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023
職場での「歩くミーティング」は、日中の活動量を無理なく増やす良い機会となります。
スタンディングデスク活用:座りっぱなしを防ぐ工夫
長時間の座りっぱなしは健康リスクの温床です。一部でもスタンディングデスクを導入するだけでも、姿勢改善や集中力向上につながります。導入コストを抑えるためには、昇降式の台を共用エリアに設置するなど、柔軟な選択肢を設ける工夫も有効です。
健康ドリンクの設置:“選択肢”から変える食習慣
オフィスの自販機や冷蔵庫に無糖のお茶やミネラルウォーター、プロテイン飲料などの「健康ドリンク」を常備することで、日々の選択行動にポジティブな影響を与えます。
“何を飲むか”の選択が変わることで、血糖値や睡眠の質にも好影響を与えるケースがあります。
マインドフルネス時間の導入:メンタルのセルフケア支援
昼休みや業務後に、5分程度の呼吸瞑想やマインドフルネス動画を視聴する時間を設けることで、ストレス軽減や集中力回復が期待できます。特にリモートワーク下では、心の整理や切り替えの時間が不足しがち。その意味でも、“立ち止まる時間”を意図的に組み込むことは、組織にとって大きな価値を持ちます。
チームで取り組む健康習慣の新常識:WellWaが生み出す職場のウェルビーイング
“やらされ感”を払拭する共創型アプローチ
健康習慣の定着には、従業員の主体性と楽しさが欠かせません。WellWaは、部署単位で目標を決めたり、イベントを一緒に楽しんだりする仕組みにより、チーム全体で取り組む文化を醸成します。
「たのしい健康」イベントでチームの一体感を育む
歩数・睡眠・食事報告などを通じた部署対抗イベントやポイント獲得キャンペーンにより、自然と健康行動とコミュニケーションが融合し、日常的な一体感が生まれます。
「おいしい健康」×福利厚生で継続意欲を向上
健康行動に応じてポイントを獲得し、社内カフェや提携店の商品と交換できる仕組みは、モチベーション維持に直結します。「頑張った分だけ得になる」という構造が、無理なく継続できる習慣づくりを後押しします。
健康のROIを可視化するサーベイと分析モデル
WellWaでは、25問の独自サーベイによって健康指標の投資対効果(ROI)を数値化する機能を搭載。経営層への説得材料としても有用で、人的資本開示にもつながる設計となっています。
健康習慣を社内に根づかせるための導入・運用ステップ
Step1:課題とニーズの明確化
まずは「どの健康課題に困っているのか」「何なら続けられそうか」という現場の声を集めることが出発点です。社内アンケートや1on1ミーティングを通じ、課題の“見える化”と施策ニーズの把握が鍵になります。
Step2:小さく始める→効果検証のサイクル化
いきなり全社導入するのではなく、一部署や有志メンバーでの小規模な試行から始めるのが効果的です。トライアル後には効果を可視化し、次の展開につなげるPDCAサイクルが重要です。
Step3:健康リーダー・巻き込み型仕組みの活用
各部署に「健康推進リーダー」を配置するなど、現場主導の取り組みが成功の鍵です。また、WellWaのように自然に巻き込める仕組みがあれば、従業員の参加率も高まります。
Step4:継続を後押しする評価・インセンティブ設計
健康習慣が続くかどうかは、「褒められる・認められる」経験があるかにかかっています。
達成度に応じたポイントや社内表彰、福利厚生との連携が継続の原動力となります。
まとめ:小さな健康習慣が大きな成果を生む理由
健康習慣が組織文化に与える長期的影響
健康習慣の定着は、単なる施策にとどまらず、「社員を大切にする会社」という文化の礎をつくります。これは、エンゲージメントや定着率、採用力の向上にもつながる中長期的な経営投資です。
今すぐ始めるべき理由と、最初の一歩
健康習慣は、一人の小さな行動からでも始められます。「昼休みに一緒にストレッチしませんか?」という呼びかけからでも構いません。 “始めやすく、続けやすい”環境づくりが、未来の職場の健全性を形づくる第一歩となるのです。