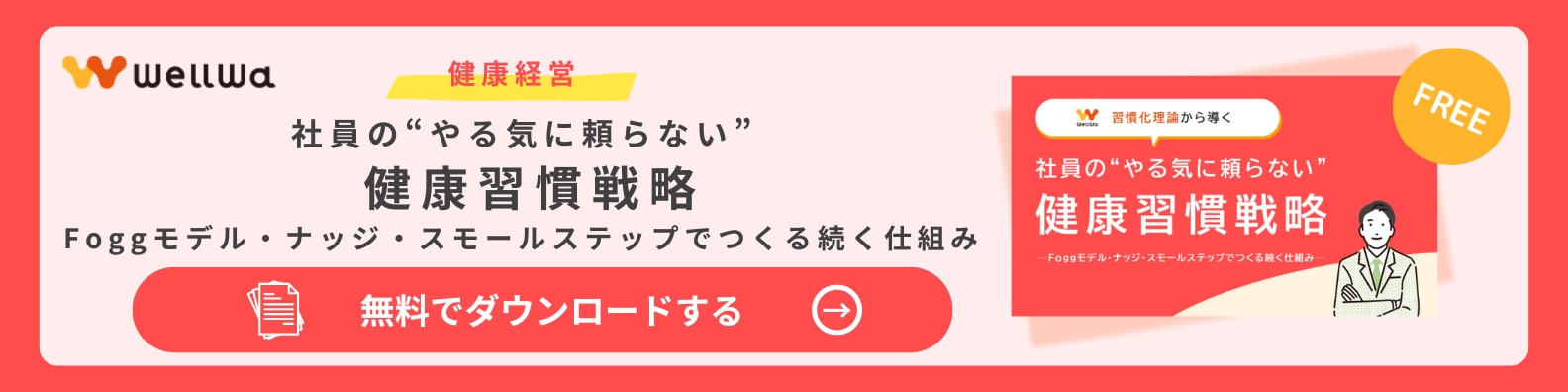ヘルスリテラシーが高い人の特徴とは?健康意識の高い人がしている5つの習慣
本記事では、健康意識の高い人に共通する5つの習慣と企業が注目する理由をわかりやすく解説します。
目次[非表示]
- 1.ヘルスリテラシーとは?企業でも注目される理由
- 2.ヘルスリテラシーが高い人に共通する5つの特徴
- 2.1.1. 「健康でありたい」という前向きな意識が行動の原点になっている
- 2.2.2. 健康情報を鵜呑みにせず、正確に取捨選択できる
- 2.3.3. 自分の体調・数値・行動に常に“気づき”を持っている
- 2.4.4. 小さな健康習慣を日常に無理なく組み込んでいる
- 2.5.5. 必要に応じて医療機関や専門家を正しく活用できる
- 3.ヘルスリテラシーが高い人が実践している行動パターン
- 3.1.朝・昼・夜の生活リズムを大切にしている
- 3.2.情報だけでなく“行動”にまで落とし込んでいる
- 3.3.食事・運動・睡眠のバランスをデータで管理している
- 3.4.定期的な振り返り・セルフチェックをしている
- 3.5.SNSや職場で健康を話題にし、共有・巻き込みをしている
- 4.なぜヘルスリテラシーの高い社員は組織を強くするのか
- 5.社員のヘルスリテラシーを高めるための職場の仕掛け
- 5.1.健康情報を“自分ごと化”させるコミュニケーション
- 5.2.可視化とフィードバックで日々の行動に気づきを与える
- 5.3.管理職や健康リーダーによるポジティブモデルの発信
- 5.4.健康意識を育てる“きっかけづくり”の工夫
- 6.WellWaで“気づく・学ぶ・続ける”健康行動を習慣に
- 7.まとめ:自分とチームを変えるのは“正しく知る力”から
ヘルスリテラシーとは?企業でも注目される理由
健康情報を「理解し、判断し、活用できる力」
「ヘルスリテラシー」とは、健康に関する情報を適切に読み取り、判断し、日常に活かす力を指します。
単に正しく理解するだけでなく、実際の行動につなげられる力が重要です。
WHOでも「健康情報にアクセスし、理解し、使える能力」と、明確に定義されており、近年ますます注目が高まっています。
ヘルスリテラシーと医療・栄養・行動科学との関係
この能力は、医療リテラシー(受診行動や医薬品活用)や栄養リテラシー(食の選択)、行動科学(習慣形成)と密接に関係しています。
たとえば、「血圧が高い」と知ったあとに減塩や運動を取り入れられるかどうかは、ヘルスリテラシーのレベルによって大きく左右されます。
健康経営・人的資本経営で注目される背景
企業が「ヘルスリテラシー」に注目するのは、社員の健康が組織の生産性に直結するためです。
とくに人的資本開示が義務化されつつある今、健康を“自己管理できる力”として高める支援は、経営戦略の一部になりつつあります。
ヘルスリテラシーが高い人に共通する5つの特徴
1. 「健康でありたい」という前向きな意識が行動の原点になっている
まず大前提として、ヘルスリテラシーが高い人は、健康をポジティブに捉えている傾向があります。
“病気にならないように”ではなく、“よりよく働き、人生を充実させるために”健康を重視する思考が強く、その意識が日々の行動に自然と反映されています。
2. 健康情報を鵜呑みにせず、正確に取捨選択できる
インターネットやSNSで健康情報があふれる今、正しく見極める力=情報リテラシーも重要です。
信頼できる情報源を選び、エビデンスベースで判断する姿勢は、健康施策の効果を高める上でも欠かせません。
3. 自分の体調・数値・行動に常に“気づき”を持っている
ヘルスリテラシーが高い人は、「最近眠れていない」「歩数が減っている」などの自覚に敏感です。
これは“記録する習慣”や“内省する時間”によって身につきます。
体調の変化に気づくことで、早めの対処や習慣改善にもつながります。
4. 小さな健康習慣を日常に無理なく組み込んでいる
いきなり激しい運動をするのではなく、「階段を使う」「昼間に日光を浴びる」など小さな工夫を取り入れているのが、ヘルスリテラシーが高い人の特徴でもあります。
こうした人は健康習慣に対するハードルが低く、習慣の継続率が高い傾向にあります。
5. 必要に応じて医療機関や専門家を正しく活用できる
不調を我慢せず、早期に適切なサポートを受ける行動もヘルスリテラシーの一環として考えます。
セルフケアと医療・制度のバランスを理解し、無理せず相談・受診ができるという点も重要です。
ヘルスリテラシーが高い人が実践している行動パターン
朝・昼・夜の生活リズムを大切にしている
生活リズムを整えることが、体調や集中力に与える影響を理解しています。
特に、「朝食をとる」「昼休みに外を歩く」「夜はスマホを控える」など、時間帯ごとのセルフケアが定着しています。
情報だけでなく“行動”にまで落とし込んでいる
健康知識を得ただけで満足せず、「実際に試す」「実行に移す」ことを大切にしているのが特徴です。
たとえば、睡眠の重要性を学んだら、翌日から「寝る前のスマホを控える」といった行動をすぐに実行しています。
食事・運動・睡眠のバランスをデータで管理している
アプリやウェアラブル端末を活用し、健康行動を“可視化”することが習慣になっています。
日々の歩数・睡眠時間・体重などを記録し、生活習慣の変化に早く気づける工夫をしているのです。
定期的な振り返り・セルフチェックをしている
ヘルスリテラシーが高い人は、健康状態や行動について定期的な振り返りを習慣化しています。
たとえば、週末に歩数や睡眠の記録を見直したり、健康診断の結果を元に次のアクションを決めるなど、“振り返って改善する”ことを自然に実行しています。
SNSや職場で健康を話題にし、共有・巻き込みをしている
健康行動をポジティブに発信することも、ヘルスリテラシーの高い人に共通する特徴です。
SNSでのシェアや、職場内での雑談を通じて、周囲を巻き込む力を持ち、チーム全体の意識向上に貢献しています。
なぜヘルスリテラシーの高い社員は組織を強くするのか
プレゼンティーズムの予防につながる
ヘルスリテラシーの高い社員は、自分の体調変化に敏感で早期に対応できるため、不調を抱えながら働く“プレゼンティーズム”のリスクを下げることができます。
結果として、業務パフォーマンスや集中力の低下を防ぎ、全体の生産性向上に貢献します。
健康行動がチーム全体の文化に波及する
個人の前向きな健康行動は、チーム内に波及しやすいのも特徴です。
たとえば、ランチ後の軽いストレッチや歩数記録への取り組みが“当たり前”になると、健康意識の高い組織文化が自然に醸成されます。
自立した人材が増えることで健康経営が定着する
ヘルスリテラシーが高い社員は、企業からの指示を待たずに自分の健康管理を自律的に行える人材です。
こうした社員が増えることで、健康施策の“義務感”がなくなり、健康経営そのものが自然と定着する土壌が整います。
社員のヘルスリテラシーを高めるための職場の仕掛け
健康情報を“自分ごと化”させるコミュニケーション
健康情報を一方的に伝えるだけでは、社員の行動は変わりません。
「それが自分にどう関係するのか」が納得できるストーリーや事例を交えることで、“自分ごと化”のスイッチを入れることが重要です。
可視化とフィードバックで日々の行動に気づきを与える
歩数・睡眠・食事などの行動を“見える化”し、定期的なフィードバックを行うことで、習慣の変化に気づきやすくなります。
数値と感覚のギャップを埋めることで、自己理解が深まり、行動変容のきっかけになります。
管理職や健康リーダーによるポジティブモデルの発信
上司やロールモデルとなる社員が積極的に健康行動を発信することで、組織全体のムードを変えることができます。
Slackや社内報での共有、チームでの「歩数チャレンジ」参加など、“自分もやってみよう”と思える雰囲気づくりがカギとなります。
健康意識を育てる“きっかけづくり”の工夫
社員一人ひとりが、健康の重要性を実感できるようなエピソード・体験型イベント・セミナーを通じて、内発的な動機を引き出します。
知識提供よりも、感情に訴える“気づきの体験”がリテラシー向上には効果的です。
WellWaで“気づく・学ぶ・続ける”健康行動を習慣に
歩数・睡眠・飲酒などのデータを記録して“気づく”
WellWaでは、歩数や睡眠時間、飲酒の量など日々の行動が自動で記録・可視化され、健康状態の変化に気づくきっかけが得られます。
これにより、「今日は歩数が少なかったから帰りに一駅分歩こう」といった前向きな意識が生まれ、自然と行動が改善されます。
イベントやセミナーで“学び”を自分ごとに変える
チーム対抗イベントや社内セミナーを行うことで、楽しみながら健康について学ぶ機会が提供されます。
単なる情報提供ではなく、“参加する中で理解が深まるよう設計されている”のが特長です。
チームで取り組む仕組みで“続けられる”状態をつくる
スタンプ機能やランキング、ポイント制度によって、「義務感」のない継続支援が可能になります。
健康行動を“組織文化”として定着させるための仕組みとして有効です。
まとめ:自分とチームを変えるのは“正しく知る力”から
ヘルスリテラシーは一人の健康を守るだけではない
ヘルスリテラシーは、社員一人ひとりの行動変容だけでなく、職場全体のエンゲージメントや業績にもつながる原動力となります。
健康について正しく理解し、知識を活用できる社員が多いほど、組織はより強く、しなやかになります。
健康意識とリテラシーの“両輪”が習慣化を支える
知識だけでは行動は変わりません。
「なぜやるか」という目的意識と、「どうやるか」の具体的な知識の両方があることで、初めて健康の習慣化が実現します。
この両輪を回すために、企業は“きっかけ・共感・継続”を意識した支援設計を行うことが重要です。