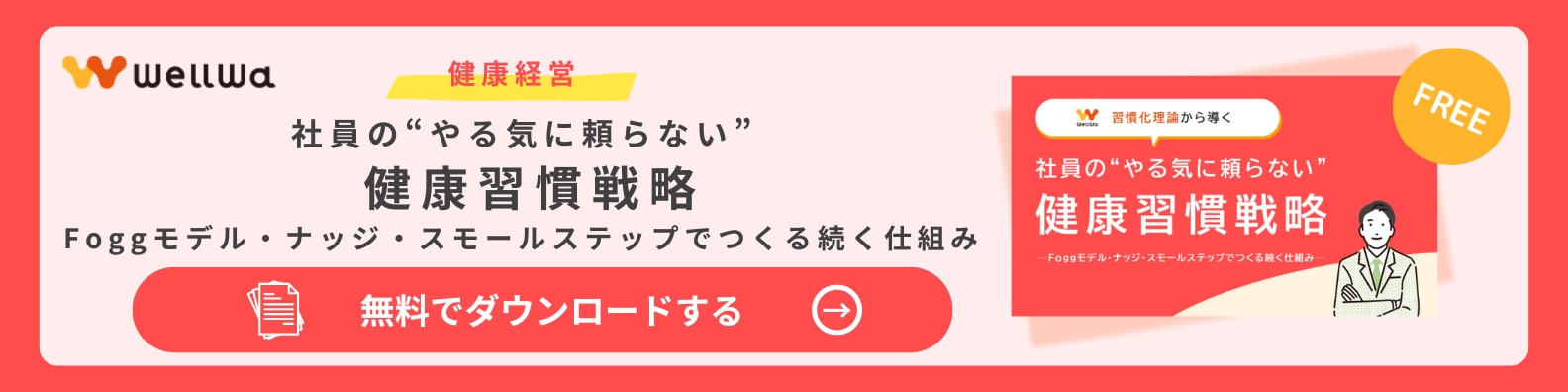従業員のヘルスリテラシーを高めるには?健康意識を育てる習慣と職場の工夫
本記事では、社員のヘルスリテラシーを高めるための習慣づくりと職場でできる具体的な工夫をわかりやすく解説します。
目次[非表示]
- 1.ヘルスリテラシーを高めることがなぜ重要なのか
- 2.健康リテラシーが低い組織で起こる3つの課題
- 3.ヘルスリテラシーを高めるための3つのアプローチ
- 4.社員の意識を育てる!日常に取り入れたい習慣づくり
- 4.1.健康情報を日常の“気づき”に変えるマイクロ学習
- 4.2.ランチタイムや会議前後でできる「ながら教育」
- 4.3.健康に関する自己記録・振り返りの習慣化
- 4.4.職場でできる!ヘルスリテラシー向上を促す環境整備と仕掛け
- 4.5.ポスター・社内チャット・動画活用による情報の視覚化
- 4.6.管理職の巻き込みと“率先する”健康文化の醸成
- 4.7.小さな行動を評価する仕組みとインセンティブ設計
- 5.WellWaを活用したリテラシー向上の実践例
- 6.まとめ:ヘルスリテラシーが根づく組織が成果を生む
ヘルスリテラシーを高めることがなぜ重要なのか
健康意識を高め、自分の健康状態を“正しく理解し活用する力”
ヘルスリテラシーとは、健康に関する情報を理解・評価・活用し、自らの意思で健康行動を選択・実践できる力を意味します。
この力が高ければ、日常のセルフケアや予防行動がスムーズに行えるようになり、健康リスクの低減にもつながります。
働く世代のセルフケア能力が組織成果を左右する時代
現代は、病気になってから治すのではなく、未然に防ぐ「予防」への転換が求められています。
特に働き盛りの世代においては、プレゼンティーイズム(不調を抱えながらの就労)による生産性低下が大きな課題です。
その解決策のひとつが、社員一人ひとりのヘルスリテラシー向上による行動変容です。
健康経営・人的資本開示とのつながり
近年では、企業の人的資本に対する開示要求やESG投資への注目が高まっており、健康経営の推進は経営戦略の一部とされています。
その中で、「ヘルスリテラシーの向上」は、健康投資の効果を最大化する基盤として位置づけられています。
健康リテラシーが低い組織で起こる3つの課題
健診結果の放置と生活習慣病のリスク増加
せっかく受けた健康診断の結果を「見て終わり」にしていませんか?
ヘルスリテラシーが低いと、再検査や生活改善といった次のアクションにつながらず、生活習慣病のリスクが放置されやすくなります。
健康施策の認知不足・やらされ感による形骸化
健康経営の取り組みをしていても、「よくわからないから参加しない」「やらされているだけで意味を感じない」といった声が出て、施策が形骸化してしまうのは、社員の理解度=ヘルスリテラシーの差が要因となっていることが考えられます。
健康情報の誤解がもたらす風評リスク・不安
SNSやネット情報が溢れる今、正しい情報を見極めるリテラシーがなければ、間違った健康法や過剰な不安を助長するリスクもあります。
これにより、職場内での誤解や不信感が広がる恐れも無視できません。
ヘルスリテラシーを高めるための3つのアプローチ
【知識】わかりやすく伝える健康情報の設計
社員が健康知識を理解しやすくするためには、専門用語を避けた「翻訳力」が重要です。
たとえば、図解・チャット形式・アニメーション動画などを活用すると、「読むのが面倒」「意味がわからない」といった心理的ハードルが下がります。
【態度】自分ごと化させるエンゲージメントの工夫
「健康は個人の責任」という意識から一歩進めて、「自分の健康がチームや会社にも良い影響を与える」と実感できるようにすることが大切です。
そのためには、チーム(部署)単位で参加するワークショップや健康イベントなどの“体験型アプローチ”が有効です。
【行動】気づきと実践につなげるフィードバックの仕掛け
たとえば、歩数や睡眠時間を可視化し、「今週は先週より多く歩けた」などのポジティブなフィードバックを定期的に受けられる仕組みがあると、継続的な行動変容に結びつきます。
“気づき→行動→習慣化”の流れが肝です。
社員の意識を育てる!日常に取り入れたい習慣づくり
健康情報を日常の“気づき”に変えるマイクロ学習
長文の資料や研修よりも、「1分で読める」「短くてわかりやすい」コンテンツが日々の気づきを促します。
健康に関する豆知識を朝のメールや社内チャットで配信するだけでも、「知らなかった」「やってみよう」と思える行動のきっかけになります。
ランチタイムや会議前後でできる「ながら教育」
まとまった時間を取らなくても、業務の合間を活用することで学習の定着は可能です。
たとえば、ランチタイムに啓発動画を流したり、会議冒頭に「今日の健康クイズ」を実施すると、リテラシー向上が“日常の一部”になります。
健康に関する自己記録・振り返りの習慣化
行動変容には、「自分を知ること」=内省の時間が欠かせません。
歩数・睡眠・体調などの自己記録を日常的に行い、「昨日の自分」と比較できる仕組みを取り入れることで、自然と健康への関心が高まり、リテラシーも育まれます。
職場でできる!ヘルスリテラシー向上を促す環境整備と仕掛け
ポスター・社内チャット・動画活用による情報の視覚化
ヘルスリテラシー向上には、繰り返しの情報接触と視覚的な理解がカギとなります。
ポスターの掲出やデジタルサイネージ、社内チャットでの動画共有など、“見えるところにある”設計で、社員の記憶に残る健康情報を発信しましょう。
管理職の巻き込みと“率先する”健康文化の醸成
トップや管理職が率先して健康的な行動を見せることで、「健康につながる行動は許容されている」という安心感と共感が広がります。
部署単位で健康活動を共有したり、「○○部長も実践している」という情報が浸透すると、社員の態度も変化しやすくなります。
小さな行動を評価する仕組みとインセンティブ設計
ヘルスリテラシーは、“実際の行動”に反映することで初めて効果を発揮します。
そのため、「歩数記録」「健康セミナー参加」など小さなアクションに対してポイントや評価が得られる仕組みを用意することで、社員の継続意欲が高まります。
WellWaを活用したリテラシー向上の実践例
歩数・睡眠時間などの可視化→“気づき”につなげる記録アプリ
WellWaでは、歩数・睡眠・飲酒などの行動が自動で記録され、個人・チーム単位で可視化されます。
これにより、“なんとなく健康”から“気づいて改善する”姿勢への変化が期待できます。
社内セミナーやクイズ形式で“知識を楽しく学べる”
アプリ連動型でのセミナーやクイズコンテンツを用意すれば、ヘルスリテラシーをゲーム感覚で学べる場になります。
社員の参加率が上がり、“理解”と“活用”を橋渡しする設計が可能です。
サーベイ×フィードバックで行動変容の効果を実感
WellWaのサーベイ機能では、ヘルスリテラシーの現状把握とその変化を可視化できます。
定期的なレポートによって、「自分の変化」や「組織の成長」を実感できることが、継続と改善サイクルにつながります。
まとめ:ヘルスリテラシーが根づく組織が成果を生む
リテラシーの前提としての「意識づくり」が最重要
知識や行動の前に必要なのは、「自分の健康は大切」という意識の土台です。
この意識が育たなければ、どんな仕組みも長続きしません。
ヘルスリテラシーが企業文化になれば、組織が変わる
社員一人ひとりの健康への理解と行動が、組織全体の活力や持続性を支える力となります。
今こそ、健康情報を“知識”で終わらせず、“文化”として根づかせていくことが重要です。