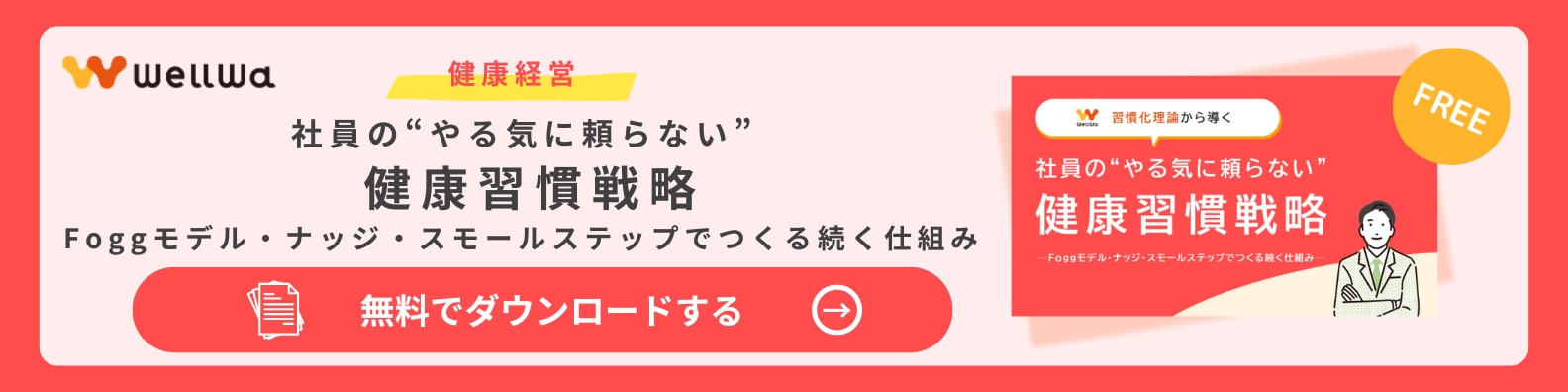ヘルスリテラシーとは何か?健康経営で注目される理由と企業への影響
近年注目されている「ヘルスリテラシー」は、とくにビジネスパーソンにとっては生活習慣病の予防やパフォーマンスの維持だけでなく、企業全体の生産性やエンゲージメント向上にも直結します。
本記事では、ヘルスリテラシーの意味・必要とされる背景・健康経営との関係・企業に与える影響をわかりやすく解説します。
目次[非表示]
ヘルスリテラシーとは?意味と定義をわかりやすく解説
WHO・厚労省が定義する「ヘルスリテラシー」
ヘルスリテラシーとは、「健康に関する情報を入手・理解し、適切に判断・活用できる力」のことを指します。
世界保健機関(WHO)や日本の厚生労働省も、健康に関する意思決定能力を支える基盤として、ヘルスリテラシーを重視しています。
健康情報を“理解”し“判断”し“活用”する力
ヘルスリテラシーは、具体的には「睡眠は何時間が理想か」「食べ過ぎた翌日にどうリカバリーするか」など、日常生活で、自らの状況を理解し、自律的な判断を下す能力が問われます。
正しい情報を選び、行動に移せるかがリテラシーの本質です。
ヘルスリテラシーを支える“健康意識”の重要性
豊富に情報があっても、実際に活用し、「健康に留意しよう」という意識や価値観がなければ活かされません。
つまり、ヘルスリテラシーの土台には、“自分の健康を大切にする”という意識が不可欠です。
医療リテラシーや栄養リテラシーとの違い
「医療リテラシー」は病院や薬の正しい選び方、「栄養リテラシー」は食品や栄養素の理解を指します。
ヘルスリテラシーはこれらを包括する“健康全般に関する判断力”であり、より広く、行動全体に関わる概念です。
なぜ今、ビジネスパーソンにヘルスリテラシーが求められているのか
情報過多の時代に「正しく選ぶ力」が問われる
SNSやネットには健康情報が溢れていますが、中には根拠のない噂や偏った知識も多数存在します。
その中から「本当に正しい情報」を見極めるには、リテラシーの高さが不可欠です。
働く世代の不調の多くが“生活習慣”に起因
実際、肩こり・頭痛・睡眠不足・慢性疲労といった不調は、「運動・食事・ストレスの管理ができていない」など、その多くは日常習慣の乱れが原因となっています。
つまり生活改善は、「気づく力」と「変える力」が不可欠であると言えます。
自分の健康は自分で守る時代にシフト
高度経済成長期やバブルの時代は、手厚い福利厚生により「会社が社員を病気から守る」傾向も見られましたが、現在は個人の主体性が求められる時代です。
テレワークや副業など、働き方の多様化により、自律的な健康管理の必要性が高まっています。
健康意識が“学ぶ姿勢”を育てる土台になる
ヘルスリテラシーの高い人は、日々の体調の変化に敏感になり、改善方法を自ら学ぼうとする傾向があります。
これは企業にとっても学習意欲・成長意欲の高い人材を育てるうえで、大きな武器となります。
健康経営におけるヘルスリテラシーの重要性
組織の生産性と健康の“目に見えないつながり”
健康経営の要は、「健康=企業発展のための投資」と捉える視点です。
ヘルスリテラシーが高い社員は、欠勤や生産性低下のリスクが低く、パフォーマンスの安定性も高いとされています。
健康施策の効果を左右する“理解力”の差
たとえば「睡眠セミナー」「健康アプリ」「食事サポート」などの福利厚生があっても、情報を理解し、意味を感じ、行動につなげる社員が少なければ効果は半減します。
つまり、リテラシーが低いとせっかくの施策も“やらされ感”で終わるのです。
健康リテラシーとエンゲージメントの相関
ヘルスリテラシーが高い社員は、自分の体調をコントロールできるため、仕事への前向きな姿勢やモチベーションを維持しやすくなります。
これはエンゲージメント(組織との関係性)の向上にも直結します。
ヘルスリテラシーが低いと起こるリスクと課題
健診受診率・セルフケア率の低下
ヘルスリテラシーが低い社員は、自分の健康状態に無頓着であることが多く、健診を受けない/再検査を放置するといった行動が見られます。
これにより、疾患の早期発見・早期対応が遅れ、重症化のリスクを招きかねません。
健康情報の誤解・偏見によるリスク行動
「ネットで見たから」「同僚が言っていたから」といった非科学的な情報に左右されて、危険な健康法やサプリに手を出すケースも見られます。
これは企業としての健康施策の成果を妨げる要因にもなります。
組織としての対応力・危機管理力の低下
パンデミックや健康不安が高まった際に、正しい知識に基づく行動ができるかどうかで、組織全体の安全管理・レジリエンス(回復力)にも大きな差が出ます。
ヘルスリテラシーが低いと、組織の対応力にもブレーキがかかるのです。
組織としてヘルスリテラシーを高める3つのアプローチ
情報を“わかりやすく伝える”仕組みづくり
健康情報は専門的な表現が多く、読む気が起きない/理解できないという社員も少なくありません。
そのため、動画や図解・チャットボットなど、親しみやすい形式で伝えることが重要です。
自分ごと化を促す対話・ワークショップ
座学だけでなく、実体験・ディスカッション形式のワークショップを取り入れることで、「自分の生活とどう関係するのか」を深く考えるきっかけになります。
“わかる”から“やってみる”へと一歩踏み出せるよう支援する場が不可欠です。
行動につながる“見える化”とフィードバック
たとえば、歩数・睡眠・飲酒の記録データを可視化してフィードバックを行うことで、「自分はどう行動しているのか」を客観的に見直す機会が生まれます。
ここから、内発的動機づけ=自発的な行動変容を促すことが可能です。
実践例:WellWaを活用した「行動変容×学び」の仕組みづくり
行動データから“気づき”を得るアプリ設計
WellWaは、歩数・睡眠・飲酒などの健康行動を自動で記録し、自分自身の変化に気づくことができるアプリです。
こうした可視化は、「自分って意外と運動してない」といった気づきの第一歩を与えます。
社内イベントやセミナーで“理解から行動”へつなぐ
「健康情報に関するクイズ」「チーム対抗イベント」など、学びながら健康習慣が身につく仕掛けを提供することで、ヘルスリテラシーの向上と行動の定着を同時に実現できます。
サーベイとレポートで学びと成長を振り返る仕掛け
WellWaは、25問のサーベイで組織全体の健康リテラシー傾向が可視化されます。
分析レポートと組み合わせれば、現状→改善→結果の“学びの循環”が生まれ、より本質的な定着が進みます。
まとめ:ヘルスリテラシーは“企業の未来リスク”を防ぐ力にもなる
健康を読み解く力が、組織の変化を生む
ヘルスリテラシーの高い社員が増えれば、健康課題の早期発見や自己管理が可能となり、組織全体のパフォーマンス・エンゲージメントも向上します。
ヘルスリテラシーは「育てる」時代へ
健康は個人任せではなく、企業が教育・支援する仕組みを持つことが求められる時代です。
健康意識と行動が変われば、組織文化も変わり、未来のリスク耐性が高くなるのです。