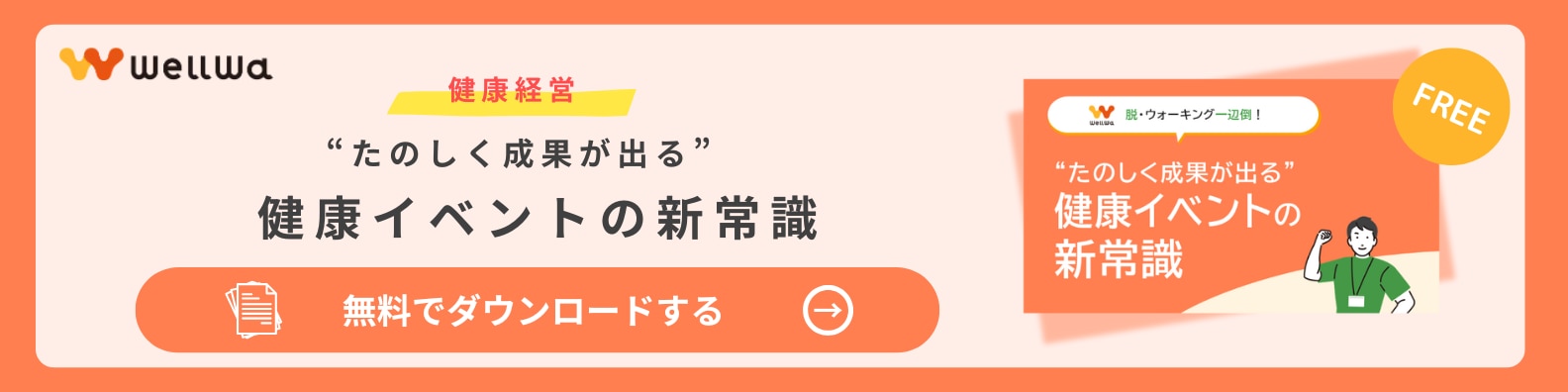デスクワーカーの健康を守る!“ながら運動”で運動不足を撃退
本記事では、デスクワーク中にできる簡単な運動方法とその効果、さらに企業が従業員の健康を守るための取り組みについてわかりやすく解説します。
目次[非表示]
- 1.1日8時間以上座っている人は当たり前?
- 2.運動不足が引き起こす健康リスクとは?
- 3.デスクワーク中にできる!“ながら運動”のメリットと効果
- 4.今日から始められる!おすすめ“ながら運動”7選
- 4.1.1. 座ったままストレッチ&姿勢リセット
- 4.2.2. デスクでできる「かかと上げ・足パタ体操」
- 4.3.3. 背伸びタイムをルーティン化
- 4.4.4. 会議中に立つ・歩く「スタンディングミーティング」
- 4.5.5. タイマー活用!1時間に1回の立ち上がりリマインド
- 4.6.6. 仕事中にできる軽いスクワット or ランジ
- 4.7.7. SlackやTeamsで「健康促進リマインドBot」を活用
- 5.デスクワーク中の“ながら運動”を促進する仕組みと工夫
- 6.WellWaで習慣化を支援!見える化+楽しさで継続を実現
- 7.まとめ:運動不足対策は“ながら”から始めよう
1日8時間以上座っている人は当たり前?
オフィス勤務者の多くは、1日8時間以上座りっぱなしという状況が常態化しています。
日本人の1日の平均座位時間は世界最長クラスとされており、特にパソコン業務や会議中心の働き方では、ほとんど体を動かさないまま1日が終わることも珍しくありません。
リモートワーク普及でさらに減少する日常の運動機会
出社がなくなったことで、通勤やオフィス内の移動など“無意識の運動機会”が大幅に減少しています。
リモート勤務者の歩数は、対面勤務に比べて1日2000〜3000歩少ないという調査もあり、座位時間の長時間化+歩行減少という二重の悪影響が健康を損なう要因となっています。
座りすぎが“新たな健康リスク”として注目されている理由
近年では、「座りすぎ」が喫煙と同レベルのリスクとして注目され、“座る”は“吸う”に匹敵する悪習慣(Sitting is the new smoking.)とされています。
長時間の座位は、血流の停滞・代謝低下を引き起こし、生活習慣病や血栓、がん、うつのリスクまで高めるという研究結果もあります。
運動習慣の有無にかかわらず、「長時間座ること」自体が健康に悪影響を及ぼすのです。
運動不足が引き起こす健康リスクとは?
糖尿病・高血圧・メタボリックシンドローム
運動不足によって筋肉の活動量が減少し、インスリン抵抗性が上がることから糖尿病のリスクが上昇します。
また、脂質代謝の低下は高血圧や内臓脂肪の蓄積(メタボ)にも直結します。
これらはすべて、企業にとってプレゼンティーイズムや医療費増大の引き金となり得る深刻な課題です。
筋力低下・姿勢不良・肩こり・腰痛
座りっぱなしは体幹・下半身の筋力低下を招き、猫背や骨盤の歪みなどの姿勢不良を引き起こします。
結果として、肩こり・腰痛・首の痛みといった筋骨格系のトラブルが慢性化し、生産性や集中力にも悪影響を与えるようになります。
メンタルヘルスや集中力低下にも影響
身体活動の減少は、脳の活性化や神経伝達物質の分泌の低下をもたらし、うつ症状などメンタル不調の原因にもつながります。
また、血流の停滞によって集中力や思考力の低下を招き、仕事の質にも悪影響を及ぼします。
運動不足は、身体的なリスクに加え、精神的・認知的な課題にも波及するのです。
デスクワーク中にできる!“ながら運動”のメリットと効果
時間を取らずにできる=継続のハードルが低い
“ながら運動”とは、仕事の合間や業務中に行える軽い運動のこと。
あらためて時間を確保する必要がないため、業務に支障をきたさずに継続できる点が最大の利点です。
わずか1分~3分の動作を積み重ねることで、確実に効果が期待できます。
気分転換・集中力アップの副次効果も
ちょっとしたストレッチやスクワットは、脳への血流を促進し、眠気・倦怠感の解消に貢献します。
短時間の運動でもパフォーマンスの維持・向上につながるため、業務効率を高める手段として推奨に値します。
周囲に気づかれずこっそり健康行動が可能
特にリモートワーク中やフリーアドレスの職場では、目立たずに行動できる“ながら運動”は非常に取り入れやすい施策です。
人目を気にせず、自分のペースで実行できることで、心理的ハードルを下げ、継続率向上につながります。
今日から始められる!おすすめ“ながら運動”7選
1. 座ったままストレッチ&姿勢リセット
首・肩・背中のストレッチは、姿勢改善と血流促進に効果的です。
肩を回す、胸を張る、背筋を伸ばすなど、1分程度の動作で十分に効果が得られます。姿勢を整えるだけでも、集中力や作業効率がアップします。
2. デスクでできる「かかと上げ・足パタ体操」
ふくらはぎの血流を促すかかと上げ運動や、太ももを刺激する足パタ体操(太ももをパタパタ動かす)は、エコノミークラス症候群の予防にもつながります。
足元でこっそりできるので、周囲の目を気にせず継続できます。
3. 背伸びタイムをルーティン化
1時間に1回、大きく伸びをするだけでも体はリセットされます。
「決まった時間に背伸びをする」という習慣を社内文化にするだけで、体も気分も軽くなり、眠気も防止できます。
4. 会議中に立つ・歩く「スタンディングミーティング」
短時間の会議やブレストでは、立って行うことで集中力がアップします。
さらに、“歩きながら話す”ウォーキングミーティングを取り入れれば、運動とコミュニケーションを同時に促進できます。
5. タイマー活用!1時間に1回の立ち上がりリマインド
デスクワークに没頭すると、あっという間に2~3時間座り続けてしまいます。
タイマーやアプリを使った立ち上がりリマインドを設定し、定期的に立って動く行動を習慣化しましょう。
6. 仕事中にできる軽いスクワット or ランジ
トイレ休憩やコピーの待ち時間など、業務の合間に3回スクワットするだけでも運動効果は得られます。
下半身の筋肉を使うことで代謝が上がり、全身の血流改善につながります。
7. SlackやTeamsで「健康促進リマインドBot」を活用
社内チャットに「1時間ごとにストレッチや水分補給を促すBot」を導入することで、社員の健康意識を自然に高めることが可能です。
デジタルツールを活用した“仕掛け”も、行動変容を後押しします。
デスクワーク中の“ながら運動”を促進する仕組みと工夫
管理職から率先!「健康行動」へのロールモデルづくり
組織内での浸透には、上司やマネージャーの実践が重要です。
「管理職が背伸びや立ちミーティングを始めたら、社員も同様に動く」という“上から始まる健康文化”を推進しましょう。
健康チャネルやワークショップでの啓発
社内ポータルやTeams上に健康情報の専用チャネルを作成し、簡単にできる運動やストレッチ動画を共有しましょう。定期的なミニワークショップ開催も、継続率アップに効果的です。
環境整備:スタンディングデスク・動スペース・歩ける動線設計
物理的な環境も、行動変容を促進します。
スタンディングデスクの導入や、歩ける動線(プリンターの距離など)を意識的に設計することで、無意識のうちに“動ける環境”が整います。
WellWaで習慣化を支援!見える化+楽しさで継続を実現
歩数・活動量の記録で日々の変化を“見える化”
WellWaアプリでは、歩数や活動時間が自動記録され、本人もチームも変化をリアルに把握することができます。
「実感を伴う達成感」と「続ける意欲」が生まれやすくなります。
チーム対抗・スタンプ・ポイント制度で“やりたくなる”仕組み
スタンプラリーやポイント制で、運動=楽しい活動へと転換。
部署対抗イベントやランキング表示で、「誰かと競える・一緒にできる」楽しさを提供します。
生活習慣サーベイで個人と組織の課題を分析→対策へ
25問の健康サーベイ機能により、組織単位での健康課題を可視化。
健康経営のPDCAをデータに基づいて回せる環境を整えることができます。
まとめ:運動不足対策は“ながら”から始めよう
小さなアクションが未来の健康をつくる
大がかりにジムでトレーニングをしなくても、簡単なな“ながら運動”の積み重ねが健康習慣につながります。
1分、3分の行動でも、組織全体の健康水準を底上げできます。
業務と健康はトレードオフではない、両立が企業の成長につながる
健康的な働き方は、生産性や従業員エンゲージメントを高め、離職防止にも寄与します。
運動不足対策は、もはや福利厚生ではなく“戦略的投資”のひとつです。