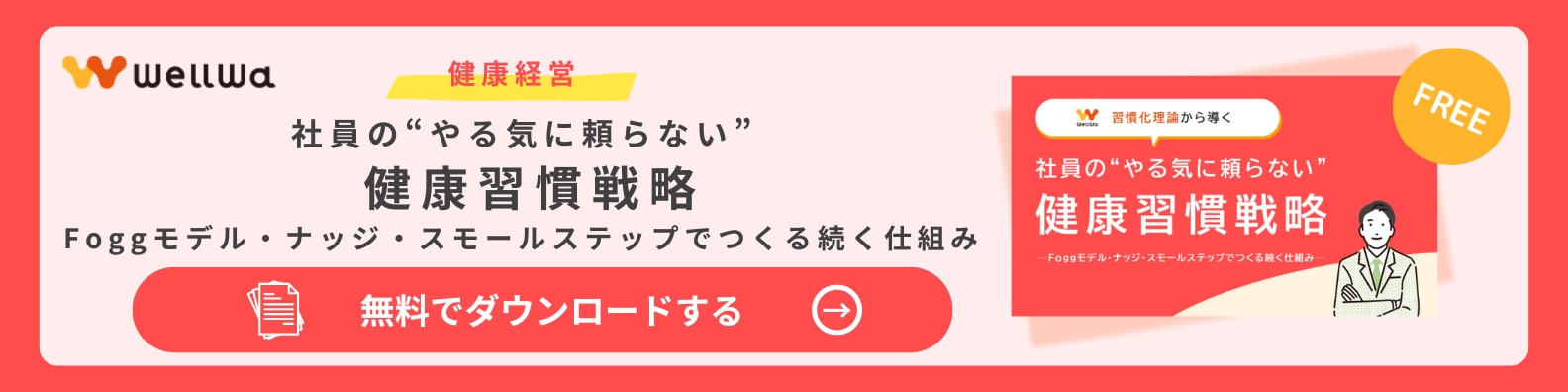社員の運動不足、まずはここから!“今日から始める”簡単3ステップ
テレワークやデスクワークの増加で、社員の運動不足が深刻な企業課題となっています。
本記事では、健康経営の観点から注目される「運動習慣づくり」の重要性を解説し、誰もが取り組みやすい今日から始められる3ステップを紹介します。
目次[非表示]
なぜ今「運動不足解消」が企業に求められているのか
“座りっぱなし”勤務と健康リスクの関係
テレワークやデスクワークの常態化により、多くの社員が1日8時間以上“座りっぱなし”の生活を送っています。
この「座りすぎ」は、肥満・高血圧・糖尿病・心血管疾患など生活習慣病のリスクを高めるとされており、“静かなる健康リスク”とも言われています。
さらに近年の研究では、たとえ週に数回の運動を行っていたとしても、「日常の歩行・軽度の活動が少ない」ことが健康状態に大きな悪影響を及ぼすことがわかってきました。大切なのは運動の強度ではありません。 “運動していない時間”の長さが問題なのです。
運動不足がもたらすプレゼンティーイズム
身体を動かさないことで引き起こされるのは、単なる体調不良だけではありません。
- 疲れやすい
- 集中力が続かない
- モチベーションが下がる
こうした「なんとなく不調」の状態=プレゼンティーイズム(出勤していても能力を発揮できない状態)が、企業の生産性に見えない損失を与えています。
慢性的な運動不足は、社員のQOL(生活の質)の低下につながるため、、経営課題としての“健康投資”が、喫緊の課題となっています。
健康経営・人的資本経営の流れと運動の重要性
人的資本開示が義務化される中で、「従業員の健康管理」や「生産性の可視化」は、企業の社会的責任としても注目されています。
中でも“運動”は、低コストかつ効果がわかりやすい健康アプローチとして、健康経営・人的資本経営の両面から評価されています。
特に歩数や運動時間は数値化・可視化しやすく、PDCAにも落とし込みやすいため、「はじめの一歩」として最適な施策です。
まずは何から始める?誰もが始めやすい“最初の一歩”とは
「運動=きつい」という思い込みの払拭
多くの人が「運動=きつい」「時間がない」「スポーツジムに通うのは面倒」と考えがちです。
しかし、運動は“汗をかくレベルの激しい活動”である必要はありません。
厚生労働省も、“座り時間を減らすだけ”でも健康効果があるとしており、ウォーキングやストレッチといった軽度な活動を行うだけで十分です。
大切なのは、健康施策を“最初の一歩”を踏み出せる設計にすることです。
日常の“ながら動作”から始めるアプローチ
- エレベーターではなく階段を使う
- 歯磨きをしながら片足立ちをする
- 通話中に立って歩く
- コピーやお茶くみのついでに肩を回す
このように、「ながら」でできる動作を提案することで、心理的ハードルを下げつつ、運動習慣を生活に取り込むことが可能です。
社内報やSlackで「今月のながら運動チャレンジ」などを設けると、より参加しやすくなります。
成果ではなく“やってみた”を評価する文化づくり
「どれだけ歩いたか」「どれだけ痩せたか」ではなく、 「昨日より500歩増えた」「1日1回ストレッチをした」といった小さな実行をポジティブに評価する文化が、継続を後押しします。
社内で“行動そのもの”を称えるメッセージや、健康ポイント制度などのインセンティブを活用すれば、さらに参加率が高まります。
社員が続けたくなる!運動習慣づくり3ステップ
【ステップ1】まずは歩く:1日1000歩増やす工夫
運動不足解消の第一歩は「歩数アップ」です。特に1日1000歩増やすだけで、生活習慣病のリスクが下がるという研究結果もあります。
- エレベーターより階段
- 昼休みに散歩
- 会議室間の移動を歩数にカウント
など、“無理なく自然に”歩ける導線を職場に設計していくことがポイントです。
【ステップ2】座りすぎ対策:ストレッチ&スタンディング導入
1時間に1回立つだけでも、血流改善や集中力向上の効果が期待できます。
- デスク脇でできるストレッチ
- スタンディングデスクの導入
- タイマーやリマインダーによる“立つきっかけ”の提供
など、“座りっぱなし防止”を仕組みで支援する工夫が必要です。
【ステップ3】チームで取り組む:イベント形式で楽しく継続
個人任せではなく、チーム対抗のウォーキングイベントや、部署間での歩数バトルなど、“楽しさ”と“つながり”を感じられる工夫が継続率を高めます。
WellWaのようなアプリを活用すれば、スタンプやポイントでゲーム感覚の要素も取り入れられ、運動が“楽しい習慣”へと進化します。
職場でできる運動促進アイデアと環境づくり
社内でできる“1分体操”や“歩く会議”の推進
短時間でも効果があるのが“1分間の軽運動”です。朝礼やミーティング前のラジオ体操や肩回し運動をルール化する企業も増えています。
また「歩く会議」など、業務と運動を融合した新しい働き方も注目されています。
スタンディングデスクや立ち話スペースの設置
オフィス環境からのアプローチとして、
- 高さ調整が可能なデスク
- 立ったまま話せる共有スペース
- 「立って考える」文化の浸透
といった、自然に立つ時間を増やす仕掛けが効果的です。
業務中に運動できる“インターバル習慣”の設計
1時間に1回、2〜3分の簡単なストレッチや足踏みをルール化することで、“ながら運動”が定着しやすくなります。
アプリ通知や社内チャットでのリマインドも有効です。
継続を支える仕組みとモチベーション設計
WellWaを活用した歩数記録とチームランキング
WellWaでは歩数を自動記録し、部署別ランキングやスタンプ制で、“健康行動が可視化される”文化をつくることが可能です。仲間と競い合いながら歩数アップを目指すこともできます。
健康アプリのスタンプ・ポイント制度で楽しく続ける
アプリ内での健康ミッション達成によりスタンプが貯まり、福利厚生と連動したポイントに変換できる設計は、行動継続の強力な動機づけになります。
健康行動に対する社内表彰・福利厚生連動の仕掛け
- 健康習慣表彰
- 歩数チャンピオンの月間報奨
- 健康ポイントと社食・カフェ・ECと連動
といった“健康が得になる”設計があることで、運動が自然と習慣化されていきます。
まとめ:小さな運動が、大きな組織変化を生む
運動は“健康”以上の価値を組織にもたらす
「歩く・立つ・動く」このシンプルな行動が、健康増進のみながらず、社員の集中力・生産性・チーム力・エンゲージメント向上といった“人材価値の底上げ”につながります。
今日からできる最初の一歩を“推奨”から“文化”に変えよう
運動を「やらせるもの」ではなく「続けたくなるもの」へ。
運動を個人任せにするのではなく、組織の文化として根付かせる仕掛けを生み出すことが、企業が取り組むべき次の健康経営のあり方です。