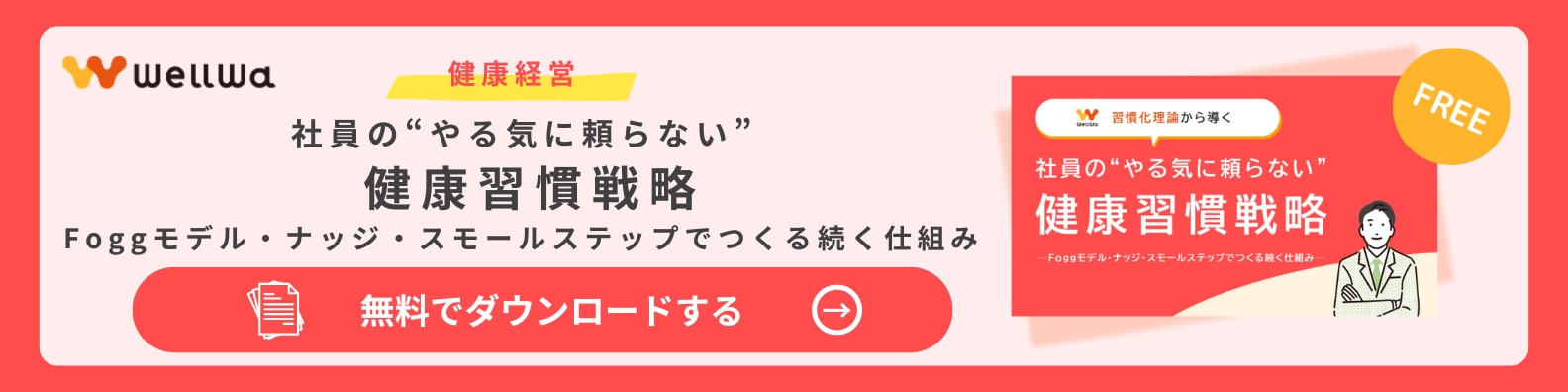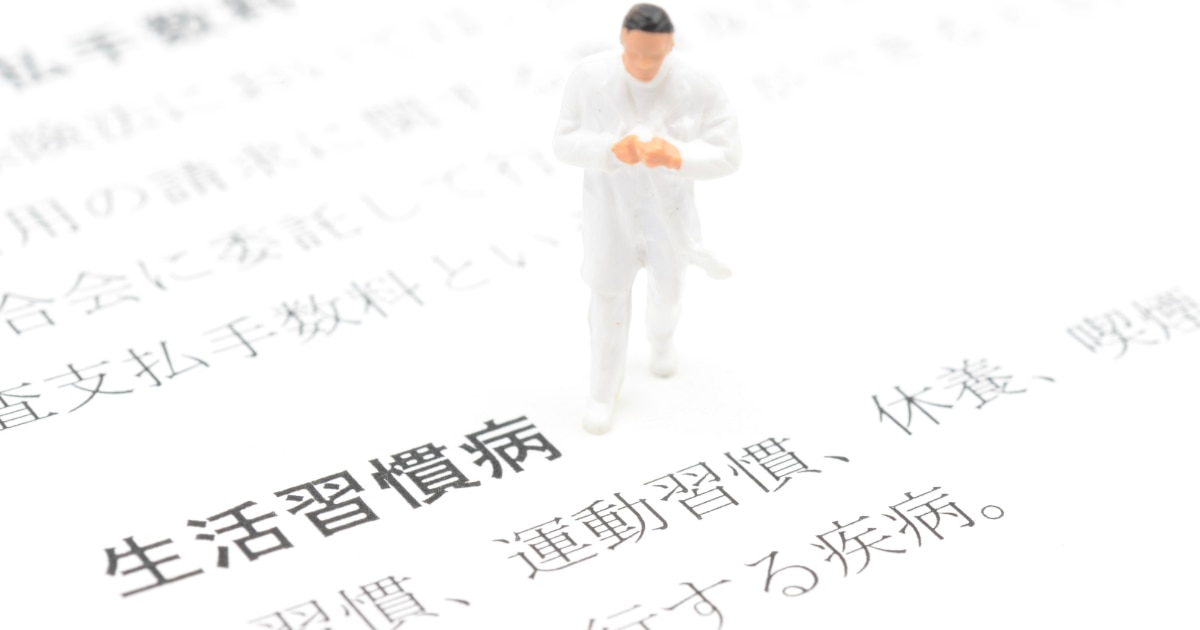
生活習慣病を防ぐには?健康経営に欠かせない「予防」の視点
本記事では、健康経営の観点から生活習慣病を防ぐための効果的な予防施策と組織全体で習慣化を促す仕組みづくりを紹介します。
目次[非表示]
なぜ今、生活習慣病の「予防」が企業にとって重要なのか
医療費の増加と生産性低下のリスク
日本国内の医療費は年々増加しており、その大きな要因が「生活習慣病」です。糖尿病、高血圧、脂質異常症などは、一見軽い症状に見えても、慢性的な不調や重大疾病の引き金になります。結果として企業には、従業員の生産性低下・業務効率悪化・欠勤増加といったリスクが押し寄せます。
つまり、従業員の健康は経営リスクと直結しており、企業が予防的な取り組みを始める意義は高まっています。
プレゼンティーズム・アブセンティーズムの実態
病気や不調によって本来のパフォーマンスを発揮できない「プレゼンティーズム」。欠勤などの「アブセンティーズム」。
これらは企業にとって「見えないコスト」となり、業績をじわじわと蝕みます。特に生活習慣病由来の慢性疲労・頭痛・集中力低下などは、従業員本人も気づかないまま生産性を落としているケースも多いのが実情です。
健康経営が「攻めの経営戦略」として評価される理由
従業員の健康支援は、もはや「福利厚生の一環」ではありません。現在は人的資本経営の文脈でも、健康経営は「攻めの戦略」として評価されています。健康を資本投資の一部と位置づけ、病気になる前に手を打つ企業こそ、エンゲージメント・定着率・採用力の向上を実現しやすい時代です。
生活習慣病の主なリスク要因と予防の基本
食事・運動・睡眠・ストレスの4大要素
生活習慣病の多くは、「日々の選択の積み重ね」から発症します。特に以下の4つは、予防の柱です。
- 食事:塩分・脂質・糖質の過剰摂取、不規則な食事タイミング
- 運動:通勤・デスクワーク中心による活動不足
- 睡眠:短時間・質の低下による回復力の欠如
- ストレス:慢性的な心理的負担・休養不足
これらはすぐに体に影響が出にくく、軽視されがちですが、蓄積されれば生活習慣病の引き金となります。
予防は「早期発見」より「日常改善」が鍵
健診や人間ドックなどの早期発見は大切ですが、そもそも病気にならない状態をつくる「予防」こそが最も効果的な戦略です。「毎日あと1,000歩多く歩く」「ランチを1品ヘルシーメニューに変える」といった小さな改善を習慣化することで、長期的には大きな成果に繋がります。予防は「診断結果」ではなく「日々の行動」から始まります。
健診や数値だけでは変わらない行動の壁
健診結果やストレスチェックの数値が悪くても、多くの人は行動を変えようとはしません。その理由は、「自分にはまだ関係ない」「何から始めればいいか分からない」「続ける自信がない」といった心理的な抵抗感と行動へのハードルがあるからです。
行動変容を促すには、仕組み・気づき・チーム支援がセットで必要になります。
健康経営における「予防施策」の考え方と位置づけ
「個人任せ」から「組織全体で支える予防」へ
従業員の健康を「自己責任」に委ねる時代は終わりました。現在の健康経営では、組織全体で予防を支える文化づくりが求められています。「健康を当たり前に意識できる職場環境」を構築することで、社員一人ひとりの行動変容を支援する体制が生まれます。
データ活用によるターゲティング型施策
従業員全体に一律で健康施策を打つのではなく、健康診断結果やストレスチェックなどのデータを活用し、必要な人に必要な施策を届ける「ターゲティング型アプローチ」が有効です。これにより、施策の無駄を省き、個別ニーズに応じたサポートが可能になります。
業種や勤務形態に応じたカスタマイズが鍵
現場業務・デスクワーク・リモートワークなど、職種・勤務形態によって健康リスクは異なります。予防施策も画一的ではなく、柔軟にカスタマイズする設計力が必要です。
生活習慣の予防を仕組み化する実践施策
オフィス設置型の健康飲料・軽食で「食」から改善
職場に無糖茶やスムージー、健康スナックなどを設置することで、従業員が自然と健康的な選択をする環境が整います。「買うのが面倒」「何を選べばいいか分からない」といった障壁を減らし、「選びやすさ」で健康行動を後押しできます。
毎日の歩数・睡眠記録で行動変容を促す習慣化支援
ウェアラブルデバイスやアプリを活用し、歩数や睡眠時間を自動記録することで、自身の習慣を「見える化」できます。可視化された記録は、「あともう少し頑張ろう」という動機付けにもつながり、無理なく継続できます。
体調チェック・ストレスサーベイの定期実施
定期的な簡易チェックやアンケートで、メンタルや体調の変化を早期にキャッチします。これにより、重症化や長期休職を防ぎ、予防的対応がしやすくなります。
チーム参加型イベントで楽しみながら継続
健康施策は「個人戦」にしないことが大切です。チーム単位で歩数イベントや健康クイズなどを行うことで、楽しさと協力意識が生まれ、自然な継続につながります。
行動に対するインセンティブ設計で予防を習慣に
「歩数1万歩でポイント付与」「サーベイ回答で社内通貨ゲット」など、健康行動に具体的なリターンを設定することで、参加率・定着率が向上します。
WellWaを活用した「見える化」と「習慣化」
歩数・睡眠・飲酒の記録とチーム管理
WellWaを活用すれば、歩数や睡眠などの健康行動を自動で記録し、チーム単位で進捗を共有できます。個人だけでなく、組織全体の行動変容を「見える化」しやすい点が強みです。
サーベイ×分析で従業員の状態と成果を可視化
WellWaの25問サーベイを使えば、エンゲージメントや疲労感、健康行動の変化を定量的に分析できます。結果はダッシュボードに表示され、施策の有効性を“経営層に説明できる形”で可視化可能です。
予防の定着に不可欠な「続けやすさ」と「共感設計」
WellWaはゲーム性やスタンプ機能、ポイント制度などで、「やらされ感」を抑えつつ、自発性を育む設計が特徴です。「楽しいから続く」「共感できるから習慣になる」──これが予防の定着に欠かせない視点です。
まとめ
生活習慣病予防はコストではなく「将来の損失を防ぐ投資」です。健康な組織は、生産性も高く、離職も少なく、競争力の源泉となります。予防が当たり前の行動として根付くには、組織としての仕組みと、従業員の共感が両輪で機能することが重要です。WellWaのようなツールをうまく活用しながら、予防を「文化」として組織に定着させていきましょう。