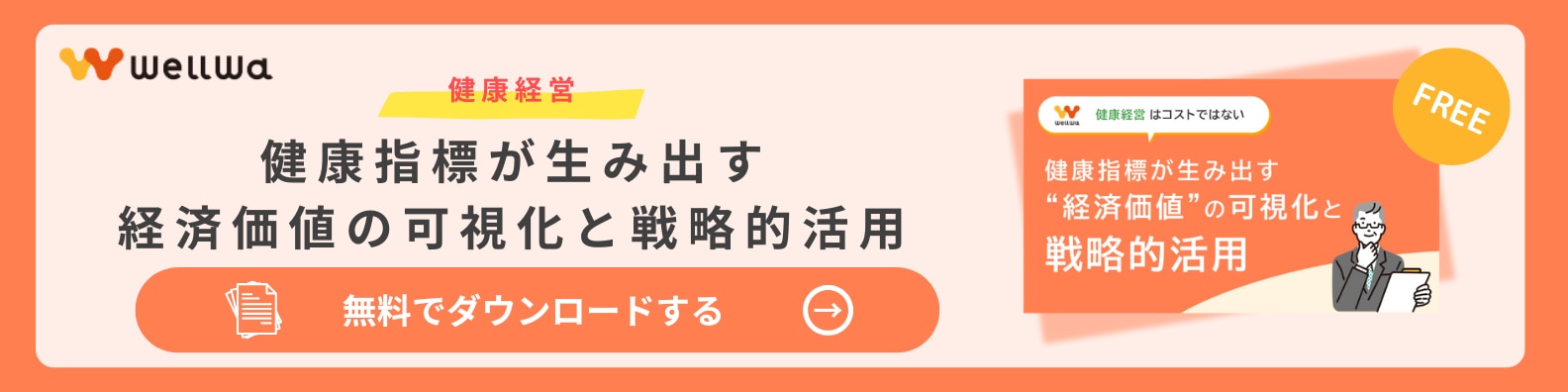健康データで“見える化”と改善!企業が守るべきルールと活用法
企業の健康経営や人的資本経営が注目される今、「健康データの活用」は欠かせない取り組みです。
本記事では、健康データを使った“見える化”と改善のメリット、企業が必ず守るべきルール、そして実践に役立つステップをわかりやすく解説します。
目次[非表示]
なぜ今「健康データ」が注目されているのか
健康経営・人的資本経営とデータの関連性
企業が従業員の健康を戦略的に捉える時代になり、健康経営や人的資本経営が注目されています。これらの取り組みの中核を担うのが「健康データ」です。
従来の健康施策は「良かれと思って」導入されるケースが多く、効果測定があいまいになりがちでした。しかし今は、健康状態や行動の実態を客観的なデータで可視化し、PDCAを回すことが前提となっています。
健康経営を「感覚」ではなく「戦略」として実践するには、定量・定性の両面からの健康データ活用が不可欠なのです。
デジタルヘルスとウェアラブルの普及が背景に
近年、スマートウォッチや活動量計などのウェアラブルデバイスが急速に普及し、歩数・睡眠時間・心拍数などのデータが簡単に取得できるようになりました。加えて、食事や体重、気分の記録ができるヘルスケアアプリも多く登場し、企業側が従業員の健康行動を支援するインフラが整ってきています。
これらのテクノロジーの進化は、健康データ活用の裾野を広げ、「無理なく・自然に・継続的に」データが集まる環境を提供しています。
出典:経済産業省 健康経営の推進
感覚ではなく「見える化」で改善する時代へ
「なんとなく疲れている」「最近よく眠れていない気がする」といった曖昧な状態は、感覚だけでは対処が難しいもの。しかし、歩数や睡眠スコア、心身のストレス度が数字として可視化されれば、問題の所在が明確になり、対策もしやすくなります。
組織全体として傾向を把握することで、「部署ごとにエンゲージメント低下の原因」や「特定職種での健康リスク増加の背景」など、組織課題の早期発見にもつながります。
健康データの種類と取得方法|何を、どう集めるべきか
定量データ(歩数・体重・睡眠・食事記録など)
定量的な健康データは、数値で測定可能な客観的情報です。具体的には、歩数(活動量)、体重・BMI、体脂肪率、睡眠時間、睡眠の質、食事のカロリーや栄養バランス、血圧、血糖、脈拍などのバイタルデータが含まれます。
これらはウェアラブル端末やスマートフォンアプリを活用することで日常的に取得可能であり、健康改善の定量的な効果測定に役立ちます。
定性データ(健康意識・ストレス度・アンケート)
数値では測りきれない「心の健康」や「行動意欲」などは、定性データとしてサーベイやヒアリングから収集します。ストレス度合いや主観的健康感、職場の人間関係や心理的安全性、健康行動への意識や満足度、改善施策に対するフィードバックなどが該当します。
こうしたデータは、数値と組み合わせて使うことで、より立体的な健康経営分析が可能になります。
取得方法の選択肢:アプリ連携、ウェアラブル、健診結果など
健康データの取得方法は、目的や体制によって選択肢が広がっています。スマートフォンアプリでは、歩数、睡眠、食事記録などを自動で連携。ウェアラブルデバイスではFitbit、Apple Watchなどと連携して詳細データを取得できます。
また、企業検診の結果を活用して定期的な基礎データを蓄積したり、ツールでストレスや健康意識を可視化したりすることも可能です。
これらを組み合わせてデータ基盤を整えることで、個人・組織両方の健康状態を正確に把握できるようになります。
健康データ活用のメリットと企業にもたらす効果
不調の予兆を捉えてリスクマネジメント
健康データは、従業員の心身の変化を早期に察知し、重大な健康トラブルを未然に防ぐリスクマネジメント手段となります。睡眠時間の著しい低下や歩数の激減は、心身の不調のサインであることも。
定点観測で得たデータを継続的に分析することで、休職・離職リスクの低減や、安全配慮義務の一環としての早期介入が可能になります。
健康施策のPDCAが高速化する
従来の健康施策は「導入して終わり」になりがちでしたが、データを活用すれば施策の効果検証→改善→再設計といったPDCAを迅速に回せます。
「睡眠改善プログラムを導入したが、改善が見られない」場合でも、データから対象層の特徴や改善の壁を読み解くことで、的確な打ち手を講じられます。
社員のモチベーション・エンゲージメント向上にも貢献
健康データの可視化は、個人のモチベーションアップに直結します。歩数や睡眠スコアなどの成果が「見える化」されると、取り組みに対する納得感や達成感が生まれます。チーム単位での取り組みに展開すれば、組織全体のエンゲージメント向上やコミュニケーション活性化にもつながります。
企業が必ず押さえておくべき健康データの取扱いルール
個人情報保護法と健康情報の扱い方
健康データは「要配慮個人情報」に該当し、特に慎重な取り扱いが求められます。企業が収集・活用する場合には、個人情報保護法(改正含む)に準拠し、情報の安全な管理と漏洩防止措置を講じる必要があります。
出典:個人情報保護委員会
取得時の同意と活用目的の明示
従業員から健康データを取得する際は、あらかじめ明確な同意を得ることが不可欠です。収集の目的・利用範囲・第三者提供の有無などを文書等で明示し、従業員が自分の意思で同意できる状態を整える必要があります。
利用者の信頼を損なわない透明性の確保
最も重要なのは、従業員との信頼関係を損なわないこと。健康データを経営判断に活かす一方で、個人が特定されないように配慮し、「評価や査定には使わない」などのルールも含めて透明性を担保するガイドラインの整備が重要です。
成果を生む健康データ活用のポイントと実践ステップ
活用目的を明確にし、収集項目を絞る
「なんでもかんでもデータを取る」ことは、むしろ逆効果になる場合があります。最も重要なのは、「なぜ取得するのか」を明確にし、それに必要なデータだけを選別すること。「エンゲージメント向上」を目的とするなら、歩数や睡眠、ストレススコアなどが有効な指標となります。
データ分析で「気づき」を引き出す工夫
データは蓄積するだけでは意味がありません。見せ方の工夫や現場の気づきを引き出す分析視点が求められます。ダッシュボード化やグラフでの可視化、組織別・属性別の傾向分析などにより、「だからこの施策が必要なのか」と納得できる「気づき」を提供しましょう。
アクションに結びつけるフィードバックと支援設計
データから示唆が得られたら、それを具体的な行動変容にどうつなげるかが成功の鍵。歩数が少ない社員には「歩くミーティング」を提案するなど、パーソナライズされたフィードバックと行動支援を組み合わせることで、継続的な改善が期待できます。
WellWaを使った健康データのスマートな活用
歩数・睡眠・飲酒データの自動記録で生活習慣を可視化
WellWaは、歩数・睡眠・飲酒などのデータをスマホやウェアラブルと連携して自動記録する仕組みを提供しています。日々の行動データが簡単に蓄積され、社員は無理なく“自分の健康状態”を知ることができます。
25問で完結!キリン独自の健康ROI分析モデル
WellWaに搭載された25問の健康サーベイは、身体・心理・社会の3側面から健康を可視化し、投資対効果(ROI)を測定する独自のモデルです。健康施策の成果を「数値」で確認でき、経営層への説明や施策立案に役立ちます。
組織別の傾向把握とランキングで施策の狙いを明確化
WellWaでは、組織単位でのスコア比較やランキングも可能です。部署ごとの課題が浮き彫りになり、ピンポイントでの改善アプローチが可能になります。楽しさと効果測定を両立した仕組みが、継続的な改善を後押しします。
まとめ:健康データを「数字で終わらせない」企業の新常識
健康データは「行動を変えるきっかけ」に使う
健康データは単なる記録ではなく、従業員が自分の働き方・生活習慣を見直すきっかけになります。「数字が悪いから注意」ではなく、「こうすれば改善できる」という前向きな提案と支援をセットにすることが大切です。
収集だけで満足せず、改善サイクルを回すことが成功の鍵
大切なのは、データを集めて終わりにしないこと。見える化→分析→アクション→改善というサイクルを組織的に回し続けることで、健康経営は「成果」へとつながっていきます。