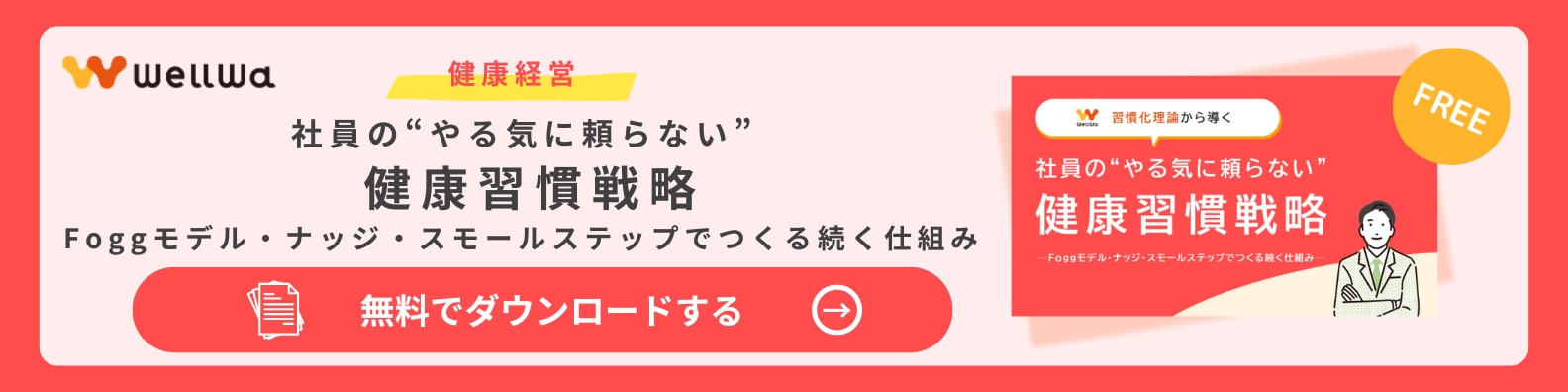社員の生活習慣を変えるには?健康経営成功企業の取り組み5選
今、健康経営や人的資本経営の観点から生活習慣改善は「企業価値を高める戦略的取り組み」として注目されています。
本記事では、健康経営に成功した企業の具体的な5つの取り組みを紹介し、社員が楽しく・主体的に習慣を変える仕組みづくりのヒントを解説します。
目次[非表示]
- 1.なぜ今、生活習慣の改善が企業の課題になっているのか
- 2.生活習慣が仕事に与えるインパクトとは
- 3.生活習慣改善の取り組み5選
- 3.1.毎日の歩数記録で健康意識を底上げ
- 3.2.昼食改善×社内設置の健康スナック活用
- 3.3.就業中のマインドフルネス導入でメンタルケア
- 3.4.7時間睡眠チャレンジで生活リズムを是正
- 3.5.全社対抗の健康イベントで習慣化を推進
- 4.習慣化を定着させるための3つの視点
- 5.健康施策を仕組みで支える!健康支援サービス「WellWa」
- 5.1.WellWaとは?健康を「楽しく・チームで」続けられる新発想
- 5.2.生活習慣を見える化!歩数・睡眠・飲食の記録機能
- 5.3.チーム対抗・スタンプ機能でコミュニケーション活性化
- 5.4.ポイント制度×福利厚生で“食”から健康をサポート
- 5.5.健康のROIも測定可能!サーベイ連動で効果を可視化
- 6.まとめ:生活習慣改善が組織力を高める理由と第一歩
なぜ今、生活習慣の改善が企業の課題になっているのか
働き方の変化で増える“見えない健康リスク”
リモートワークやフレックスタイムの普及により、従業員の働き方は柔軟になった一方で、生活習慣の乱れが顕在化しにくくなっています。出社機会が減り、通勤などの日常的な運動機会が失われることで、運動不足や食生活の偏り、睡眠リズムの乱れといった問題が深刻化しているのが現状です。
こうした「見えない健康リスク」は、やがて集中力の低下や生産性の悪化、メンタル不調につながり、企業にとって目に見えないコストを膨らませる原因となりかねません。
健康経営・人的資本経営の文脈における重要性
健康経営が人的資本経営の入口として注目される今、従業員の生活習慣改善は「企業価値を高めるための戦略的取り組み」と位置づけられつつあります。経済産業省の「健康経営優良法人認定制度」や人的資本情報開示の潮流を受け、企業は「従業員の健康づくり」を具体的な経営課題として取り組む必要性が高まっています。
その中核にあるのが、日常の生活習慣=働く力の土台です。睡眠、運動、栄養といった基礎習慣を整えることは、従業員の活力やパフォーマンスの源となり、組織の生産性・定着率・エンゲージメント向上に直結します。
心身の健康がもたらす相乗効果
生活習慣の乱れは体調不良だけでなく、メンタル面にも大きく影響します。睡眠不足はイライラや注意力散漫を引き起こし、人間関係の摩擦や判断ミスにもつながりやすくなります。
慢性的な運動不足は自律神経のバランスを崩し、メンタル不調のリスクを高めます。心身の健康は相互に影響し合うため、職場全体の活力を維持するには、生活習慣の改善が欠かせません。
生活習慣が仕事に与えるインパクトとは
睡眠・運動・食事が生産性に与える影響
基本的な生活習慣である睡眠、運動、食事は、従業員の思考力や判断力、集中力を大きく左右します。睡眠の質が悪ければ午前中の集中力は著しく下がり、業務効率が落ちることは明白です。
朝食抜きや糖質過多なランチは血糖値の乱高下を招き、午後の眠気やパフォーマンス低下を引き起こします。適度な運動は血流や脳の活性化に寄与することから、生活習慣が仕事の質に直接反映されると言えるでしょう。
プレゼンティーズムによる企業損失
企業が特に注目すべきなのは、体調不良でも出社しているが、能力を十分に発揮できていない状態=プレゼンティーズムです。欠勤とは異なり、見た目にはわかりにくいものの、企業全体としては大きな損失を生んでいます。
健康診断の数値に異常がなくても、「なんとなく不調」が続く従業員は少なくありません。こうした状況を放置すれば、職場全体の生産性やチームの士気にも悪影響を及ぼします。
習慣を変えることで得られる組織の活力
生活習慣の改善に取り組むことで、従業員の身体的・精神的コンディションが整い、業務の効率化・対人関係の良化・モチベーションの向上といったポジティブな変化が生まれます。
個人にも組織にも“余白”が生まれることで、新しい挑戦や学びの機会が創出されます。生活習慣の見直しは「健康のためだけでなく、未来志向の組織づくり」の起点となるのです。
生活習慣改善の取り組み5選
毎日の歩数記録で健康意識を底上げ
歩数はシンプルかつ測定しやすい指標であり、全社員が取り組みやすい健康行動です。ウェアラブル端末やアプリを活用して歩数を記録し、チーム対抗形式にすることで、ゲーム感覚で楽しみながら歩数が自然と増える環境をつくることができます。
多くの企業で「歩数記録の共有が社内の健康意識を底上げした」という成果が報告されており、生活習慣改善の入口として有効です。
昼食改善×社内設置の健康スナック活用
社員食堂や休憩スペースに低糖質・高たんぱくの健康スナックやドリンクを導入することで、自然と食習慣が改善されます。「サラダバーを導入し、野菜摂取量が増加した」など、企業の工夫が成果を上げている例もあります。
「健康に良い選択肢がすぐそばにある」環境を整えることが、社員の意識改革にもつながります。
就業中のマインドフルネス導入でメンタルケア
毎日数分でも呼吸法や瞑想によるマインドフルネスを習慣化することで、ストレス軽減や集中力向上の効果が期待されます。「昼休みに5分のマインドフルネスタイムを設けた結果、午後の業務効率が向上した」といった具体例も報告されています。
特にデジタル業務に従事する社員にとって、心身のリセット手段として非常に有効です。
7時間睡眠チャレンジで生活リズムを是正
健康経営において見落とされがちな睡眠ですが、十分な睡眠はパフォーマンスに直結します。社員に「7時間以上の睡眠」を目指してもらい、記録と共有を行う「睡眠チャレンジ」を実施する企業も増えています。
これは単なる記録にとどまらず、生活の質そのものの向上にも寄与する取り組みです。
全社対抗の健康イベントで習慣化を推進
運動、食事、睡眠などをテーマに、全社・部署対抗のイベントを開催することで、健康行動が「楽しく継続できるもの」になります。歩数や健康食の摂取回数を競い合う企画は、エンゲージメント向上にもつながる好事例です。
習慣化を定着させるための3つの視点
「強制」でなく「共感」から始めるアプローチ
生活習慣の改善は、上からの命令ではなく共感や納得感のあるアプローチから始めることが大切です。従業員に「これは自分のため」と感じてもらえるよう、目的や効果をしっかり伝えることが求められます。
可視化・数値化によるモチベーション維持
行動を記録し、グラフやスコアで可視化することで、自分の変化に気づきやすくなります。この「見える化」がモチベーションを維持する鍵となり、チーム間での共有も刺激となって個人の行動が広がりを持つようになります。
チーム・部署単位での巻き込みが効果的
健康習慣の定着には、組織単位での取り組みが効果的です。例えば「部署ごとの歩数ランキング」や「食事改善レポートの共有」など、日常業務と連動させることで職場文化として定着しやすくなります。
健康施策を仕組みで支える!健康支援サービス「WellWa」
WellWaとは?健康を「楽しく・チームで」続けられる新発想
WellWa(ウェルワ)は、従業員一人ひとりの生活習慣改善を支援しながら、チームで取り組む「たのしい健康経営」を実現するアプリケーションです。企業ごとにカスタマイズできる設計で、習慣化と組織活性化を同時に支援します。
生活習慣を見える化!歩数・睡眠・飲食の記録機能
歩数、睡眠、食事などの行動を手軽に記録でき、グラフやスコアで健康状態が可視化されます。従業員は日々の自分の変化に気づきやすくなり、モチベーションが自然と維持される仕組みです。
チーム対抗・スタンプ機能でコミュニケーション活性化
部署対抗イベントや「ありがとう」を送り合うスタンプ機能など、コミュニケーションを促進する仕掛けが随所に盛り込まれています。これは心理的安全性の醸成や、チームビルディングにも効果的です。
ポイント制度×福利厚生で“食”から健康をサポート
健康行動に応じてポイントが貯まり、福利厚生と連動して健康的な食品やドリンクと交換可能。「おいしい健康習慣」として、日常に無理なく組み込める仕組みです。
健康のROIも測定可能!サーベイ連動で効果を可視化
WellWaでは、行動データとサーベイ結果を組み合わせることで、生活習慣改善の効果=健康のROI(投資対効果)を定量的に可視化できます。人的資本情報開示においても重要なポイントとなります。
まとめ:生活習慣改善が組織力を高める理由と第一歩
健康習慣が定着すれば、組織はもっと強くなる
個人の生活習慣が整えば、パフォーマンスが向上し、、組織全体の生産性と一体感が高まります。習慣の定着は企業文化の進化であり、人への投資の成果として最も確かな手ごたえとなるでしょう。
まず始めたいのは「自分事化」×「楽しい仕組みづくり」
生活習慣は変えづらいもの。だからこそ、「自分のためになる」と感じられる仕掛けが必要です。楽しさ、可視化、共感をベースに、今こそ企業は「健康=戦略資産」として、第一歩を踏み出す時です。