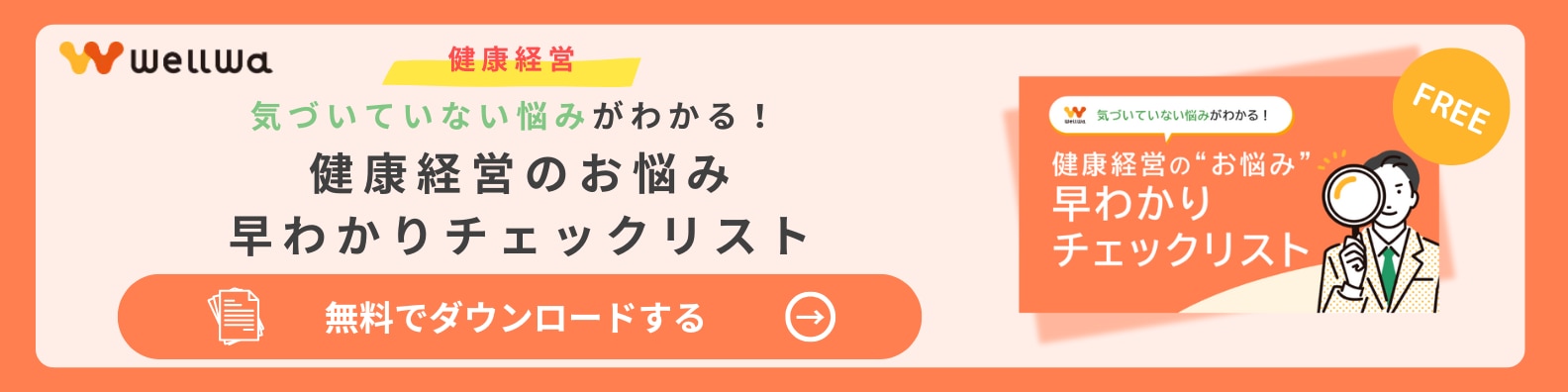健康も業績も上がる!「働き方改革」時代の健康的な仕事術
本記事では、健康的な働き方を実現するための実践的な仕事術や企業の仕組みづくり、最新の健康支援サービスの活用法を紹介します。
社員の心身を守りながら業績を伸ばす“健康経営”のヒントを、わかりやすく解説します。
目次[非表示]
- 1.なぜ今「健康的な働き方」が求められるのか
- 2.健康を害する働き方とは?見落とされがちな3つの落とし穴
- 3.健康と仕事を両立させる!実践したい仕事術7選
- 3.1.90分サイクルの集中×休憩ルーティン
- 3.2.スタンディングワークで座り過ぎを防ぐ
- 3.3.歩くミーティングで運動と創造性を両立
- 3.4.健康的な間食でパフォーマンスを維持
- 3.5.質の高い睡眠で仕事効率を底上げ
- 3.6.デジタルデトックスで脳をクリアに
- 3.7.タスク管理で「疲弊しない働き方」へ
- 4.続けるための職場づくりと仕組み化のポイント
- 4.1.健康習慣の定着には「組織の仕組み」が不可欠
- 4.2.“やらされ感”を減らす工夫
- 4.3.チームでの取り組みと可視化
- 5.企業導入が進む健康支援サービスの活用例
- 6.まとめ:個人も組織も、健康的な働き方で未来が変わる
なぜ今「健康的な働き方」が求められるのか
働き方改革・人的資本経営の中での健康の重要性
働き方改革や人的資本経営が注目される中、「健康的な働き方」は企業の競争力を左右するテーマとなっています。従業員の健康は、単なる福利厚生ではなく、経営資源の一つ=人的資本として位置づけられるようになりました。
健康経営優良法人認定制度や人的資本情報開示により、企業は健康への投資姿勢を社会に示すことが求められています。社員の心身の健康が、組織の持続可能性や生産性に直結するという認識が広がっているからです。
健康と生産性はトレードオフではない
かつては「成果を出すためには多少の無理が必要」と考えられていましたが、今では健康と生産性は両立できることが明らかになっています。健康な状態こそが、集中力や創造力、対人関係能力といった「働く力」の源泉なのです。
十分な睡眠や適度な運動、良質な食事は脳のパフォーマンスを高め、業務効率や判断力、ひいては仕事の質の向上につながります。健康は「コスト」ではなく「投資」という考え方が重要です。
企業・個人にとっての「健康損失」の見えないコスト
従業員の不調が表面化しないまま業務に支障をきたす状態、いわゆるプレゼンティーズム(presenteeism)は、多くの企業にとって「見えない損失」を生んでいます。欠勤や医療費のように数字に表れにくいため軽視されがちですが、実際には企業損失の多くを占めているとも言われます。
心身の不調が蓄積すると、離職や休職のリスクに直結します。こうした問題を防ぐには、日常の働き方を「健康前提」で設計することが重要な戦略となります。
健康を害する働き方とは?見落とされがちな3つの落とし穴
長時間労働と慢性的な睡眠不足
現代のビジネスパーソンが直面する最大の健康リスクの一つが慢性的な睡眠不足です。特に長時間労働が常態化している職場では、帰宅が遅くなり、睡眠時間が削られることで回復力が損なわれる悪循環に陥りがちです。
睡眠不足は集中力の低下やミスの増加を引き起こし、仕事の効率を著しく下げてしまいます。業務量と就業時間の適正化は、健康経営の基本中の基本と言えるでしょう。
座りっぱなし・動かなさすぎによる体力低下
デスクワーク中心の働き方が主流の現代では、1日8時間以上座っていることが当たり前になっています。しかし、長時間の座位姿勢は、肥満・心疾患・糖尿病・腰痛といった健康リスクを高めることが明らかになっています。
運動不足は筋力や代謝の低下にもつながり、疲れやすい体質をつくります。「動く時間」を業務の中に意識的に取り入れることが、健康的な働き方の第一歩となります。
メール・会議過多による集中力と精神消耗
「1日中メール対応と会議で終わってしまう」という声が多く聞かれる今、脳の疲労やストレスの蓄積が無視できない問題になっています。マルチタスクや会議過多は、集中力を奪い、業務効率を低下させます。
この働き方を見直すには、メールや会議の「断捨離」が有効です。「返信不要の情報共有」「会議の目的明確化」「ノーミーティングデーの導入」など、仕事のやり方そのものにメスを入れることが必要です。
健康と仕事を両立させる!実践したい仕事術7選
90分サイクルの集中×休憩ルーティン
人間の集中力は90分周期で上下します。このリズムに合わせて、90分作業+10〜15分の休憩を組み込むと、パフォーマンスを持続しやすくなります。集中タイムは通知を遮断し、休憩時は軽いストレッチや目のリフレッシュを行いましょう。
スタンディングワークで座り過ぎを防ぐ
長時間の座位姿勢を避けるため、スタンディングデスクの導入は有効です。メール返信や資料閲覧など軽めのタスクは立ったまま行うことで血流が促進され、集中力も高まります。
歩くミーティングで運動と創造性を両立
会議室に座って行う打ち合わせを、「歩きながら」行うウォーキングミーティングに変えることで、会話のテンポや発想の柔軟性が向上します。気分転換にもなり、アイデア創出が求められる場面に特に効果的です。
健康的な間食でパフォーマンスを維持
昼食後の眠気や夕方の集中力低下は、血糖値の乱高下が原因のことがあります。間食に「ナッツ」「無糖のお茶」「高カカオチョコレート」などを選ぶことで、血糖コントロールと集中維持を両立できます。
質の高い睡眠で仕事効率を底上げ
質の高い睡眠は、仕事のリズムと集中力に直結します。就寝1時間前はスマホを控え、カフェインを避ける。朝は日光を浴びて体内時計を整える。こうした基本的な習慣が、日中の生産性を大きく左右します。
デジタルデトックスで脳をクリアに
常に通知に追われる状態は、脳のマルチタスク疲労を引き起こします。「昼休みはスマホを見ない」「終業後は通知を切る」といったミニ・デジタルデトックスを習慣化し、集中力の回復を図りましょう。
タスク管理で「疲弊しない働き方」へ
仕事の疲弊感は、業務量だけでなく、「やるべきことが見えない状態」からも生じます。タスクを細分化し、重要度×緊急度で優先順位を明確にするだけで、心理的負担が軽減されます。
続けるための職場づくりと仕組み化のポイント
健康習慣の定着には「組織の仕組み」が不可欠
個人努力だけに頼った健康行動は、継続が難しいものです。朝礼前のストレッチ、健康イベントの定期開催など、会社ぐるみの取り組みが継続性を生み出します。
“やらされ感”を減らす工夫
健康施策を導入する際は、“やらされている感”の払拭が重要です。参加自由であることを前提にしつつ、ポイント付与や表彰制度で自然なモチベーションを生む工夫が効果的です。
チームでの取り組みと可視化
健康活動の「見える化」は、モチベーション維持に有効です。部署ごとの歩数ランキングや、ウェルネス達成バッジの配布など、楽しく成果を実感できる仕組みを取り入れましょう。
企業導入が進む健康支援サービスの活用例
WellWa:歩数や睡眠を楽しく記録・可視化
健康支援アプリ「WellWa」は、歩数や睡眠、運動記録をゲーム感覚で楽しめるのが特長です。部署単位でのチーム対抗戦やスタンプ機能など、「たのしく続く」仕組みで社員の主体的な参加を促します。
WellStock:職場に置ける健康飲料で食環境改善
「WellStock」は、職場に設置できる置き型の健康飲料支援サービスです。ルイボスティーや低糖質スムージーなど、選択肢を健康寄りに変えることで、自然な行動変容を促します。
サーベイで健康投資の効果を可視化
WellWaでは、25問サーベイによって健康行動や組織エンゲージメントを可視化し、投資対効果(ROI)を分析できます。これにより、「数値に基づいた改善サイクル(PDCA)」が実現します。
まとめ:個人も組織も、健康的な働き方で未来が変わる
健康は、個人の幸福度と組織の生産性の両方を高める最強の資産です。働き方改革や人的資本経営の視点からも、健康的な仕事術はこれからのスタンダードとなるでしょう。
まずはできることから小さく始めることが大切です。仕組み化・見える化・楽しさをうまく取り入れることで、個人と組織が一体となった「持続可能な健康経営」が実現します。