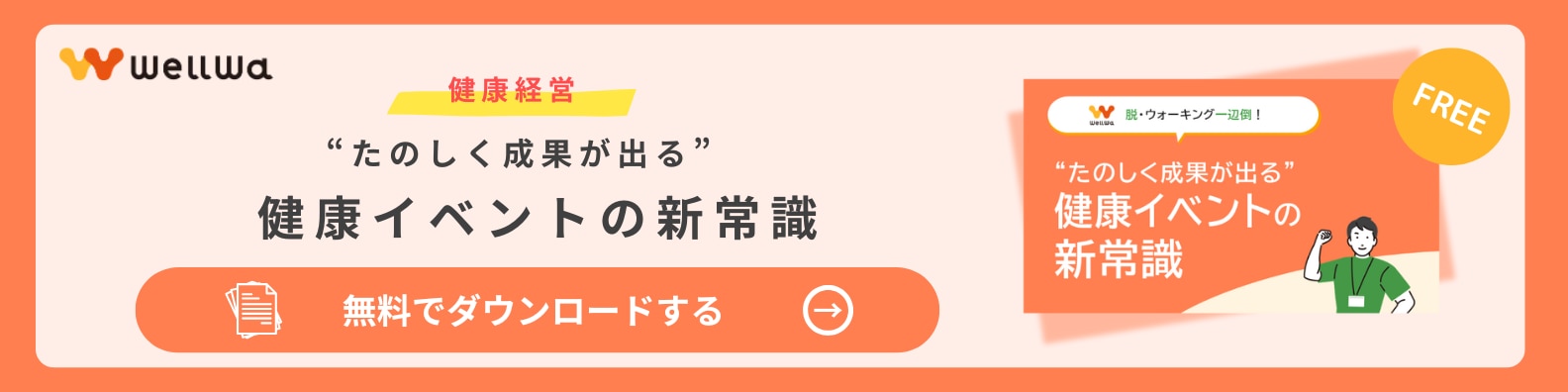1日何歩がベスト?企業ができる“歩数増加”の工夫と仕組み化
本記事では「1日何歩が理想か」という最新データを整理しつつ、社員が自然に歩数を増やせるオフィス設計やイベント企画など、企業が実践できる仕組み化の工夫を解説します。
目次[非表示]
歩数と健康の関係:なぜ「歩くこと」が注目されるのか
歩数と死亡率・生活習慣病リスクの相関
歩数と健康リスクの関係については、国内外の研究で明確な相関が示されています。特に注目されているのは、1日の歩数が増えるほど死亡率や生活習慣病のリスクが低下するという事実です。
国際的な研究によると、「1日6,000〜8,000歩でも十分な健康効果」が得られることが明らかになっており、厚生労働省の「健康日本21(第三次)」では、成人男女8,000歩、高齢男女6,000歩が目標として設定されています。
出典:厚生労働省「健康日本21(第三次)における身体活動・運動の目標」
歩くことは特別な運動器具や時間を必要とせず、誰もが手軽に始められる最も基本的な予防行動です。その一方で、デスクワークやリモートワークの普及により、「気づかぬうちに1日の歩数が2,000〜3,000歩以下」という人も増えており、健康リスクが見えにくくなっているのが現状です。
企業としては、社員の平均歩数や行動傾向を把握し、歩くことの価値をデータで「見える化」して伝えることが、行動変容の第一歩となります。
メンタルヘルスや集中力にも影響する“歩く力”
「歩くこと」は身体の健康だけでなく、心の健康にも大きな影響を与える行動です。
実際、ウォーキングによって脳内のセロトニンやドーパミンの分泌が促進されることで、気分の安定や意欲の向上に効果があるといわれています。
特に注目すべきは、軽度の有酸素運動がストレス軽減や不安の緩和に有効とされる研究が多数存在している点です。歩行はその代表的な手段であり、「考えすぎ」や「疲労感」による集中力低下の防止にも寄与します。
加えて、定期的に歩く習慣がある人ほど、認知機能や創造性、記憶力といった脳のパフォーマンスが維持されやすいことも報告されています。これは、特に知的労働の多いビジネスパーソンにとっては無視できない利点です。
つまり、「歩く力」は身体と心の両面に効く“万能ビタミン”とも言える存在であり、社員のメンタルヘルスケアや生産性向上に直結する行動習慣として企業が重視すべき取り組みの一つです。
WHOや厚労省も推奨する「日常活動としての運動」
「歩くこと」が健康習慣として推奨される背景には、世界的な保健機関のガイドラインが存在します。世界保健機関(WHO)は、成人に対して「1日あたり最低でも20〜30分程度の中強度の運動」を推奨しており、その具体的な手段として「歩行」が最も基本かつ重要な活動とされています。
出典:WHO「身体活動・座位行動ガイドライン2020」
また、厚生労働省が策定する「健康づくりのための身体活動指針(アクティブガイド)」でも、“+10(プラス・テン)=今より10分多く体を動かす”ことが奨励されており、歩行はその手軽で実践しやすい手段のひとつとして強く推奨されています。
特別な運動プログラムを組まなくても、「通勤時に一駅分多く歩く」「昼休みにオフィス周辺を散歩する」など、日常の“ついで”でできる歩行が健康に寄与することは明白です。
企業としては、こうした公的ガイドラインを社内で共有し、歩行=正しい生活習慣であるという共通認識を醸成することが、従業員の行動変容を後押しする土台となります。
健康維持に必要な歩数の目安と、最新研究のポイント
「1日1万歩」は本当に正しい?新常識の歩数ガイド
「1日1万歩」という目安は広く知られていますが、近年の研究では“質”と“継続性”がより重要であることが明らかになっています。最新の国際的なメタ分析では、1日7,000〜8,000歩でも十分な健康効果が得られるという結果が示されました。
また、1万歩という数字は、1960年代の日本の万歩計メーカーが作ったキャッチコピーに由来しており、必ずしも科学的根拠に基づいていなかったことも注目されています。大切なのは、「無理なく継続できる歩数を毎日積み重ねること」なのです。
年代・性別・業種別で考える適正歩数
歩数の目安は、年代や性別、ライフスタイルによって最適値が異なります。厚労省の調査では、20〜40代の男性は平均6,793歩、女性は5,832歩ですが、デスクワーク中心の業種では5,000歩未満という例も少なくありません。
出典:厚生労働省「令和元年 国民健康・栄養調査結果の概要」
そのため、企業の健康施策では、一律で歩数目標を設定するのではなく、部署や職種ごとの特性に応じた設計が必要です。例えば製造部門と総務部門では、そもそもの活動量が異なるため、「公平性」よりも「納得感」を優先する工夫が求められます。
歩数と運動強度(METs)で見る効果的な活動量
歩数だけでなく、運動の強度(METs:代謝当量)も考慮することで、より実効性のある健康支援が可能になります。例えば、「通常歩行」は約3.0 METs、「速歩き」は約4.3 METsとされており、同じ歩数でも速さや姿勢によって効果が変わります。
健康経営を推進する企業では、単なる歩数だけでなく、“どのような質の歩行か”を分析・評価に加えることが、人的資本経営の視点でも重要になります。
歩数が増えない3つの原因と企業ができる対応策
通勤・在宅勤務・座り仕事による活動量の減少
テレワークやフリーアドレス化が進む一方で、業務中の移動機会が激減している現状があります。特にリモート勤務では、通勤やオフィス内の移動がなくなり、1日の歩数が数百歩程度にとどまるケースも珍しくありません。長時間座ったままでいることで、血流の低下や集中力の減退にもつながります。
このような変化を放置すると、従業員の健康リスクだけでなく、生産性の低下やエンゲージメントの喪失にも直結します。企業側がこうした背景を把握し、歩く機会の創出に向けた具体的な仕組みを提供することが求められます。
継続できない原因は「心理的ハードル」と「面倒さ」
「歩かなければ」という義務感だけでは行動は続きません。多くの従業員が感じるのは、「意識して時間を取るのが面倒」「一人でやっても楽しくない」といった心理的ハードルです。特に成果がすぐに見えない健康行動は、モチベーション維持が難しい傾向があります。
だからこそ、健康施策には“「楽しさ」や「仲間とのつながり」を感じられる工夫が不可欠です。行動変容を促すには、「やらされる」のではなく、自分の意思で続けたくなる環境づくりが鍵を握ります。
企業の支援不足が歩数低下を招く構造
従業員の健康課題に取り組む姿勢はあっても、具体的な支援や仕組みが不足している企業は少なくありません。単発の健康キャンペーンで終わってしまい、継続的な改善や行動変容に結びつかない例も多いのが実情です。
こうした「支援の空白地帯」を埋めるためには、企業側が仕組みとして歩数支援を制度に組み込むことが効果的です。例えば、歩数記録の見える化や報酬制度との連動など、従業員が「日常の中で自然に歩ける」導線を設計する必要があります。
社員が自然に歩きたくなる!歩数アップの仕組みと工夫
オフィス環境でできる「無理なく歩ける動線設計」
企業がすぐに実践できる取り組みの一つが、オフィスの動線設計です。プリンターや会議室、給湯室などを意図的に分散配置することで、無意識のうちに歩数が増える工夫が可能です。
また、エレベーターを避けて階段を促す「階段推奨シール」や、「オフィス周辺マップ付きの散歩ルート」なども、小さな工夫で大きな効果を生む好事例といえるでしょう。
仕事と歩数を両立する「歩く会議」「立ち話」導入
業務の中に歩行を自然に取り込む手法として注目されているのが、「歩く会議」や「立ち話でのブレスト」といったミーティングスタイルです。長時間座ることによる身体の負担を軽減し、会議の効率化や発想の活性化にもつながります。
特にマネジメント層から率先して取り入れることで、社内の文化として根づきやすくなります。業務と健康を両立させるには、「ながら健康」の視点が不可欠です。
ゲーム感覚で続けられる「歩数チャレンジ」企画
歩数促進を習慣化させるには、ゲーム性や報酬の仕組みが効果的です。社内で歩数チャレンジイベントを開催し、部署ごとの対抗戦や個人ランキングを導入することで、参加率や継続率が飛躍的に高まる傾向があります。
こうした取り組みには、健康アプリやウェアラブル端末との連携も効果的です。定期的なイベントや報奨制度を通じて、「楽しく歩く」文化を醸成することが企業の役割です。
WellWaで実現する“歩数増加×組織活性化”の新しいカタチ

歩数イベントを「たのしく続ける」WellWaの魅力
WellWa(ウェルワ)は、「たのしく健康経営」を実現するアプリです。特に歩数イベントでは、日常の歩行をゲーム感覚で継続できる仕掛けが満載です。
参加者同士の応援やフィードバック、達成感の共有が可能なため、“やらされ感”のない健康習慣として社員に定着しやすいのが特徴です。
チーム対抗×スタンプ機能で歩くことが社内文化に
WellWaでは、チームごとの歩数合計によるランキングや、歩いた人へのスタンプ送信機能など、社内コミュニケーションを促進する設計がなされています。このように、“歩くこと”が業務の枠を超えて一体感やチーム力の強化にもつながる点が注目されています。
部署別ランキング×可視化でエンゲージメント向上
リアルタイムで歩数データが可視化されることで、部署間の競争意識が自然に高まり、モチベーション維持にも効果的です。また、可視化されたデータは、人事部門や経営層が健康経営の成果を分析・評価する材料としても活用できます。
健康投資としてのROIを測定・分析できる仕組み
WellWaには、健康施策の効果を25問のサーベイで可視化する機能があり、歩数向上とともにエンゲージメントや集中力の変化を数値化できます。これにより、人的資本経営の観点からも投資対効果(ROI)の検証が可能になります。
まとめ:企業が歩数を「成果」に変えるためにできること
小さな歩数が大きな組織成果を生む理由
歩行はシンプルな行動ですが、健康・集中力・組織活性化の要素をすべて内包する戦略的行動です。小さな積み重ねが、従業員の健康意識を高め、職場の生産性やエンゲージメント向上にもつながります。
まずは「歩くこと」に意識を向ける文化をつくり、継続しやすい仕組みを企業が整えること。それこそが、人的資本経営の第一歩と言えるでしょう。