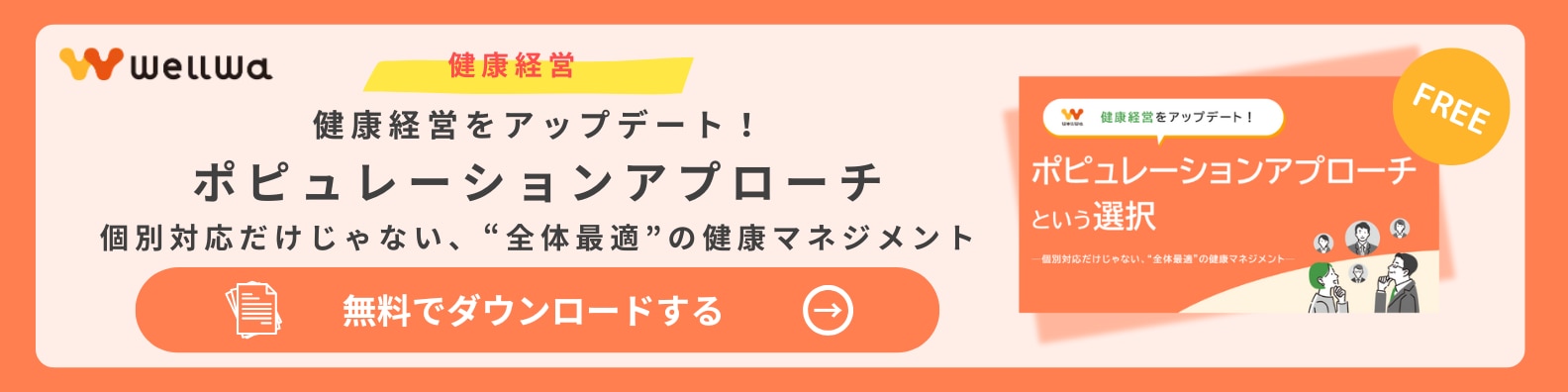成果を出す職場はここが違う!生産性を高める健康経営の新常識
企業が、本当に成果を上げるために必要なのは「働き方改革」だけではありません。今、多くの経営者や人事責任者の関心を集めているのが、従業員の健康とパフォーマンスを直結させる健康経営の考え方です。ただ制度を導入するだけでは効果は得られません。本当に意味のある健康施策は、組織全体の文化や行動にまで踏み込む必要があります。本記事では、健康経営がどのように生産性に寄与し、成果につながるのかを解説します。
目次[非表示]
- 1.なぜ今「健康経営」が注目されるのか?
- 2.健康経営が生産性に与える「3つの効果」
- 3.健康投資がうまくいかない企業に共通する課題とは?
- 3.1.「やらされ感」で終わる取り組み
- 3.2.人事部門のリソース・アイデア不足
- 3.3.個人任せで組織全体に浸透しない施策
- 4.成果につながるオフィス施策5選【環境・仕組み編】
- 4.1.データ活用で組織改善につなげる「健康スコア管理」
- 4.2.会話と行動が生まれる「チャレンジ型イベント」
- 4.3.ミッション制で楽しく続く「習慣化の仕掛け」
- 4.4.部署別ランキングで競争&協力の文化を醸成
- 4.5.デジタルとリアルを融合した健康体験の設計
- 5.コミュニケーション×健康の好循環をつくるには?
- 6.WellWaが実現する生産性向上の仕組みとは
- 7.まとめ:健康経営で実現する、生産性と働きがいの両立
なぜ今「健康経営」が注目されるのか?
生産性向上のカギは「プレゼンティーズム」の改善にあり
これまで「生産性向上」といえば、業務効率化やツールの導入といった働き方の外側が注目されてきました。しかし実際の職場では、体調が万全でないまま働き続けるプレゼンティーズムこそが生産性を最も低下させる要因となっています。
厚生労働省の調査でも、従業員のプレゼンティーズムが1人あたり年間50万円以上の損失を生んでいるとの試算があり、企業のコスト構造にも大きな影響を及ぼしています。これは、欠勤や離職といった目に見える損失以上に深刻な問題です。
出典:厚生労働省「データヘルス・健康経営を推進するためのコラボヘルスガイドライン」
心身の不調がもたらす組織パフォーマンスへの影響
心身の不調は、単なる健康の問題にとどまらず、モチベーション・集中力・判断力といった「見えない能力」全体に影響を与えます。たとえば、睡眠不足の従業員は注意力が散漫になり、ミスやトラブルが増える傾向があります。メンタル不調が続けば、コミュニケーションが減り、チーム全体の連携や創造性にもブレーキがかかります。
つまり、従業員一人ひとりの健康状態が、そのまま組織パフォーマンスの土台を形成しているということです。
日本企業での導入事例と注目の背景
健康経営がこれほど注目される背景には、経済産業省が推進する「健康経営優良法人認定制度(大規模法人部門)」の存在も大きく関係しています。いわゆる「ホワイト500」と呼ばれるこの制度では、健康投資の効果を“見える化”することが重視されており、ESG投資や採用ブランディングの観点からも企業価値を高める取り組みとして評価されています。
味の素やサントリー、キリンなど、大手企業でも健康経営と生産性向上を両輪で進める事例が広がりつつあり、中小企業でも関心が高まっています。
健康経営が生産性に与える「3つの効果」
健康習慣の改善での労働生産性向上
「朝食の習慣化や水分補給、適度な運動」こうした基本的な生活習慣の改善が、実は日々の集中力・判断力に大きな影響を与えます。たとえば、ウォーキングやストレッチを取り入れることで午後の眠気が減り、1日を通して安定したパフォーマンスを維持できるようになるといった効果は、多く報告されています。
健康施策は「プライベートの問題」と切り離すのではなく、業務時間の生産性向上につながる投資として設計することが重要です。
コミュニケーション量の向上でエンゲージメントUP
健康経営がうまく機能している組織では、単なる健康施策の枠を超えて「つながりのある職場」づくりが進んでいます。たとえば、ウォーキングイベントや水分補給チャレンジなど、参加型の健康企画をチーム単位で実施することで、自然と雑談や応援の文化が生まれます。これにより、部門の壁を越えた交流や、心理的安全性の醸成が進み、結果としてエンゲージメントの向上にもつながります。
メンタルケアの強化で離職リスクの低減
プレゼンティーズムと並ぶ組織課題が、メンタルヘルス不調による離職リスクです。精神的な疲弊は、早期退職や長期休職というかたちで顕在化しやすく、対応が後手に回れば組織への影響は非常に大きくなります。
ここでも鍵になるのは、「日常的な会話のきっかけ」や「変化に気づける職場風土」を整えること。健康経営は、こうしたメンタル面の改善と直結しており、離職防止や組織安定に寄与する攻めの福利厚生として機能します。
健康投資がうまくいかない企業に共通する課題とは?
「やらされ感」で終わる取り組み
多くの企業が健康施策に取り組むものの「全社で実施したのに参加率が上がらない」「途中で形骸化した」という課題が散見されます。その多くは、施策がトップダウンの一方通行であることが原因です。
健康経営は誰かにやらせるものではなく、自分ごととして参加したくなる工夫が重要です。インセンティブ設計や、チームでの取り組み導入によって「楽しい」「仲間とできる」感覚を引き出す仕組みが不可欠となります。
人事部門のリソース・アイデア不足
忙しい人事部門にとって、健康施策をゼロから企画・運用するのは大きな負担です。加えて「何が効果的か分からない」という声も多く、実行まで至らない構想止まりの健康経営が増えているのが現状です。
アウトソースを視野に入れ、外部ツールや仕組みを丸ごと活用するのもひとつの手段です。ポイント制度やチーム設計・効果測定までパッケージ化されたソリューションを用いることで、担当者の負担を最小限にしつつ、成果が得られる運用が可能になります。
個人任せで組織全体に浸透しない施策
「健康管理は自己責任」とする職場文化が根強いと、どれだけ良い施策を整えても定着しません。健康経営を組織全体に浸透させるためには、職場ぐるみで取り組むカルチャーづくりが不可欠です。そのためには、管理職の巻き込み、取り組み状況の可視化、評価制度との連動といった組織を動かす仕掛けが必要です。
成果につながるオフィス施策5選【環境・仕組み編】
データ活用で組織改善につなげる「健康スコア管理」
企業が生産性を高めるために不可欠なのが、「定量的な指標による可視化」です。健康経営においても例外ではなく、個人の行動だけでなく、組織全体の健康状態を“スコア”として可視化する仕組みが求められています。
睡眠・運動・水分摂取・ストレスといった日常の健康行動をアプリで記録し、その変化をダッシュボードで確認できれば、管理者側は、職場全体の健康状態を把握しやすくなります。それを基に施策のPDCAを回していくことで、成果に直結する健康投資へと変換できます。
会話と行動が生まれる「チャレンジ型イベント」
制度があっても、実際にエントリーする人がいなければ意味はありません。そこで効果的なのが、参加型・体験型の健康チャレンジイベントです。
たとえば「水分補給チャレンジ」や「階段のぼり選手権」など、業務中に取り組めるミニイベントを実施することで、自然と会話と行動が生まれる環境がつくられます。重要なのは“成果”を競うのではなく、“行動のきっかけ”をつくることです。
ミッション制で楽しく続く「習慣化の仕掛け」
健康行動は、単発で終わらせず“毎日無理なく続けられること”が重要です。そこで有効なのが、1日1つの健康行動を促す「ミッション制」の導入です。
「15時になったら立ち上がってストレッチ」「朝1杯の白湯を飲もう」など、小さなタスクが毎日届き、完了するとスタンプがもらえる設計は、ゲーム感覚で継続を後押しします。できたが積み重なることで、行動が習慣になり、最終的には体調や仕事の質の改善につながります。
部署別ランキングで競争&協力の文化を醸成
チーム単位でのランキング制度を導入すれば、健康への取り組みが個人の努力から組織の推進力へと変化します。部署別にチャレンジ参加率やポイント達成率を可視化することで、社内に自然な競争と応援の文化が生まれます。
さらに、上位部署を称える制度や、サンクススタンプの交換などを組み合わせれば、楽しみながら全社を巻き込む健全なカルチャー形成が促進されます。
デジタルとリアルを融合した健康体験の設計
生産性向上に寄与する施策は、ツールやデジタル設計だけにとどまりません。アプリ内ミッションをリアルな社内環境と連動させることで、五感を使った体験が従業員の行動変容を後押しします。
たとえば、「ミッションクリアでポイントが貯まる」「ポイントが貯まると健康ドリンクと交換できる」」など、デジタルとフィジカルの連動が、職場の空気そのものを変える原動力になります。
コミュニケーション×健康の好循環をつくるには?
雑談・共感が生まれる「偶発的接点」の設計
会話が生まれる職場は、信頼関係が築かれやすく、心理的安全性が高まります。とはいえ、わざとらしい雑談促進は逆効果。そこで効果的なのが、偶発的に人が交わる仕掛けです。
たとえば、チャレンジの途中経過をシェアする掲示板や、健康習慣の取り組み状況を表示する社内ディスプレイなど、見える化によって自然な声かけが生まれる環境を整えることがポイントです。
チーム対抗やスタンプ送信で広がるつながり
個人の努力に加え、仲間と取り組める仕掛けがあると継続率は飛躍的に向上します。チャレンジにチームで参加したり、行動達成に対してスタンプやリアクションを送れる設計は、心理的報酬と共感の醸成に効果的です。
このように「応援」「承認」「共有」が日常的に起きる仕組みは、健康とコミュニケーションの好循環を生み出します。
オフィス内「健康スポット」で自然な交流を
健康支援を促進するには、行動の起点となる物理的な仕掛けも不可欠です。たとえば「オフィス内の健康スポット」―水分補給ステーション、ストレッチエリア、歩数計付きの導線設計などを整備すれば、自然と従業員が集まり、会話が生まれる場になります。
健康支援と社内交流を切り離さずに設計することが、結果的に生産性とエンゲージメントを同時に引き上げる近道となります。
WellWaが実現する生産性向上の仕組みとは
「チャレ活」や「健康選手権」で部署を巻き込む
WellWa(ウェルワ)では、部署単位で参加できる「チャレ活(チャレンジ活動)」や、全社規模の「健康選手権」など、楽しみながら健康習慣に取り組める施策が充実しています。
部署ごとの達成度や参加率がランキングで可視化することもでき、自然と部署対抗戦のような雰囲気が生まれ、巻き込み型の運用が可能になります。
「デイリーミッション」で継続的な健康アクションを支援
毎日届く健康習慣ミッションをクリアすることでポイントが貯まり、スタンプやインセンティブに変換できるのがWellWaの特長のひとつです。「短時間」「低負荷」で、業務の合間に無理なく続けやすく、挫折しにくい設計となっています。
この継続しやすい設計が、健康習慣の定着と生産性向上をサポートします。
WellStockで生まれる健康×福利厚生の新しい形
WellWaで貯まったポイントは、オフィス内のWellStock(ウェルストック)で健康ドリンクなどと交換が可能です。福利厚生と連動した行動変容施策として機能し、「健康にいいことをすればするほど得する」という体験を従業員に提供できます。
さらに、交換時に雑談が生まれたり、社内のつながりが深まることで、職場の空気がやさしく前向きになる副次効果も期待できます。
まとめ:健康経営で実現する、生産性と働きがいの両立
生産性の源泉は、ツールや制度ではなく「人」にあります。そして、その人が本来の力を発揮できる環境を整えることこそが、健康経営の基盤となります。
- 健康状態の可視化と習慣化の設計
- 部署を巻き込む仕組みとチーム戦略
- 会話と共感を生む場と仕掛け
これらを統合したWellWaのようなサービスを活用すれば、生産性向上と働きがいを両立できる組織基盤の構築につながります。