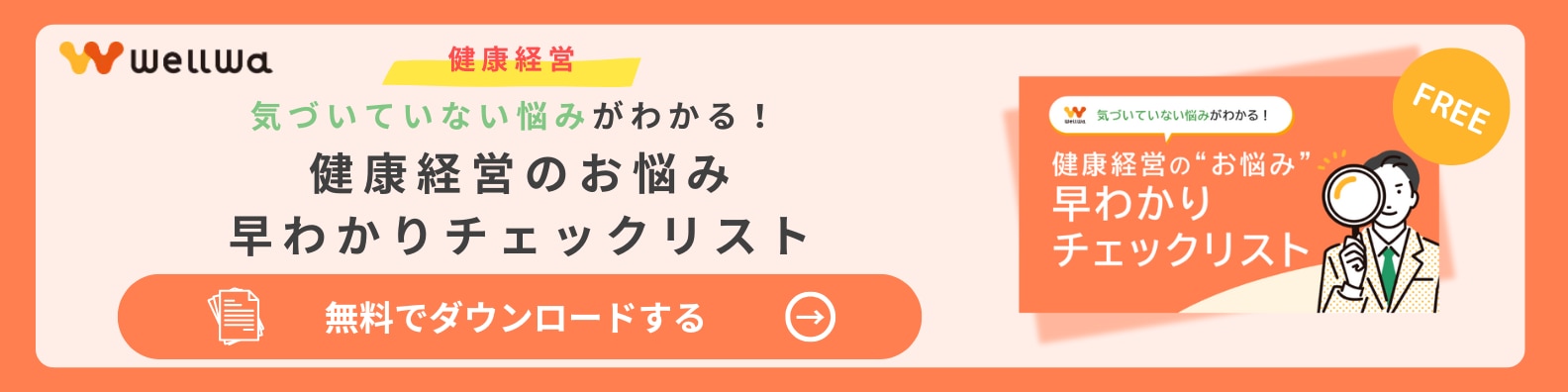【健康経営2025年】企業が注目すべき最新トレンドと現在地
2025年、健康経営は「従業員の健康管理」を超え、企業価値を高める成長戦略の中核として進化しています。
本記事では、経済産業省が提唱する「健康経営2.0」や最新の官民連携動向、性差・年代別施策、心の健康保持、そして社会全体への波及まで、企業が押さえるべき最新トレンドと実践事例を詳しく解説します。
健康経営推進のあり方について
健康経営の波及効果と目指すべき姿(2.0)
近年、健康経営は「従業員の健康管理」という枠を超え、企業の成長戦略の一環として注目されています。従業員の生産性向上や医療費削減といった直接的な成果に加え、エンゲージメントの向上や企業価値向上といった波及効果も明らかになりつつあります。
経済産業省が提唱する「健康経営2.0」では、健康経営を「企業価値向上の投資」として位置づけています。経営者にはリーダーシップを発揮し、人的資本経営の中核に健康を据えることが求められます。
健康診断受診率の向上や禁煙施策といった個別の取り組みにとどまらず、経営戦略と一体となった包括的な施策設計こそが、今後の健康経営のあるべき姿といえるでしょう。
参照:経済産業省資料「健康経営の推進」
健康経営の現在地:新たな官民連携へ
日本における健康経営の取り組みは、年々制度化が進み、官民連携のもとで発展しています。「健康経営優良法人認定制度」や「健康投資管理会計ガイドライン」など、企業活動を支援する枠組みが整備され、2024年度には「健康経営銘柄」選定企業が過去最多を記録しました。投資家からの注目も高まり、背景にはESG経営や人的資本開示といった世界的潮流があります。
民間では、健康経営に特化したコンサルティング企業やアプリケーションサービスの普及が進み、データに基づく施策運用(PDCA)の高度化が加速しています。今や健康経営は「一部の先進企業の取り組み」ではなく、企業価値を左右する「共通言語」になりつつあるのです。
これからの健康経営「従業員だけでなく社会全体へ」
健康経営の射程は、もはや社内施策にとどまりません。企業が社会と共に健康を育む、そんな潮流が始まっています。
大手飲料メーカーによる地域住民向けの健康セミナーの実施や、大学との共同研究を通じた学生の健康啓発などがその一例です。企業が保有する知見やインフラを活かして、社会全体の健康水準を高める「社会実装型健康経営」の可能性が広がっています。
企業が地域や次世代と関わる「共創」の姿勢を見せることは、SDGsやCSV(共通価値の創造)とも親和性の高いアプローチです。健康経営の成果を社外にも波及させることが、企業の存在意義やブランド価値の向上につながるでしょう。
国際展開によるヘルスケア産業の成長機会
健康経営はグローバル市場においても関心が高まっています。特に、アジア諸国では生活習慣病の増加や高齢化が進行しており、日本企業の予防医療や健康支援ノウハウが強く求められています。
経済産業省は「アジア健康構想」などを通じて、健康経営の知見を輸出し、ヘルスケア産業の国際展開を後押ししています。日本企業が持つ予防・生活習慣改善のナレッジやサービスは、海外企業との連携やビジネス機会の創出にもつながり得るのです。
教育機関との連携事例
教育機関との連携も重要性を増しています。ある企業では、大学と連携し、「次世代健康経営共創講座」を開講。県内の企業担当者と学生を対象に、健康リテラシーを高める活動を行っています。
出典:新潟大学「次世代健康経営共創講座」(企業・学生対象講座)
2025年の最新トレンド:多様性への配慮
2025年時点では、従来の一律的な健康施策ではなく、性別や年齢、メンタルの状態といった個人差に配慮した取り組みが企業競争力の鍵となっています。注目される3つの重点分野は以下の通りです。
1. 性差に配慮した健康施策
これまでの企業施策では見落とされがちだった「女性の健康課題」が、今や経営レベルでの関心事となっています。特に、月経・妊娠・更年期など、ライフステージごとの変化に伴う体調の波は、就労継続や生産性に密接に関わる重要なテーマです。
経済産業省も「女性の健康経営」への取り組みを強化しており、企業によっては婦人科検診の強化、PMS対応休暇、フェムテックサービスとの連携など、制度面でも変革が進んでいます。
単に制度を整えるだけではなく、「配慮されている」と実感できる心理的安全性の醸成や、社内での適切な情報提供(社内セミナーやポータル発信)も効果的です。性差への配慮は働きやすさだけでなく、離職率の低下やキャリア継続支援という観点でも、企業価値を高める施策といえるでしょう。
2. 高年齢層への対応
少子高齢化が加速する中、企業の現場では50代〜60代のベテラン人財が長く働ける職場設計が課題になっています。身体的な衰えに配慮した作業環境の改善や、フレキシブルな勤務体制、再雇用後の役割設計など、年齢に応じた配慮が必要です。
近年では「健康年齢の維持」に向けた個別支援が進んでおり、運動機会の提供・生活習慣病予防のセミナー・定期的な健康データのフィードバックなどを組み合わせた支援が効果を上げています。加えて、デジタルリテラシーや役割の変化に伴う心理的ストレスの軽減にも注目が集まり、身体面だけでなくキャリア支援やメンタル面での伴走設計も今後の鍵となります。
3. 「心の健康保持」へのシフト
従来の事後対応型メンタルヘルスから、予防・早期発見を重視する「心のウェルビーイング維持」へ移行しています。
日々の気分やストレス状態を定期的に確認し、早期に変調に気づく仕組みを導入したり、1on1ミーティングやチャットベースでの相談窓口を設けたりする企業が増加しています。また、「孤独・つながり不足」がメンタルに影響するというエビデンスに基づき、社内コミュニティ・雑談スペース・デジタル上での共通体験の創出も、心の健康を守る重要な要素とされています。
このように、心の不調を診断名に落とし込む前の「グレーゾーン」をいかに支えるかが、今後の健康経営の優劣を分ける要素となっていくでしょう。
性差・年代に配慮した健康施策のポイントとは
女性の健康推進を評価軸に加えた制度改定のポイント
2025年以降、健康経営において特に注目されているのが「性差」に配慮した制度設計です。今後の評価制度では、女性の健康に関する取り組みが明確な評価対象になる流れが加速しています。
月経や更年期に関するサポート体制の整備、婦人科健診の受診促進、育児とキャリアの両立支援などが評価項目として盛り込まれ始めています。制度改定においては、「選択と配慮」がキーワードです。すべての女性に同一の対策を適用するのではなく、ライフステージに応じた柔軟な対応が求められます。
参照:内閣府男女共同参画局「厚生労働省における男女の性差に配慮した施策の推進について」
高年齢層対象プログラムの実装事例とコスト構造
高齢従業員の増加に伴い、企業は健康施策の再設計を迫られています。特に、運動機能・体力の維持や生活習慣病の予防は、高年齢層の就労継続における大きな課題です。
コスト面では、初期投資こそ一定額必要ですが、プレゼンティーズム(出勤はしているが、パフォーマンスが低い状態)改善による生産性向上がコスト回収に寄与しています。
年代別ニーズを捉える組織データ戦略の仕組み構築
20代はメンタルケアへの関心が高く、30〜40代は育児や介護との両立が健康行動に影響を与え、50代以降は慢性疾患予防への意識が強まる傾向があります。
これらの違いを可視化し、施策に活用するには、部門別・年代別の健康データを蓄積・分析する仕組みが不可欠です。最近では、スマートウォッチ連携やアプリでの記録データを基に、エンゲージメント指標と照合する「組織におけるデータ戦略」が注目されています。
「心の健康保持」への対応の仕方について
制度改定で変わる評価項目と運用のチェックポイント
メンタルヘルス施策は、「予防」「早期発見」「復職支援」の3段階で設計されることが一般的ですが、2025年からは「心の健康保持」への定性的な配慮も評価項目に含まれる傾向にあります。
ストレスチェックの結果を単なる集計で終わらせず、改善アクションの明示と経年比較を行っているか、社内でオープンに議論される文化が根付いているか、といった点が重視されます。
気軽に相談できる社内体制の構築とその効果
メンタルヘルス対策において、「誰に相談できるのか」という心理的安全性は、実効性に大きく影響します。近年は、産業医や人事部門だけでなく、ピアサポーター(社内メンター)を活用した支援体制の構築が進んでいます。
ある企業では、全社員に相談窓口ポータルを配布し、心理士とのチャット相談も導入。結果として、ストレスチェックの高リスク者の減少と、離職率の改善につながりました。
心の健康に関するデータ活用と改善サイクルの導入
ストレスチェックや勤怠データは、心の健康状態を把握する貴重な手がかりです。重要なのは、定点観測と横断的分析による「改善サイクル」の仕組み化です。勤怠データから残業増加や有給取得低下を検知し、該当部署でメンタルリスク調査を実施。その結果をもとに施策を修正し、再度データを確認する、というPDCAの循環が理想的です。
WellWaで実現する心の健康保持
チャレ活・健康選手権で部署間の繋がりを創出
KIRINが提供するWellWa(ウェルワ)は、心の健康保持にも強みを持つ健康経営支援アプリです。「チャレ活」や「健康選手権」といった参加型イベントは、部署を超えた交流を促進します。孤立感やストレスは、職場での人間関係にも深く関わる要素です。チームで楽しむイベントを通じて、心理的なセーフティーネットが自然と形成されるのがWellWaの特徴といえるでしょう。
ポイント機能で心の健康の「継続」へ導く
WellWaには、日々の健康活動に応じてポイントが貯まり、飲料交換できる「WellStore」「WellStock」といった福利厚生機能が備わっています。
日々の小さな行動が積み重なることで、自分の変化に気づき、モチベーションが保たれる。WellWaはこの「継続性」に着目し、心身の健康を無理なく日常に取り入れられるよう設計されています。
まとめ
健康経営は今、企業戦略の中核へと進化しつつあります。2025年以降は、性差・年代への配慮、心の健康保持、社会との共創といった新しい視点が重視され、評価制度も大きく変化していくでしょう。
このような流れに対応するには、自社独自のデータ分析と施策設計、そして継続性を意識した仕組みづくりが不可欠です。WellWaのような包括的な支援ツールを活用することで、従業員の健康と組織の成長を同時に実現する健康経営を、より確実に推進していくことができるでしょう。