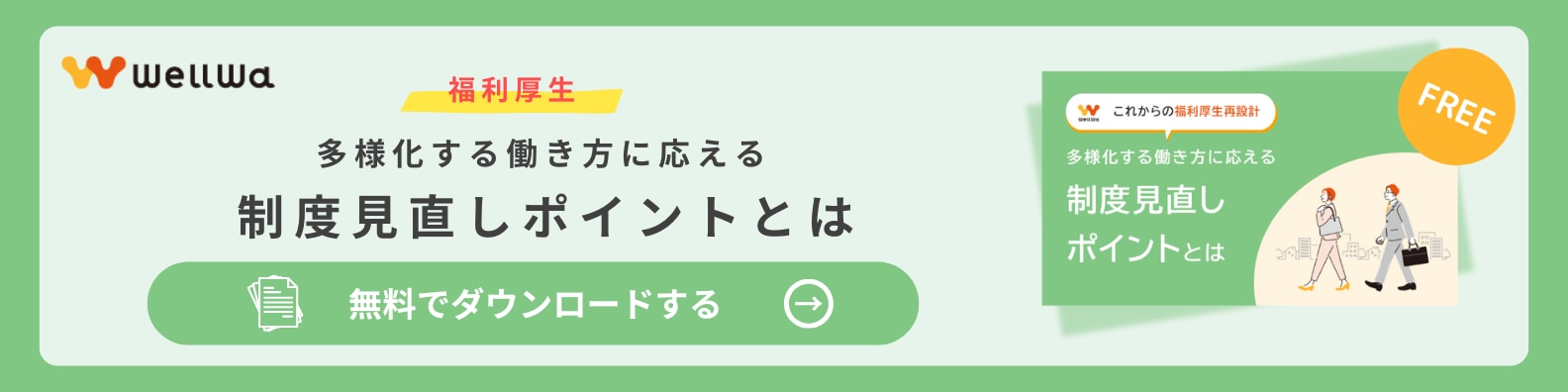休める職場が人を育てる!オフィスに必要なリセット空間のつくり方
かつてのオフィスにおける「休憩スペース」は、単に疲れたときに一息つくための“待避場所”でした。しかし今、その役割は大きく変わりつつあります。社員がパフォーマンスを最大限に発揮し、健やかに働き続けるためには、「集中」と「リセット」のバランスが不可欠です。とりわけ、組織の持続可能性や健康経営の実現を目指す企業にとって、戦略的な休憩スペースの設計は欠かせないテーマとなっています。
本記事では、オフィスにおける休憩スペースの重要性と、今すぐ取り入れられる最新のトレンドをご紹介します。
目次[非表示]
なぜ今、オフィスに「休憩スペース」が必要なのか?
働き方の変化とリフレッシュ環境の重要性
テレワークと出社のハイブリッド勤務が広がり、働く時間と空間の境界が曖昧になる中で、オフィスの果たす役割も変化しています。単に作業する場所ではなく、社員同士が交流し、気持ちを切り替えることができる「心身回復の機能」が求められているのです。
とりわけ、目まぐるしくタスクが切り替わる現代のビジネス環境においては、集中しっぱなしの状態が続けば、パフォーマンスは低下してしまいます。意図的に脳と身体を休ませる空間の創出こそが、成果を生み出すエネルギー源となるのです。
生産性・創造性に与えるポジティブな影響
人は、休息を取ることで脳のワーキングメモリをリセットし、再び集中力を取り戻せるといわれています。さらに、無意識にぼんやりしている“デフォルト・モード・ネットワーク”の状態では、アイデアがひらめきやすくなるとも言われており、良質な休憩が創造性にも好影響をもたらすことが、科学的にも示されています。
つまり、休憩スペースはただの“サボり場”ではなく、集中力の再起動やひらめきのきっかけを生む仕掛けとして機能するべき空間なのです。
社員の満足度・定着率を左右する空間づくり
社員のエンゲージメントや定着率は、報酬や業務内容だけでなく、「働きやすい環境が整っているかどうか」も強く影響を受けます。特に20〜30代の若手社員を中心に、働き心地や居心地の良さへの意識が高まっており、オフィスの休憩スペースはその象徴的な要素となっています。
気軽に立ち寄れるカフェのような空間、植物に囲まれた癒やしのゾーン、ちょっと横になれる仮眠スペース。こうした場所があるだけで、「この会社は社員を大事にしている」という信頼感が生まれ、結果的に離職の抑止につながるのです。
オフィス休憩スペースの最新トレンド4選
カフェ風ラウンジ:雑談とアイデアが生まれる第三の場
オフィスの中に、まるで街角のカフェのような空間を設ける企業が増えています。そこは、仕事場でも自宅でもない第三の場として機能し、社員が自然とリラックスしながら会話を交わせる場所です。
コーヒーを飲みながらカジュアルな雑談を交わす時間が、部署を超えたアイデアの交換や、新たなプロジェクト立ち上げのきっかけになることも少なくありません。カフェ風の空間は、堅苦しさを取り除き、人間関係をなめらかにする潤滑剤のような役割を果たします。
リラックス×健康を両立する「ながら空間」
ストレッチや軽い運動ができるマットスペースや、マッサージチェア、足裏のツボ押しマットを置いたコーナーなど、「ながら健康」が意識された休憩スペースも注目を集めています。
こうした空間は、休憩中にも健康を意識できることから、「休んでいるのに罪悪感がない」「身体も気持ちも軽くなる」と社員の満足度が高く、プレゼンティーズムの軽減にもつながっています。
「交流型」自販機が会話のハブに
一見、普通の自動販売機のようでいて、実はコミュニケーションを促す仕掛けが施されている交流型自販機も有効です。社員のおすすめコメントが貼られていたり、ランダムに当たりが出る遊び心があったりと、つい誰かに話したくなるような演出が施されています。
そんな何気ない仕掛けが、「これ知ってる?」「それ、美味しかったよね」といった雑談の種となり、結果的に職場のつながりを生む起点になります。
ながら運動ができるヘルスサポート型スペース
デスクワークの合間に軽く身体を動かせる「ながら運動」ができるスペースも、現代オフィスの新定番になりつつあります。バランスボールに座れるカウンター席や、ステッパーを使って足を動かしながら会話ができるスペースなどが代表例です。
これらは、運動とコミュニケーションを同時に促進できるという点で、健康経営とエンゲージメント向上を両立する仕組みとして注目されています。
成功する休憩スペースの共通点とは?
目的と対象を明確にした設計コンセプト
良い休憩スペースは、単に「なんとなくおしゃれな空間」であるだけでは成立しません。重要なのは、その空間が誰に、どのような状態になってもらいたいかという設計意図に基づいて作られているかどうかです。
たとえば、集中力を回復させたいなら、照明はやや落ち着いた色温度が適しています。気分転換や同僚との会話を促すなら、視線が交わりやすいカウンター型の配置に変更してみるのも、ひとつの手段です。利用者の年代や職種のニーズに応じて、自分のリズムを取り戻せる静寂と、にぎわいのある共有スペースをうまく組み合わせる設計が理想的です。
「滞在時間が伸びる」空間演出と配置の工夫
よくある失敗例は、せっかく休憩スペースを設けたのに、使われずに放置されてしまうケースです。これは「そこに行きたい」と思わせる要素が欠けていることが主な原因です。
たとえば、観葉植物やアートの装飾が施されているだけでも空間の心理的印象は変わります。音楽やアロマを使って五感を心地よく刺激する演出は、「ただの休憩スペース」から「行くと癒される空間」へと価値を引き上げてくれます。
また、執務スペースのすぐ近くに設置するより、少し離れた目的を持って足を運ぶ距離に配置することで、より効果的なリフレッシュが促されます。「ちょっと寄りたくなる場所」にする工夫で、滞在時間と活用率が高まります。
社員の声を反映した巻き込み型プロセス
休憩スペースの設計においては、利用者である社員の声を反映することが何よりも大切です。トップダウンで空間を整えるのではなく、「どんな場所が欲しい?」「どんな工夫があったら使いたくなる?」という声をヒアリングしながら、空間づくりに社員が関わるプロセスを、設計段階から組み込むことが理想です。
そのプロセス自体が、職場への愛着や帰属意識を高め、導入後の定着にも大きく貢献します。「自分たちの声で生まれた場所だから使いたくなる」そんな意識を醸成することが、戦略的な休憩スペースの土台となります。
休憩スペースを福利厚生の中心に据えるべき理由
単なる「休む場所」から「組織文化を育む空間」へ
従来の休憩スペースは、休むための消費空間として位置づけられてきました。しかし今、先進企業ではそこを「組織の価値観を伝える文化発信の場」として活用する動きが広がっています。
たとえば、空間内に会社のミッション・ビジョンをさりげなく掲示したり、社員の健康行動や社会貢献活動を紹介するボードを設置したりすることで、社員は自然と企業理念と接点を持つことになります。リラックスの場でありながら、組織の一員であることを自覚できる内発的なモチベーションの源として機能するのです。
ウェルビーイング経営との連動性
健康経営・人的資本経営の潮流の中で、「ウェルビーイング」は単なる流行語ではなく、経営戦略の中核に位置づけられつつあります。心身の健康、つながり、自己実現—これらを支えるインフラとして、休憩スペースはますます重要性を増しています。
特に「働きやすさ」「働きがい」といった社員の主観的満足度を可視化・改善していく上で、休憩スペースは組織の精神面におけるインフラとして重要な役割を果たします。
福利厚生施策としての評価・定着への寄与
福利厚生施策においては、「存在すること」より「活用されること」が評価の対象になります。その点で、日常的に立ち寄りやすい休憩スペースは、社員の実感も得やすく、施策定着の入り口となる重要な要素です。
また、休憩スペースを核に、健康アプリやポイントプログラムと連携させることで、健康行動の可視化・促進につながるため、福利厚生の活用の選択肢が広がり、戦略的な運営が可能になります。
WellWaが提供する自然に会話が生まれる空間と仕掛け
WellWaとは:健康×コミュニケーションをつなぐ新発想
WellWa(ウェルワ)は、健康行動の習慣化と、社内コミュニケーションの活性化を同時に実現するサービスです。従来の福利厚生が“与えるもの中心だったのに対し、WellWaは社員の主体性とつながりを引き出す巻き込み型の設計が特徴です。
このような設計は、休憩スペースづくりにおいても非常に親和性が高く、自然と社員が集まり、会話が生まれ、健康にもつながるという価値を創出しています。
「チャレ活」や「健康選手権」で、休憩時間をもっと有意義に
WellWaが提供する「チャレ活」や「健康選手権」は、チームで参加できるミッション型の施策です。たとえば、昼休みにストレッチをする、階段を使う、水分補給を記録するといった健康行動を、ゲーム感覚で楽しみながら取り組めます。
こうした仕掛けは、健康増進につながるだけでなく、同僚との自然な雑談や励まし合いを生む“会話のきっかけ”にもつながります。
WellStockで出社する理由をつくる
出社率やオフィス回帰の推進に課題を感じている企業においては、「WellStock(ウェルストック)」が有力なソリューションとなります。これは、チャレ活で獲得したポイントを使って、オフィス内のドリンクと交換できる仕組みです。
この仕掛けがあることで、「休憩がてら寄ってみよう」「ポイントを使ってリフレッシュしよう」と、社員がオフィスに出社する動機が生まれやすくなるのです。
健康データが会話のタネに変わるコミュニティ型設計
WellWaでは、歩数やミッション達成率などの健康データがチーム単位で共有され、可視化されます。これによって、「すごいね、昨日はよく歩いたね」「そのミッション、私もやったよ」といった気軽なコミュニケーションが生まれやすくなります。
健康を“個人の努力”ではなくみんなで楽しむ文化に変えるこの設計は、休憩スペースをコミュニティのハブにする理想的なアプローチにつながります。
まとめ|休憩スペースは企業価値を高める空間になる
休憩スペースは、ただ疲れを癒やす場所ではありません。社員の健康を支え、つながりを育て、創造性を引き出すための戦略的な空間なのです。目的と設計思想を持って整えられた空間は、組織文化をかたちにし、社員のエンゲージメントを高める職場づくりの原動力になります。
WellWaのような仕組みと組み合わせることで、休憩スペースは単なる福利厚生ではなく、「健康経営の起点」としての価値を創出します。今こそ、“休める職場”の創造、すなわち企業の未来を支える空間づくりに踏み出してみてはいかがでしょうか。