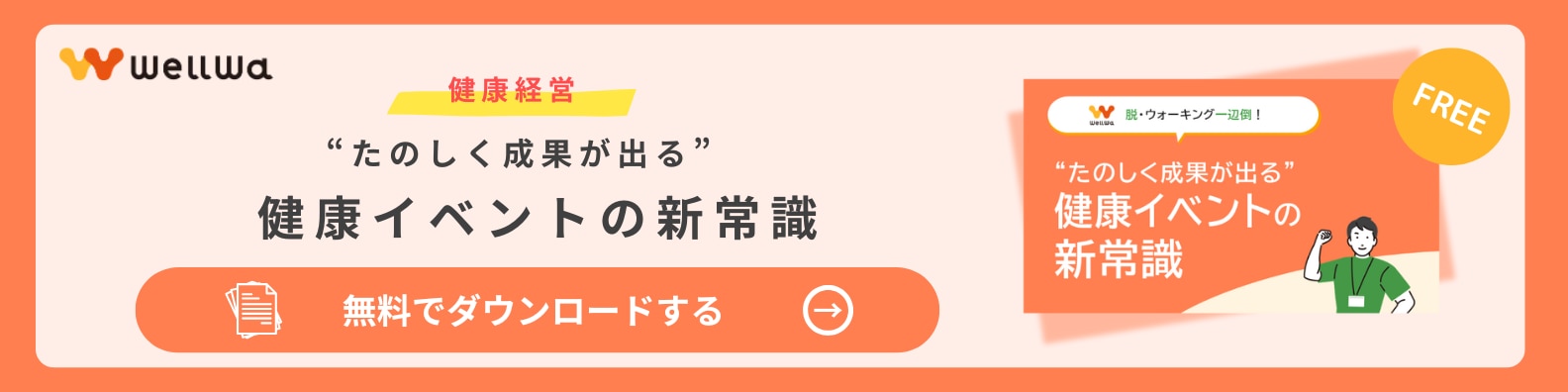オフィスがジムになる!? 社員の健康を守る「ながら運動習慣」
多くの企業が健康経営を掲げるなかで、いま改めて注目されているのが「運動習慣」の見直しです。とはいえ、忙しい日常の中で運動のためのまとまった時間を確保するのは容易ではありません。そんな課題を背景に、働く時間の中で自然に体を動かす「ながら運動」が、オフィス内でも実践できるヘルスケア施策として支持を集めています。
この記事では、社員の健康を守るために企業が取り組むべき“オフィス×運動”の最新アイデアと、習慣化のコツをご紹介します。
目次[非表示]
社員の運動不足が招くリスクとは?
座りっぱなしが健康に与える影響
現代のオフィスワーカーの多くは、1日に8時間以上も座り続けていると言われています。この“座りっぱなし”の状態が、健康に深刻な影響を与えることはすでに多くの研究でも明らかになっています。
長時間の着座は、血流や代謝の低下を引き起こし、肥満や糖尿病、心疾患などのリスクを高めます。また、首・肩・腰への負担も大きく、慢性的な痛みや不調につながるケースも少なくありません。さらに、運動不足は精神面にも影響を及ぼし、集中力の低下やストレスの蓄積につながる恐れがあります。
このように、単に「動かないだけ」と軽視されがちな問題が、実は長期的な健康と生産性に大きな影を落としているのです。
運動不足が企業にもたらすコスト(プレゼンティーズム、離職率)
社員一人ひとりの運動不足は、企業全体にも見えないコストとして跳ね返ってきます。代表的なのが、プレゼンティーズムと呼ばれる状態です。これは、出勤していても体調不良や集中力の低下により、本来のパフォーマンスを発揮できていない状態を指します。
運動習慣のない社員は疲れが取れにくく、業務効率が落ちたり、モチベーションの低下から小さなミスを繰り返すこともあります。これがチーム全体の負担となり、最終的には職場環境への不満や離職リスクへとつながっていくのです。
つまり、運動不足は個人の健康問題にとどまらず、企業の生産性と組織力を脅かす潜在的リスクともいえます。
健康経営視点から見た「オフィス運動」の重要性
健康経営を掲げる企業にとって、運動習慣の支援は重要な柱のひとつです。とはいえ、外部ジムの法人契約やフィットネス研修を用意しても、社員が自主的に活用しない限り効果は限定的です。だからこそ、オフィスという日常の場で自然に運動を取り入れられる環境設計が重要になります。
健康経営優良法人の多くは、オフィス内に軽いストレッチスペースや健康器具を設置するだけでなく、朝礼前の軽運動、昼休みのヨガタイム、アプリ連動型の歩数チャレンジなど、日常に溶け込む「ながら運動施策」を展開しています。
これらは社員の参加ハードルが低く、無理なく継続できることから、健康習慣の定着と組織全体の活性化に貢献しています。
今注目の「ながら運動」施策とは?
デスクワーク中でもできる「ながらエクササイズ例」
「運動はしたいけど、仕事が忙しくて時間が取れない」そんな声に応えるのが、デスクでできる簡単なエクササイズです。たとえば、椅子に座ったまま足を浮かせてキープする腹筋トレーニングや、太ももに挟んだクッションを押し合う内転筋トレーニングなどは、書類作成やメールチェックの合間にも取り入れやすいメニューです。
また、肩回しや首のストレッチ、目の疲れを癒すツボ押しなども、デスクワークとの相性が良く、リフレッシュ効果も高いとされています。ポイントは、“ながら”でできる手軽さと、習慣として継続しやすいこと。業務を中断せずとも実践できることが、オフィスでの運動施策成功の条件といえるでしょう。
会議中・移動中に取り入れられる運動アイデア
運動のチャンスは、会議や移動の時間にも内在しています。たとえば、オンライン会議中に立ち姿勢で参加することで、下半身の血流改善や姿勢保持の効果が見込めます。また、「社内移動時には階段利用を促すポスターを設置する」「遠回りルートを“健康ルート”として推奨する」など、遊び心のある仕掛けが社員の行動を自然と変えていきます。
スタンディング会議やウォーキングミーティングを取り入れている企業も増えており、「話しながら歩く」ことが思考の活性化やチームの一体感につながるという副次的なメリットも見逃せません。
運動実践率倍増!「運動習慣化」のコツ
運動習慣を根づかせるには、「やらされ感」のない工夫と、「楽しさ」の演出が不可欠です。たとえば、社内でミニチャレンジを開催し、歩数やミッション達成数をチームごとに競う形式にすると、自然と社員同士の励まし合いや雑談が生まれ、コミュニケーションの活性化にもつながります。
失敗しない!オフィス運動施策の導入ポイント
社員にやらされ感を抱かせない工夫
オフィスでの運動施策を導入する際に最も注意すべきなのは、社員に「やらされている」と感じさせないことです。義務化された運動や一方的な指示は、健康習慣の支援どころか反発やストレスの温床になりかねません。
そのためには、参加を強制しない“選べる自由”を残しつつ、興味を引く仕掛けを盛り込むことが重要です。たとえば、社内ポスターやイントラネットで運動の効果や小ネタを紹介し、自然と「やってみようかな」と思わせるような空気を醸成する。こうした“自発的に取り組んでいる感覚”を与える設計が、社員の納得感と参加意欲を引き出します。
部署を巻き込む仕組みづくり
一部の健康意識の高い社員だけが取り組むのではなく、組織全体を巻き込む仕掛けも不可欠です。そのためには、部署単位やチーム単位で運動に取り組む形式が有効です。個人の成果ではなく、チームの平均スコアや参加率を可視化することで、互いに声をかけ合いながら行動を促す文化が育っていきます。
また、部署内に「運動推進リーダー」のような役割を設けることで、自然と情報が共有されやすくなり、現場に即した調整も行いやすくなります。施策の導入は、トップダウンだけでなく、ボトムアップとの組み合わせが成功のカギとなるのです。
定着させるための「インセンティブ設計」
最初は盛り上がっても、時間が経つと参加率が落ちる。そんな悩みを防ぐために必要なのが、運動の継続を支える“ご褒美設計”です。
たとえば、日々の活動に応じてポイントが付与され、ドリンクや軽食、景品と交換できる仕組みがあると、行動が習慣に変わりやすくなります。ポイントを貯める楽しさや、“健康に取り組むと得をする”体験を通じて、運動のモチベーションが自然に高まります。
企業としても、少額のインセンティブで健康投資が行えることから、コストパフォーマンスの高い施策として注目されています。
つながりと健康を両立!WellWaによる“ながら運動習慣”の新提案
「チャレ活」で楽しく続く!チームで取り組む健康習慣
WellWa(ウェルワ)が提案する「チャレ活」は、チームで楽しみながら運動習慣を定着させる仕組みです。歩数や飲酒量、睡眠時間などを共有し、スタンプで励まし合ったりすることで、取り組みが義務ではなく楽しみに変わります。
何より、チームで活動することで生まれる会話や応援の文化が、職場の雰囲気をやわらかくし、メンタルケアやエンゲージメント向上にもつながる副次的な効果をもたらします。
オフィスで使える「WellStock」でモチベーションUP
チャレ活で得たポイントをオフィス内で使えるのが「WellStock(ウェルストック)」の魅力です。これは、ポイントと引き換えにドリンクなどを交換できるサービスで、運動へのモチベーションを日常の中で維持する強力な仕掛けとなります。
特に、「運動してよかった」という体験がリアルに報酬として返ってくることで、参加者の満足度が高まり、「次も頑張ろう」という前向きな気持ちが自然と芽生えます。健康とちょっとした楽しさをつなぐ役割として、WellStockは非常に効果的な存在です。
健康行動が自然と習慣に!「デイリーミッション」の活用法
WellWaのもうひとつの注目機能が「デイリーミッション」です。これは、毎日のちょっとした健康行動をミッション形式で提示し、実践できたらポイントを獲得できる仕組みです。
たとえば、「エレベーターではなく階段を使ってみる」「目の体操をする」「5分間ストレッチをする」といった小さな行動が日替わりで提示されることで、“今日は何しよう?”というワクワク感と気軽な取り組みの習慣化を後押しします。
忙しい社員でも続けられる工夫が随所にあることが、WellWaの大きな強みです。
ながら運動が変える、これからの働き方
心と身体の健康が生産性を上げる
身体を動かすことが、血流の改善、脳の働きの活性化につながることは医学的にも解明されています。つまり、“ながら運動”は健康対策のみならず、業務効率を高める有効な手段としても注目されています。
社員が心身ともに安定して働ける環境を整えることで、プレゼンティーズムの抑制や集中力の向上が見込まれ、結果的に生産性が上がるという好循環が生まれます。
エンゲージメントと社内コミュニケーションの活性化
運動習慣の共有は、職場内の会話を増やすきっかけにもなります。「今日はどんなミッションだった?」「意外とキツかったね」などの何気ないやり取りが、チームの連帯感を生み出し、組織全体のエンゲージメント向上にもつながります。
こうした日常の“ゆるやかな接点”こそが、信頼関係の基盤となり、健康経営を支える土壌となるのです。
健康経営の推進に向けた次のアクション
これからの企業に求められるのは、「健康施策を導入すること」ではなく、「社員の行動を変える健康施策を推進すること」です。ながら運動は、時間もコストも最小限で始められ、組織文化にもなじみやすいアプローチです。
WellWaのようなツールを活用すれば、誰でも・どこでも・すぐに健康行動を始められる環境が整います。健康維持は一人で頑張るものではなく、職場全体で“支え合いながら楽しむもの”へとシフトしつつある今、ながら運動こそが次のアクションにつながるのではないでしょうか。