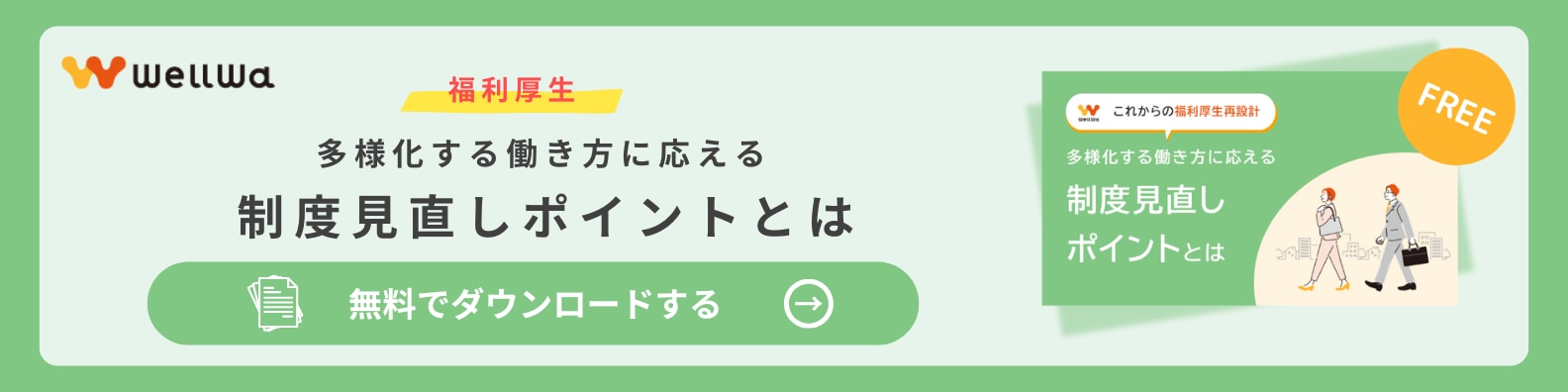採用力もUP!健康経営に効く最新オフィス福利厚生
「働く人の健康を守る」ことが、企業の競争力そのものを左右する時代。そんな中で注目されているのが、オフィスにおける福利厚生の見直しと強化です。ただ「制度を設ける」のではなく、日常の働き方と連動し、健康経営を実現するための環境設計が問われる時代へと変化しています。
本記事では、健康経営の推進と従業員エンゲージメントの向上を同時にかなえる「オフィス福利厚生」の最新トレンドと実践アイデアをご紹介します。
目次[非表示]
オフィス福利厚生の今:なぜ健康経営とセットで語られるのか
働き方の多様化と福利厚生ニーズの変化
リモートワークやフレックスタイム制度の普及により、社員一人ひとりの働き方やライフスタイルが大きく変化しています。それに伴って、「会社が設けるべき福利厚生」のあり方も問い直されるようになりました。
かつての福利厚生といえば慰労の意味合いが強く、住宅手当やレクリエーション施設といった“生活面や余暇活動の支援”が主流でした。しかし今は、「健康を維持しながら働ける環境が整っているか」「心身の状態に気を配ってもらえる仕組みがあるか」が、従業員の満足度や定着率に直結するポイントになっています。
つまり、福利厚生は単なる“ご褒美”ではなく、働きやすさを担保し、生産性やモチベーションを支える“経営インフラ”へと進化しているのです。
健康経営銘柄・ホワイト500に見る共通項
経済産業省が主導する「健康経営銘柄」や「ホワイト500(大規模法人部門の健康経営優良法人)」の取得を目指す企業も増えています。これらの評価基準を見ると、単に制度が整っているかどうかではなく、社員の行動変容を促し、継続的な健康維持に貢献しているかどうかが重視されています。
実際、認定企業の多くはオフィス空間や福利厚生制度を通じて、スムーズに健康的な選択ができるような環境づくりを進めています。例えば、健康的な軽食の提供や、階段利用を促すポスターの掲示、仮眠スペースやマッサージチェアの導入など、「無理せず、楽しみながら健康に近づけるオフィスづくり」が共通して見られる特徴です。
従業員エンゲージメントと生産性の関係性
福利厚生は“制度”として存在しているだけでは不十分であり、実際に使われ、効果を実感できることが大切です。そのためには、制度の設計段階から「従業員の利用意欲や参加意識」を高める視点を持つことが不可欠です。
こうした制度がうまく機能すると、従業員のエンゲージメント(仕事や組織に対する主体的な関与)も高まり、自律的な健康管理や積極的なコミュニケーションが促進されます。そして、その状態は業務への集中力や創造性にも直結し、結果的にチーム全体の生産性を高める原動力となります。
つまり、福利厚生は“使われること”によって初めて価値を持ち、それが健康経営の成果として表れるのです。
健康経営を加速させるオフィス福利厚生の最新トレンド
食・運動・睡眠をカバーする日常型施策
健康経営における基本軸となるのが、「食事」「運動」「睡眠」の三要素です。これらを日常の中で無理なく支援できる福利厚生は、特に高い効果を発揮します。
たとえば、栄養バランスの整った食事を社内で提供したり、自動販売機にプロテイン飲料や栄養補助食品を配備するなど、「食事や間食で健康的な選択ができる」環境を整えることが有効です。また、ランチ後のストレッチタイムや、就業中のパワーナップ(仮眠)スペースも職場環境改善の一環として注目を集めています。
これらは、あくまで“社員が無理なく使える”ことがポイントです。気軽に使えて、効果が実感できる施策こそが、オフィスにおける健康支援の要となります。
離職防止に効く社内コミュニケーションの強化型施策
社員が働き続けたいと感じる職場には、「人間関係の良さ」が欠かせません。そのため、近年のオフィス福利厚生では、“つながり”を促進するコミュニケーション支援施策が重要視されています。
たとえば、部署を横断した1on1ミーティングや、月1回のランチトークイベント、バーチャルオフィスを活用した雑談タイムなどが、自然な交流の場として機能しています。
こうした施策は、メンタルヘルスの安定にもつながり、結果としてプレゼンティーズム(出勤しているが本来の力を発揮できない状態))の予防や離職率の低下といった経営成果にも寄与します。
インセンティブ型による自発的な行動変容促進
社員の健康行動を「義務」ではなく「楽しみ」に変える仕組みとして、インセンティブ型の福利厚生も浸透し始めています。
たとえば、歩数や健康ミッションの達成に応じてポイントが付与され、それをドリンクや軽食、景品と交換できる仕組みなどは、ゲーム感覚で参加でき、継続しやすい設計となっています。
こうした制度は、社員の内発的動機づけを刺激し、健康への意識改革を自然と促してくれます。行動変容が起きれば、社員自身も体調や気分の変化を実感しやすくなり、「健康への取り組み=自分ごと」として定着していくのです。
従業員の健康×つながりを生む「ウェルビーイングな福利厚生」
チーム制×ポイント制のチャレンジ企画
近年、心理学・行動科学・公衆衛生などの分野において研究が進み、健康行動の定着には「仲間とのつながり」と「達成感」が重要な役割を果たすことが明らかになってきました。そのような背景を受け、一部の企業で実践されているのが、チームで参加するチャレンジ型の福利厚生企画です。
例えば、部署単位で歩数や健康ミッションに取り組み、達成度に応じてポイントを獲得するスタイルが好評を得ています。チームで目標を共有することで、競争というより“協力しながら健康を意識する”空気が自然と職場に広がります。達成した際の小さな称賛や拍手も、メンバー同士の信頼を育み、職場の一体感を高める起点となります。
ランキング・可視化で会話が生まれる仕掛け
チャレンジを楽しさに変えるもうひとつの要素が“見える化”です。日々の歩数やポイントをランキングとして可視化することで、参加者のモチベーションが高まり、自然と職場内での会話が増えていきます。
「今週の1位はあの部署らしい」「あと少しでうちのチームも目標達成しそう」など、健康を話題にした前向きなコミュニケーションが生まれる仕掛けは、メンタルケアや心理的安全性の維持にもつながります。ただ数字を追うのではなく、“仲間とともに過ごす日常”のなかに健康が息づいていることが重要です。
ストック型サービスによる継続モチベーション維持
一時的な盛り上がりではなく、継続的な行動変容を促すためには「積み上げられる成果」が欠かせません。そこで注目されているのが、健康活動の結果をポイントとして蓄積できる「ストック型」の福利厚生サービスです。
毎日のミッション達成やチャレンジ企画への参加によって得られるポイントが、ドリンクや軽食などに交換できるような仕組みは、健康行動の習慣化と福利厚生の活用を同時に実現します。社員にとっては「頑張った成果が形になる」体験となり、会社にとっては施策の定着率と社員満足度向上の両立が期待できるため、優れた投資効果が見込まれます。
健康×コミュニケーションを両立!注目の『WellWa』とは?
雑談と健康を同時に促す「チャレ活」とは?
「WellWa(ウェルワ)」は、健康経営を実践する企業の間で注目を集めている、コミュニケーション促進型の福利厚生サービスです。中でも特徴的なのが「チャレ活」と呼ばれるチーム参加型の活動プログラムです。
このチャレ活では、歩数や飲酒量、睡眠時間といった日々の健康習慣を記録することで、健康管理や運動習慣を促進します。その過程で、「今日のミッション、終わった?」「スタンプたくさん来たね」といった雑談が自然に生まれ、健康と会話が一体化して職場に溶け込んでいきます。こうしたライトなやり取りが、職場の空気をやわらげ、心理的な安心感のある関係づくりにつながります。
出社を促進する福利厚生「WellStock」の魅力
WellWaが提供するもう一つの機能が、オフィス内で利用できるポイント交換型サービス「WellStock(ウェルストック)」です。これは、社員が健康ミッションを達成して得たポイントを、職場内で提供しているドリンクと交換できる仕組みです。
この仕掛けにより、出社の動機が“ただの勤務”から“ちょっとした楽しみ”へと変わります。とくにオフィス出社とリモートワークを組み合わせている企業では、出社率の底上げとオフィスコミュニケーションの促進に大きく寄与しています。
リモート勤務者も恩恵あり!「WellStore」で広がる活用
WellWaの強みは、リモートワーク中心の社員も置き去りにしない点にあります。「WellStore(ウェルストア)」というオンラインストア機能では、貯めたポイントを使って自宅配送型の商品と交換することができ、遠隔勤務の社員も等しくサービスの恩恵を受けられます。
このように、出社・在宅の働き方にかかわらず、一体感と公平感を保ちながら、健康支援を広げられる設計は、これからのハイブリッドワーク時代に非常にマッチしています。
継続的な活用のための社内巻き込み術
効果を長く持続させるためには、「制度をどう使ってもらうか」だけでなく、「誰が巻き込み役になるか」という観点も欠かせません。成功企業の多くは、社内で“仕掛け人”となる健康推進担当者やチームリーダーを明確にし、部署横断的に小さなイベントを仕掛けています。
ポイントは、最初から完璧を目指さないこと。少人数でのトライアルから始め、成果を社内に共有していくことで、自然な形で輪が広がっていく仕組みをつくることが施策推進のカギになります。
まとめ
自社に合う施策をどう選ぶか?
成功する福利厚生の共通点は、「社員のリアルな課題に寄り添っていること」です。他社の事例をそのまま真似るのではなく、自社の働き方、年齢構成、コミュニケーションの課題などを丁寧に洗い出したうえで、施策をデザインすることが成果を生む近道になります。
福利厚生はコストから投資”へ
オフィス福利厚生は、単なるコストではなく、「健康」「エンゲージメント」「離職率」「採用力」など多方面に波及する“未来への投資”と捉えるべきです。とくにWell-beingや人的資本経営が注目されるいま、従業員一人ひとりの「働きがい」に直結する環境整備は、企業価値を高める武器になります。
今すぐ始められるWellWaの導入ステップ
WellWaは、無料の資料請求やトライアル導入など、スモールスタートに最適な導入支援体制が整っています。「まずは部署単位で使ってみたい」「継続できるか不安」といった声にも柔軟に対応しており、健康経営をこれから始める企業にとっても非常にハードルが低い選択肢となっています。