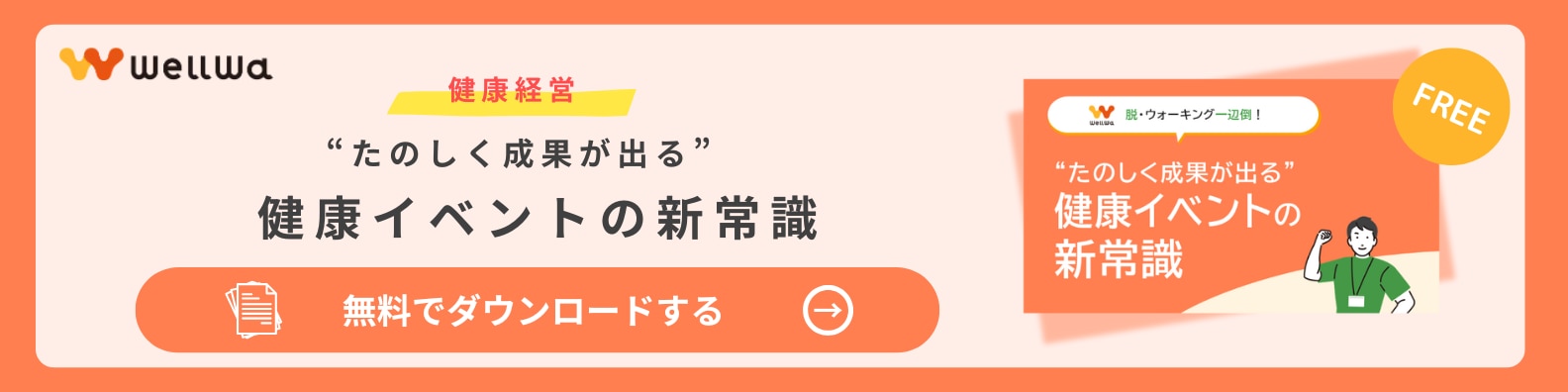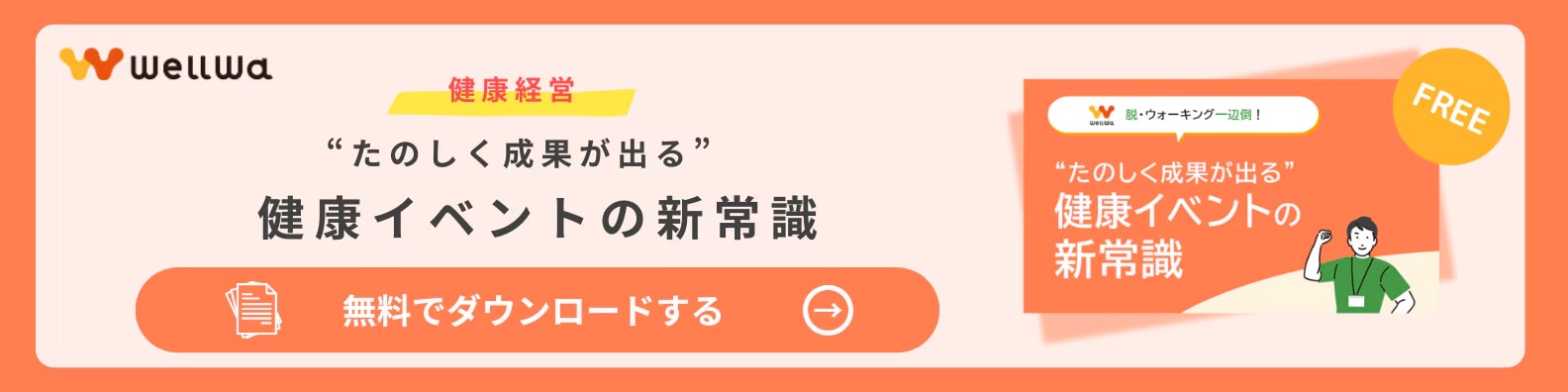社内がひとつになる!健康経営を後押しする職場でのイベントの新しい形
「最近、社員の表情が硬い気がする」「部署間の交流が減ってチームワークに不安がある」
そんな課題感を持つ企業にこそ、注目していただきたいのが「職場イベント」です。イベントは単なる娯楽や余興ではありません。エンゲージメントの向上、健康促進、心理的安全性の醸成など、多方面から企業価値を底上げする施策として再評価が進んでいます。
本記事では、健康経営と社員エンゲージメントの観点から、今企業が注力すべき職場イベントのあり方を解説します。
目次[非表示]
なぜ今、職場でのイベントが求められているのか?
社員エンゲージメントと離職率の関係性
社員のエンゲージメントが低い職場では、
- 上司や同僚とのつながりが薄い
- 会社に対する帰属意識が低い
- 成果よりも「こなす」ことが優先される
といった空気が蔓延しやすく、生産性の低下や早期離職のリスクが高まります。
一方、適切な社内イベントは「社員同士がつながる」「会社に感謝されている実感が湧く」といったポジティブな体験を提供し、エンゲージメントを高める起点になります。実際に、社内交流施策の充実度と離職率の低さには相関があることが、国内外の人事データからも示されています。
離れていた「つながり」を取り戻す手段として
コロナ禍以降、テレワークやフレックスタイムの普及により、社員同士の物理的・心理的距離は大きく広がりました。
- チームメンバーの顔を知らない
- 雑談や非業務の会話が一切ない
- 部署間の連携が希薄になっている
こうした分断を回復させるには、意図的に接点をつくる「職場イベント」が非常に有効です。 特に部署をまたいだ交流型イベントは、横断的な関係構築や情報の非公式共有にもつながり、組織全体の風通しを改善します。
健康経営の観点からの注目背景
健康経営においては、「従業員の身体的・精神的健康」だけでなく、働く人の社会的つながりや心理的安心感も重要な要素とされています。
この点で職場イベントは、
- 社員同士の会話を促進
- オフラインでの再会のきっかけに
- 運動・食・メンタルケアと連動させやすい
といった利点を持ち、ウェルビーイングを推進する実行しやすい手段として注目が集まっているのです。
健康経営とエンゲージメントを高める職場イベントの条件
心と身体の両方に働きかける内容が鍵
ただ集まるだけのイベントでは、時間を取る意味がありません。これからの職場イベントには、「参加者の心身にポジティブな刺激を与えること」が求められます。
例えば
- 軽い運動やストレッチを取り入れたランチ会
- リラックスを目的としたヨガ・瞑想ワークショップ
- 感謝や賞賛を伝えるピア・フィードバック型イベント
など、身体と心の両面にアプローチする設計が、参加者の満足度を高めるポイントになります。
全社員が「気兼ねなく参加できる」配慮
イベント設計では、「一部の人だけが盛り上がる」状況は避けたいところ。体力・性格・ライフスタイルにかかわらず、誰もが自分らしく関われる余白を持たせることが重要です。
具体的には
- 競争要素よりも協力型にする
- リアル/オンラインのハイブリッド形式にする
- 任意参加を前提にし、参加ハードルを下げる
といった配慮により、イベント参加が「義務」ではなく「自発的な楽しみ」になる空気をつくることが大切です。
一過性ではなく「定期性・継続性」があること
年に1回の大規模イベントよりも、小さく、軽やかに、繰り返すイベント設計のほうが、エンゲージメント向上には効果的です。
- 月1回の「部門対抗ウォーキングバトル」
- 毎週開催の「雑談テーマ共有ミーティング」
- 季節ごとの「ウェルビーイング週間」
といった形式で、日常に馴染む継続型イベントを用意することで、社員同士のつながりの習慣化が促進されます。
目的別に見る!社内イベントのアイデア集
コミュニケーション活性型
目的:会話のきっかけと関係性づくり
- 社歴や所属に関係なく、1対1で30分雑談をする「1on1ラリー」
- 異なる部署メンバーを組み合わせた「ランチミートアップ」
- 全社員参加型の「「私の推し」紹介イベント」
こうした施策は、偶発的な関係の種まきを促し、心理的安全性の向上にも寄与します。
健康促進型
目的:体調管理と気分転換、行動変容のきっかけづくり
- チーム対抗の歩数チャレンジやラジオ体操選手権
- 「水分摂取ミッション」「睡眠記録」などのヘルスミッション
- 健康知識を競う「健康クイズ選手権」
これらは「健康」という共通の関心軸で、自然な雑談や協力関係を生み出す効果もあります。
キャリア支援型
目的:働きがいや自分らしさに目を向ける機会づくり
- 管理職向けの「傾聴力・共感力研修」
- 若手社員向けの「キャリア対話ワークショップ」
- ライフプランを考える「未来の自分設計セッション」
これらのイベントは、エンゲージメントの核となる「自己理解」と「会社への信頼」を同時に育てる効果が期待されます。
効果を最大化するには?職場イベント設計3つポイント
ターゲットを明確にする
イベントの成功は、「誰に届けるか」を明確にすることから始まります。
- 若手社員向け:気軽さ・フラットな雰囲気・ゲーム性がある内容
- 管理職向け:組織づくりやコミュニケーションリーダーを意識した研修型
- 在宅勤務者向け:オンラインで完結する設計と「参加しても浮かない」空気づくり
それぞれのターゲットに応じて、時間帯・雰囲気・求められる成果を調整することが参加意欲を左右します。
時間帯・開催頻度・告知方法の効果的なやり方
イベントは開催して終わりではなく、参加率・継続性・話題性を意識した運用が重要です。
- 時間帯:業務中の15〜30分、昼休み直後、金曜午後などの“余白”を狙う
- 開催頻度:月1〜2回程度の定期開催が、心理的距離を縮めるペースとして最適
- 告知方法:メール一斉配信+チャットツールでのラフな呼びかけの併用が有効
事前のワクワク感を高める演出(例:「今月のテーマは◯◯!」)も、参加者の期待値を引き上げる重要な仕掛けです。
実施後のフィードバック活用法
イベント後は、必ず振り返りと可視化を行いましょう。
- 「今回の満足度」「また参加したいか」などの簡単なアンケート
- 写真・感想・スタンプコメントの社内共有
- 次回予告と参加者の声をセットで発信
このように、参加者の反応を「データ」として蓄積・発信・改善につなげることが、継続参加を生む組織文化の鍵になります。
WellWaが実現する「健康経営イベント」の進化形
WellWaとは?従業員の心身の健康を可視化・支援する仕組み
WellWa(ウェルワ)は、キリンビバレッジが提供する健康経営支援サービスで、日々の健康行動を「見える化」し、チームでの取り組みに変える仕組みが特長です。
- チャレ活(チャレンジ活動):部署やチームで健康ミッションに挑戦
- 健康選手権:期間限定イベントでポイントや歩数を競う
- WellStock:貯めたポイントを使って健康飲料と交換
こうした機能を通じて、「イベント=健康+つながり+楽しさ」の価値を同時に提供しています。
イベント企画を「データ起点」で変える新アプローチ
WellWaでは、参加率やミッション達成率、リアクションスタンプ数などをリアルタイムで可視化できるため、イベントの成果を「見える数字」で把握・改善可能です。
- どの部署が盛り上がったか
- どのテーマが人気だったか
- 誰が中心になって盛り上げたか
といったファクトベースの設計・改善・表彰が可能になるため、イベント施策が“属人化せずに継続できる”という強みがあります。
まとめ
職場イベントは、社員のエンゲージメントや健康を支える「経営戦略」のひとつとして、今こそ見直されるべき存在です。
- 心と身体の両面にアプローチ
- 誰もが気軽に関わることができる設計
- 継続的に「つながり」を育てる工夫
- 成果を「見える化」し、文化にする
こうした視点を押さえたうえで、WellWaのような仕組みを活用すれば、ただのイベントが「企業力を底上げする仕組み」へと進化します。
小さなイベントが”職場の空気と社員の心を変えていく”そんな未来を、一歩ずつ実現してみませんか?