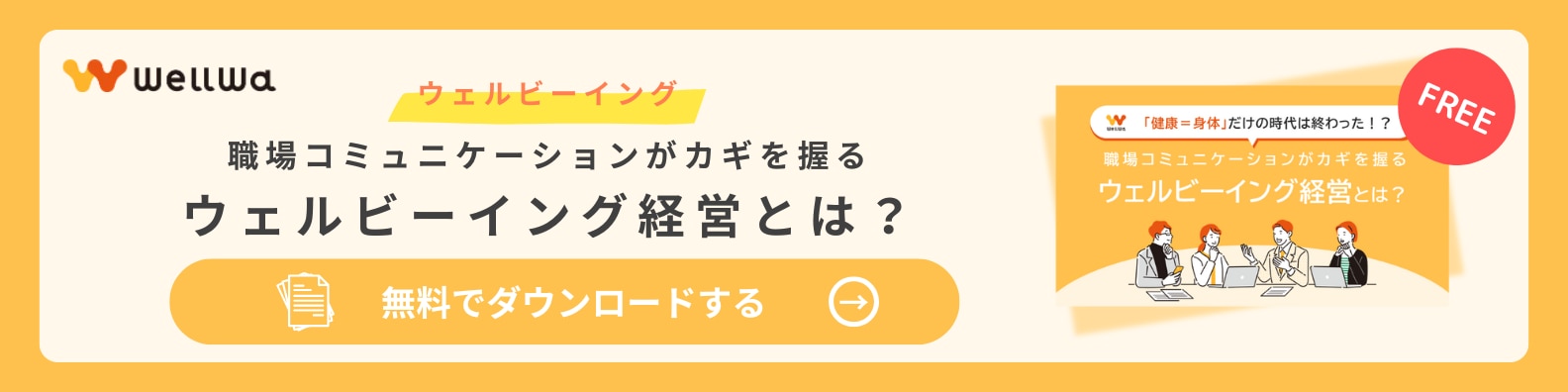雑談が生む心理的安全性!職場での自然なコミュニケーションを促す工夫とは?
「業務に関係ない話は必要?」「雑談しているとサボってると思われるのでは?」
そんなふうに「職場の雑談」が敬遠されがちだった時代から、今は雑談こそが職場の雰囲気づくりや、心理的安全性の鍵として注目されています。
本記事では、企業の健康経営推進担当者・福利厚生担当者に向けて、職場の雑談が果たす役割や、その促進がもたらす心理的・組織的メリットを明らかにします。
目次[非表示]
なぜ今「職場の雑談」が必要とされているのか?
ハイブリッドワーク化で薄れる「ちょっとした会話」
コロナ禍以降、リモートワークやフレックス制の浸透により、社員同士の接点は確実に減っています。
- 通勤途中の雑談
- エレベーターや給湯室での立ち話
- 会議前後の一言二言のやり取り
これらの「ついでの会話」が、ハイブリッドワークの環境下では意識しなければ生まれなくなりました。その結果、「必要なことだけを話す」効率重視のコミュニケーションが定着し、「気軽な会話のない静かな職場」が増加傾向にあります。
しかし、業務上の効率性が上がった一方で、職場に孤立感や情報断絶のリスクが潜んでいることにも注意が必要です。
雑談は生産性に直結する?
雑談は一見、生産性とは無関係のように思えますが、近年の研究では雑談の頻度とチームのパフォーマンスには正の相関関係があることが示されています。
2022年にMicrosoftが発表したレポートによると、「雑談が多いチームは意思決定が早く、創造的アイデアも多い」という結果が報告されています。
出典:Microsoft 「New Future of Work Report」(2022年)
またMITエクセター大学の2024年の研究によると、「日常的な雑談がその日一日を通してポジティブな感情を高め、対人信頼を育んだ」と報告されています。
出典:エクセター大学「エクセター大学ビジネススクールによる小話の職場効果研究」(Academy of Management Journal掲載)
つまり、雑談は単なるコミュニケーションの潤滑油ではなく、生産性やチーム力の基盤となる重要な要素といえるのです。
健康経営の文脈で高まる「コミュニケーション」の重要性
健康経営の取り組みが進む中で、「組織の風通し」や「人間関係の質」が注目指標として位置づけられるようになりました。実際、経済産業省が認定する「健康経営優良法人」では、コミュニケーションの活性化も評価の対象になっています。
- 雑談の機会をどう設けているか
- 心理的安全性をどう醸成しているか
- リモート勤務下での「つながりの仕掛け」があるか
といった観点が、今や健康経営を推進するうえでの評価される取り組みとなっているのです。
雑談がもたらす心理的・組織的メリットとは
雑談が生む「心理的安全性」とその効果
心理的安全性とは、「このチームでは安心して意見を言える」「否定されずに受け止めてもらえる」という感覚のこと。この土壌を育てるうえで、最も効果的な入り口が雑談です。
何気ない会話の積み重ねは、
- 「この人とは気軽に話せる」
- 「小さな違和感でも伝えていい」
- 「失敗しても受け止めてもらえそう」
という信頼感を生み出し、結果的に意見の共有や助け合いが自然に起きる文化へとつながっていきます。
縦・横・斜めの連携を強化するハブとしての雑談
職場の連携には、「上下」だけでなく、「同僚同士」「他部署」「後輩や新人」など多層的な接点が求められます。その中で雑談は、肩書きや役割を越えた「フラットなつながり」を築く場として機能します。
- 普段関わらない部署の人と雑談したことで連携がスムーズに
- 管理職と部下が趣味を共有することで報連相のハードルが下がった
- 新入社員が雑談を通じて社内の雰囲気に早く馴染めた
といった効果が、自然に生まれてくるのです。
ストレス緩和・エンゲージメント向上にも寄与
雑談には、「脳を休める」「感情を共有する」「気分転換になる」といった心理的な癒やし効果があります。
職場での孤立感や過度な緊張状態が続くと、プレゼンティーズム(体調不良によるパフォーマンス低下)や離職リスクが高まりますが、日常の雑談がクッションの役割を果たすことで、その防止に効果を発揮します。
また、雑談がある職場では「ここにいていい」という感覚が強まり、エンゲージメントや定着率の向上にもつながるのです。
雑談が生まれにくい職場の特徴と要因
業務効率優先文化がもたらす「沈黙」
現代のビジネス環境では、「無駄を省く」「業務の生産性を高める」といった効率重視の風土が根付いています。その結果、雑談はやらなくても困らないものとして排除されがちです。
- 会議は議題のみ、時間厳守
- ランチもデスクで一人
- 何か話すにも「意味はあるのか?」と自問する風潮
このような環境では、話したいことがあっても「雑談=時間のムダ」と感じてしまい、会話を自制してしまう社員も少なくありません。
雑談=ムダという誤解
雑談が職場に必要であることが注目されている一方で、いまだに「業務と無関係な会話は甘え」「真面目にやっていないように見える」といった固定観念も根強く残っています。
特に、管理職やリーダーがこうした認識を持っていると、部下は「雑談しただけで評価を下げられるのでは」と警戒しがちです。雑談をムダとせず、信頼関係や心理的安全性を育てる重要な時間と認識を転換することが、組織としての第一歩です。
働き方・働く場の多様化による接点の減少
リモートワーク、フリーアドレス、サテライトオフィスなど、柔軟な働き方が進む一方で、「出社日がすれ違う」「なかなか会えない」「話す機会がない」という現象が増えました。
特に異なる部署間や役職の異なる社員同士は、業務上の関わりがなければ、接点そのものが生まれない構造になりがちです。こうした「偶然の出会い」がない環境では、雑談はつくろうとしない限り起きないものになるのです。
雑談を自然に生み出す職場づくりのアイデア
「雑談しやすい空気」をつくるマネジメントの工夫
雑談を推進するうえで最も重要なのは、上司やマネージャーの姿勢です。管理職自身が、
- ちょっとした声かけを欠かさない
- 自分から日常の話題を共有する
- 雑談を咎めず、歓迎する空気を醸成する
といったふるまいをすることで、部下も「話していいんだ」と安心できます。雑談は「許される文化」がなければ生まれません。まずは上司から「雑談しやすい職場モデル」をつくっていくことが求められます。
物理的・デジタルの「偶発的接点」を仕掛ける
「雑談が偶然に生まれる」仕掛けを用意することも効果的です。
【物理的施策】
- 社内カフェ・リラックススペースの設置
- フリーアドレスや部署混在エリアの活用
【デジタル施策】
- 雑談専用チャネルの運用
- バーチャルオフィス空間でのランダムマッチング
- 「今日のお題」投稿によるコメント交流
こうした仕掛けにより、会話の「きっかけ」が意図的に設けられ、自然な交流が促されます。
テーマや仕掛けで「意味ある雑談」を後押しする
「何を話せばいいか分からない」「会話が続かない」という課題には、テーマ設定や企画の導入が効果的です。
- 毎週の「今週のおすすめ本」「最近ハマってるもの」紹介
- 「健康習慣チャレンジ」など共通体験型施策
- 社内ミッションをトリガーとしたゆるいトーク
このように、業務以外の共通項を設けることで、目的がなくても盛り上がれる雑談の場が生まれます。
雑談を促す「仕組み」づくりに役立つサービス:WellWaの活用法
WellWaとは?自然な会話を促進するウェルビーイングサービス
WellWa(ウェルワ)は、キリンビバレッジが提供する法人向けウェルビーイングサービスです。日々の「ちょっとした健康行動」をきっかけに、自然なつながりや雑談が生まれる仕組みを提供しています。
- チームで取り組む「チャレ活」
- 部署間で競い合う「健康選手権」
- ポイントを活用した食の福利厚生
など、健康をテーマに雑談が育つ土壌を仕掛けるツールとして、企業から高い評価を得ています。
「心と体の健康」をきっかけに雑談が生まれる仕掛けとは
WellWaのミッションは、「健康」という共感しやすいテーマを通じて、職場内に話しかけるきっかけをつくることです。
例えば、
- 「今日のミッション、やった?」
- 「最近の歩数、めっちゃ伸びてない?」
- 「ポイント何に使った?」
といったライトな会話が自然と発生し、健康習慣が「対話のハブ」として機能します。
データ活用で「雑談→関係性→健康」まで支援できる強み
WellWaでは、参加率やスタンプ送信数などを可視化し、雑談や関係性の深まりが健康指標にどう影響しているかをデータで確認できます。これは、単なる会話の促進にとどまらず、
- 心理的安全性の醸成
- 部署間連携の強化
- プレゼンティーズムやエンゲージメントの改善
といった職場全体の「状態の質」を向上させる支援ツールとしての価値を持っています。
まとめ
職場の雑談は、単なる「おしゃべり」ではありません。それは、信頼・連携・心理的安全性を育む「見えにくいけれど極めて重要な資産」です。
雑談が生まれる空気、仕組み、きっかけを丁寧に設計することで、
- 相談しやすい
- 関係性が強くなる
- 健康経営が推進される
といった組織の土台が強化されていきます。WellWaのようなサービスを活用し、健康という共通テーマを軸に、無理なく・自然に・継続的に雑談が育つ職場を目指してみてはいかがでしょうか。