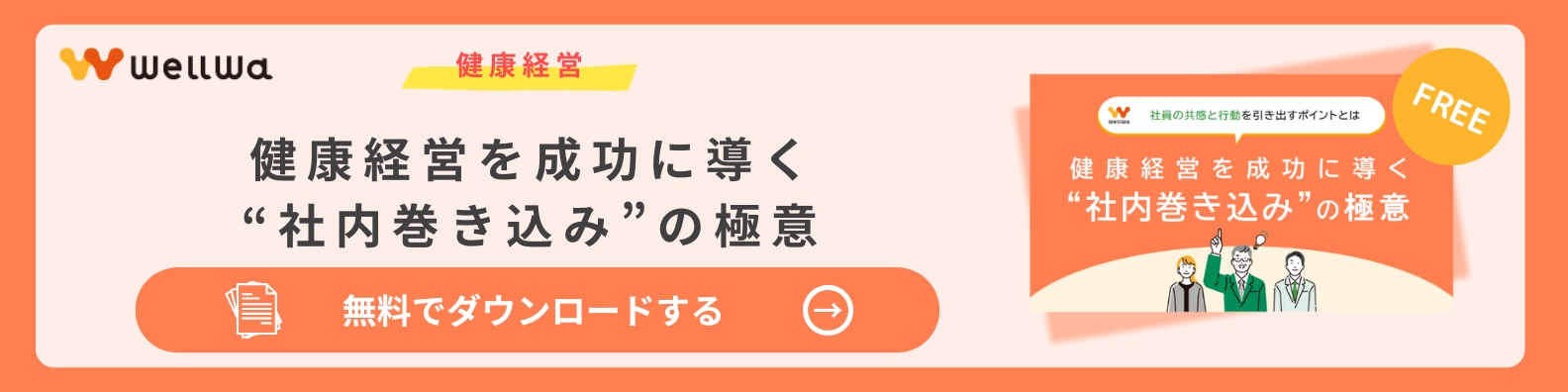若者の健康意識が低い理由とは?健康意識を高める企業のアプローチ術
企業が健康経営を推進するなかで、しばしば課題として挙がるのが「若手社員の健康意識の低さ」です。福利厚生制度や健康施策を整えても、20代〜30代前半の社員に届かず、参加率が伸び悩む……そんな悩みを抱える担当者は少なくありません。
なぜ若手社員は健康を自分ごととして捉えにくいのでしょうか?そして、そのまま放置した場合、企業全体にどのような影響が及ぶのでしょうか?
本記事では、若年層特有の心理的背景と行動特性をひもときながら、企業がとるべき支援のあり方を探っていきます。
目次[非表示]
なぜ若手社員は健康意識が低いのか?
若年層特有の「自分はまだ大丈夫」思考
20代〜30代前半の若手社員にとって、健康は遠い未来の話になりがちです。「まだ病気になったことがない」「不調が出ても一晩寝れば回復する」という体験の蓄積から、「自分はまだ大丈夫」という思考に陥りやすい傾向があります。
この過信は、生理的な若さだけでなく、社会的な経験値の少なさにも起因しています。健康被害を身近に実感したことがなく、リスクを具体的にイメージできないため、どうしても日常の優先順位から外れてしまうのです。
健康リスクが見えづらく、行動に結びつかない
加えて、健康リスクの可視化が不足していることも大きな要因です。血圧や血糖値といった数値が基準値内である間は、「改善すべき」と感じる材料がありません。若年層は生活習慣病の兆候が表面化しにくく、健診結果にも明確な警告が出ないため、行動変容のきっかけを得にくいのです。
また、運動・食事・睡眠といった習慣の乱れも、すぐに結果が出ないという性質上、取り組むモチベーションにつながりづらいというジレンマがあります。
ライフスタイルの多様化と不規則な生活習慣
近年の若年層は、働き方・住まい方・交友関係など、ライフスタイルが非常に多様です。リモートワークやフレックスタイム、個人主義的な価値観の浸透などにより、生活リズムが固定化しにくく、結果として「自己管理」の難易度が高まっています。
また、「食事はコンビニ」「運動はしていないが罪悪感もない」「夜中にスマホで動画を観ながら寝落ち」など、健康を害する生活習慣が当たり前として定着しているケースも珍しくありません。
このような背景から、健康意識の低さは単なる無関心ではなく、行動の選択肢が見えていない、あるいは自分にフィットする手段が用意されていないことの表れでもあるのです。
健康意識が低いことによる企業リスクとは?
生産性低下:プレゼンティーズムの深刻化
若手社員の健康意識が低いままでは、「なんとなく体調が悪い」「集中できない」といった状態が常態化しやすくなります。これがプレゼンティーズム(出勤しているが生産性が下がっている状態)の増加につながります。
特に、若手のうちは自身の不調に気づきにくく、無理をして働いてしまう傾向が強いため、結果としてパフォーマンスが下がっていても周囲が気づかない――という構図が生まれやすいのです。
企業にとっては、「健康状態に起因する見えない損失」が広がっていくリスクといえます。
離職・メンタル不調リスクの増加
心身のセルフマネジメントがうまくいかないまま働き続ければ、いずれ燃え尽きや離職、メンタル不調のリスクにつながります。
特に、メンタルヘルスに関しては「自分でコントロールできない」と感じた時点で急激に悪化することが多く、軽度の段階での対処が重要です。しかし、健康意識が低い層はそうしたサインに気づきにくく、「いきなり休職」「突然の退職」といった事態を引き起こすこともあります。
組織風土の停滞と「健康経営」の逆効果
健康施策を推進しても、若手社員が参加しない・盛り上がらないという状態が続くと、全社の温度差が広がり、「健康経営=形だけのもの」という認識が社内に広がってしまう可能性があります。
また、健康を「意識の高い人だけの取り組み」として限定してしまうことで、若手と他世代の分断や、施策設計における偏りが生まれやすくなります。
結果として、「健康経営に取り組んでいるのに、職場の空気は変わらない」という逆効果に陥るリスクがあるのです。
若者に響く!健康意識を高めるアプローチ5選
若手社員の健康意識を高めるには、「必要性を伝える」だけでは不十分です。彼らが日常的に触れている世界観に寄り添い、「楽しさ」や「仲間との共感」を軸にした設計が鍵となります。ここでは、行動変容を促すための効果的なアプローチを5つご紹介します。
デジタル×習慣化で「可視化」と「ゲーミフィケーション」
スマートフォンを肌身離さず持つ世代にとって、アプリを使った行動記録やデータの可視化は、ごく自然な体験です。歩数、睡眠、食事といった日々の健康行動をスコア化・グラフ化する仕組みがあるだけで、継続のモチベーションは大きく変わります。
加えて、「達成バッジ」や「レベルアップ」「クイズチャレンジ」といったゲーミフィケーション要素を加えると、ゲーム感覚で楽しく続けられる仕掛けになります。
同期・仲間との「チーム参加」で巻き込み力アップ
若手社員は、個人よりも「仲間との一体感」や「誰かと一緒にやること」に価値を感じやすい傾向があります。そこで効果的なのが、同期・小グループ単位でのチーム参加形式の施策です。
「チーム対抗ウォーキングチャレンジ」や「部署ごとの睡眠改善月間」などは、楽しみながら取り組むきっかけになります。競い合うだけでなく、励まし合う文化が育まれる点でも、大きな効果が期待できます。
ポイント制やインセンティブで「やって得する」設計に
義務ではなく、「やったほうが得」と感じてもらうことも、行動変容の促進に有効です。健康行動に応じてポイントが貯まり、それが社内カフェや自販機、ECで使える仕組みがあれば、「行動=報酬」の構造が自然と根づきます。
このようなインセンティブ型設計は、特にきっかけがないと動かない若手層の初動を後押しするうえで非常に効果的です。
社長や役員が「先頭に立って挑戦」する文化づくり
若手社員に響くのは、「トップが本気で取り組んでいる姿勢」です。社長がチームリーダーとしてイベントに参加する、役員が健康記録を社内に公開する、といった上からの参画は、組織全体の空気を変える原動力になります。
「上層部がやっているなら、自分も少し試してみようかな」と思わせるような文化づくりこそ、持続可能な施策の土台です。
ミニイベント×リアルな体験で五感に訴える
アプリや仕組みだけではなく、リアルの場での体験を交えることも重要です。「健康おやつの試食会」「その場で体組成を測るミニチェック」「音楽を流したストレッチタイム」など、五感に訴える施策は記憶に残りやすく、面白かったからまたやりたいという行動につながります。
気軽に参加できるミニイベントを月1回でも実施するだけで、健康が他人事から自分ごとへと変わっていきます。
失敗しない導入のコツ:押しつけず、巻き込む仕掛けを
「健康」を話題にするための社内コミュニケーション導線
若手社員に健康を語れる話題にしてもらうには、日常的に会話が生まれる場づくりが不可欠です。「今週のチャレンジ共有スレッド」や「健康スタンプ送り合い文化」のような導線を社内に設けることで、自然と意識が高まり、共感が連鎖します。
データの見える化で、行動変容を実感できるようにする
人は、自分の行動が「意味のある変化を生んでいる」と実感できたときに、ようやく継続に向かいます。そこで重要なのが、行動と結果をつなぐデータの可視化です。
アプリ上での「歩数の推移グラフ」や「睡眠時間のスコア化」、チーム内の達成度などが数字として見えることで、「自分、ちゃんと変わってきたかも」という実感が芽生えます。
現場の声を起点とした「カスタマイズ」設計の重要性
施策が上からの押しつけに感じられると、若手社員は距離を置いてしまいます。そのため、現場の声を取り入れた設計が非常に重要です。
「ミッションテーマを社内アンケートで決める」「自分たちで健康イベントを企画するチームを設ける」といった仕組みがあれば、若手の当事者意識が高まり、主体的な参加につながります。
健康行動を「楽しく、続ける」仕組みならWellWa
チャレ活・健康選手権で「自然と会話が生まれる」
WellWa(ウェルワ)は、キリンビバレッジが開発した健康支援サービスです。チーム単位で健康習慣に取り組む「チャレ活」や、部署対抗でランキングを競う「健康選手権」などを通じて、自然な会話と行動変容を同時に促す仕組みを備えています。
若手社員同士が「今週は何歩だった?」「野菜チャレンジ参加してる?」など、健康をフランクに話題にできる環境づくりに最適です。
ポイントで飲料交換も!WellStockで福利厚生にもつながる
WellWaでは、チャレンジの達成やミッション実施に応じてポイントが付与され、社内専用ストア「WellStock」や「WellStore」でスムージーや健康飲料と交換可能です。
「やったら得する」という設計により、健康行動が習慣として根づくだけでなく、福利厚生満足度の向上にもつながるメリットがあります。
ミッションのカスタマイズで「自社らしさ」を演出
WellWaのもう一つの魅力は、日替わりで届くミッションのカスタマイズ性にあります。企業ごとにテーマを設定したり、社員からアイデアを募って作成したりすることが可能なため、自社の文化や言葉を取り入れた共感度の高い施策が実現できます。
「うちの会社らしいね」と感じられる体験は、若手社員の心理的なハードルを下げ、自発的な参加につながります。
まとめ
若者の健康意識が低い背景には、リスクへの実感の乏しさや、ライフスタイルの変化があります。しかし、それをやる気のなさと捉えるのではなく、伝え方・関わり方の工夫次第で行動は変わることを、企業は理解すべきです。
「見える化」「仲間とのつながり」「楽しさ」「得する感覚」――こうしたキーワードがそろえば、若手社員の健康リテラシーは自然と育ちます。そして、そうした仕組みを支えるパートナーとして、WellWaのようなサービスは大きな可能性を秘めています。
今こそ、若手世代に響く健康文化を、職場に根づかせていきましょう。