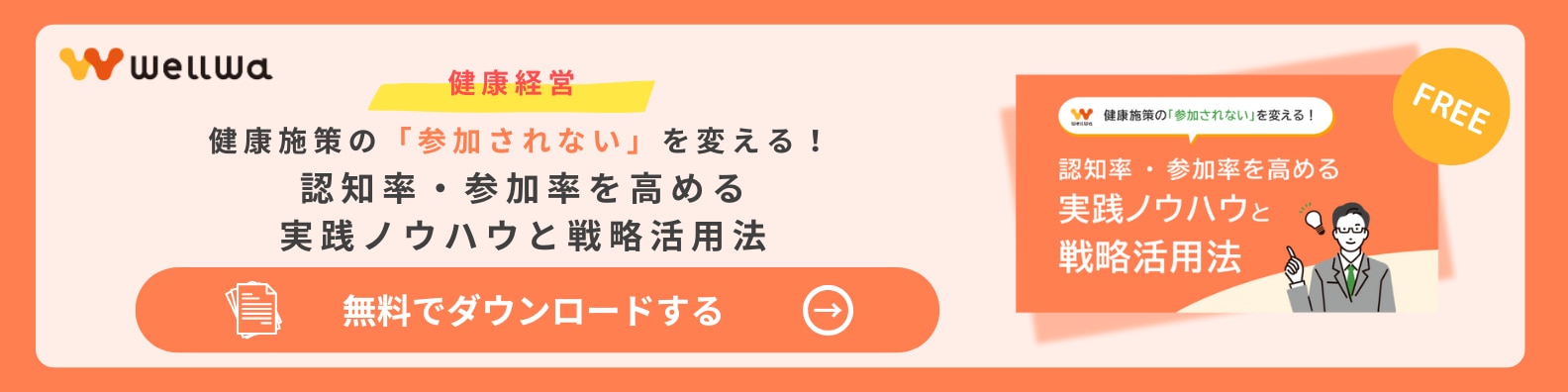社員の健康意識の向上を促進するにはどうすべき?5つの仕掛けをご紹介
「健康経営に取り組んでいるが、社員の反応がいまひとつ……」 そんな悩みを抱える担当者に共通しているのが、「健康意識の温度差」にどう対応するかという課題です。
健康意識の高い社員は制度や施策を積極的に活用してくれますが、無関心層にとってはどれだけ整った制度も「自分には関係ないこと」として捉えられてしまいがちです。
本記事では、「社員の健康意識をどう高めるか?」という視点で、今なぜこのテーマが企業にとって重要なのかを掘り下げた上で、無関心層の特徴とその対応策について考えていきます。
目次[非表示]
- 1.なぜ今「健康意識の向上」が企業に求められるのか
- 1.1.健康経営の注目と社会的背景
- 1.2.生産性・離職率・医療費への影響
- 1.3.健康無関心層がもたらすリスクとは
- 2.健康意識が低い社員に共通する3つの特徴
- 2.1.健康の「自己責任化」による無関心
- 2.2.情報過多と選択疲れによる混乱
- 2.3.生活習慣の固定化と行動変容の壁
- 3.社員の心を動かす!健康意識を高める5つの仕掛け
- 3.1.楽しく続けられる「ゲーミフィケーション」
- 3.2.行動変容を促す「ナッジ理論」の活用
- 3.3.健康と業務をつなぐ「ビジネスメリット」の提示
- 3.4.上司・管理職の巻き込みとロールモデルの存在
- 3.5.会社全体のムードを作る「仕掛け人」の存在
- 4.デジタルの力で継続を支援!WellWaの活用ポイント
- 5.健康意識の向上は「企業文化」で定着させる
- 6.まとめ
なぜ今「健康意識の向上」が企業に求められるのか
健康経営の注目と社会的背景
近年、企業の経営戦略において「健康経営」は欠かせないキーワードとなっています。経済産業省主導の「健康経営優良法人認定制度」や、人的資本の情報開示の義務化により、従業員の健康を守ることが経営の質として評価される時代が到来しています。
さらに、コロナ禍をきっかけに人々の健康意識が再定義され、企業にも「安心して働ける環境づくり」が強く求められるようになりました。これらの社会的背景から、健康施策はあればいいものから不可欠なものへと位置づけが変化しているのです。
生産性・離職率・医療費への影響
健康意識の低さは、社員本人だけでなく企業全体のパフォーマンスやコスト構造にも大きく影響します。
- 疲労や不調を抱えたまま働く「プレゼンティーズム」による生産性の低下
- メンタル不調や体調不良に起因する休職・離職リスクの増大
- 生活習慣病の進行による企業負担型医療費の増加
これらの問題は、日々の健康意識が低い状態を放置することで起こりやすくなることがわかっています。逆に言えば、健康意識の向上は、将来的な損失を未然に防ぐ「投資」であり、経営の根幹に関わるテーマです。
健康無関心層がもたらすリスクとは
企業の健康施策がうまく機能しない要因のひとつが、「健康に無関心な層の存在」です。健康意識が高い人ばかりを対象にした施策は効果が偏り、見えないサイレントリスクが放置されたままになります。
この無関心層がもたらすリスクは以下の通りです。
- 健康情報をスルーし、早期介入のタイミングを逸する
- 組織全体の健康文化づくりが進まず、雰囲気が育たない
- 他社員の巻き込みが難しくなり、健康経営の形骸化を招く
だからこそ、無関心層にどう働きかけて意識を変えていくかは、健康経営の成否を分ける重要なテーマといえるのです。
健康意識が低い社員に共通する3つの特徴
健康の「自己責任化」による無関心
多くの無関心層が抱えているのは、「健康はプライベートの問題であり、会社に関係ない」「体調管理は自己責任だから干渉されたくない」という価値観です。
この健康の自己責任化は、個人の自由を尊重する反面、企業としての支援を受け入れにくくする壁にもなります。
そのため、企業は押しつけではなく、寄り添うスタンスを意識し、社員に「自分のためにやるんだ」と思わせる仕組みづくりが求められます。
情報過多と選択疲れによる混乱
健康に関する情報は世の中にあふれており、「何を信じていいのかわからない」「調べるのが面倒」という状況に陥っている人も少なくありません。
- 「糖質制限がいい?でもバランスも大事?」
- 「○○式トレーニングが流行ってるけど、自分に合うのか不安」
- 「YouTubeを観て始めてみたけど、結局続かない」
このように、情報はあっても行動や継続につながらないのは、選択疲れやノイズの多さによる混乱が原因のことも多いのです。
生活習慣の固定化と行動変容の壁
特に30代以降の社員に顕著ですが、「長年の生活習慣がすでに出来上がっており、変えるにはエネルギーが要る」という壁も存在します。
「夜更かしが習慣」「運動が面倒」「朝食を摂らない」といった行動パターンは、本人にとっては当たり前になっており、外部からの介入だけでは変わりづらいのが実情です。
このような場合は、「少しずつできること」「成果を感じられること」「周囲に応援してもらえること」といった小さな変化を積み重ねる支援設計が有効です。
社員の心を動かす!健康意識を高める5つの仕掛け
楽しく続けられる「ゲーミフィケーション」
健康行動を習慣化するために効果的なのが、ゲームの要素を取り入れた「ゲーミフィケーション」です。歩数や食事記録に応じてバッジが獲得できたり、ランキング形式でチームの成績が可視化されたりすると、「義務感」ではなく「楽しさ」から行動が継続しやすくなります。
特に、若年層や無関心層にとっては、行動そのものよりも楽しい仕掛けの方が行動の入口になることが多いため、施策設計時には必ず検討すべきアプローチです。
行動変容を促す「ナッジ理論」の活用
「ナッジ(nudge)」とは、そっと背中を押すという意味で、「ナッジ理論」とは、行動経済学に基づいたアプローチです。社員食堂で野菜メニューを手前に配置する、歩数記録アプリで「昨日より100歩多く歩いてみましょう」と通知するなど、無意識の行動選択を促す仕組みがナッジ理論の特徴です。
説得や強制ではなく、「自然と体に良い選択をしたくなる」環境を整えることで、無理なく健康意識を育てることができます。
健康と業務をつなぐ「ビジネスメリット」の提示
健康は自分のためだけでなく、仕事のパフォーマンスを高め、ひいてはチーム全体の成果につなげるためのもの──という視点を持つことも大切です
例えば、「睡眠の質が上がると集中力が高まり、午前中の生産性が15%アップする」といったデータとともに伝えることで、社員は仕事のためにも健康が重要と実感しやすくなります。
上司・管理職の巻き込みとロールモデルの存在
健康意識の向上を職場に定着させるには、現場のリーダー層が率先して取り組むことが不可欠です。上司がミッションに参加している、管理職が自分の睡眠ログを確認しているといった姿勢が、若手や無関心層の背中を押すことになります。
「忙しい人こそやっている」というモデルがあると、社員の間にも自然とやってみようという雰囲気が生まれます。
会社全体のムードを作る「仕掛け人」の存在
社員を動かすうえで意外と大きいのが、社内の「仕掛け人」の存在です。健康に前向きな社員が中心となって施策を盛り上げると、「あの人がやっているなら参加してみようかな」という共感が広がり、文化の根づきが早まります。
正式な役職でなくても、自然と場を活性化できる社員を巻き込み型リーダーとして任命することが、健康経営を成功させる秘訣です。
デジタルの力で継続を支援!WellWaの活用ポイント
健康活動の「見える化」で意識変容をサポート
WellWa(ウェルワ)は、健康行動をアプリで日々記録・可視化できる仕組みを提供しています。歩数や食事、睡眠の記録がグラフで表示され、チームランキングも閲覧できるため、成果が目に見えることで行動継続が促されます。
「気づいたら1週間続けていた」という経験が、無関心層にもやってみようかなという前向きな気持ちを芽生えさせます。
個別最適化されたアプローチで「やらされ感」を解消
WellWaでは、デイリーミッションのテーマや難易度を企業や個人の状況に合わせてカスタマイズ可能です。若手には「睡眠記録ミッション」、管理職には「1on1で健康を話題にする」など、自分ごと化しやすいテーマの設計が可能です。
これにより、施策が一律で押しつけられるものではなく、自分のための取り組みに変わり、参加率と満足度が向上します。
組織全体での取り組みを促進する機能とは?
WellWaには、部署ごとのスコア集計やチーム間の対抗戦、スタンプ機能による応援・共感の可視化といった、組織として取り組む仕組みが備わっています。
このように個人と組織を同時に巻き込める設計により、健康行動が「文化」として根づきやすくなり、組織全体の健康意識が自然と底上げされます。
健康意識の向上は「企業文化」で定着させる
一過性ではなく「仕組み化」が鍵
施策を単発イベントで終わらせるのではなく、継続できる仕組みとして社内に組み込むことが重要です。月ごとのチャレンジ設計、定期的な成果報告、健康に関する社内表彰制度などがあると、習慣化のスピードが格段に上がります。
健康経営をミッション・ビジョンに組み込む
「企業として健康を大切にする」というスタンスを、MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)に明記することで、経営と社員の意識を一致させることができます。
「社員のウェルビーイングを支えることが競争力につながる」といったメッセージを明文化すれば、施策の一貫性と説得力が高まります。
社内評価制度への組み込み・ES向上との連動
健康行動や健康施策への参加を、人事評価やチーム目標の中に組み込むことで、組織的な推進力を得ることができます。また、健康施策がES(エンゲージメントサーベイ)向上と結びつけば、人的資本の可視化という観点でも企業価値が上がります。
まとめ
健康意識の向上は、単に「正しい情報を与えること」ではなく、社員一人ひとりが自分のこととして行動を起こすための環境づくりにかかっています。そのためには、可視化・習慣化・チームでの共感・楽しい体験といった要素が融合した仕組みが必要です。そして、その仕組みに共感し、巻き込まれていく人の力も重要です。
WellWaのようなツールを活用することで、「健康なんて興味ない」という社員にも、ちょっと試してみようと思わせる一歩をつくることができます。企業全体の健康意識を高め、持続可能な組織へと導くために、今できることから始めてみましょう。