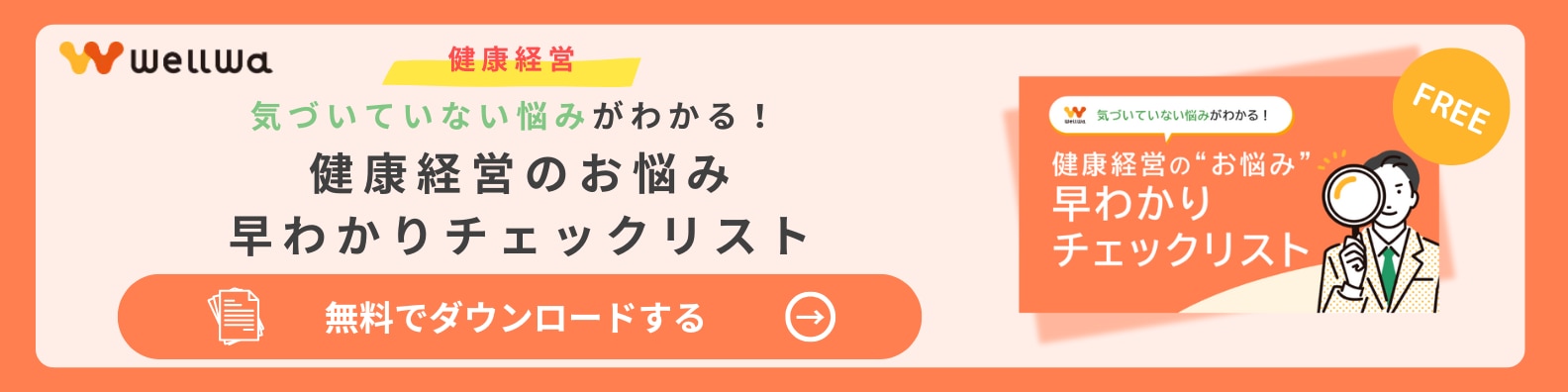今さら聞けない「健康管理」とは?企業が知っておくべき基本と実践法
働き方の多様化や従業員の高齢化、メンタルヘルス問題の顕在化など、企業を取り巻く労働環境は年々複雑になっています。
こうした背景のもと、注目を集めているのが「健康管理」という概念です。聞き慣れてはいても、実は「健康経営」と混同している方も多いのではないでしょうか。
この記事では、健康管理の基本から、企業活動における役割と実践方法までを解説します。健康経営推進担当者や人事・総務ご担当者が社内で取り組みを展開する際の基礎知識として、ぜひご活用ください。
健康管理とは?企業にとって重要な理由
健康管理の個人・組織における位置づけ
「健康管理」とは、個人が自身の身体やメンタルの状態を把握し、生活習慣やストレスのコントロールを通じて心身の健康を保つための取り組みを指します。これは従業員一人ひとりにとって基本的なセルフマネジメント行動であると同時に、企業側にとっては業務パフォーマンスや職場環境を維持するための経営課題でもあります。
近年では、個人任せの健康維持では限界があることが明らかになりつつあります。特にメンタルヘルスや過重労働の問題は、放置すれば事故や離職、訴訟リスクにもつながるため、企業として積極的に健康管理に関与する必要性が高まっているのです。
健康経営との違いと関係性
「健康管理」と「健康経営」は混同されがちですが、意味合いとスコープには明確な違いがあります。健康管理は、日常的な健康状態のチェックや対策を含む、比較的ミクロな視点の活動です。一方、健康経営はその先にある、経営戦略としての健康投資の考え方です。
つまり、健康管理は健康経営を実現するための「手段」であり、両者は補完関係にあります。従業員の健康状態を可視化し、継続的にマネジメントしていく仕組みがあってこそ、健康経営の効果検証やROI(投資対効果)の測定が可能になります。
出典:経済産業省「健康経営とは」
企業が健康管理に取り組むメリット
企業が従業員の健康管理に積極的に関わることで得られるメリットは多岐にわたります。第一に挙げられるのが「労働生産性の向上」です。健康な身体と安定したメンタルを維持できれば、集中力や創造力が持続し、業務パフォーマンスが高まります。
また、健康起因による欠勤(アブセンティーズム)や、出勤はしているものの生産性が著しく低下している状態(プレゼンティーズム)を予防・軽減できる点も見逃せません。さらに、従業員の健康を大切にする姿勢は、エンゲージメントの向上や企業ブランドの強化にもつながります。
健康管理は単なるコストではなく、戦略的投資ととらえることが、今後の企業経営には求められています。
健康管理が企業活動に与える影響
生産性や離職率に直結する健康リスク
厚生労働省の調査によれば、過重労働やメンタル不調に起因する離職者数は年々増加傾向にあります。また、慢性的な疲労や生活習慣病のリスクを抱えたまま業務を続けることは、パフォーマンスの低下やミスの増加にもつながります。
出典:厚生労働省「生活習慣病予防の労働生産性への影響を含めた経済影響分析に関する研究」
これらの健康リスクを未然に防ぐためにも、定期的なチェック体制や職場環境の整備が欠かせません。企業が従業員の健康状態に無関心であることは、将来的に大きな損失を招く可能性があります。
プレゼンティーズムとワークエンゲージメントの関係
プレゼンティーズムとは、「体調不良や精神的不調のまま出勤しているが、十分なパフォーマンスを発揮できていない状態」を指します。近年、この状態による企業の損失額がアブセンティーズム(欠勤)を大きく上回るともいわれており、見過ごせない課題です。
健康状態とワークエンゲージメント(仕事への熱意や前向きな姿勢)には密接な関係があります。適切な健康管理がなされていれば、従業員はポジティブな気持ちで仕事に取り組むことができ、結果的に組織全体の活力が高まります。
企業でできる健康管理の実践方法【基礎編】
健康診断・ストレスチェックなどの法令対応
企業がまず対応すべきは、健康診断の実施やストレスチェック制度など、法令で定められている健康管理施策です。これは労働安全衛生法に基づき、従業員の心身の異常を早期に発見し、必要な対応を講じるために義務化されています。
特にストレスチェックは、メンタル不調の予兆を捉えるうえで有効な制度です。ただし、「実施して終わり」ではなく、結果の分析やフォローアップ体制までを含めて設計することが大切です。
出典:厚生労働省「ストレスチェック制度について」
社内コミュニケーションを活かしたメンタルヘルス対策
メンタル不調は、業務外の要因も絡むため、データや診断だけでは把握しきれないケースも少なくありません。そのため、日常的な社内コミュニケーションの質を高めることが、最も効果的なメンタルヘルス対策のひとつといえます。
例えば、1on1面談の定着、チーム単位での健康に関するカジュアルな情報共有、ピアサポート制度の導入などが挙げられます。こうした対話の場があることで、従業員は「相談できる」「見守られている」と感じやすくなり、早期のストレスサインの把握につながります。
フレックスタイムや休憩制度の見直しで体調維持を支援
働き方改革の文脈でも注目されているのが、「柔軟な勤務制度による健康支援」です。フレックスタイム制やリモートワークの導入、仮眠室やマッサージスペースの設置、ランチ休憩の拡充などは、心身の回復力を高める環境整備につながります。
重要なのは、制度だけを用意するのではなく、実際に従業員が利用しやすいようにルールや文化を醸成することです。利用率が低いままでは、健康管理施策としての効果は限定的です。人事制度や評価との整合性も視野に入れて設計を進めましょう。
企業でできる健康管理の実践方法【発展編】
デジタルツールでの行動変容支援(アプリ・IoT連携)
近年の健康管理では、スマートフォンアプリやIoTデバイスの活用が大きな潮流となっています。歩数や睡眠時間、心拍数などのデータを自動で取得し、グラフで可視化できるサービスは、従業員自身のセルフモニタリングを習慣化するうえで有効です。
具体例を挙げると、オムロンの「Wellness LINK」は体組成計と連動し、数値変化をリアルタイムで把握できます。また、WellWaのようなサービスでは、アプリで記録するだけでなく、チーム参加型のイベントやポイント付与によって、楽しみながら継続的に取り組む設計がなされています。
食・運動・睡眠の習慣化を促すインセンティブ施策
健康行動を促すうえで、インセンティブの設計も効果的な手法です。単なる義務や啓発では継続しづらい健康習慣も、楽しさや報酬があれば自然と身につきやすくなります。
例えば、1日8,000歩の達成でポイントを付与し、社内ストアで飲料や軽食と交換できる制度や、睡眠記録を継続したチームに表彰やノベルティを配布する取り組みなどが挙げられます。
WellWaでは、健康習慣で貯めたポイントを「WellStock(置き型販売)」や「WellStore(アプリ内EC)」で利用できる仕組みが整っており、健康と福利厚生が一体化した好循環を生み出しています。
部署横断の連携を促す「巻き込み型」プログラムの導入
健康管理を組織文化に根づかせるには、部署単位での取り組みにとどまらず、部門を超えた巻き込みが鍵となります。拠点対抗のウォーキングイベント、役職別の健康チャレンジ、リーダー主導のチーム編成などを行うことで、社内全体での一体感を生み出せます。
WellWaでは、「チャレ活」や「健康選手権」といったイベントを軸に、部署間の連携を促す工夫がされており、現場主導の健康文化が自然と形成されていきます。
健康管理施策の成功に向けた3つのポイント
目的とKPIを定めて「成果」を可視化する
健康施策は「なんとなく良さそう」では説得力を持ちません。実施前に明確な目的とKPI(評価指標)を設定することが、経営層の納得や全社的な推進の鍵となります。
「アブセンティーズムを前年比で5%改善」「プレゼンティーズムスコアを3ポイント上げる」など、具体的な数値目標を持つことで、PDCAサイクルを回しやすくなります。
健康無関心層にも届く「楽しさ・続けやすさ」の仕掛け
健康施策が陥りやすい課題のひとつが、「健康意識の高い層にしか届かない」という偏りです。継続率や参加率を上げるには、楽しさや報酬といったモチベーションの仕掛けが必要です。
「スタンプを送る」「チームランキングで競う」「食事や運動のちょっとした変化がポイントになる」といった仕組みは、健康に関心の薄い従業員でも無理なく参加できます。
経営層・管理職の巻き込みと社内文化への落とし込み
いくら制度や仕組みが整っていても、経営陣が関心を持たなければ、現場は「形だけ」と感じてしまいます。
経営陣が自らイベントに参加したり、月次会議で健康KPIに言及するなど、メッセージの発信と行動で背中を見せることが効果的です。
管理職層には、健康施策を現場運営に組み込むようなサポートが必要です。
WellWaで実現する「つながり×健康」の好循環
WellWaとは? ― 健康経営を支援するサービス
WellWa(ウェルワ)は、キリンビバレッジが開発した法人向けの健康管理支援サービスで、「たのしい健康」「おいしい健康」「健康のROI」という3つの軸から健康経営を支援する点が特長です。
チームのコミュニケーションが生まれる機能や、福利厚生サービスとの連動など、健康へのアクションを促す仕組みで、ウェルビーイングの輪を広げていきます。
現場で活用されるWellWaの機能
WellWaでは、以下のようなプログラムが展開されています。
- チャレ活:部署・チーム単位で取り組む健康チャレンジ。歩数や睡眠、食生活などテーマは多彩。
- 健康選手権:月ごとの健康指標を部署対抗でランキング化。部署間コミュニケーションの促進にも効果あり。
- WellStock / WellStore:貯めたポイントを置き型販売やアプリ内ECで即時利用。福利厚生としての満足度も高い。
参加方法も柔軟で、個人でも、任意チームでも、企業指定のチームでも参加できる点が特長です。
プレゼンティーズム・ワークエンゲージメント改善の実績データ
キリングループ社内での検証によれば、健康習慣(食事・運動・睡眠・飲酒)をひとつ改善するだけで、年間19.6万円/人の生産性向上につながるという統計が得られています。
また、会話量やメンタルスコアとエンゲージメントスコアの上昇といった成果が確認されています。
導入しやすいWellWaの活用メリットと導入ステップ
社員も管理者も使いやすい設計
WellWaはスマートフォンひとつで使えるシンプルなアプリ設計ながら、記録・ポイント・イベンなど多機能です。プッシュ通知や個別ミッション、家族アカウントにも対応可能で、現場に寄り添った設計がなされています。
管理者向けには、部署別集計や利用状況レポートも整っており、定量・定性の両面から効果測定ができます。
コスト感と導入フロー:定額で始めるウェルビーイング施策
2つの料金プラン(レギュラー・エントリー)が用意されており、月額250円/人〜から利用可能です。最低契約人数は明示されており、スモールスタートにも対応しています。
導入も短期間で完結し、初期費用が抑えられている点から、コストを抑えながら成果を出したい企業にとって非常に導入しやすいサービスです。
リアルイベントや社内ミッションと組み合わせて浸透を加速
WellWaはアプリ内施策だけでなく、リアルでの体力測定や健康セミナーとの連動も可能です。また、社内公募型ミッションや、健康保険組合とのタイアップも柔軟に設計できるため、他部署との連携や全社展開もスムーズに進められます。
このように、デジタル×リアルのハイブリッド設計により、職場全体を巻き込む仕組みが実現できます。
まとめ
人口減少・人財流動化・働き方多様化が進む今、企業が競争力を維持するためには、社員一人ひとりのコンディションと能力を最大限に引き出す環境づくりが求められます。その第一歩が「健康の見える化」と「継続的な支援の仕組み化」です。
まずは自社の現状を把握し、法令対応だけでなく戦略的な健康管理へと視野を広げてみましょう。そのうえで、WellWaのような実績豊富なツールを活用し、楽しみながら続けられる体験設計を整えることが、持続的な健康経営の実現につながります。健康管理は単なるコストではなく、企業の未来を支える重要な投資です。今こそ、従業員の健康を軸にした経営への転換を始めてみませんか。