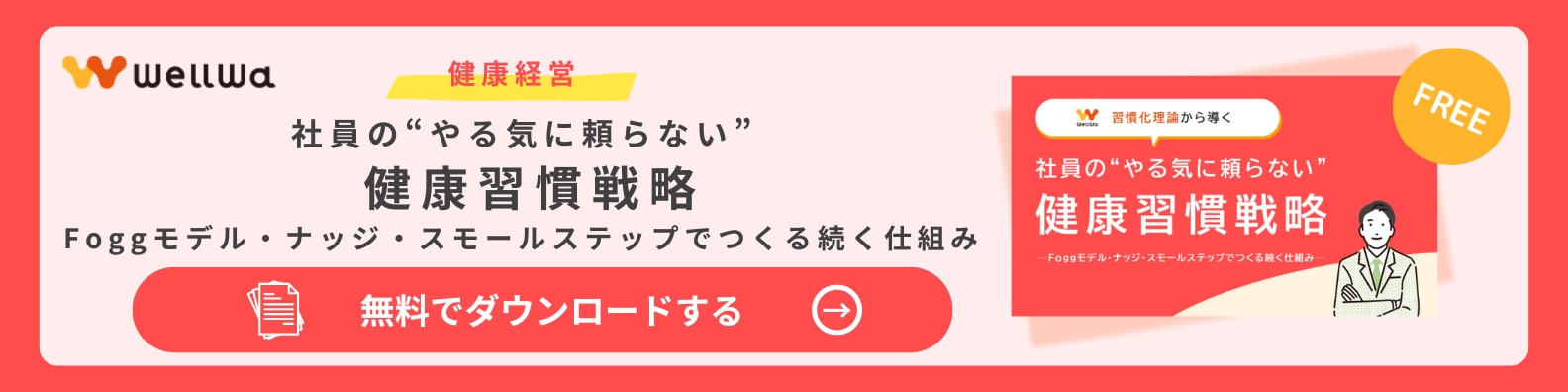健康管理で「自分で守る健康」を促進!社員の自己管理力を高める5つの施策
企業の健康経営が当たり前になりつつある今、次のステージとして注目されているのが「社員一人ひとりの健康管理による自己管理力向上」です。健康診断やストレスチェックといった外からの支援だけでは、社員の行動や意識は根本からは変わりません。最も重要なのは、社員自身が自らの体調に関心を持ち、自律的にケアを継続できる力を身につけることです。
この記事では、社員の健康管理・自己管理力を高める意義と課題、そして企業が今すぐ実践できるアプローチを解説します。健康経営担当者・人事・福利厚生の責任者にとって、行動変容の本質を見直すヒントになれば幸いです。
目次[非表示]
- 1.なぜ今、社員の「健康管理による自己管理力」が重要なのか
- 2.自己管理力向上を阻む3つの壁と企業の課題
- 2.1.関心の低さと「やらされ感」
- 2.2.継続性が生まれない取り組みの限界
- 2.3.上司や同僚との「つながり」が不足
- 3.社員の健康管理・自己管理を促進する5つの実践施策
- 3.1.1. 習慣化を支援する「ミッション型アプローチ」
- 3.2.2. チームで取り組む「チャレンジ型イベント」
- 3.3.3. ポイント制で行動を可視化し、インセンティブに
- 3.4.4. 雑談・共感を促すコミュニケーション施策
- 3.5.5. 組織文化として根付かせる「部署別ランキング」導入
- 4.成果につながる取り組み方の工夫と継続のコツ
- 5.社員の自律的な健康習慣を支援する「WellWa」とは
- 6.まとめ
なぜ今、社員の「健康管理による自己管理力」が重要なのか
健康経営の鍵は「自律性」にあり
健康経営に取り組む企業が増えるなかで、注目すべきキーワードの一つが「自律性(オートノミー)」です。これは、社員が自らの健康状態を把握し、目的意識を持って行動を選び、習慣を継続する力のことを指します。
従来の企業の健康施策は、健診やセミナーといった外から与える支援が中心でした。しかし、これだけでは一時的な行動変化にとどまり、根本的な生活習慣の改善にはつながりにくいのが実情です。
そこで問われるのが「社員が自ら主体的に健康を意識できているかどうか」です。企業側は、制度やツールの提供に加えて、社員の内発的動機づけを引き出す仕組みを構築する必要があります。ここに健康経営の本質があるのです。
プレゼンティーズム改善と生産性向上の関係
自己管理力が低いまま仕事を続けると、体調不良や集中力の欠如などから生産性が落ちる「プレゼンティーズム」に陥りやすくなります。これは、企業にとっては見えにくい損失であり、欠勤よりも深刻な影響を及ぼす場合もあります。
逆に言えば、社員の自己管理力が高まることで、こうした状態を未然に防ぐことができ、結果として業務効率やパフォーマンスの向上につながります。実際、キリンビバレッジの社内検証でも、運動・睡眠・食事のいずれかを1つ改善するだけで年間数十万円規模の生産性向上が確認されています。
このように、健康管理による自己管理は、個人の問題にとどまらず、組織全体の業績にも影響を与える重要な要素なのです。
自己管理力が組織エンゲージメントを左右する理由
健康を自ら整えられる人ほど、日々の業務にも前向きに取り組むことができる傾向があります。これは、自己効力感(自分で状況をコントロールできているという感覚)が、仕事の満足度やエンゲージメントに直結するためです。
さらに、自分自身の健康状態に意識を向けられる人は、他者への気配りやコミュニケーションにも余裕を持ちやすく、結果として職場の心理的安全性やチームの結束力にも良い影響を与えます。
自己管理力の向上は「個人のパフォーマンス向上」だけでなく、「チームや組織の健全性」にまで波及する。これが、企業が今あらためて健康自己管理に注力すべき最大の理由です。
自己管理力向上を阻む3つの壁と企業の課題
関心の低さと「やらされ感」
最初の障壁は、健康そのものへの関心の低さです。「まだ若いから大丈夫」「忙しくてそれどころじゃない」などの理由で、社員が健康を自分ごととして捉えられていないケースは少なくありません。
また、企業側が一方的にセミナーや制度を押しつけることで、社員が「やらされている」と感じてしまうことも、継続意欲を損なう大きな要因です。
この課題に対しては、「参加したくなる」「自然に続けられる」仕掛けが重要になります。仲間と楽しめるイベント形式の施策や、ミッション型のポイント制度などが有効です。これにより、健康行動が内発的動機からスタートするきっかけをつくることが出来ます。
継続性が生まれない取り組みの限界
健康施策は一過性になりやすく、「実施したけれど続かない」「気づけば誰も使っていない」といったケースが多く見られます。その背景には、行動変容の難しさと、継続を支援する仕組みの不在があります。
具体的には、健康アプリを導入したものの、使い方が複雑で離脱者が続出する、記録してもフィードバックがなくモチベーションが保てない、といった問題が挙げられます。
このような状況を打破するには、「使いやすさ」と「楽しさ」を兼ね備えた仕組み設計が必要です。加えて、成果を実感できるフィードバックや、定期的な声かけなど、人による支援も継続性には不可欠です。
上司や同僚との「つながり」が不足
個人の自己管理力は、職場の人間関係や心理的安全性にも大きく左右されます。孤立した状態では、「体調が悪くても言えない」「気持ちを整える場がない」といった悩みを抱えやすくなり、結果として健康意識も薄れてしまいがちです。
企業ができるのは、自己管理を個人任せにせず、チーム全体で健康を意識する文化を育てることです。たとえば、上司との1on1で健康の話題を取り入れる、チーム単位で目標を共有する、職場に健康に関する雑談や情報共有の場を設けるなど、日常の中でつながりを生む工夫が求められます。
社員の健康管理・自己管理を促進する5つの実践施策
自己管理力を高めるには、ただ「意識してください」と呼びかけるだけでは不十分です。継続的に取り組みやすく、かつ周囲との関係性も活かせる仕組みを設計することが成功のカギとなります。ここでは、実践的で導入しやすい5つの施策を紹介します。
1. 習慣化を支援する「ミッション型アプローチ」
健康行動を「習慣」として定着させるには、小さな目標をクリアし続ける体験が効果的です。「今日は1駅分歩いてみよう」「夜11時までに寝よう」など、日々の生活に無理なく取り入れられるミッションを提示する形式です。
こうした「ミッション型」のアプローチでは、自分の行動が「達成」として可視化されることで達成感が得られ、モチベーションの維持につながります。また、クリアごとにポイントが貯まるように設計すれば、報酬要素も加わって継続率が高まります。
2. チームで取り組む「チャレンジ型イベント」
健康管理は個人の努力と捉えられがちですが、チームで取り組むことで楽しさや一体感が生まれます。「チーム対抗 歩数チャレンジ」や「部署対抗 睡眠記録選手権」などのイベントを企画することで、社員同士が励まし合いながら取り組む文化が育ちます。
このような「チャレンジ型」の取り組みは、他部署との交流促進や社内コミュニケーションの活性化にも効果的です。孤立を防ぎ、健康への関心を広く共有するきっかけとしても有効です。
3. ポイント制で行動を可視化し、インセンティブに
行動を定量的に可視化し、努力が報われる仕組みをつくることで、健康施策の効果は大きく高まります。たとえば、日々の記録やイベント参加でポイントが貯まり、それを飲料や社内ストアで使える仕組みにすることで、社員の関与度が格段にアップします。
重要なのは、必ずしも「高得点を取る」ことだけを目的にしないことです。日々の小さな積み重ねに意味を持たせることで、全社員が自分のペースで参加しやすくなります。
4. 雑談・共感を促すコミュニケーション施策
健康管理を個人だけに委ねず、「共有できる話題」として職場に根づかせることも大切です。雑談アプリや社内SNSで「今日の睡眠時間」や「ランチで食べた野菜」などを気軽に共有できる環境を整えることで、自然な健康会話が生まれます。
また、スタンプやリアクション機能を通じて「共感」や「応援」の気持ちを伝えられる設計にすれば、孤立しがちな社員も安心して参加できるようになります。
5. 組織文化として根付かせる「部署別ランキング」導入
社員のモチベーションを引き上げるには、可視化と競争の要素も有効です。部署ごとに健康記録の平均値をスコア化し、毎月ランキング形式で発表することで、チーム単位での意識醸成が進みます。
重要なのは、あくまで楽しみながら取り組める環境にすること。上位・下位に優劣をつけるのではなく、「部署全体で応援し合う雰囲気」を育むことが、組織風土の変革につながります。
成果につながる取り組み方の工夫と継続のコツ
マネジメント層を巻き込んだ仕掛けづくり
自己管理力を組織に根づかせるには、管理職やマネジメント層の巻き込みが不可欠です。部長自らがチャレンジに参加する、1on1で健康の話題を取り入れるなど、行動で見せることが職場全体への波及につながります。
また、部門ごとのKPIに健康スコアを紐づけたり、管理職評価にチーム健康データを参考指標として加えるといった設計も、責任感と主体性を引き出す手段になります。
楽しさと意義を両立させるデザイン設計
健康施策が「義務感」に変わると、参加率はすぐに落ちてしまいます。重要なのは、遊び心やワクワク感を施策に組み込むことです。
日替わりでミッションが変わる、キャラクターが進捗を応援する、スタンプを送り合えるといった工夫が、楽しさを生み出します。同時に、「自分の健康がパフォーマンスに直結する」という意義づけも、しっかりと伝えていく必要があります。
定量・定性の両面での効果測定
健康施策の効果は、数値だけでなく、社員の声や変化を含めて多面的に捉えることが大切です。参加率や平均歩数、ストレススコアの推移に加えて、「同僚と話す機会が増えた」「最近体調がいい」といったアンケート結果も参考にすべきです。
定量データだけを見て一喜一憂するのではなく、現場のリアルな声を拾い上げ、施策の改善に反映していく。この双方向の姿勢が、社員の信頼を生み、継続の土台になります。
社員の自律的な健康習慣を支援する「WellWa」とは
WellWaの特徴:つながり×楽しさ×継続
WellWa(ウェルワ)は、キリンビバレッジが提供する法人向けの健康支援サービスです。単なる記録アプリではなく、「チームで健康を楽しむ」ことを重視したユニークな仕組みが特長です。
- チーム対抗イベントやランキング機能でつながりを生み
- デイリーミッションやスタンプ送信で楽しさを演出し
- ポイント交換制度で継続を支援する
この3つの要素が絶妙に組み合わさっており、自己管理力を自然に高める文化が職場に育ちます。
毎日の習慣化を促すデイリーミッションとポイント設計
WellWaでは、歩数や食事、睡眠などに関する「日替わりミッション」が毎日配信され、クリアすることでポイントが貯まります。ポイントは飲料や福利厚生商品と交換できるため、モチベーション維持に直結します。
また、チームで参加するイベントでは、スタンプを送り合ったり、チャットで励まし合うことができ、孤立を防ぎながら習慣化を後押しします。自己管理を楽しく、自然に、継続的に支援する仕組みとして、高い評価を得ています。
まとめ
健康は、企業にとって個人の自由に任せておくにはリスクが大きすぎるテーマです。一方で、押しつけではなく、社員自身の気づきと行動から始まる取り組みにこそ、長期的な変化が生まれます。自己管理力を高める施策とは、健康を自分ごととして捉え、チームで支え合い、楽しみながら続けられる仕組みのこと。WellWaのようなツールを活用することで、その文化は自然と職場に根づいていきます。健康は「自己責任」ではなく、「チームで育てる」時代へ──その第一歩を、今こそ踏み出してみてはいかがでしょうか。