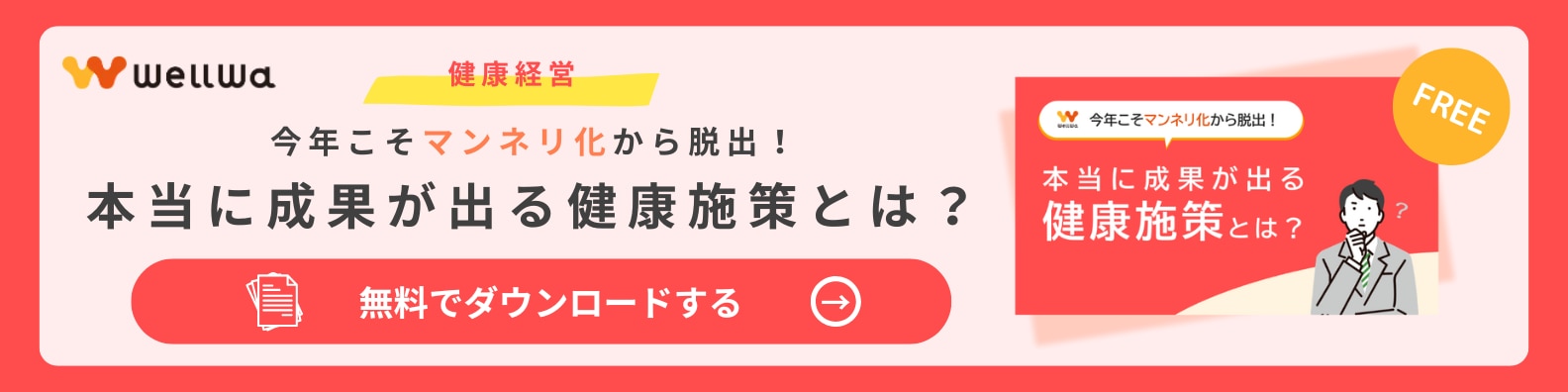職場こそ健康管理の要!すぐに実践できる社員の自己管理力を高める施策7選
テレワークと出社のハイブリッド化が進み、働く環境が多様化するなか、「職場における健康管理」の重要性がかつてないほど高まっています。健康は従業員個人の問題とされがちですが、実際には業務のパフォーマンスや職場の人間関係、さらには企業の業績にまで影響を及ぼします。
そこで問われるのが、「職場で何ができるか」という視点です。企業として法令遵守にとどまらず、自己管理を支援する職場環境を整え、社員が自然と健康行動に取り組める仕組みづくりが求められています。
本記事では、職場で実践可能な健康管理の考え方と、自己管理力を高める施策を紹介します。
目次[非表示]
なぜ今、職場での健康管理が重要なのか
健康課題の企業損失は年々拡大
厚生労働省や経済産業省が公開しているデータによると、従業員の健康課題によって生じる企業損失額は年々増加傾向にあります。例えば、厚生労働省の「令和5年版 労働経済の分析」によると、2022年の休業者数(病気やケガで一時的に仕事を離れている労働者)は約213万人となり、前年より5万人も増加しました。
出典:厚生労働省「令和5年版 労働経済の分析」
特に注目されるのが「プレゼンティーズム(出勤しているが体調不良等で生産性が低下している状態)」による損失です。厚生労働省の調査では、企業が負担する健康関連コストの主要因はプレゼンティーズムであり、アブセンティーズム(欠勤)による損失をはるかに上回ることが判明しました。
出典:厚生労働省保健局「データヘルス・健康経営を促進するためのコラボヘルスガイドライン」
プレゼンティーズムは、アブセンティーズムよりも見えにくいため放置されやすく、実は企業にとって最も深刻な「隠れコスト」ともいえます。慢性的な疲労や睡眠不足、軽度のメンタル不調が、集中力や判断力の低下を招き、事故・ミス・生産性の低下につながります。
こうした課題に対処するには、定期的な健康診断やストレスチェックだけでなく、職場での健康管理を日常の中で支援する仕組みが必要不可欠です。
自己管理力の高い社員が企業にもたらす好影響
自己管理力とは、健康状態を把握し、必要な行動を自発的に実行・継続できる能力を指します。この力を持った社員は、心身ともに安定した状態で仕事に取り組むことができるため、生産性が高く、他者との協調性にも優れています。
自己管理力のある社員は「自分のことだけで精一杯」にならず、チームへの配慮や後輩へのサポートも積極的です。これは、組織全体の雰囲気や文化にもポジティブな影響を与え、長期的には離職率の低下やエンゲージメント向上といった効果も期待できます。
つまり、健康管理は「制度としてやるべきこと」ではなく、企業の生産性と持続的成長のための戦略的投資なのです。
健康経営とエンゲージメントの相関とは
経済産業省が推進する「健康経営」では、従業員の健康を企業の資本と捉え、その維持・増進を経営課題として位置づけることが求められています。この文脈で近年注目されているのが、エンゲージメントとの相関です。
実際、健康状態が良好な従業員ほど、会社に対して前向きな感情(愛着・貢献意欲など)を持ちやすい傾向があるとする調査結果もあります。逆に、体調が万全でない状態が続くと、仕事への熱意が失われ、離職意向が高まることが指摘されています。
職場での健康支援が「業務効率」だけでなく、「人財の定着」「チームの活性化」「職場の雰囲気改善」といった多面的な効果をもたらすことは、今や明白です。
健康管理を「自分ごと化」させる職場施策の考え方
健康施策が「やらされ感」で終わる理由
企業が一方的に提供する健康施策がうまく機能しない理由のひとつに、「やらされ感」が挙げられます。義務的に受けさせられるセミナーや、参加を強制されるイベントでは、社員の内発的なモチベーションは育ちにくく、「面倒」「意味がわからない」という反発につながることもあります。
本来、健康は個人にとって最も重要な資産であり、自分の意思で守っていくべきものです。しかし、企業施策の設計次第では、その当事者意識を逆に遠ざけてしまう危険もあるのです。
自己決定理論から考える行動変容のヒント
ここで参考になるのが、心理学における「自己決定理論(Self-Determination Theory)」です。この理論では、人が行動を自発的に継続するためには、「自律性」「有能感」「関係性」の3つの要素が重要だとされています。
- 自律性:自分で選んでいるという感覚があること
- 有能感:できた、達成したという実感があること
- 関係性:誰かとつながっているという安心感があること
職場での健康管理施策にこの理論を取り入れることで、「やらされ感」ではなく「やってみよう」と思える仕組みに変えることが可能です。
目標を自分で設定できる健康チャレンジ、同僚と励まし合えるチーム型イベント、達成が見えるポイント制などがそれに当たります。
すぐに実践できる!社員の健康意識を高める7つの施策
職場での健康管理は、「特別な取り組み」ではなく「日常に溶け込む工夫」が重要です。ここでは、今すぐ導入可能で、社員の健康意識を高める7つのアイデアを紹介します。
【1】アプリ連動型の健康習慣チャレンジ
スマートフォンを活用したアプリ連動型の施策は、手軽さと継続性の両立に優れています。歩数・睡眠・食事記録を日々記録し、目標達成でポイントやバッジを獲得するチャレンジ形式が効果的です。
WellWaのように、デイリーミッションが用意され、チーム対抗で楽しめる設計であれば、「やらされ感」を抑えつつ、自発的な行動変容を促すことができます。
【2】スナック菓子禁止より「健康おやつ選び」習慣
職場の間食環境を見直すことも、健康意識を高めるきっかけになります。ただし、「禁止」では反発を招きやすいため、「選び方」を提案するスタイルがベターです。
例えばナッツ・ドライフルーツ・高カカオチョコレートなど「健康おやつ」を社内売店で展開し、「今月のおすすめ」コーナーを設けることで、自然な行動変容が期待できます。
【3】オフィスに歩数マップを設置
オフィス内の移動を運動に変える施策として、歩数換算マップの掲示が有効です。「1周すると〇歩」「エレベーターを使わず階段で〇歩」といった情報を可視化し、日常動作に健康要素を取り入れます。
視覚的に楽しく、職場を「歩きたくなる空間」に変えることで、意識の変化が促されます。
【4】体調記録ボード/バイオリズム可視化
日々の体調を「見える化」することで、自己管理の意識が高まります。カレンダー形式のホワイトボードに色分けシールで体調を記録する簡易記録法や、アプリ連動のバイオリズム表示などがあります。
個人で記録するだけでなく、チーム内で「今週は調子がいい人が多いな」「ちょっと疲れてる人が多いかも」など共有する仕組みにすれば、気配りと対話のきっかけにもつながります。
【5】朝活やヨガなど「ゆるコミュニティ」支援
朝のストレッチやランニング、ランチヨガなど、強制されず、参加しやすい「ゆるコミュニティ」を育てることで、健康習慣が楽しく続けやすくなります。
ポイントは「成果を求めないこと」「多様な層が参加できる雰囲気をつくること」。自主性が尊重される場であれば、自然と人が集まり、健康への関心も高まります。
【6】ストレスリリースカードで心理的安全性アップ
ストレスは健康意識を鈍らせる最大の敵です。「気持ちを言語化できる」「誰かに共感してもらえる」環境を整えることで、自己管理力の土台となる心理的安全性が高まります。
「今の気分を1枚のカードで表す」「気分カードをもとにランチ雑談する」といった簡単な仕掛けでも、効果は十分です。
【7】ヘルスリテラシー向上セミナーの定期開催
どれだけ環境が整っていても、知識がなければ行動は変わりません。睡眠・栄養・ストレス管理など、テーマを絞ったミニセミナーを定期開催することで、健康行動の根拠や意味を学ぶ機会が得られます。
座学だけでなく、クイズや体験型ワークショップなど、参加型の要素を取り入れることで、理解と定着が進みます。
職場の健康管理におけるPDCA
実施だけで満足しない、効果測定の仕組み
施策を「実施した」だけで終わってしまっては、健康経営は成立しません。行動変容を促すためには、「何が、どれだけ、変わったのか」を測る仕組みが不可欠です。
アンケート、参加率、アプリのログデータなど、定量と定性の両面から分析し、改善ポイントを洗い出すPDCAサイクルを構築しましょう。
参加率・継続率が伸びるフィードバック方法
「続けたくなる仕組み」には、適切なフィードバックが必要です。「部署別ランキング」「目標達成者の紹介」「メッセージ付きポイント付与」など、行動の可視化と称賛をセットにした仕掛けが効果的です。
特に、仲間同士のスタンプやコメントなど、「人の気持ちが介在するフィードバック」が継続率に影響を与えることが分かっています。
WellWaで実現する職場の健康管理
WellWaで実現する「習慣化支援」
WellWa(ウェルワ)は、デイリーミッション、ポイント制度、チームランキング、部署別レポートなどを備えた法人向け健康支援サービスです。行動記録の習慣化だけでなく、チームで健康を楽しむ文化づくりにも貢献します。
企業は、WellWaを通じて自己管理力の支援だけでなく、健康経営のKPI(エンゲージメント、プレゼンティーズムなど)の見える化も同時に進めることが可能です。
無理なく健康習慣を定着させる機能とは?
重要なのは、「がんばらなくても続けられる」設計です。日々のミッションが短時間で完了できたり、ワンタップで記録できたりと、「簡単・短時間・小さな達成感」が行動定着の鍵を握ります。
WellWaでは、キリン独自の統計分析モデルにより、25問の設問で健康指標の投資対効果が可視化できます。
まとめ
健康施策を社内に浸透させるには、まずは少人数チームからの「スモールスタート」が効果的です。部門内での実証実験を通じて成功体験をつくり、他部署への展開へとつなげましょう。どれほど担当者が熱意を持っても、仕組みが使いづらければ定着しません。ポイントは「ユーザーにとって使いやすい設計」であり、感覚的に操作できるUIや、すぐに効果を実感できるフィードバック設計が重要です。
職場における健康管理の最初の一歩は、「見える化」と「共感」を両立させる仕組みを整えること。社員一人ひとりが「気づき」と「つながり」を得られる環境こそが、行動変容の起点になります。今こそ、職場に「健康を支え合う文化」を育てていきましょう。そのためのツールとして、WellWaのような仕組みを活用することが、新たな未来への第一歩となるはずです。