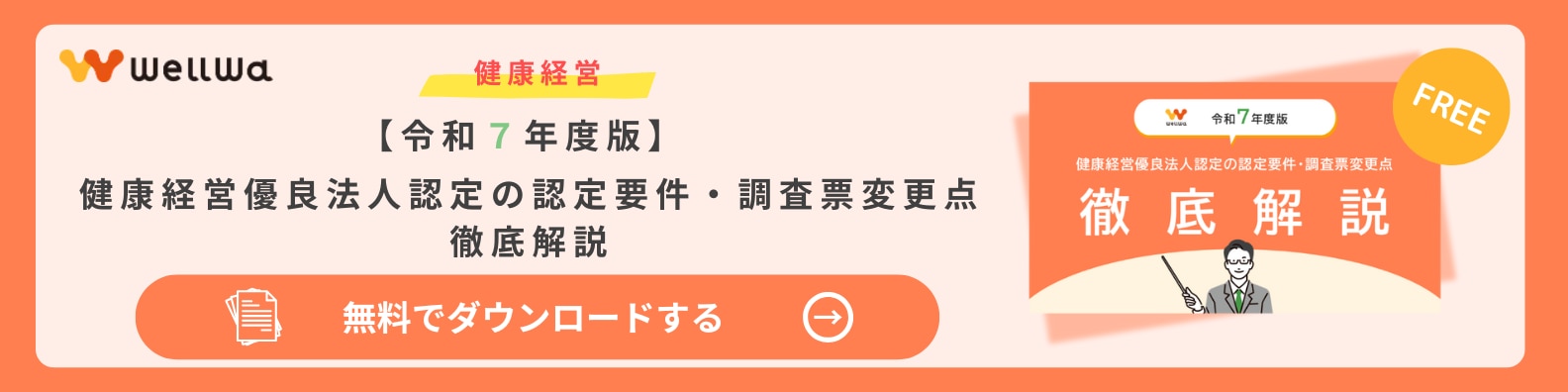企業の責任とは?従業員の健康管理に関する義務とリスク解説
健康経営という言葉が浸透しつつある一方で、見落とされがちなのが、「企業が従業員の健康を守ることは、単なる善意ではなく義務である」という点です。法令に基づいた健康配慮は、現代の働き方において避けて通れない責任領域となっています。
本記事では、企業が法的に負う健康管理義務の内容と、その背景、違反時のリスクについて解説。人事・総務・健康経営の担当者の方にとって、制度整備やリスクマネジメントの参考となる情報をお届けします。
目次[非表示]
健康管理は企業の「義務」
増える健康トラブルと企業への責任追及
長時間労働やメンタルヘルス不調、過労死・過労自殺など、働く人の健康をめぐるトラブルは年々深刻化しています。厚生労働省の「過労死等の労災補償状況」によると、精神障害に起因する労災認定件数は高止まりを続けており、企業の管理体制が厳しく問われる状況にあります。
こうした事例では、「企業側が適切な健康管理措置を怠った」として、安全配慮義務違反や健康配慮義務違反により損害賠償責任を問われるケースも少なくありません。健康被害が業務起因と認められた場合、その責任は経営側に重くのしかかるのです。
働き方改革と健康経営の位置づけ
2019年に施行された働き方改革関連法により、労働時間の上限規制や有給休暇の取得義務化が進みましたが、その根底にあるのが「健康的な働き方を前提とした労働環境づくり」です。
また、経済産業省が推進する「健康経営」の枠組みにおいても、従業員の健康保持・増進は、企業価値の向上と直結する戦略的テーマと位置づけられています。
今の時代における健康管理は、コンプライアンス対応だけでなく、企業ブランディングや人財確保の面でも不可欠な取り組みとなっているのです。
健康管理義務が注目される3つの背景
企業の健康管理義務が近年ますます注目されている背景には、以下の3点があります。
- 社会的責任の高まり ESG(環境・社会・ガバナンス)経営の広がりとともに、従業員の健康配慮が「社会的責任」の一環とされ、株主や投資家からの関心も高まっています。
- 労働力不足と定着支援 少子高齢化が進む中、健康に働き続けられる職場づくりは、離職率の低下や人財定着のカギとなります。職場の健康配慮は、採用力・定着力に直結する要素です。
- 情報公開の義務化 人的資本開示の動きにより、健康関連のKPI(ストレスチェック実施率、プレゼンティーズムなど)を可視化し、外部に公開する企業が増えています。この流れは、企業の対応レベルを客観的に示す指標ともなっています。
出典:経済産業省「健康経営の推進」
法的に企業が負う従業員の健康管理義務とは?
労働安全衛生法で定められた義務
企業が従業員の健康を守る法的根拠として最も基本となるのが、「労働安全衛生法」です。この法律では、企業に対して以下のような義務が課されています。
- 健康診断の実施(年1回以上)
- ストレスチェック制度の実施
- 衛生管理者の選任・衛生委員会の設置
- 長時間労働者への産業医面談の実施
これらは「努力義務」ではなく、法令で定められた「義務」です。怠った場合には行政指導や罰則の対象となるほか、万が一健康被害が発生した際のリスクも高まります。
出典:厚生労働省「労働安全衛生法の概要」
判例から読み解く「健康配慮義務」
法令に加え、判例上でも「健康配慮義務」が企業に課されていることが明確になっています。これは、労働契約法第5条に定められた「安全配慮義務」の一環として、企業が従業員の健康と安全を保持するよう配慮すべき責任を負うという考え方です。
過重労働によるうつ病発症が労災認定され、企業側が損害賠償を命じられた事例では、「長時間労働を把握していながら放置した」「産業医の意見を無視した」ことが、企業の落ち度とされました。
つまり、単に制度を整えるだけでなく、「実際に現場で健康配慮がなされているか」が問われる時代に来ているのです。
義務違反がもたらすリスクとペナルティ
企業が健康管理義務を怠った場合、次のようなリスクに直面します。
- 労災認定による企業名の公表
- 損害賠償請求(民事)や刑事責任の追及
- 企業イメージの毀損・炎上リスク
- 離職・採用難・株主対応など経営への波及
これらのリスクは、規模を問わずすべての企業が直面しうるものです。つまり、健康管理は「義務であり、経営リスク対策でもある」という視点で捉える必要があります。
実務で問われる!健康管理の具体的対応とは
健康診断の実施・就業制限の留意点
まず基本となるのが、年1回以上の定期健康診断の実施です。これは労働安全衛生法第66条に基づく義務であり、実施だけでなく、医師の意見聴取・就業判定・本人への結果通知・有所見者へのフォローアップまで含まれます。
特に注意が必要なのが、「健康診断結果によって就業制限を勧められた場合」の対応です。企業側には、対象者に対する配置転換や就業時間の調整など、健康を守る配慮義務が生じます。
メンタルヘルス対策の必要性と厚労省の指針
精神疾患に関する労災請求は増加傾向にあり、メンタルヘルス対策の整備は急務です。厚生労働省は「職場における心の健康づくり指針(通称:4つのケア)」を策定し、一次予防から復職支援までの対応を推奨しています。
- セルフケア
- ラインによるケア(管理職の関与)
- 事業場内産業保健スタッフによるケア
- 事業場外資源によるケア(外部カウンセラー等)
企業としては、ストレスチェックの結果分析だけでなく、職場改善アクションや管理職への研修・相談体制の充実が必要です。
出典:厚生労働省「職場における心の健康づくり」
ハラスメントや長時間労働への予防策
健康被害の大きな要因となるのが、ハラスメントと長時間労働です。パワハラ対策は、2022年4月から全企業に義務化され、相談体制の整備、研修の実施、再発防止措置などが求められます。
また、長時間労働についても、36協定(サブロク協定)(※)の遵守、勤怠管理の徹底、長時間労働者への医師面談など、実効性のある予防策が必要です。
※36協定(サブロク協定)とは、労働基準法第36条に基づいて、会社が従業員に法定労働時間(原則1日8時間、週40時間)を超える時間外労働や休日労働をさせる場合に、会社と従業員の間で締結する協定のこと
健康管理義務と健康経営の違いと接点
義務:最低限のライン/経営:能動的な投資
健康管理の「義務」とは、法令遵守のための最低ラインです。これに対し、「健康経営」は企業自らが主体的に取り組む投資活動であり、未来の人的資本価値を高める戦略です。
義務はリスク回避が目的、経営は成果創出が目的。この違いを理解したうえで両者を位置づけ直すことが、実効性のある健康支援の第一歩となります。
両立させることで得られる企業メリット
義務対応を土台に、健康経営の視点で施策を広げていくことで、次のようなメリットが生まれます。
- 従業員の生産性向上・離職防止
- 組織エンゲージメントや心理的安全性の向上
- 採用・ブランド価値の強化
- 健康起因の損失(プレゼンティーズムなど)の削減
単なる「リスク管理」にとどまらず、「組織の価値創出」へつなげる視点が、企業には求められています。
健康経営優良法人認定が示す「信用力」
経済産業省と日本健康会議が推進する「健康経営優良法人認定制度」は、健康経営の取り組みを可視化する制度です。2023年度の認定企業数は約15,000社に達し、今や企業評価の基準の一つとなっています。
この認定を取得することで、採用力や金融優遇、取引先からの信頼向上など、多面的な価値が得られます。義務対応から一歩踏み出した取り組みとして、検討する価値は大きいでしょう。
リスク回避だけじゃない!従業員の行動変容を支援するWellWaとは
WellWaとは:健康と「人とのつながり」を同時に育てる仕組み
WellWa(ウェルワ)は、キリンビバレッジが提供する法人向けの健康支援サービスです。単なる健康記録アプリではなく、チーム単位での参加、スタンプ機能、部署対抗イベントなどを通じて、従業員の行動変容と組織の一体感づくりを同時に実現する点が特長です。
法的対応を超えた「職場のウェルビーイング文化」づくり
WellWaは、健康診断やストレスチェックといった法令対応を超えて、「楽しみながら続けられる」仕組みで健康文化を育てることを目的としています。
- 毎日届く健康ミッションで生活習慣を改善
- 部署単位でのランキングでチーム意識を醸成
- 健康行動に応じてポイントが貯まり、福利厚生に還元
このように、健康管理を「自分ごと化」し、かつ「組織文化として定着」させることが、WellWaの真価といえるでしょう。
プレゼンティーズムやエンゲージメント改善の効果
WellWaを通じて従業員の健康習慣が改善されることで、生産性やエンゲージメントの向上といった効果が報告されています。また、会話量やメンタルスコアが改善されたことで、職場の風通し改善にもつながったという声が多数寄せられています。
出典:WellWa公式サイト
まとめ:「守り」と「攻め」の両輪で、持続可能な職場づくりを
健康管理は、法令対応という「守り」と、健康経営という「攻め」の両輪で進めることが求められています。法的義務を果たすだけでは、リスクは防げても成果は生まれません。一方で、制度を整えるだけでも、現場に行動が根づかなければ効果は出ません。だからこそ、「制度」と「文化」、「仕組み」と「体験」を両立させる視点が重要です。WellWaのようなツールを活用することで、健康への気づきを日常に浸透させ、従業員一人ひとりの行動変容を促す環境づくりが実現できます。今こそ、「義務を果たす」から「価値を生む」健康管理へ。企業の未来を守り、育てるための一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。