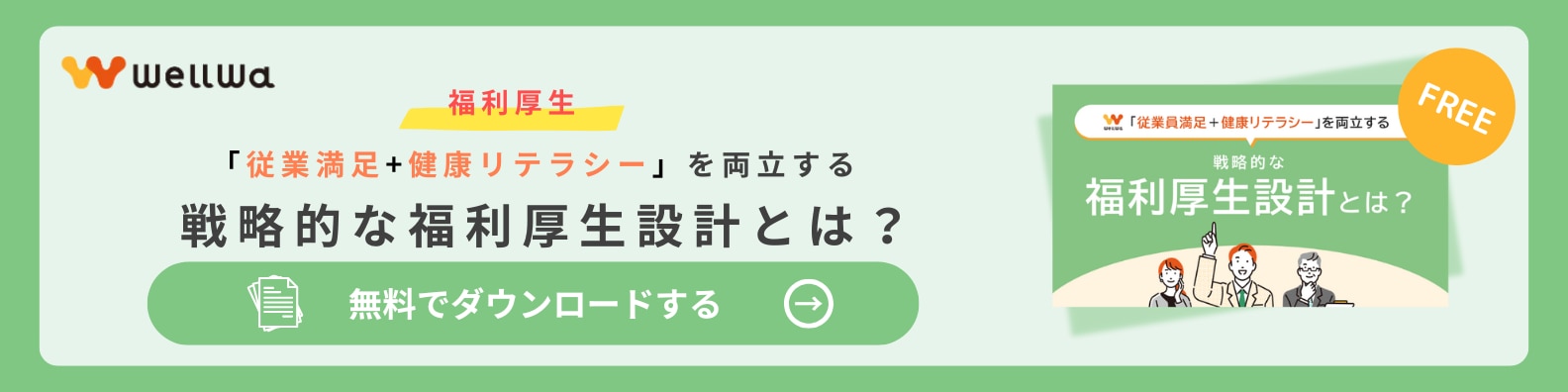なぜ今「健康意識の高まり」が?企業が知るべき背景と対応
働き方や生活様式が大きく変わる中で、健康に対する人々の意識がかつてないほど高まっています。この「健康意識の高まり」は、企業の人財戦略や福利厚生施策にどのような影響を与えるのでしょうか。すべての従業員が同じように意識を高めているわけではないとすれば、その温度差をどう捉え、対応すべきなのでしょうか。
本記事では、社会全体の価値観変化から、職場での健康意識の実態、施策設計に必要な視点まで、企業の健康経営担当者が押さえておくべき知識を整理してお伝えします。
目次[非表示]
健康意識の高まり──いま、社会で何が起きているのか
新型コロナ以降の価値観変化と「健康」への再注目
新型コロナウイルスの世界的流行は、私たちの生活と価値観に大きな変化をもたらしました。とりわけ「健康」に対する意識は、これまでとは比較にならないほど社会全体で高まっています。
在宅勤務や外出制限が続いた中で、多くの人が運動不足や孤独感、ストレスに直面し、心身のバランスがいかに重要かを実感しました。また、感染予防行動やワクチン接種といった日常的な選択を通じて、「自分の健康は自分で守る」という自律的な意識も育まれました。
こうした変化は、コロナ収束後の現在も続いています。食事・睡眠・運動への関心はもちろん、メンタルヘルスやウェルビーイングといった視点でも、個人の行動や消費の基準に「健康」が組み込まれつつあるのです。
Z世代・ミレニアル世代の健康志向の特徴
特に注目されているのが、Z世代・ミレニアル世代といったデジタルネイティブ世代の健康意識の変化です。彼らは単なる身体的健康だけでなく、「心の充足」「人生の質(QOL)」を重視する傾向が強く、ウェルビーイングやサステナブルな生活習慣にも高い関心を寄せています。
具体的には、加工食品よりもオーガニック食品、飲み会よりもヘルシーなカフェ、長時間労働よりもライフワークバランスを優先するといった行動傾向がその表れです。また、スマートウォッチや健康アプリを活用して、日々のコンディションを「見える化」することにも積極的です。
こうした世代に支持される企業になるためには、健康に関する施策も「義務的」ではなく、「共感」や「自分ごと感」を引き出せる設計が求められています。
健康が「個人の課題」から「社会全体のテーマ」へ
かつては「健康=自己責任」という認識が一般的でしたが、近年ではそれが大きく変化しています。健康格差、メンタルヘルス問題、生活習慣病の増加といった課題が顕在化する中で、「健康は社会全体で支えるべきテーマ」として捉えられるようになってきました。
政府が推進する「健康日本21」や、経済産業省の「健康経営」の普及施策、SDGsの中の「すべての人に健康と福祉を(Goal3)」といった国際的な動きも、こうした価値観の変化を後押ししています。
参考:厚生労働省「健康日本21(第三次)」
このような潮流を踏まえると、企業が従業員の健康に取り組むことは、「人財への投資」であると同時に、「社会的責任(CSR)」や「企業の信頼性(ブランディング)」にもつながると言えるでしょう。
データで見る健康意識の変化と従業員の実態
内閣府・厚労省などの調査結果に見る意識変化
実際の調査データからも、健康に対する関心の高まりは明確に表れています。
たとえば内閣府が実施した「国民の健康意識調査(2023年)」では、約7割の回答者が「コロナ禍を経て健康に対する意識が高まった」と回答。特に20〜40代の若年・中堅層では、「メンタルヘルスへの関心」「栄養バランスを意識するようになった」「運動不足を自覚している」といった項目が顕著に増加しています。
また、厚生労働省の「労働安全衛生調査」でも、ストレスチェックの受検率や、健康に関する相談ニーズの高まりが報告されています。これは企業が従業員支援の選択肢を増やし、きめ細かな対応が求められていることを示しています。
出典:厚生労働省「令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)の概況」
健康に関する関心の二極化と「無関心層」の存在
一方で、すべての従業員が健康に積極的なわけではありません。実は、健康に強く関心を持つ層と、ほとんど無関心な層との「二極化」が進んでいるという指摘もあります。
これは、健康意識が高い層にとっては自発的に取り組める内容でも、無関心層には「押しつけ」に感じられてしまうリスクがあるということです。企業の健康施策が全社に行き渡らない原因の一つは、こうした温度差の見落としにあります。
施策設計においては、「無関心層をどう巻き込むか」「楽しさ・共感・報酬といった要素で自然な行動を引き出せるか」が重要な視点となります。
なぜ企業が「健康意識の高まり」に対応すべきなのか
エンゲージメント・生産性・離職率との相関関係
従業員の健康状態は、企業の成果に直結します。体調が安定している人ほど仕事への集中力が高まり、協調性も生まれやすくなります。逆に、健康不安を抱えたまま働き続けると、パフォーマンスが低下し、離職リスクも高まる傾向があります。
実際に、経済産業省が推進する「健康経営」の枠組みでは、エンゲージメントスコア、プレゼンティーズム(出勤しているが体調不良で生産性が低下している状態)、離職率といった指標との相関が示されています。
企業が従業員の健康意識を支援することは、単なる福利厚生にとどまらず、経営課題へのアプローチでもあるのです。
健康経営の実践が「選ばれる会社」への道となる
採用難が続く現在、企業選びの基準は「給与や勤務地」だけではありません。若年層を中心に、「働きやすさ」や「心身の健康への配慮」が重視されており、健康経営への取り組みは企業の信頼性を左右する要素となっています。
健康経営優良法人に認定された企業は、求職者からの注目度が高まり、取引先からの評価向上、資金調達条件の優遇といった副次的な効果も得られます。健康意識の高まりに企業が対応することは、「選ばれる会社」になるための投資でもあるのです。
健康意識を「行動変容」につなげる施策のヒント
続かない理由は「仕組み」と「共感」の欠如
健康意識が高まっても、行動が続かない――その理由は、意志の問題ではなく、「仕組み」と「共感」が不足しているからです。
「運動を習慣化したい」と思っても、何をどれだけすればいいかが明確でなかったり、誰からも応援されない状況では、継続は難しくなります。つまり、健康行動の意味づけと応援の仕組みが重要なのです。
社員の習慣を変えるには「コミュニケーション」がカギ
職場で健康行動が定着するかどうかは、対話と共感の量に大きく左右されます。
例えば、上司が「最近よく歩いてるね」と声をかけたり、同僚同士でスタンプを送り合ったりするだけでも、社員は「見られている」「応援されている」と感じ、前向きに行動を続けやすくなります。
このように、コミュニケーションを仕組みに落とし込むことが、行動変容の起爆剤となります。
ゲーミフィケーションや仲間意識を活かすアプローチ
人は楽しさや一体感があると、自然と動きたくなるもの。だからこそ、健康施策にはゲーム性や仲間とのつながりを意識的に取り入れるべきです。
部署ごとの歩数ランキングや、睡眠改善チャレンジのチーム対抗イベントなどは、健康に関心がなかった層も巻き込む効果があります。
ただし、競争に偏りすぎないゆるく続けられる設計にすることが、長期的な定着には欠かせません。
共感・習慣・コミュニケーションを支援するWellWaの可能性
WellWaとは?つながりから健康行動を促す仕掛け
WellWa(ウェルワ)は、キリンビバレッジが提供する法人向けの健康支援サービスです。「たのしい健康」「おいしい健康」「健康のROI」という3つの要素を軸に、従業員の行動変容と組織のエンゲージメント向上を支援します。
特に注目すべきは、つながりを通じて自然と健康行動が促進される設計です。スタンプの送り合いやチームランキングなど、日常的なコミュニケーションを通じて「応援し合う文化」が職場に根づきます。
チャレ活・デイリーミッションで「無関心層」にも届く理由
WellWaでは、日替わりで配信される「デイリーミッション」や、1ヶ月間の「チャレ活(チャレンジ活動)」を通じて、健康行動のきっかけを提供しています。
これらは、短時間・低ハードルで参加できる設計になっており、「健康に関心はなかったが、やってみたら意外と楽しい」と感じる無関心層へのアプローチとして効果的です。
また、ポイント制度と組み合わせて行動を可視化・報酬化することで、楽しさと達成感を両立させています。
数値で示せる効果と、エンゲージメントへの好影響
WellWaは、25問の簡易サーベイ機能を通じて、健康習慣とプレゼンティーズム・エンゲージメントとの相関を数値で可視化できる点も強みです。
キリングループでは、従業員が4つの生活習慣(食事・運動・睡眠・飲酒)の内の1つを改善するだけで、年間19.6万円/人の試算価値に換算できることを統計的に確認しており、施策の効果を社内外に説明するエビデンスとして活用できます。
健康意識を行動に変え、行動を成果へと導くWellWaは、まさに企業にとっての実践的なパートナーといえるでしょう。
まとめ
健康意識の高まりは、社会の流れであると同時に、企業にとっての好機でもあります。従業員の気づきや意欲を、組織の成果につなげるためには、「行動変容を支援する仕組みづくり」が不可欠です。その鍵となるのが、共感・習慣・コミュニケーション。WellWaのようなツールを活用し、健康施策を制度ではなく文化として根づかせることで、企業は持続的な成長と信頼性を両立できるはずです。今こそ、健康を新たな企業資産として捉え、未来に向けた投資を始めましょう。