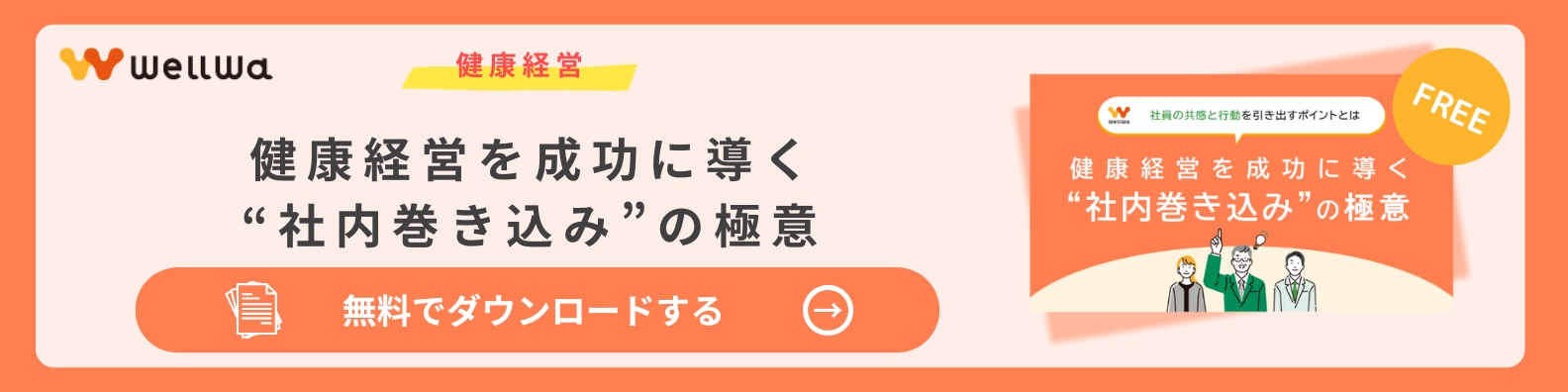健康経営を社内に浸透させる「巻き込み力」|経営層・従業員を動かす3つの仕掛け
健康経営を社内に浸透させる鍵は、「制度」ではなく人を動かす巻き込み力です。本記事では経営層・管理職・従業員を動かすための3つの仕掛けを解説します。孤立型の推進から脱却し、全社一丸となって健康経営を文化として根付かせるための実践ノウハウを、WellWaの活用事例も交えて紹介します。
なぜ健康経営は「巻き込み」が鍵になるのか?
健康経営の成功は組織の動きで決まる
健康経営とは、単に従業員の健康を守る制度を整えることではありません。組織全体の健康意識を高め、業務の質や成果につなげていく「経営戦略」として位置づけられるものです。
しかし実際の現場では、「健康施策は人事や総務の担当でしょ」と受け取られがちで、なかなか全社的な取り組みへと広がらないケースも少なくありません。制度やツールだけを用意しても、組織の行動が伴わなければ、健康経営は根付かないからです。
そのため、健康経営の実行力を高めるうえで最も重要なのは、「誰をどう巻き込むか」を考え抜くこと。つまり、経営層・管理職・一般社員がそれぞれの役割を持ち、自発的に動くための設計が求められます。
担当者1人で進めるには限界がある理由
健康経営を推進する担当者の多くが直面するのが、「施策を打っても反応が薄い」「取り組みが一部の部署で止まっている」といった浸透の壁です。その要因は、多くの場合、巻き込みが不十分で孤立型推進になってしまっていることにあります。
実際、健康施策は制度構築、運用、広報、評価と多岐にわたるため、1人の担当者で動かせる領域にはどうしても限界があります。さらに、健康はプライベートに踏み込みやすいテーマでもあるため、一律のアプローチでは反発や無関心を招きやすいという難しさも伴います。
このような背景からも、部署や階層を超えて連携を生み出す「巻き込みの仕組み」こそが、健康経営を本質的に成功へ導く鍵なのです。
経営層を動かすために必要な3つの視点
投資対効果(ROI)と人的資本開示へのつながりを示す
経営層を巻き込むためには、「健康経営が経営上のメリットに直結する」ことを具体的に示すことが重要です。例を挙げると、
- プレゼンティーズム改善による生産性の向上
- メンタル不調の減少による医療費抑制
- 健康リテラシー向上によるエンゲージメントの向上
といった明確な投資対効果(ROI)を提示することで、健康経営が単なる福利厚生ではないことが伝わります。
また、2023年度以降、上場企業では人的資本の開示義務が広がっており、健康関連指標(欠勤率、ストレスチェック結果、ワークエンゲージメントスコアなど)は注目される情報項目になっています。
こうした時流を踏まえ、「健康経営は投資家へのアピールにもつながる」ことを訴求すれば、経営層の関心を確実に高めることができます。
データで語る:WellWaのサーベイを活用
抽象的な価値ではなく、「数字で語る」ことが経営層への説得には不可欠です。そこで有効なのが、健康行動の可視化とレポート出力が可能なWellWaのサーベイです。
一例を挙げれば、以下のようなデータを定期的に報告することで、健康経営の進捗と成果を共有できます。
- 生産性に関わる健康スコア
- 部署別の健康習慣(歩数・睡眠・飲酒など)
- 健康への関心度や健康リテラシー
- コミュニケーション量やメンタルヘルススコア
これにより、経営層は施策が現場でどう受け入れられているかをリアルに把握でき、次の投資判断や制度改定の根拠として活用することが可能になります。
経営課題とリンクさせたストーリーテリングの重要性
数字の裏にある「人の変化」や「現場の声」も、経営層を動かすうえで非常に大きな力を持っています。
- 「離職を考えていた社員が健康支援を通じて職場に定着した」
- 「健康イベントがきっかけで職場の雰囲気が良くなった」
といったストーリーは、企業の温度感のある成果として心に響きやすいものです。
また、企業が抱える課題(人材確保、組織風土改革、生産性向上など)と健康施策の成果を結びつけた語り方ができれば、健康経営が「本業への貢献」であることが明確に伝わります。
現場の理解・協力を得るための仕掛けづくり
わかりやすさと参加しやすさを両立させる設計
健康経営を社内に浸透させるためには、複雑な制度や指示ではなく、誰でもすぐに「参加できる・理解できる」設計が求められます。特に現場の従業員にとっては、業務と無関係に感じられる施策は敬遠されやすいため、次のような工夫が有効です。
- 施策の目的と意義を明文化し、伝え方を工夫する(例:「疲労軽減のために今月は睡眠強化月間です」)
- 1日1アクションなど、ハードルの低いタスクから始める
- スマホで完結するなど、日常行動と自然に連動できる仕組みを整える
このように、「何を」「なぜ」やるのかを直感的に理解できる仕掛けを設けることで、現場の納得感と参加意欲が一気に高まります。
ポイント制度やチャレンジ企画で楽しさを演出
行動の継続には、「楽しさ」や「ちょっとした達成感」が必要不可欠です。そこで効果を発揮するのが、ポイント制度や社内チャレンジ企画といった、ゲーミフィケーション要素の導入です。
- 1日〇歩達成でポイント付与
- 朝活参加でスタンプ獲得
- チーム対抗で月間歩数レース
など、楽しみながら健康になれる仕掛けを導入することで、従業員の自発性を引き出すことができます。
さらに、ポイントが社内の特典や商品と交換できる仕組みを設ければ、「やってよかった」と実感できる満足感にもつながります。
家族巻き込み・部署対抗など仲間との連動で継続率UP
健康行動は1人ではなかなか継続しづらいものですが、「誰かと一緒に取り組む」だけで、その難しさは大きく和らぎます。そこで注目されているのが、家族や部署を巻き込んだ「連動型の仕掛け」です。
例えば、
- 家族と一緒に行う健康ミッション(例:食事記録、早寝チャレンジ)
- 部署対抗のランキングイベント
- 上司と部下のペアミッション
といった仕組みを設けることで、職場や家庭に「応援し合う文化」が生まれ、施策の継続率と定着率が大きく向上します。
WellWaが実現する全社巻き込み型健康経営の支援機能
健康サーベイで経営・管理職への報告が簡単に
WellWaでは、従業員の健康スコアをサーベイを用いて可視化できるため、経営層や管理職への報告もデータを元にして行えます。
- 部署別や性年代別の傾向
- 経年比較や他社比較
などをレポートとして出力できるため、「どの施策が成果につながっているか」を見える化し、次の施策設計にも活用可能です。
チーム対抗イベントで部署横断的なつながりを創出
WellWaのイベント機能は、部署や年齢を超えた横のつながりを創出する仕掛けとして活用できます。
- 部署別ランキング
- テーマ別のエントリー型イベント(例:「適正飲酒チャレンジ」)
といった企画を通じて、健康施策が共通体験となり、企業文化としての定着が加速します。
社内に健康経営を定着させるステップと継続の工夫
スモールスタート→PDCA型展開のプロセスを設計
すべてを一度に始めようとすると、現場の負担や混乱が生じやすくなります。そのため、健康経営の施策は「まずは1テーマ、1部署から」始めるスモールスタートが基本です。
- 小規模なイベントで効果測定
- 結果を元に改善
- 成功事例を横展開
というPDCAサイクルを前提とした設計が、長期的な定着と社内の合意形成につながります。
成果の見える化と社内広報で成功事例を共有
取り組みの効果が見えることは、参加者のモチベーションを高める大きな要因です。社内報やイントラネット、朝礼などを活用し、
- イベント参加率
- 健康改善の声
- 参加者インタビュー
といった内容を継続的に発信していくことで、成功体験が組織全体の意識改革を促します。
Wellwaアプリはお知らせやプッシュ通知機能を備えているため、健康経営担当者の発信業務の負担軽減にも貢献します。
まとめ
健康経営を動かすのに必要なのは、説得力のある資料よりも共感を生む仕掛けです。共に楽しみ、成果を分かち合える体験こそが、人を動かす本質的なエネルギーになります。
組織を巻き込む健康経営においては
- データで経営を説得
- ストーリーで現場に共感を促す
- ツールで実行と改善を支援
という三位一体の構造が不可欠です。あなた自身がその旗振り役となり、社内の一人ひとりが自ら健康に向き合う仕組みをつくっていきましょう。健康経営は、「やらされるもの」ではなく、「みんなで育てていく文化」です。