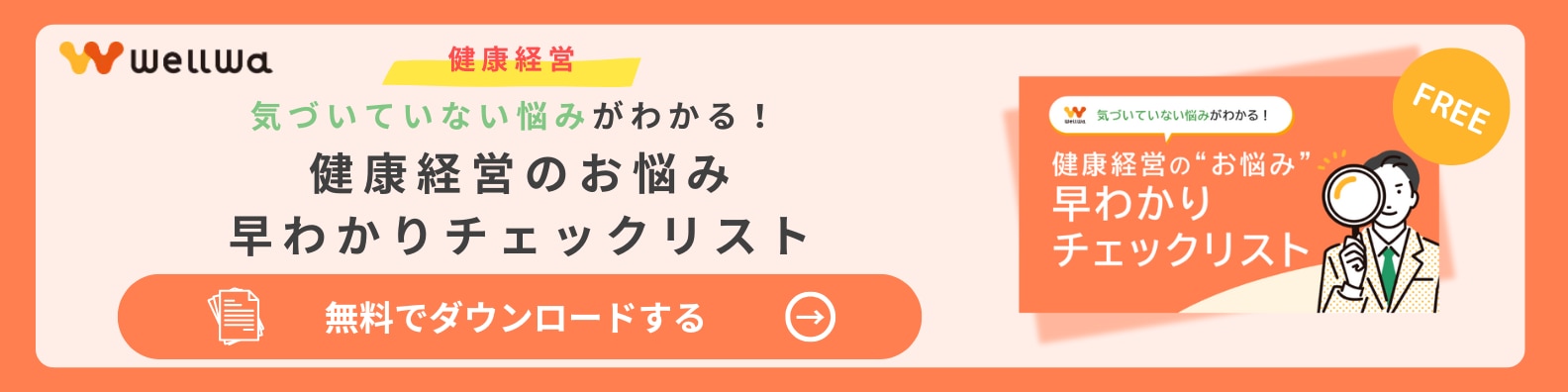なぜ今、健康経営に女性特有の健康課題が求められるのか?―企業価値を高める新たな視点と実践法
健康経営の重要テーマとして「女性特有の健康課題」への対応が、いま企業価値向上のカギを握っています。
本記事では、月経・PMS、妊娠・出産・不妊治療、更年期、メンタルヘルスなどライフステージごとの課題に対し、制度設計・風土改革・データ活用で支援する方法を解説。経済産業省の健康経営度調査票や認定制度の評価項目にも対応した最新の実践ポイントを紹介します。
「女性の健康支援」が健康経営に求められている理由
女性活躍推進と人的資本経営の時代背景
女性の活躍推進は、もはや人事制度の一部ではなく、企業の持続可能性を支える中核的な経営課題となっています。近年では、人的資本経営の観点から「多様性への配慮」と「働きやすさの設計」が重視されており、その中でも女性特有の健康課題への対応が欠かせないテーマとなっています。
事実、出産や更年期といった女性のライフイベントにおける体調変化や就業継続の困難さは、キャリア形成やエンゲージメントにも直結しています。こうした変化に企業が無関心であれば、優秀な人財の流出リスクを高め、結果として組織の生産性や競争力に悪影響を及ぼします。
いま企業に求められているのは、「働き続けられる環境を整備すること」と「それを公正かつ戦略的に伝えること」です。健康経営を通じて、女性の健康支援が個別配慮ではなく、「組織全体の成長戦略」として位置づけられる時代が到来しているのです。
経済産業省も注目する「女性の健康と企業の生産性」の関係
経済産業省は、2023年以降の「健康経営推進検討会」において、女性の健康と企業の持続的成長の関係性を明確に打ち出しています。女性特有の症状によるプレゼンティーズム(出勤しているがパフォーマンスが低下している状態)や、メンタルヘルス不調による早期離職は、企業全体の生産性や人的資本ROIに直結する課題とされています。
さらに、健康経営を推進する上での「人的資本の情報開示」や「ESG経営」においても、女性の健康支援は見える化されるべき経営指標”の一つとして注目を集めています。
出典:経済産業省「女性の健康と企業の生産性」資料
健康経営度調査票にも反映される女性特有の課題項目とは
2025年版(令和7年度)以降の「健康経営度調査票」でも、女性の健康支援に関する項目はより重要性を増しています。実際に、「女性特有の健康課題に対する配慮があるか」「プレコンセプションケアに関する啓発が行われているか」など、制度・教育・周知の3側面で問われる設問が明記されており、認定要件としての存在感が増しています。
この流れを受けて、健康経営優良法人認定を目指す企業は、女性の健康支援を単なる福利厚生の範囲にとどめず、制度設計・データ管理・情報発信の三位一体で取り組む姿勢が求められます。
妊娠・出産・更年期といったライフステージごとに異なる課題を捉え、継続的に見直しながら支援の精度を高めることも、企業価値向上につながる施策となります。
女性特有の健康課題とは?企業が把握すべき4つのテーマ
月経・PMSへの配慮が職場定着率を左右する
月経痛やPMS(月経前症候群)は、症状の重さに個人差があるにもかかわらず、職場では「我慢するもの」として扱われがちです。しかし実際には、体調不良により業務効率が著しく低下したり、欠勤が続くケースも珍しくありません。
そのため、健康経営の一環としては「生理休暇の取得率を上げること」だけでなく、事前の相談体制の整備やテレワーク・時差出勤など柔軟な勤務制度との併用が必要です。
加えて、男性管理職への理解促進や、月経に関する情報を社内に周知するなど、社内風土そのものを整える取り組みも定着率の向上に寄与します。
妊娠・出産・不妊治療支援とキャリアの両立支援
妊娠・出産は、女性の健康にとって最もセンシティブなライフイベントの一つです。近年では、不妊治療を受けながら働く社員も増加傾向にあり、その実態を把握した上での制度設計が不可欠です。
一例を挙げると、柔軟な勤務体系、治療のための通院休暇、有給取得の運用変更などは、身体的・精神的な負担を軽減し、離職のリスクを抑えるポイントになります。
「職場復帰後のキャリア支援」や「社内メンター制度の導入」など、妊娠・出産とキャリアを両立できる人事設計が評価される流れが加速しています。制度整備だけでなく、上司や同僚とのコミュニケーション支援も必須でしょう。
更年期の症状がパフォーマンスに与える影響
40代後半から50代にかけて訪れる更年期には、ホルモンバランスの急激な変化により、発汗、動悸、不眠、イライラ、うつ傾向などの不調が生じやすくなります。これらの症状は仕事のパフォーマンスや人間関係に大きな影響を与えるにもかかわらず、職場では見過ごされがちです。
更年期の知識を企業側が共有し、相談できる窓口やメンタルケア支援を用意することは、女性の中長期的な活躍に欠かせません。
メンタルヘルス・ジェンダーギャップの視点も重要に
女性はライフステージごとに複数の役割を担うことが多く、キャリア・家庭・介護といったマルチロールが心身の負荷を高めやすい傾向にあります。加えて、昇進や発言の機会におけるジェンダーギャップの存在が、自己効力感やモチベーションを低下させる要因にもなりえます。
企業としては、メンタルヘルス支援を性別・年齢に応じて多様化させるとともに、ジェンダーにとらわれない公平なキャリア支援策の整備が必要です。
女性の健康課題に向き合うことで得られる組織メリット
生産性・エンゲージメント・プレゼンティーズムの改善
女性特有の健康課題に対する適切な支援は、組織全体のパフォーマンス向上に直結します。月経痛や更年期症状、不妊治療などによって集中力や身体的パフォーマンスが低下した状態(プレゼンティーズム)は、放置すれば全体の生産性を著しく損なう要因となります。
一方、企業がそうした体調変化や働きにくさに配慮し、柔軟な制度や相談体制を整えることで、従業員の安心感や信頼が高まり、エンゲージメントの向上にもつながることが、各種調査からも明らかになっています。
つまり、「働きやすさ」は直接的なKPIには見えにくくとも、持続的な成果を生む土台として無視できない投資先なのです。
離職防止とリーダー層の育成基盤強化
妊娠や更年期を機に退職を選択する女性は、現在も一定数存在します。多くは体調や通院との両立困難、職場理解の欠如といった要因に起因しており、制度が整っていないことが離職の引き金になるケースが少なくありません。
しかし、こうしたタイミングでの離職は、企業にとっても大きな損失です。なぜなら、出産や更年期の時期にある女性社員は、専門性や経験を積んだ貴重な戦力であり、リーダー層候補であることが多いためです。
適切な支援制度やキャリア継続の道筋を提示できれば、離職を未然に防ぎ、将来の管理職候補を組織内に確保することにもつながります。
健康経営優良法人認定や企業イメージ向上への寄与
女性の健康支援は、外部評価の向上にも影響を与えます。特に経済産業省が主導する「健康経営優良法人認定」では、女性の健康課題への対応が評価項目として明記されており、積極的な支援姿勢が認定取得の後押しとなるのは間違いありません。
さらに、採用市場においても「女性に優しい企業」であることは大きな差別化要素となり、企業ブランディングや社会的信用の向上にも貢献します。女性の健康支援は個別対応ではなく、企業価値を高める戦略的施策なのです。
出典:経済産業省「健康経営における女性の健康の取り組みについて」
女性の健康支援を職場にどう組み込むか?
まずは実態把握から:サーベイ・データで見える化を
施策の第一歩は「知ること」です。女性特有の健康課題は目に見えにくく、表面化しづらいため、まずは社内アンケートやヒアリングを通じた実態の見える化が欠かせません。
「何がつらいのか」「どんな支援があれば助かるのか」といった声を定量・定性の両面から収集することで、ニーズと優先課題が明確化され、施策の的確な打ち手を検討できるようになります。
雑談や共感のきっかけづくり
制度を整えても、実際に使われなければ意味がありません。そのためには、日常的に雑談や共感を通じて健康の話題をタブー視しない空気を醸成することが大切です。
社内報で女性社員の体験談を特集したり、上司が自ら情報発信したりすることで、「声を上げてもいい職場」だという心理的安全性が生まれます。こうした共感の積み重ねが、制度の活用率にも大きく影響します。
プレコンセプションケアへの意識付け
「妊娠の前から自分の健康を考える」というプレコンセプションケアの概念は、近年注目を集めています。企業にできることは、この考え方を社内で啓発し、健康意識の底上げを図ることです。
具体的には、栄養・睡眠・婦人科検診などの情報提供や、専門家によるセミナー開催などが有効です。将来妊娠を希望している社員だけでなく、すべての男女に向けて健康意識を高める取り組みとして浸透させていくことが重要です。
女性の健康課題にアプローチするためのWellWa活用法
部署横断の健康アクションが共感と会話を生む
WellWa(ウェルワ)は、健康経営を日常に落とし込む実践ツールとして、女性の健康支援にも効果的です。中でも、「チャレ活」や「健康選手権」といったイベント機能を活用すれば、部署や年齢を超えたコミュニケーションが生まれやすくなります。
「今月のテーマは睡眠」「今週はリフレッシュ週間」といった形で、女性にとって取り組みやすいテーマを設定することで、「自分ごと」として行動するきっかけになります。
健康記録を共有したり、スタンプで応援し合う機能は、気軽なコミュニケーションや共感のきっかけにもなります。
女性社員の声を反映したミッション設計で当事者意識を醸成
WellWaでは、デイリーミッションやイベント内容をカスタマイズ可能な点も特長です。「野菜を一品増やす」「1日1回深呼吸」「月経日記をつける」といった、小さな行動に対してポイントが付与されるよう設定すれば、女性社員が自分の健康に向き合うきっかけが自然と生まれます。
さらに、ミッション案を社員から募集したり、表彰制度に社員の投票を取り入れることで、当事者意識と主体的な関わりが高まり、制度の定着にもつながるでしょう。
まとめ
女性の健康課題は、これまで個別の配慮として扱われてきましたが、いまや経営戦略の一環として真正面から取り組むべきテーマになっています。月経・妊娠・更年期・メンタルヘルスといったライフステージごとの支援を通じて、企業は生産性の向上、離職率の低下、リーダー育成、ブランディング強化といった多くの恩恵を得ることができます。
まずは現場の声に耳を傾け、データに基づいた施策を設計し、ツール(WellWaなど)を活用して日常の行動に落とし込む仕掛けづくりから始めてみてはいかがでしょうか。
「誰もが自分らしく働ける職場」は、企業の競争力を生む最大の資産です。