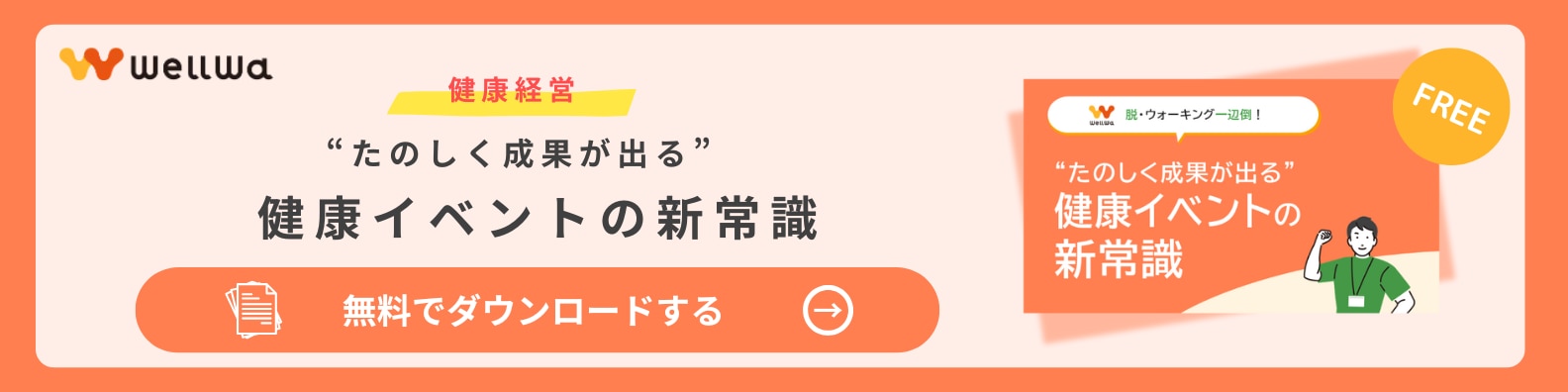在宅勤務による運動不足の影響と、企業ができる解消策
在宅勤務の普及により、通勤やオフィス移動といった日常的な運動機会が減り、多くのビジネスパーソンが深刻な運動不足に陥っています。長時間の座りっぱなしは、肩こり・腰痛・倦怠感といった身体の不調だけでなく、集中力低下やメンタル不調など、生産性や健康経営にも悪影響を及ぼします。本記事では、在宅勤務による運動不足の原因とリスク、企業が実践できる効果的な解消法、そして健康習慣を定着させる仕組みづくりまでをわかりやすく解説します。
なぜ在宅勤務で運動不足が進むのか
通勤・移動の機会が減る
在宅勤務は、通勤ラッシュから解放され、時間と体力に余裕ができる一方で、日常の無意識の運動機会が激減する環境でもあります。駅までの徒歩、オフィス内の移動、営業や打ち合わせでの外出など、出社時には自然に発生していた活動が、在宅勤務ではすべてゼロになってしまうのです。
その結果、1日あたりの歩数は出社時の半分以下に落ち込む人も多く、運動不足が慢性化する傾向が強まっています。こうした変化は自覚しにくく、知らず知らずのうちに健康リスクを高めているのが現状です。
長時間座位によるエネルギー消費の少なさ
在宅勤務では、朝から晩まで自宅の椅子に座ったまま、PC画面に向き合い続ける日が珍しくありません。会議も資料作成もすべてが画面上で完結するため、一日中ほとんど体を動かさないという状況が常態化しています。
長時間座り続けることで、血流の悪化や筋肉の硬直が進みやすくなります。特に、ふくらはぎや下半身の血行が滞り、むくみや倦怠感の原因にもなります。また、エネルギー消費量が極端に少ないため、摂取カロリーとのバランスが崩れやすく、体重増加や内臓脂肪の蓄積といった問題にも直結します。
「家の中だから大丈夫」という油断
在宅勤務には、服装も自由、時間も柔軟というメリットがありますが、それが健康管理に対する油断につながるケースも存在します。リラックスできる反面、姿勢が崩れやすかったり、ソファでの作業や床での長時間作業などが身体に負担を与えます。
さらに、「在宅だから少し体調が悪くてもそのまま作業できてしまう」ため、軽い不調が放置され、慢性化してしまうリスクも。目の疲れ、肩こり、腰痛、倦怠感といった初期症状があっても、無理をして仕事を続けてしまう……これが在宅勤務特有の隠れた健康問題の一因でもあります。
在宅勤務による運動不足がもたらす影響
肩こり・腰痛・倦怠感など身体への直接的影響
運動不足が続くことで、まず現れるのは身体への直接的な不調です。長時間同じ姿勢で作業を続ければ、肩や首、腰への負担が蓄積し、筋肉の緊張や関節のこわばりが慢性化します。特にデスクや椅子の高さが適切でない在宅環境では、身体にかかる負担はさらに大きくなります。
こうした身体の不調は、単に疲れとして済まされがちですが、実際には生産性や集中力を奪い、作業効率を大幅に低下させる要因になっています。
気分の落ち込み・集中力低下などメンタル面の悪化
身体だけでなく、メンタル面への影響も深刻です。運動不足になると、脳内のセロトニンやドーパミンといった神経伝達物質の分泌が減少し、気分の落ち込みや不安感、やる気の低下といった心理的な問題を引き起こしやすくなります。
また、在宅勤務では上司や同僚との日常的な雑談やフィードバックの機会が減り、孤立感が強まることでエンゲージメントの低下やストレスの蓄積にもつながります。メンタル不調は見えづらく、表面化したときには深刻な状況になっていることも少なくありません。
生産性・エンゲージメントの低下と企業への損失
身体の不調とメンタルの低下が重なることで、業務パフォーマンスの全体的な低下が避けられなくなります。集中力や判断力の低下、仕事への意欲の減退は、プレゼンティーズム(出勤しているが十分に働けない状態)やアブセンティーズム(欠勤)を引き起こす原因にもなります。
結果として、企業全体の生産性が落ちるだけでなく、離職リスクの上昇や採用・育成コストの増加といった間接的な損失が積み重なっていきます。在宅勤務の利点を活かしつつ、運動不足への対策を組織として講じることは、いまや企業の持続可能性にも関わる重要なテーマなのです。
在宅勤務下でもできる「簡単・続く」運動解消法
1日5分から始めるストレッチ・軽運動
在宅勤務中の運動不足対策は、「がっつりやる」ことではなく、「少しでも動く」ことから始めるのが現実的です。特におすすめなのが、デスク周りでできる肩回しや首のストレッチ、立ち上がってのスクワット、ふくらはぎの上下運動などの軽い動きです。これらは1日5分からでも血行促進や姿勢改善に効果があり、身体が軽くなるのを実感できるでしょう。
身体をほぐす時間を運動と意識するだけでも、行動へのハードルは大きく下がります。重要なのは、完璧を目指すのではなく、できる範囲で「続けること」です。
「ながら運動」でこまめに動く
仕事に集中している時間でも、ちょっとした工夫で身体を動かすことは可能です。たとえば、オンライン会議中に座りっぱなしにならないよう、足を軽く動かす・かかとを上げ下げする・背筋を伸ばすといった「ながら運動」は、意外と馬鹿にできない効果をもたらします。
また、スタンディングデスクを活用して定期的に立ち作業に切り替えるなど、姿勢を変えるだけでも疲労感や集中力に違いが出ます。こうした“こまめな身体刺激”の積み重ねが、日々の健康維持につながります。
日常に組み込んで習慣化
運動を習慣化するには、「時間の確保」よりも「生活の流れに組み込む」視点が大切です。朝の業務開始前にストレッチをする、昼休みに10分のウォーキングを入れる、夕方に1分だけその場で足踏みする、といった行動は、ルーティン化すれば自然に身についていきます。
さらに、記録や目標を可視化するとモチベーションの維持に役立ちます。日々の運動量や体調の変化をメモするだけでも、自分の変化に気づけるきっかけになります。習慣は「意識せずにやれること」になるまで継続することが鍵です。
WellWaで在宅勤務の健康習慣をサポート
歩数や運動記録を自動で可視化・スコア化
WellWa(ウェルワ)は、ユーザーが日々の健康行動を意識的に記録しなくても、自動で歩数などを記録し、スコアとして可視化できる機能を備えています。これにより、在宅勤務中の「見えにくい努力」や「小さな習慣」が明確になり、自分の健康行動を肯定的に捉えられるようになります。
また、スコアの変化が見えることで、「今日は少しでも体を動かしてみよう」という前向きな気持ちが自然と芽生えやすくなります。
自宅から参加できる「チャレ活」「健康選手権」
WellWaの「チャレ活」や「健康選手権」は、在宅勤務者でも自宅から気軽に参加できる健康増進イベントとして注目されています。チームや部署ごとの参加も可能で、離れていても仲間と目標を共有しながら取り組めるのが魅力です。
「朝ヨガ週間」「1日5,000歩チャレンジ」など、短期間で達成できるミッション形式のイベントは、ちょっと頑張ればできそうな達成感が習慣化を後押ししてくれます。
ポイント機能で運動が続く仕組みに変わる
運動行動の継続を後押しするため、WellWaでは行動スコアに応じてポイントが付与され、それをWellStoreで商品やサービスに交換できる仕組みも提供しています。この「見返りがある」という体験は、特に在宅勤務中の孤独な健康管理に対して、大きなモチベーションとなります。
在宅勤務者を対象にした運動促進施策の設計ポイント
時間・空間制約を考慮した短時間プログラム導入
在宅勤務者向けの施策では、「忙しくてもできる」「狭いスペースでもOK」という条件が不可欠です。朝礼での1分ストレッチや、業務前のラジオ体操動画配信など、取り組みやすく、継続しやすい設計が求められます。
従業員が生活の中に自然と溶け込ませられる運動を提供することで、強制感なく、健康意識の底上げが可能になります。
チーム・部署単位での参加企画でモチベーションアップ
在宅勤務では、組織への帰属感やモチベーションの低下が課題になりがちです。そこで効果的なのが、チーム対抗の運動イベントや、部署ごとのランキング制度などを取り入れた参加型の企画です。
一人で取り組むのではなく、仲間と一緒に取り組むことで、自然と声をかけ合ったり、励まし合ったりといった社内コミュニケーションの活性化も期待できます。
WellWaを使った行動ログ分析とレポートでPDCAを回す
施策の実効性を高めるには、導入して終わりではなく、「継続できているか」「効果が出ているか」を見える化し、改善を繰り返すことが不可欠です。WellWaでは、個人・部署ごとの行動ログや参加状況を分析し、レポートとして出力する機能があります。
これにより、管理職や経営層への報告もスムーズになり、PDCAサイクルに基づいた戦略的な健康経営の推進が可能になります。
まとめ
在宅勤務の普及とともに、運動不足という新たな課題が浮き彫りになっています。企業としては、従業員が無理なく、楽しく、そして続けられる運動習慣を支援することが求められています。生活環境の中に自然と運動を組み込む工夫と、それを支える仕組みづくりこそが、健康経営の真価を発揮する場面です。
WellWaのようなツールを活用すれば、自宅でもチームでも連携しながら、心と体の健康を育む風土が育ちます。これからの時代の健康経営にふさわしい在宅勤務施策を、一歩ずつ実践していきましょう。