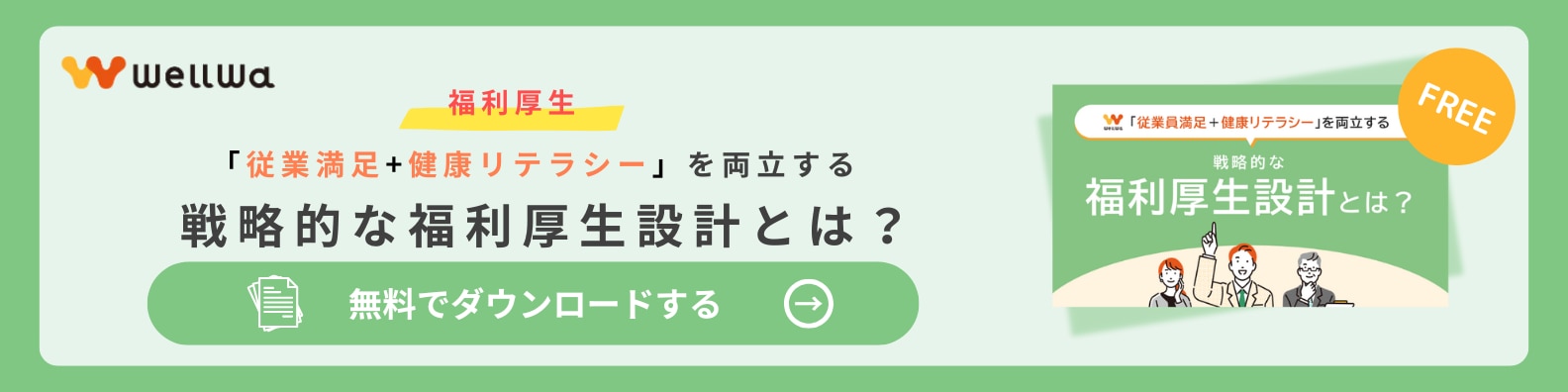社員の健康を守る福利厚生事例|食事改善と運動習慣促進の施策
現代の企業経営において、社員の健康は生産性や組織力を高める重要な資産となっています。健康経営を掲げる企業が増える中で、食事改善や運動習慣の定着を支援する福利厚生制度への注目が高まっています。本記事では、実際の事例を交えながら、社員の健康を守るための具体的な施策とその効果について解説します。
目次[非表示]
- 1.健康支援型福利厚生が注目される背景
- 2.食事改善を促進する福利厚生事例
- 2.1.健康的な社員食堂・カフェの設置
- 2.2.栄養セミナーや健康講座の実施
- 2.3.健康的なスナックや飲料の提供
- 2.4.食習慣改善のためのデジタルサポート
- 3.運動習慣を促進する福利厚生事例
- 3.1.社内フィットネス施設の設置とジム利用補助
- 3.2.運動イベントや社員向けチャレンジの開催
- 3.3.柔軟な勤務形態による運動時間の確保
- 3.4.ウェアラブルデバイスやアプリの提供
- 4.健康支援型福利厚生がもたらす効果
- 4.1.従業員のエンゲージメント向上
- 4.2.生産性向上と医療コスト削減
- 4.3.採用活動と企業ブランディングへの効果
- 5.健康支援型福利厚生の導入ポイント
- 5.1.企業規模や予算に応じた施策の選定方法
- 5.2.社員ニーズの把握と反映
- 5.3.継続的な効果測定と改善
- 6.健康支援を手軽に始められるサービス
- 7.まとめ
健康支援型福利厚生が注目される背景
食事改善や運動習慣の促進は、社員の健康維持だけでなく、企業全体の活性化にもつながります。バランスの取れた食生活は集中力や思考力を高め、運動習慣の定着はストレス解消やメンタルヘルスの改善に効果的です。
企業にとって、従業員の健康管理は単なる義務ではなく、戦略的な投資です。体調不良や慢性的な疾患を未然に防ぐことで、職場全体の活気や生産性が向上し、チームの連携やコミュニケーションも円滑になります。
栄養バランスの良い食事と継続的な運動は、生活習慣病の予防や免疫力の向上に直結します。こうした健康支援が企業にもたらす主な効果として、以下が挙げられます。
- 病欠や離職率の低下
- 生産性の向上
- チームワークの強化
- 企業イメージの向上
食事改善を促進する福利厚生事例
社員の食生活を改善するための福利厚生施策は、日々の食事から健康意識を高めることを目的としています。以下では、実際に企業で導入されている食事改善施策の事例を紹介します。
健康的な社員食堂・カフェの設置
サイボウズの事例:
同社では栄養バランスに配慮したランチを提供する社員食堂を運営。管理栄養士が監修したメニューを手頃な価格で提供することで、社員が自然と健康的な食習慣を身につける環境を整えています。
Googleの事例:
オフィス内に複数の食堂を備え、無料でオーガニックや低カロリーの料理を提供しています。
パナソニックの事例:
社員食堂に「健康応援メニュー」を導入し、カロリーや塩分を抑えた食事を提供。栄養素の表示も徹底し、社員が食事内容を意識できるよう工夫しています。
栄養セミナーや健康講座の実施
アメリカン・エキスプレスの事例:
定期的に栄養士を招いた健康セミナーを開催。食生活の改善方法や栄養バランスについての知識を社員に提供し、日常的な食習慣の見直しを促しています。
リクルートの事例:
社内で食育講座や生活習慣病予防に関する研修を実施。理論だけでなく、実践的なアドバイスを提供することで、社員の健康意識向上に貢献しています。
健康的なスナックや飲料の提供
多くのIT企業では、オフィス内に健康を意識したスナックや飲料を常備しています。ナッツ類やドライフルーツ、栄養バランスの良いエナジーバーなどを無料または低価格で提供することで、間食の質を高める取り組みが広がっています。
Yahoo! Japanの事例:
社員が空腹を満たしながら、健康を損なわないよう工夫された軽食が常備されています。これにより、社員の間食の質が改善され、集中力の維持にも効果が見られています。
食習慣改善のためのデジタルサポート
ユニリーバの事例:
社員に健康管理アプリを提供し、食事記録や栄養バランスの確認を促進。アプリを通じたコンサルティング機能も備えており、個人の状況に合わせたアドバイスが受けられる仕組みを整えています。
このような食事管理アプリの導入は、特にリモートワークが増えた現在、社員の食生活をサポートする効果的な施策となっています。
運動習慣を促進する福利厚生事例
食事改善と並び、運動習慣の定着は社員の健康維持に欠かせません。以下では、実際に企業で行われている運動促進の福利厚生事例を紹介します。
社内フィットネス施設の設置とジム利用補助
Googleの事例:
同社の多くのオフィスには社内フィットネスセンターが設置されており、社員はいつでも無料で利用できます。忙しい業務の合間にも気軽に運動できる環境が整えられています。
運動イベントや社員向けチャレンジの開催
楽天の事例:
社内ウォーキングチャレンジを定期的に実施。部署対抗で歩数を競うことで、社員の運動へのモチベーションを高めるとともに、チームビルディングにも効果をあげています。
リクルートの事例:
社内ランニングクラブの活動支援や、マラソン大会への参加費補助を実施。運動好きの社員だけでなく、初心者も参加しやすいプログラムを用意しています。
こうした参加型イベントは、単に運動を促すだけでなく、社員間のコミュニケーション活性化にも寄与しています。
柔軟な勤務形態による運動時間の確保
サイボウズの事例:
フレックスタイム制度や時短勤務制度を整備し、社員が自身のライフスタイルに合わせて運動時間を確保できるよう配慮しています。
運動習慣を定着させるためには時間の確保が重要であり、柔軟な働き方を認める制度は間接的に運動促進につながっています。
ウェアラブルデバイスやアプリの提供
アメリカン・エキスプレスの事例:
希望する社員にウェアラブルデバイスを貸与し、日々の活動量や睡眠の質をモニタリング。データに基づいた健康アドバイスを提供しています。
健康支援型福利厚生がもたらす効果
食事改善や運動促進の福利厚生は、社員の健康に直接働きかけるだけでなく、企業全体にも様々な好影響をもたらします。
従業員のエンゲージメント向上
健康を重視した福利厚生は、「会社が自分の健康を大切にしてくれている」という実感を社員に与えます。この信頼感は職場への帰属意識や仕事へのモチベーション向上につながり、結果としてエンゲージメントの高い職場環境が形成されます。
生産性向上と医療コスト削減
健康状態が良好な社員は、集中力や判断力が高く、業務効率も向上します。また、病気による欠勤の減少は、チーム全体の生産性維持にも貢献します。
さらに、予防医療の観点からは、生活習慣病などの発症リスク低減による医療コストの削減効果も期待できます。健康保険組合を持つ大企業では、福利厚生と健康保険施策を連携させることで、より効果的な健康経営を実現している例も多く見られます。
採用活動と企業ブランディングへの効果
充実した福利厚生制度は、企業イメージの向上にも寄与します。特に健康支援に力を入れている企業は、「社員を大切にする会社」として評価され、採用活動においても優位性を持ちます。
近年の就職活動では、給与や業務内容だけでなく、福利厚生や社内環境を重視する傾向が強まっており、健康支援の施策は重要な差別化要素となっています。
健康支援型福利厚生の導入ポイント
実際に健康支援型の福利厚生を導入する際のポイントについて解説します。
企業規模や予算に応じた施策の選定方法
健康支援型の福利厚生は、必ずしも大規模な投資を必要としません。企業の規模や予算に応じて適切な施策を選ぶことが重要です。
大企業向け施策例:
- 社内フィットネスセンターの設置
- 専属の管理栄養士によるメニュー開発
- 総合的な健康管理プログラムの導入
中小企業向け施策例:
- 外部ジムとの法人契約
- 定期的な健康セミナーの開催
- 健康アプリの導入支援
- オフィスでの健康的なスナック提供
社員ニーズの把握と反映
福利厚生の成功には、社員のニーズを的確に把握することが不可欠です。社内アンケートやヒアリングを通じて、社員が求める健康支援を理解し、それに基づいた施策を設計することが重要です。
また、年齢層や職種によって健康ニーズは異なるため、多様な選択肢を用意することも効果的です。一部の社員だけでなく、できるだけ多くの従業員が利用できる施策を心がけましょう。
継続的な効果測定と改善
導入した施策の効果を定期的に測定し、必要に応じて改善していくことも重要です。効果測定には以下のような指標が活用できます。
- 社員満足度調査の結果
- 健康診断データの推移
- 施策の利用率
- 欠勤率や有給取得率の変化
データを基にした継続的な改善により、より効果的な健康支援を実現できます。
健康支援を手軽に始められるサービス
健康支援の福利厚生を導入したいと考える企業向けに、手軽に始められるサービスも増えています。キリンビバレッジが提供している置き型健康飲料サービス「WellStock」は、オフィスに常備できる健康志向の飲料を提供することで、初期投資なしで導入できる点が魅力です。
「WellStock」以外にも従業員のヘルスリテラシー向上のためのセミナー開催や、食事・運動・睡眠・飲酒などの生活習慣改善につながるKIRINのオリジナルプログラムなど、様々なサービスをアプリで気軽に体験することでできる「WellWa」もおすすめです。
「WellWa」はミッション達成によるKIRINの美味しい健康飲料が購入できるポイント付与機能もあり「楽しい健康」を体験できるのが魅力の一つです。
〈詳細はこちら〉
まとめ
食事改善や運動習慣の促進を中心とした福利厚生制度は、社員の心身の健康を支えるだけでなく、企業の生産性向上や人材確保にも大きな効果をもたらします。
Googleやサイボウズなどの先進企業の事例からも分かるように、健康支援型の福利厚生は今後の企業運営において重要な要素となっています。企業規模や予算に応じて適切な施策を選び、社員のニーズを反映しながら継続的に取り組むことで、持続可能な健康経営を実現できるでしょう。
健康支援の福利厚生は、社員と企業の双方にメリットをもたらす施策です。まずは小規模な取り組みからでも、自社に合った健康支援を検討してみてはいかがでしょうか。