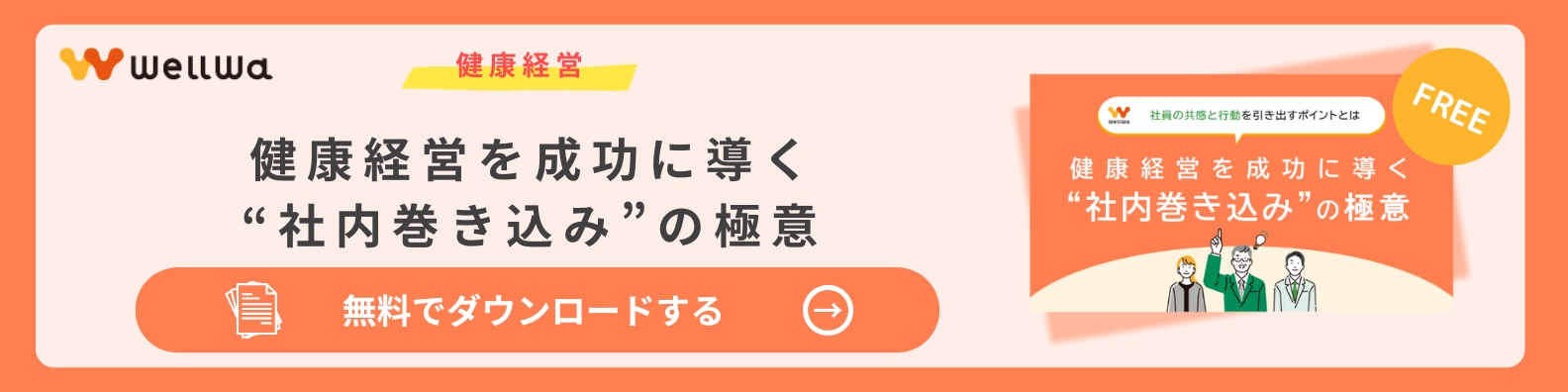福利厚生の利用率を高める従業員アンケートの実践ガイド
従業員が福利厚生を有効に活用することで、企業全体の満足度や生産性が高まります。しかし、制度を導入しても実際の利用率が低ければ、投資効果を十分に得ることはできません。本記事では、福利厚生の利用率を高めるために有効な従業員アンケートの作成方法や活用のポイントを解説します。
目次[非表示]
- 1.福利厚生の課題と従業員アンケートの必要性
- 2.効果的な福利厚生アンケートの設計方法
- 2.1.1. アンケートの目的を明確にする
- 2.2.2. 効果的な設問を設計する
- 2.3.3. 回答率を高める工夫
- 3.アンケート結果の分析と福利厚生の改善方法
- 3.1.低利用の原因分析と対策
- 3.2.効果的な制度改善の進め方
- 4.専門の健康サーベイサービスの活用
- 5.まとめ
福利厚生の課題と従業員アンケートの必要性
福利厚生は企業の魅力向上や従業員の定着率アップに効果的ですが、制度を整えるだけでは十分な効果は得られません。多くの企業では、以下のような課題を抱えています。
- 福利厚生制度があっても実際に利用されていない
- 従業員のニーズと提供している制度にミスマッチがある
- 制度の存在自体が従業員に十分に認知されていない
- 一部の従業員層にしか恩恵が及んでいない
これらの課題を解決するためには、従業員の声を直接集め、現状を正確に把握することが必要です。そこで役立つのが従業員アンケートです。
アンケートによって得られるメリットは多岐にわたります。
- 各福利厚生制度の利用状況と満足度を数値化できる
- 従業員が本当に求めている制度を把握できる
- 利用率が低い制度の原因を特定できる
- 従業員の声を反映した制度改善につなげられる
- 「会社が自分たちの声を大切にしている」という意識が醸成される
効果的な福利厚生アンケートの設計方法
従業員満足度や福利厚生制度の改善に向けたアンケートを作成する際は、以下のステップに沿って進めることでより有効なデータを収集できます。
1. アンケートの目的を明確にする
最初に、アンケートで何を知りたいのかを明確にしましょう。目的によって設問の内容や深堀りするポイントが変わってきます。主な目的としては次のようなものが考えられます。
- 現行の福利厚生制度の認知度と利用状況を把握する
- 各制度に対する満足度と改善要望を収集する
- 未導入だが従業員が希望する福利厚生を探る
- 制度を利用する際の障壁を特定する
複数の目的を持たせることもできますが、焦点を絞りすぎると必要な情報が得られず、広げすぎると回答者の負担が増すため、バランスが重要です。
2. 効果的な設問を設計する
回答率と回答の質を高めるために、設問設計では以下のポイントに注意しましょう。
▼適切な設問数
10〜15問程度が理想的です。長すぎるとアンケートの途中離脱率が高まります。
▼回答形式のバランス
- 選択式(単一・複数選択):客観的なデータ収集に適しています
- 評価式(5段階評価など):満足度や重要度の測定に有効です
- 自由記述式:具体的な意見や提案を集める際に活用します
バランスよく組み合わせることで、数値データと具体的な意見の両方を収集できます。
▼質問の構成例
- 基本属性(年齢層、勤続年数、家族構成など)
- 各福利厚生制度の認知度
- 利用状況と利用頻度
- 満足度評価
- 利用しない理由(該当する場合)
- 今後希望する制度
- 自由意見
3. 回答率を高める工夫
アンケートを実施しても回答率が低ければ、得られる情報は限定的です。回答率を向上させるための工夫として、以下の点を検討しましょう。
- 匿名性の確保 従業員が本音で回答できるよう、匿名でのアンケート実施を基本とします。部署や役職などの属性情報を収集する場合も、個人が特定されないレベルにとどめるべきです。
- 回答へのインセンティブを用意 回答者への特典を用意することで参加意欲を高められます。(例えば、福利厚生ポイントの付与や抽選での景品プレゼント、少額のギフト券配布など)
- 回答のしやすさ
他にも、以下のような工夫が効果的でしょう。
- スマートフォンからも回答しやすいフォーマット
- 業務時間内に解答できる環境の提供
- 回答期間の十分な確保(2週間程度)
アンケート結果の分析と福利厚生の改善方法
アンケートの実施後は、結果を適切に分析し、具体的な改善につなげることが重要です。
低利用の原因分析と対策
福利厚生の利用率が低い原因は様々です。アンケート結果から特定された原因別に、以下のような対策を検討しましょう。
認知度不足の場合
- 社内ポータルサイトでの定期的な情報発信
- 新入社員オリエンテーションでの丁寧な説明
- 福利厚生制度ガイドブックの作成と配布
- 定期的なリマインドメールの送信
利用手続きの煩雑さが原因の場合
- オンライン申請システムの導入
- 申請フローの簡素化
- ワンストップの窓口設置
- スマートフォンアプリでの申請対応
制度自体の魅力不足が原因の場合
- 従業員のニーズに合った新制度の導入既存制度の条件見直し(金額、対象範囲など)
- 選択型福利厚生(カフェテリアプラン)の検討ライフステージに合わせた制度設計
効果的な制度改善の進め方
アンケート結果を基に福利厚生制度を改善する際には、以下のプロセスで進めるとより効果的です。
1. 優先順位の決定:利用率や満足度、要望の多さなどを基準に、改善すべき制度の優先順位を決めます。
2. リソースの最適配分:人気の高い制度への予算配分を増やす一方、利用の少ない制度は縮小または廃止を検討し、リソースの最適化を図ります。
3. 改善案の策定と実行:具体的な改善策を策定し、スケジュールを決めて実行します。大きな変更は段階的に導入するのが望ましいでしょう。
4. 効果測定と継続的改善:改善後も定期的にアンケートを実施し、変化を追跡します。6カ月〜1年ごとの定点観測が効果的です。
専門の健康サーベイサービスの活用
従業員の健康状態を可視化するアンケートツールとして、専門のサーベイサービスも活用できます。キリンビバレッジのWellWaでは、健康状態の変化を可視化するためのサーベイと改善提案のサービスを提供しています。
サーベイ・分析
睡眠時間、食生活、運動習慣、メンタルヘルスなど、幅広い健康項目についてアンケート調査を実施できます。従業員一人ひとりの生活習慣や健康リスクを分析することが可能です。福利厚生制度の効果を定量的に評価できるため、健康経営のPDCAを回すうえで役立ちます。
改善提案
アンケート結果に基づいて、キリンビバレッジのWellWaの専門スタッフが職場環境や生活習慣の改善につながるアドバイスを提供します。たとえば、栄養バランスの取れた食事提案やストレス軽減策など、実行可能なアクションが提示されるため、従業員の行動変容を促しやすくなります。
まとめ
福利厚生の利用率を高め、従業員満足度を向上させるためには、適切に設計された従業員アンケートが欠かせません。アンケートを通じて収集した従業員の声を制度設計に反映させることで、より効果的な福利厚生を実現できます。
従業員満足度の向上と企業の競争力強化に向けて、今日からアンケートを活用した福利厚生の改善に取り組んでみてはいかがでしょうか。