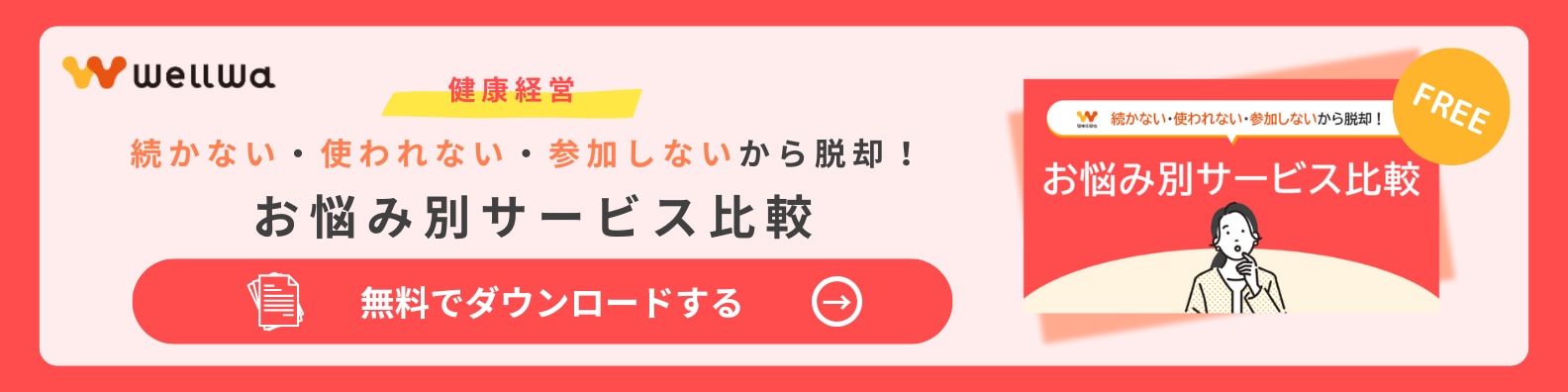福利厚生アプリの導入メリットと活用方法
企業の健康経営が重視される中、福利厚生の提供方法も変化しています。スマートフォン1つで従業員が手軽に福利厚生サービスを利用できる「福利厚生アプリ」は、DX推進の流れにも合致しています。本記事では、福利厚生アプリの概要や導入メリット、導入方法、選定のポイントについて解説します。
目次[非表示]
- 1.福利厚生アプリの基本
- 2.福利厚生アプリ導入がもたらすメリット
- 3.導入方法と成功のポイント
- 3.1.アプリ選定のポイント
- 3.2.導入プロセス
- 3.3.成功のための要点
- 4.健康経営との連携
- 5.まとめ
福利厚生アプリの基本
福利厚生アプリとは、企業が提供する各種福利厚生を、スマートフォンやPC上で一元的に管理・利用できるツールです。健康を促進するポイント付与型ミッションの提供、診断の予約、ジムの割引チケット取得、ランチ補助の申請などがワンタップで行え、従業員の利用率向上につながります。企業側も運用状況をデータで把握できるため、効率的な福利厚生管理が可能になります。
近年、こうしたアプリが注目される背景には、いくつかの理由があります。従業員の利便性向上はもちろん、企業のDX推進や健康促進の側面も大きいでしょう。
最新の福利厚生アプリはパーソナライズ機能も充実しており、従業員の年齢やライフスタイル、過去の利用履歴に基づいておすすめのサービスが表示されるなど、一人ひとりに合わせたアプローチが可能になっています。
福利厚生アプリ導入がもたらすメリット
企業側のメリット
管理負担の軽減
アプリ導入により、申請・承認フローの自動化や利用状況のリアルタイム管理が可能になり、担当者の負担が大きく軽減されます。
健康管理の効率化
健康促進アクティビティの申請・承認プロセスを自動化し、健康状態のモニタリングを容易にします。これにより、従業員の健康リスクを早期に特定し、予防的介入が可能になります。
データ分析による最適化
アプリには利用履歴が蓄積されるため、どのサービスが人気か、どの部署で利用が進んでいないかといったデータを簡単に分析できます。これにより、従業員のニーズに基づいた施策の改善や、新たな福利厚生の導入判断がしやすくなります。
コスト効率の向上
多くの福利厚生アプリは月額課金などのサブスクリプション形式で提供されており、大規模な初期投資が不要です。また、アプリに内蔵されたポイントシステムや提携先サービスを活用すれば、コストを抑えながら多様な福利厚生を提供できます。
従業員側のメリット
利便性の向上
福利厚生アプリの導入により、スマートフォンからいつでもどこでもサービスを利用できる点は大きな利点です。操作性も直感的で、ITリテラシーに関わらず誰でも簡単に使える設計がされています。
日常の健康行動のゲーミフィケーション
歩数競争や健康的な食事のトラッキングなど、日常の健康行動を楽しいゲーム感覚で行うことができます。アプリを使う中で、健康意識が自然と高まります。
カスタマイズ可能な福利厚生
多くの福利厚生アプリではポイント制を採用しており、従業員が自分の好みに合ったサービスを選べます。個々の健康状態や好みに基づいて、パーソナライズされた健康促進プログラムを提供。健康行動でポイントが貯まる仕組みや、好きなタイミングで使えるクーポンなど、一人ひとりのニーズに応じた使い方が可能です。
場所を問わない活用
テレワークが定着した現在、オンラインで完結する福利厚生の仕組みが求められています。アプリであれば、オフィスにいなくても福利厚生を実感でき、リモートワーク環境下でのエンゲージメント維持に役立ちます。
導入方法と成功のポイント
アプリ選定のポイント
企業特性との適合性
福利厚生アプリは、サービス提供企業ごとに特徴が異なります。ベンチャーや中小企業向けの柔軟性重視のものから、大企業向けの多機能タイプまで様々です。自社の企業規模や業種、従業員の属性にマッチしたアプリを選びましょう。
使いやすさの確認
どれだけ機能が充実していても、使いにくければ利用率は上がりません。操作のしやすさやデザインのわかりやすさを重視し、実際にデモ版やトライアル版で確認することをおすすめします。
既存制度との連携の福利厚生と統合できるかチェック
現在すでに提供している福利厚生サービスとの連携・統合ができるかも重要なポイントです。重複や混乱を避けるためにも、既存制度との親和性が高いサービスを選ぶことで、スムーズな移行が可能になります。
導入プロセス
1. ニーズの調査(従業員アンケート・課題の洗い出し)
まずは、自社の福利厚生制度にどんな課題があるかを明確にし、従業員のニーズを把握することが第一ステップです。アンケートやヒアリングを通じて、実際に求められているサービスや使いづらさを洗い出しましょう。このプロセスを丁寧に行うことで、導入後のミスマッチを防げます。
2. 適したアプリの選定(無料トライアル・デモ利用)
候補のアプリが見つかったら、必ずトライアルやデモ版を活用しましょう。実際の操作感やUIの使いやすさを確認することで、従業員にとって使いやすいかどうかを事前に把握できます。また、複数のサービスを比較検討することで、最適な選択が可能になります。
3. 社内ルールの整備(利用ガイドライン作成・導入告知)
導入が決まったら、社内での利用ルールを整備し、従業員にわかりやすく周知します。ポイントの使い方、対象サービスの範囲、申請ルールなどを明文化したガイドラインを作成するとスムーズです。また、導入時には社内告知や説明会を行い、従業員の理解と興味を引き出しましょう。
4. アプリの導入・運用開始(管理者向け研修・従業員向け説明)
正式な導入にあたっては、福利厚生担当者向けに管理画面や設定方法の研修を行いましょう。併せて、従業員向けの利用方法や操作マニュアルも用意します。実際の利用を想定したQ&A形式の研修や、社内イントラに使い方動画を掲載するなどの工夫も効果的です。
5. 効果測定・フィードバック収集(利用率・満足度の分析)
導入後は、定期的に利用率や従業員満足度を確認しましょう。アプリ内の分析機能を活用すれば、どのサービスが多く利用されているかや、どの部署で活用が進んでいないかを可視化できます。その結果をもとに、制度やアプリの使い方の見直しを行うことで、継続的な改善が図れます。
成功のための要点
シンプルで直感的なUIを重視
福利厚生アプリの活用促進には、操作のしやすさが大きく影響します。誰でも迷わず使えるシンプルなUI設計がされたアプリを選びましょう。
運用負担の軽減機能を確認
申請・承認の自動化、データの自動集計、レポート出力など、管理業務を効率化する機能が充実しているかをチェックしましょう。人事担当者の負担軽減は長期運用の鍵となります。
継続的な改善プロセスの構築改善
アプリ導入はゴールではなく、スタートです。定期的に従業員からのフィードバックを集め、制度や使い方を見直す仕組みを作りましょう。継続的な改善が、福利厚生アプリの価値を高めていきます。
健康経営との連携
近年の福利厚生アプリでは、健康経営との連携を重視したサービスも増えています。ここでは、一例として、キリンビバレッジが提供する「WellWa」をご紹介します。
WellWaが提供している健康促進アプリは、従業員の「健康行動」をポイント化し、そのポイントを福利厚生サービスとして利用できる仕組みを採用しています。例えば、ウォーキングや体調管理、健康的な食事などの日常的な健康習慣を記録し、それに応じてポイントが付与される仕組みです。
こうしたアプリは健康経営と従業員満足度の向上を同時に実現できるため、企業からの評価も高まっています。また、利用データの分析によって健康推進活動の効果測定も可能になり、より効果的な施策の立案にも役立ちます。
<WellWaの詳細はこちら>
まとめ
福利厚生アプリは、企業の健康経営を後押しし、従業員満足度を高める効果的なツールです。スマートフォンで簡単に利用できる仕組みは、従来の福利厚生の課題を解決し、運用の効率化や利用促進につながります。
導入に際しては、自社の特性や従業員のニーズを踏まえたアプリ選定が重要です。デモやトライアルを通じて、使いやすさや健康促進機能の充実度を確認しましょう。丁寧な社内周知と定期的に利用状況と従業員の健康改善状況を評価することが、長期的な成功につながります。
健康行動を促すポイント制度や、パーソナライズ機能など、福利厚生アプリは日々進化を続けています。自社の健康経営戦略の一環として、導入を検討する価値は十分にあるでしょう。