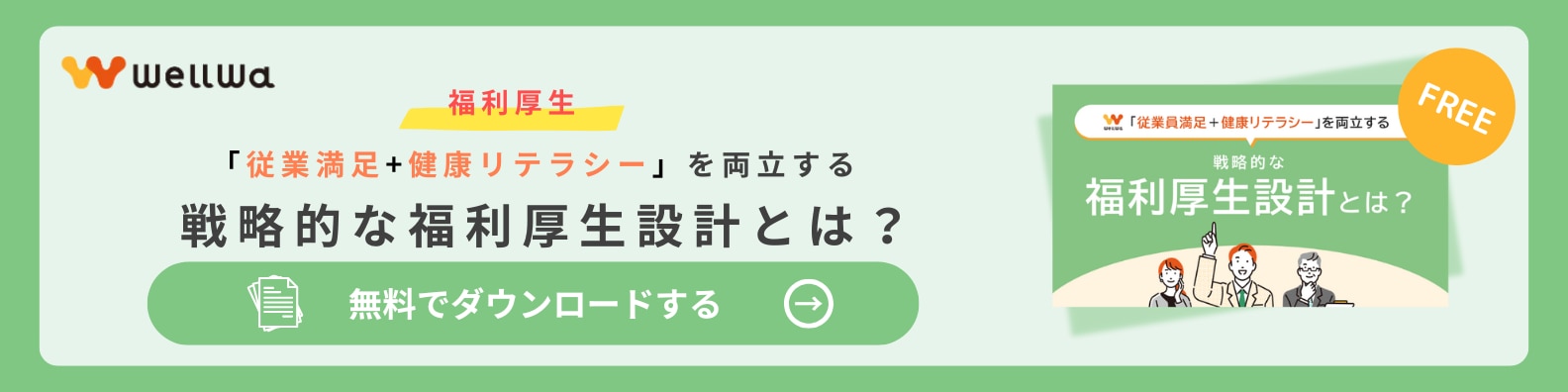福利厚生で実現する効果的な節税と制度活用術
企業が健全な経営を目指す上で、「節税」は欠かせないテーマです。従業員向けに提供している福利厚生制度の中には、上手に活用することで法人税や社会保険料の節税につながるものが多く存在します。本記事では、節税効果のある福利厚生の仕組みや制度をわかりやすく解説します。
目次[非表示]
- 1.福利厚生による節税の仕組み
- 2.節税効果のある主な福利厚生制度
- 2.1.食事補助
- 2.2.住宅手当・社宅制度
- 2.3.通勤手当
- 2.4.福利厚生サービス
- 2.5.健康診断・人間ドックの費用負担
- 2.6.研修・資格取得支援
- 2.7.社内レクリエーション・慰安旅行
- 3.節税効果を最大化するポイント
- 3.1.全従業員が対象となる制度設計
- 3.2.社内規定の整備
- 3.3.適切な金額設定
- 3.4.専門家への相談
- 4.まとめ
福利厚生による節税の仕組み
福利厚生費の多くは、企業の「経費」として処理されます。会社が従業員に提供する食事補助や通勤手当などが、税務上の損金として認められるということで、企業が納める法人税の負担が軽減されます。
給与として支払う場合、所得税や住民税、社会保険料の対象となり、会社も従業員もそれぞれに税金や保険料を負担する必要があります。しかし、非課税枠のある福利厚生費であれば、それらの負担を軽減できるため、企業にとっても従業員にとっても経済的なメリットが生まれます。例えば、非課税の通勤手当や食事補助を受けることで、従業員の手取りが増える一方、企業もその費用を損金処理できるため、双方にとって有益な関係が築けます。このように、制度設計次第では、従業員満足と節税の両立が可能となります。
節税効果のある主な福利厚生制度
実際に節税効果が見込める福利厚生制度を見ていきましょう。
食事補助
従業員に対して社員食堂を運営したり、食事券などの補助を行ったりする制度は、一定の条件を満たせば非課税となります。例えば、1食あたりの自己負担額が半額以上であるなどの要件を満たせば、会社の負担分は課税対象外になります。
具体的には、従業員が食事代の50%以上を負担し、会社負担分が月額3,500円(税抜)以下であれば、その食事提供は給与課税されず福利厚生費として扱われます。この方法により、給与として支払うよりも税務上効率的に従業員に還元できます。
住宅手当・社宅制度
社宅制度を導入することで、従業員に提供する住居費の一部を経費として計上できます。会社が物件を借り上げ、従業員に貸与する場合には、一定の評価額での貸与とすることで、税務上のメリットを受けられます。
実務上は、社宅の家賃の50%程度を会社が負担するケースが多く、この負担部分は会社の経費として認められます。給与として住宅手当を支給するよりも、社宅制度として運用する方が節税効果は高くなります。
通勤手当
公共交通機関を利用する従業員に支給される通勤手当については、月15万円まで非課税とされています。これも企業にとっては節税効果のある支出です。支給方法や金額が適切であれば、給与とみなされず、損金処理が可能となります。
通勤定期券を現物支給するか、実費精算する形式を取ることで、確実に非課税枠を活用できます。マイカー通勤の場合も、距離に応じた通勤手当が非課税となる範囲が定められており、適切に制度設計することで節税が可能です。
福利厚生サービス
福利厚生サービスを活用することで、レジャーや育児、介護支援など多岐にわたるサービスをパッケージ化して従業員に提供できます。これらのサービスにかかる費用は、業務関連性があると判断されれば経費として計上可能です。
例えば、キリンビバレッジが提供する「WellStock」のような福利厚生サービスを導入すれば、従業員が利用できるサービスの幅が広がり、会社としても一括管理が容易になります。導入費用は全額が経費として認められるケースが多いです。
〈詳細はこちら〉

健康診断・人間ドックの費用負担
定期健康診断の費用は全額非課税であり、会社の経費として処理できます。(ただし、会社が法定の定期健康診断を実施し、その費用を直接医療機関に支払う場合。会社が従業員に健康診断費用を現金で支給し従業員が支払う形にした場合、その金額は給与として課税対象となる)
また、人間ドックについても、業務上必要と認められる範囲であれば、福利厚生費として損金算入が認められるケースがあります。
研修・資格取得支援
業務に関連する研修や資格取得にかかる費用を会社が負担する場合、それは従業員のスキル向上を目的とした業務支出とみなされ、経費として処理可能です。支援の範囲や対象資格を明確にしておくことで、節税効果が得やすくなります。
社内レクリエーション・慰安旅行
従業員の士気向上やチームワーク強化を目的とした社内イベントや旅行も、一定の条件を満たせば非課税扱いとなります。具体的には、「旅行期間が4泊5日以内」「全社員が対象で実際に参加した従業員が社員全体の50%以上」「一人当たりの会社負担額が常識的な範囲(おおむね10万円以下)」であることなどが要件となります。
節税効果を最大化するポイント
福利厚生を節税に活用するには、いくつかの重要なポイントがあります。
全従業員が対象となる制度設計
節税効果のある福利厚生制度を導入する際は、特定の社員だけでなく、全社員を対象とした内容にすることが基本です。役職や年齢、勤続年数などにより利用制限がある場合でも、その理由が合理的である必要があります。
例えば、管理職だけが利用できる制度や、特定部署のみを対象とした福利厚生は、税務調査の際に給与と見なされるリスクがあります。できるだけ公平で透明性の高い制度設計を心がけましょう。
社内規定の整備
福利厚生を導入する際は、対象者や支給条件、金額などを明確にした社内規定を作成することが重要です。規定があることで、税務調査の際にも制度の正当性を説明しやすくなります。
また、規定に基づいた一貫性のある運用を行うことで、「恣意的な給付」ではなく「制度に基づいた福利厚生」として認められやすくなります。
適切な金額設定
福利厚生の金額が過度に高額な場合、税務署から「隠れた給与」と見なされるリスクがあります。業界や企業規模に応じた常識的な範囲内で設定することが重要です。
例えば、慰安旅行が高級リゾートでの長期滞在になっていたり、健康診断が必要以上に高額なコースになっていたりする場合は、福利厚生費としての経費計上が否認される可能性があります。
専門家への相談
福利厚生制度の設計や運用方法については、税理士や社会保険労務士などの専門家に相談することをおすすめします。税法や社会保険の制度は頻繁に変更されるため、最新の情報に基づいたアドバイスを受けることが重要です。
また、自社の状況に合わせた最適な制度設計を行うためにも、専門家の知見を活用することで、より効果的な節税対策が可能になります。
まとめ
福利厚生は、従業員の満足度向上と企業の節税を同時に実現できる重要な施策です。特に法定外福利厚生は、税務上の優遇措置が多く設けられており、制度設計次第で大きな効果を発揮します。
全従業員を対象とした公平性、明確な社内規定の整備、適切な金額設定などに注意しながら、自社に合った制度を構築することが成功の鍵となります。効果的な福利厚生の導入により、企業の成長と従業員の満足度向上を両立させましょう。