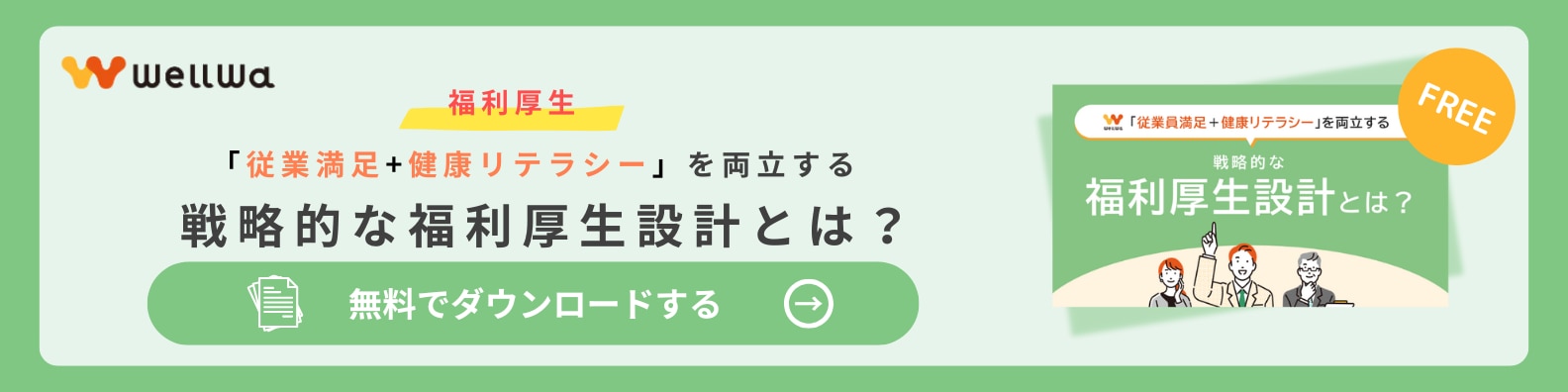福利厚生の食事補助が人気の理由!導入メリット&おすすめサービスを紹介
数ある福利厚生の中でも特に人気が高い制度が「食事補助」です。本記事では、福利厚生としての食事補助がなぜ人気なのか、その種類や導入ポイント、具体的なサービス事例をご紹介します。
目次[非表示]
- 1.食事補助が人気の理由
- 1.1.1従業員にとってのメリット
- 1.2.2企業にとってのメリット
- 2.食事補助の種類
- 2.1.1. 社員食堂(社食)
- 2.2.2. チケット・金券補助
- 2.3.3. デリバリー・外食補助
- 2.4.4. カフェテリアプラン
- 2.5.5. オフィス内に軽食・飲料サービスの設置
- 3.食事補助を導入する際のポイント
- 3.1.企業規模やニーズに合った制度を選ぶ
- 3.2.税制優遇の活用(非課税範囲の確認)
- 3.3.コストと運用負担のバランスを考える
- 4.おすすめの食事補助サービス3選
- 5.まとめ
食事補助が人気の理由
食事補助制度が多くの企業や従業員から支持されている理由には、健康促進やコスト削減など、さまざまなメリットがあります。ここでは、従業員と企業それぞれの視点から、その理由を詳しく見ていきましょう。
1従業員にとってのメリット
・食費の節約
日々のランチ代や夕食代を節約しようとすると、ついつい偏った食事になったり、食事を抜いたりしがち。そんな時、社員食堂での割引制度や、ランチ代を一部補助してくれるサービスなどがあれば、従業員への経済的支援につながります。毎日の昼食代も1ヶ月に換算すると決して少なくありません。金銭的な負担が減ることで、仕事へのモチベーションや従業員満足度の向上にもつながるでしょう。
・栄養バランスの取れた食事が可能
忙しいビジネスパーソンにとって、栄養バランスの取れた食事を毎日とることは簡単ではありません。企業が提供する食事補助は、管理栄養士が監修したメニューや健康に配慮したメニューが多く、自然と健康的な食生活を実現できます。その結果、生活習慣病の予防にもつながり、健康経営の一環としても非常に有効です。
・社内交流の促進
社員食堂やランチミーティングの場は、部署を超えた交流のチャンスでもあります。食事を通じてリラックスしたコミュニケーションが生まれ、社内の風通しが良くなったという声も多くあります。特にテレワークやフレックス勤務が広がる今、対面での交流を促進する手段としても有効です。
2企業にとってのメリット
・従業員の健康管理・生産性向上
健康的な食生活は、従業員の体調管理や集中力の維持に直結します。企業が健康に配慮した食事環境を整えることで、欠勤率の低下やパフォーマンスの向上が期待できます。
・採用・定着率の向上(福利厚生の充実度は企業選びのポイント)
求職者が企業を選ぶ際、福利厚生の内容は重要な判断材料となります。中でも食事補助は「日常的に使える福利厚生」として人気が高く、導入している企業は「働きやすい職場」として評価されやすくなります。従業員の定着率アップにも貢献するでしょう。
・税制優遇の活用(社食や食事補助の非課税枠)
食事補助は、一定の条件を満たせば給与として課税されずに非課税で提供可能です。(例えば、社員食堂での食事が1食あたり350円以下の場合や、現物支給であることなどが条件)これにより、企業側もコストを抑えつつ、効果的な福利厚生を実現できます。
食事補助の種類
一言で「食事補助」と言っても、その提供方法やスタイルはさまざまです。ここでは、代表的な5つの食事補助の種類について解説します。
1. 社員食堂(社食)
企業の敷地内やビル内に設けられた社員専用の食堂で、低価格で栄養バランスの取れた食事を提供する形式です。自社で運営するケースと外部業者に委託するケースがあり、大企業で導入されていることが多いです。社員の健康支援や交流促進にも寄与しますが、初期コストや運営負担が大きいため、中小企業にはややハードルが高いかもしれません。
2. チケット・金券補助
食券やランチチケット、プリペイドカードなどを通じて、従業員の外食や弁当購入を補助する制度です。特定の提携飲食店で使える形式や、金額を一定の範囲内で設定するものが多く、運用が比較的簡単で幅広い企業に導入されています。チケットの現物支給であれば、非課税で提供することも可能です。
3. デリバリー・外食補助
最近では、Uber Eatsや出前館といったデリバリーサービスと連携した食事補助も増えています。企業が補助する金額を設定し、従業員は好きなタイミングで食事を注文できます。外出先や在宅勤務中でも利用しやすく、多様な働き方に対応可能な柔軟な制度です。
4. カフェテリアプラン
従業員が自分のライフスタイルやニーズに合わせて福利厚生を選べる「選択型福利厚生制度」です。食事補助だけでなく、住宅手当や育児支援なども含まれ、ポイント制などで柔軟に運用できます。個人の価値観を尊重しながら福利厚生を設計できるため、従業員満足度の向上に寄与します。
5. オフィス内に軽食・飲料サービスの設置
オフィス内にスナックや飲み物を常備し、従業員が自由に利用できるようにするサービスです。手軽に空腹を満たしたり、ちょっとした休憩に役立ったりするため、特に長時間勤務が多い企業やベンチャー企業で導入例が増えています。サービス提供会社との契約により、補充や管理も任せられます。
食事補助を導入する際のポイント
制度をうまく機能させるためには、導入前にいくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。ここでは主に3つの観点から、導入時の注意点を解説します。
企業規模やニーズに合った制度を選ぶ
すべての企業にとって社員食堂が最適とは限りません。企業の規模、勤務形態、従業員の年代や働き方に応じて最適な制度を選ぶことが重要です。
例えば、小規模オフィスならチケット制やデリバリー型、大企業なら社食やカフェテリアプランが有効でしょう。導入前にはアンケート調査などを通じて、従業員のニーズを把握することが成功の鍵となります。
税制優遇の活用(非課税範囲の確認)
食事補助の制度設計においては、税制面の知識も欠かせません。国税庁の定める非課税要件に従って制度を設計すれば、課税所得の増加を防ぎ、企業・従業員双方にとってメリットの大きい制度となります。特に、現物支給・350円以下の基準・福利厚生施設での提供といった条件を満たすよう配慮しましょう。
コストと運用負担のバランスを考える
導入時の初期コストや継続的な運用負担についても検討が必要です(例えば、社員食堂は導入費が高額になる一方で、チケット制は比較的安価かつ簡単に運用可能など)。どこにどれだけのリソースをかけられるか、社内の体制や人的リソースを含めて現実的に判断する必要があります。
おすすめの食事補助サービス3選
ここでは、導入実績も豊富で評判の高い食事補助サービスを3つご紹介します。どれも従業員満足度の向上に寄与しやすいサービスばかりです。
1 WellStock(キリンビバレッジ株式会社)

「WellStock」は、オフィスで手軽に野菜不足を補えるスムージーや乳酸菌入りドリンクなど、健康に関するさまざまな商品を手軽に購入できるサービスです。野菜・果物を中心にしたナチュラルな商品設計で、健康志向の高い従業員に人気があります。スムージーは冷蔵保存されており、片手で気軽に飲むことができるため、忙しいオフィスワーカーにも好評です。
〈詳細はこちら〉
2 オフィスおかん(株式会社OKAN)
「オフィスおかん」は、冷蔵庫に常備されたお惣菜を電子レンジで温めるだけで、手軽に栄養バランスの良い食事ができるサービスです。和洋中さまざまなメニューがあり、季節ごとの入れ替えもあるため飽きが来ません。1品100円〜200円程度と企業側のコスト負担も抑えられる点が特徴です。
3 OFFICE DE YASAI(株式会社KOMPEITO)
「OFFICE DE YASAI」は、オフィスに設置された冷蔵庫に、野菜やフルーツ、ヘルシーな軽食を定期的に補充するサービスです。従業員は1品100円〜300円程度で利用でき、健康意識の高い層に特に好まれています。管理もすべてサービス提供側が担うため、企業側の手間が少なく済むのもメリットです。
まとめ
食事補助は、従業員の健康支援や満足度向上、企業の採用力アップに大きく貢献する福利厚生のひとつです。企業規模やニーズに合わせた最適な制度選びと、税制優遇の活用、コスト管理を意識することで、効果的に導入することが可能です。健康経営を目指す担当者の皆さまは、ぜひ自社に合った食事補助制度の導入を検討してみてください。