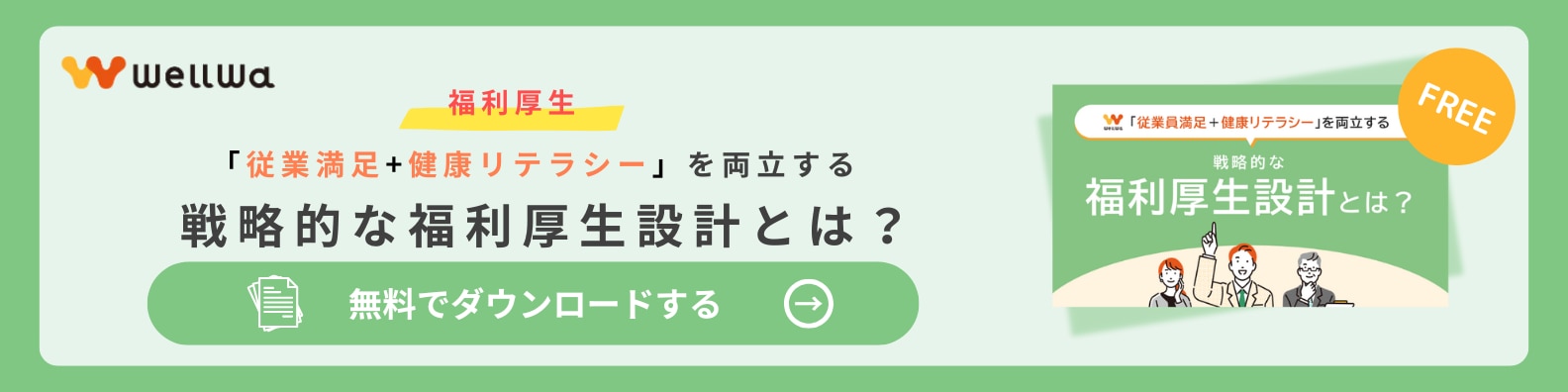福利厚生費の上限はいくらまで?税務上のルールと適切な活用法
企業が従業員の満足度や定着率を高めるために導入する「福利厚生制度」。その費用はどの程度までなら経費として認められるのでしょうか?この記事では、税務上のルールや実務上の目安、具体的な活用法を交えて詳しく解説します。
目次[非表示]
- 1.福利厚生費とは?
- 2.福利厚生費の税務上の取り扱い
- 3.福利厚生費と交際費・給与の違い
- 4.福利厚生費の適切な金額とは
- 4.1.金額の上限と実務上の目安
- 4.2.経費計上時の注意点
- 4.3.税務署が否認しやすいポイントと注意点
- 5.福利厚生費として計上できる具体例と金額の目安
- 5.1.1 社宅・住宅手当
- 5.2.2 通勤手当
- 5.3.3 食事補助(社員食堂・食券)
- 5.4.4 慰安旅行・レクリエーション
- 5.5.5 健康診断・人間ドック
- 5.6.6 研修・資格取得支援
- 6.福利厚生費を適切に活用するポイント
- 6.1.1社内規程の整備と運用管理
- 6.2.2給与との区別を明確に
- 6.3.3自社に適した制度を導入
- 7.まとめ
福利厚生費とは?
福利厚生費とは、企業が従業員の生活や健康、職場環境の向上を目的として支出する費用のことです。社宅の提供や通勤手当、社員旅行、健康診断費用などが該当します。
これらの支出は従業員のモチベーションを高めるだけでなく、企業としても税務上「福利厚生費」として扱うことで、一定の節税効果を得ることができます。つまり、適切に運用すれば、企業と従業員の双方にとってメリットの大きい制度といえます。
企業は給与として支払うよりも、福利厚生費として支出したほうが、法人税の軽減につながるケースがあります。また、従業員にとっても、家賃補助や食事補助、健康診断などの福利厚生を受けることで生活の質が向上し、会社への満足度も高まります。結果として、優秀な人材の確保や離職防止にも貢献します。
福利厚生費の税務上の取り扱い
福利厚生費を経費として認めてもらうためには、いくつかの明確な条件があります。
福利厚生費を経費として認められる条件
福利厚生費として支出した費用が、税務上も経費として認められるためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
1事業に必要であること
支出が会社の事業に関連し、必要性があるものでなければなりません。例えば、健康診断や研修制度などは、従業員の健康維持や能力向上に資するものであり、「事業の継続・発展に資する支出」として正当化できます。単なる贅沢品や従業員の私的な欲求を満たすような支出は、事業との関連性が薄く、福利厚生費とは認められません。
2全従業員が公平に利用できること
福利厚生費が認められるもう一つの重要な条件は、「すべての従業員に対して公平であること」です。特定の役職者や部署のみが利用できる制度は、福利厚生ではなく「給与」とみなされるおそれがあります。たとえば、役員だけが使える社用車や、特定社員だけが受ける海外研修などは注意が必要です。社内規程で対象範囲を明記し、公平性を保つことが大切です。
3個人的な給与としてみなされないこと
福利厚生費と給与の線引きも、税務上の大きなポイントです。例えば、家賃補助が実質的に給与と変わらない形で支給されていれば、それは課税対象となる給与とされます。制度として整備されていても、実態として個人の自由な金銭支出に近い形だと、否認される可能性があります。
福利厚生費と交際費・給与の違い
福利厚生費は「従業員向け」、交際費は「取引先向け」、給与は「対価」としての報酬という点で明確に区分されます。
交際費には年間の損金算入限度額がある一方で、福利厚生費には基本的に上限は設けられていません。ただし、実態として交際費や給与に近い使い方をすると、税務署から指摘を受けやすくなります。支出目的や利用対象、制度の透明性を明確にしておくことで、これらの混同を防ぐことができます。
福利厚生費の適切な金額とは
福利厚生費には法律上の明確な上限があるわけではありませんが、税務上の判断基準や実務上の目安は存在します。
金額の上限と実務上の目安
税法上、福利厚生費には「この金額までしか認められない」という明確な上限は設定されていません。そのため、理論上は企業の判断である程度自由に設定できます。
しかし、過度な支出や不自然な支給内容は、税務署から「給与」や「交際費」として認定される可能性があります。
一般社団法人 日本経済団体連合会の調査によると、2019年における法定外福利厚生費の平均額は従業員1人1ヶ月あたり「24,125円」でした。
出典:一般社団法人 日本経済団体連合会「第64回 福利厚生費調査結果報告」
経費計上時の注意点
企業が福利厚生費を安全に経費計上するには、社内規定を整備し、どのような福利厚生制度を、誰を対象に、どのような条件で提供するのかを明文化することが重要です。これにより、税務署に対しても制度の合理性と公平性を説明しやすくなります。
また、福利厚生費の妥当性を判断する際には、同業他社や同規模企業の支出水準と比べて著しく高くないことも重要な判断基準になります。
税務署が否認しやすいポイントと注意点
税務署が福利厚生費としての経費計上を否認するのは、次のようなケースが多いです。
- 特定の役職者だけが恩恵を受けている
- 支出内容が贅沢すぎる(例:高級リゾートでの慰安旅行)
- 実態が伴わず、形式だけ整っている(ペーパールール)
- 従業員ではなく、経営陣や家族に利益が及んでいる
これらに該当する支出は、福利厚生費ではなく「役員報酬」や「給与」と見なされ、課税対象となる可能性があるため、あらかじめ回避策を講じておくことが重要です。
福利厚生費として計上できる具体例と金額の目安
ここでは、実務上よく活用される福利厚生費の具体例と、金額の目安を紹介します。
1 社宅・住宅手当
従業員の住居費を補助する制度は人気が高く、適切に運用すれば福利厚生費として認められます。
社宅制度を導入する場合、一般的には会社が家賃の50%程度を負担する形が多く見られます。税務上も、50%以内の会社負担であれば「経済的利益の供与」とされず、非課税として認められる可能性が高くなります。
家賃補助を支給する場合も、全従業員に対して公平な条件で支給されているかが重要です。支給額は月額2〜3万円程度が一般的な目安とされ、業界や地域の住宅事情によって調整するとよいでしょう。
2 通勤手当
通勤手当は、支給額が一定の範囲内であれば非課税となります。
所得税法で定められている通勤手当の非課税限度額は、通勤手段や距離に応じて異なります。例えば、公共交通機関を利用する場合、合理的な経路および方法による運賃等の額が、1か月当たり15万円を超える場合には、15万円が非課税となる限度額となります。
3 食事補助(社員食堂・食券)
従業員の健康維持や生活支援を目的とした食事補助も、適切に制度化されていれば福利厚生費として認められます。
国税庁の通達では、会社が従業員に対して食事を提供し、そのうちの一部を従業員が負担する場合、会社負担分が「1食あたり350円以下」であれば非課税とされています。社員食堂を運営する場合や、提携先の飲食店で利用できる食券などを提供する場合、この350円のルールを目安に設定することで、税務上のリスクを抑えることが可能です。
4 慰安旅行・レクリエーション
社員旅行や運動会、レクリエーションなどは、職場の雰囲気を良くし、チームビルディングにも効果的な福利厚生です。
福利厚生としての慰安旅行は、「1人当たり年間10万円以下」が一つの目安です。これはあくまで慣習的な基準ですが、これを大きく超えると税務署から「給与」と見なされる可能性が高くなります。
税務上、社員旅行が福利厚生費として認められるには、「旅行日数が2泊3日以内」「全従業員の50%以上が参加していること」が条件とされています。この条件を満たさない場合、旅行費用は給与として課税対象になるおそれがあります。
5 健康診断・人間ドック
従業員の健康維持は、企業の責任でもあり、定期的な健康診断や人間ドックの費用は福利厚生費として計上可能です。
法定の健康診断にかかる費用は、全額を会社負担としても課税されません。さらに、人間ドックやオプション検査など、法定外の検診についても、業務上の必要性があれば福利厚生費として経費計上することが可能です。費用の目安としては1人あたり3万〜5万円程度であれば、実務上も問題となりにくいとされています。
6 研修・資格取得支援
従業員のスキルアップやキャリア支援を目的とした研修制度も、福利厚生の一環として評価されます。
資格取得支援制度を設ける際には、その資格が業務に直接関係しているかどうかが重要です。例えば、営業職に対するファイナンシャルプランナー資格、経理職に対する簿記検定などは、業務との関連性が明確であるため、会社負担で受験料や研修費を支給しても福利厚生費として認められます。
福利厚生費を適切に活用するポイント
福利厚生費は、適切な制度設計と運用が求められます。ここでは税務上のリスクを避けつつ、最大限に活用するための3つの実践ポイントをご紹介します。
1社内規程の整備と運用管理
福利厚生制度を導入する際は、必ず社内規程として明文化し、従業員にも共有しましょう。規程には対象者、支給条件、上限額などを明記し、実態と規程が一致するように運用することが大切です。実施状況の記録や証拠(領収書・出席簿など)を適切に保管することも重要です。
2給与との区別を明確に
「福利厚生費として処理していたが、実は実質的に給与だった」という指摘は、税務調査でよくあるトラブルです。支給目的を明確にし、従業員個人の裁量で使用できる自由度が低い制度設計にしましょう。例えば、現金での支給ではなく、サービスの提供やチケット制にすることで「給与」との区別が明確になります。
3自社に適した制度を導入
他社の福利厚生制度を参考にすることは有効ですが、業種や企業規模によって適切な制度は異なります。自社のニーズや財務状況に合った制度をカスタマイズして導入しましょう。従業員へのヒアリングやアンケートを通じてニーズを把握するのも効果的です。
まとめ
福利厚生費は、従業員の満足度向上と企業の節税対策に役立つ重要な制度です。法的に明確な上限はありませんが、社内規定を整備し、業界水準や過去事例を参考にしながら、合理的な範囲で運用することが大切です。
企業の財務状況に応じた継続可能な制度設計を心がけ、会社と従業員がともに恩恵を受けられる福利厚生を目指しましょう。