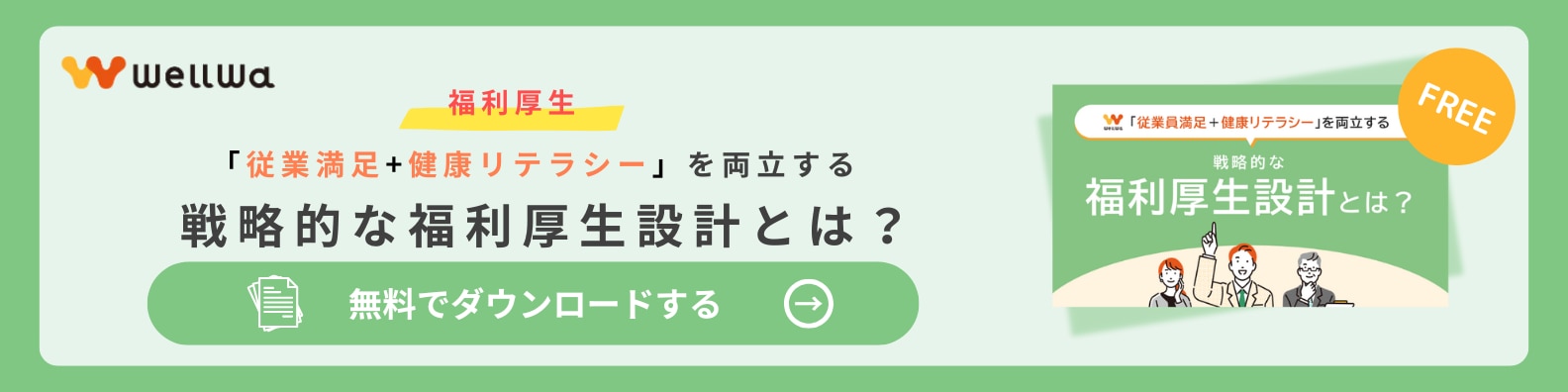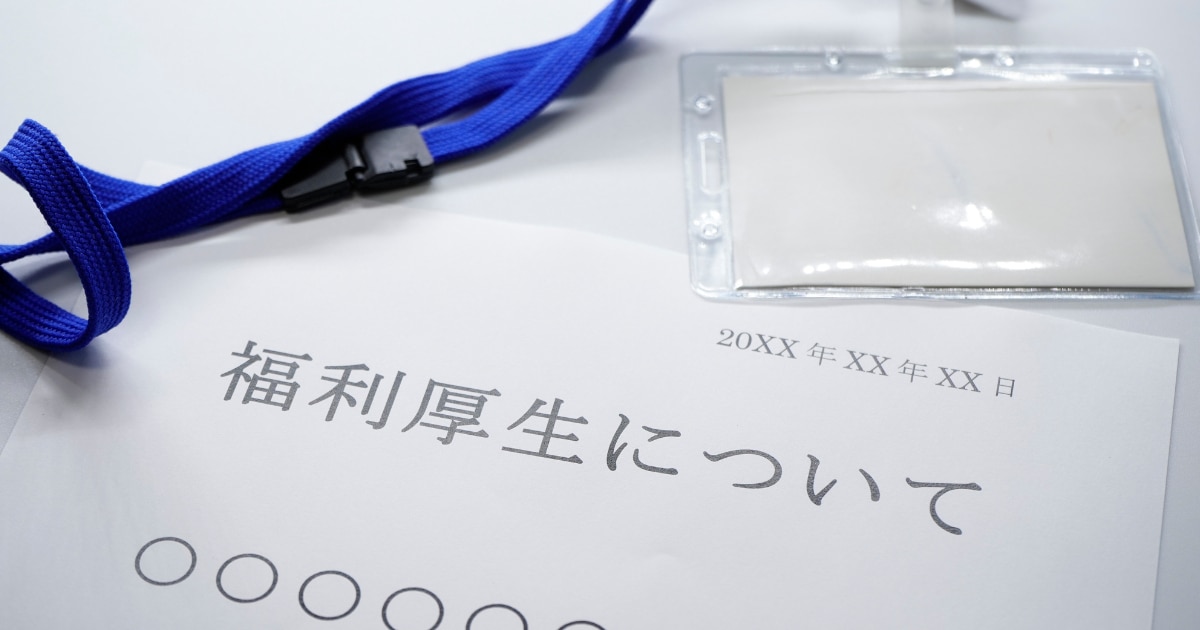
福利厚生にはどんな種類がある?分かりやすく解説
企業が従業員の働きやすさや満足度向上のために提供する「福利厚生」。その種類は多岐にわたり、自社に導入されている制度が一般的かどうか気になる方も多いのではないでしょうか。この記事では、福利厚生の基本から、主な種類と具体例をわかりやすく解説します。
目次[非表示]
- 1.福利厚生とは?
- 2.福利厚生の主な種類と具体例
- 2.1.【法定福利厚生】(法律で義務付けられているもの)
- 2.2.【法定外福利厚生】(企業が任意で提供するもの)
- 2.2.1.1. 住居関連
- 2.2.2.2. 健康・医療サポート
- 2.2.3.3. 育児・介護支援
- 2.2.4.4. 教育・自己啓発支援
- 2.2.5.5. レジャー・娯楽
- 2.2.6.6. 食事関連
- 2.2.7.7. 交通費補助
- 2.2.8.8. 特別休暇制度(誕生日休暇、リフレッシュ休暇など)
- 3.福利厚生のメリット
- 4.企業が福利厚生を選ぶ際のポイント
- 4.1.1社員のニーズを把握する
- 4.2.2企業の理念や文化に合った福利厚生を整える
- 4.3.3コストと効果のバランスを意識する
- 5.まとめ
福利厚生とは?
福利厚生は、企業が従業員に対して提供する給与以外の報酬やサービスの総称です。ここではまず、企業が法的に提供を義務づけられている「法定福利厚生」と、企業が任意で導入する「法定外福利厚生」の違いについて説明します。
「法定福利厚生」と「法定外福利厚生」の違い
福利厚生には、大きく分けて「法定福利厚生」と「法定外福利厚生」の2種類があります。法定福利厚生は法律により企業に提供が義務づけられている制度で、社会保険制度などが該当します。
一方、法定外福利厚生は企業が任意で導入する制度で、住宅手当や食事補助、健康診断など多岐にわたります。法定外福利厚生は企業ごとの特徴が出やすく、従業員満足度に直結しやすいため、他社との差別化要素としても活用されています。
福利厚生の主な種類と具体例
ここでは、福利厚生の代表的な種類について、法定福利厚生と法定外福利厚生に分けて、それぞれの特徴と具体的な制度を紹介します。
【法定福利厚生】(法律で義務付けられているもの)
1. 健康保険
健康保険は、従業員が病気やケガで医療機関を利用した際に、医療費の一部を保険でカバーする制度です。健康保険料は会社が半分を負担します。また、出産手当金や傷病手当金などの給付も含まれ、生活の保障という観点からも重要な役割を果たしています。
2. 厚生年金保険
厚生年金保険は、老後の年金受給を目的とした公的年金制度の一部で、保険料は会社が半分負担します。国民年金に上乗せされる形で支給されるため、将来の年金受給額を増やす役割があります。
3. 雇用保険
雇用保険は、失業した際に一定期間給付金を受け取れる制度で、再就職までの生活をサポートする役割があります。また、育児休業や介護休業を取得する際にも給付金が支給されるなど、生活の変化に対応した保障も含まれています。
4. 労災保険
労災保険は、業務中や通勤途中に発生した事故や疾病に対して、治療費や休業補償などを提供する制度です。全額を企業が負担するため、従業員は保険料を支払う必要はありません。労働者の安全と安心を守るため、業種にかかわらずすべての企業に加入が義務付けられています。
5. 介護保険
介護保険は、40歳以上の従業員が対象となる保険制度で、要介護状態になった場合に必要なサービスを受けられる制度です。保険料は会社が半分負担します。
6. 子ども・子育て拠出金
子ども・子育て拠出金は、次世代育成支援の一環としてすべての企業に課される制度で、保育園や幼児教育の充実を目的としています。拠出金は全額を会社が負担し、子育て世帯を支援する施策に充てられます。
【法定外福利厚生】(企業が任意で提供するもの)
1. 住居関連
社宅・寮
企業が用意する社宅や寮は、特に新卒社員や単身赴任者にとって住居費を抑える大きなメリットとなります。また社員同士の交流促進や、離職防止にもつながる制度として導入されている企業も多く見られます。
住宅手当
住宅手当は、従業員の家賃や住宅ローンの一部を補助する制度です。都市部など住宅費の高い地域では、生活コストを軽減するために非常に重要な福利厚生とされています。一定の条件(扶養家族の有無、勤務地など)に応じて金額が設定される場合が多く、従業員満足度の向上につながります。
2. 健康・医療サポート
健康診断
企業は従業員に対して年1回以上の定期健康診断を実施することが義務づけられていますが、それに加えて再検査や人間ドック費用の補助を行う企業もあります。従業員の健康管理を促進し、病気の早期発見や予防につなげるための重要な取り組みです。
インフルエンザ予防接種補助
インフルエンザ予防接種費用を全額または一部補助する制度は、季節性の感染症対策として有効です。集団感染を防ぐことで業務への支障を最小限に抑えるとともに、従業員の健康意識の向上にも寄与します。
3. 育児・介護支援
育児休暇制度
育児休暇は、出産後に一定期間仕事を休み、子育てに専念できる制度です。法定の制度に加えて、期間延長や復職支援など独自のサポートを行う企業も増えています。
託児所の設置
企業内に託児施設を設けることで、働く親が安心して子どもを預けられる環境を提供します。特に女性の社会進出や育児中の時短勤務支援の観点から注目されており、育児と仕事の両立をサポートする職場環境づくりの重要な取り組みです。
4. 教育・自己啓発支援
資格取得支援
業務に関連する資格の取得費用を一部または全額補助する制度は、従業員のスキルアップを後押しするものです。学習意欲の高い人材の育成やキャリア形成支援につながり、企業全体の競争力向上にも効果的です。
セミナー参加費補助
業務知識の習得やトレンド把握のためのセミナーや講習会の参加費を企業が補助する制度です。従業員の成長機会を増やし、自己啓発の後押しとなるため、意欲ある人材確保の一助となります。
5. レジャー・娯楽
スポーツジム利用補助
従業員の健康増進を目的として、スポーツジムの月会費や利用料金を補助する制度です。運動習慣の定着を促し、健康経営の一環として導入する企業が増えています。
社員旅行
社員旅行は、リフレッシュやチームビルディングの機会として人気の福利厚生です。非日常的な体験を共有することで、社内コミュニケーションの活性化やモチベーション向上にもつながります。
6. 食事関連
社食
企業内に食堂を設け、低価格または無料で食事を提供する制度です。健康的な食事をとることができるだけでなく、昼食時間の有効活用や従業員同士の交流促進にも貢献します。
ランチ補助
外食や弁当購入に対する金銭的な支援を行う制度で、社食がない企業にとっても導入しやすい福利厚生です。毎日の食費負担を軽減できるため、生活支援の観点でも有効です。
7. 交通費補助
通勤手当は最も代表的な法定外福利厚生の一つです。通勤にかかる交通費の全額または一部を支給することで、公共交通機関を利用する従業員の経済的負担を軽減します。
8. 特別休暇制度(誕生日休暇、リフレッシュ休暇など)
通常の有給休暇とは別に、特別な理由で取得できる休暇制度です。誕生日休暇やリフレッシュ休暇、ボランティア休暇など多彩な制度があり、心身のリフレッシュや社会貢献を促すことができます。
福利厚生のメリット
充実した福利厚生を導入することで、従業員の満足度やモチベーションの向上、離職率の低下など様々なメリットがあります。具体的に見ていきましょう。
【従業員側のメリット】働きやすさ向上、モチベーションアップ、生活の質向上
福利厚生が整っている企業では、従業員の生活をサポートする仕組みがあるため、安心して働くことができます。
例えば、住宅手当や交通費支給、健康診断や育児支援などは、日常の負担軽減やライフイベントへの対応に役立ちます。
これにより、働きやすい環境が整い、モチベーションの向上やワークライフバランスの実現が期待できます。福利厚生は、従業員の生活の質を底上げする大切な要素といえるでしょう。
【企業側のメリット】人材確保、離職率低下、企業イメージの向上
企業にとっても、福利厚生は重要な成長戦略の一部です。採用面では、求職者にとって福利厚生の充実は企業選びの重要な判断材料となるため、優秀な人材確保につながります。
また、従業員満足度の向上は定着率の改善にも効果的で、離職率の低下につながります。健康経営や子育て支援など、多様化する従業員のニーズに対応した福利厚生を取り入れることで、企業イメージの向上にも寄与します。
企業が福利厚生を選ぶ際のポイント
福利厚生は単に種類を増やせばよいというものではありません。企業が自社に合った福利厚生を選定・導入するためには、いくつかの視点が重要になります。
1社員のニーズを把握する
最も大切なのは、実際に福利厚生を利用する従業員のニーズを把握することです。アンケート調査やヒアリングを通じて、どのようなサポートが求められているのかを明らかにしましょう。若手社員には住宅手当や教育支援、子育て世代には育児休暇や時短勤務、ベテラン社員には介護支援など、年代やライフステージによってニーズは異なります。
2企業の理念や文化に合った福利厚生を整える
福利厚生は、企業の経営理念やカルチャーに沿ったものであることが重要です。たとえば「健康経営」を掲げる企業であれば、運動促進やメンタルケアなどの健康支援制度がマッチするでしょう。また働き方の多様化を推進する企業では、リモートワーク支援やフレックスタイム制度などが有効です。企業の掲げる価値観を体現する制度は、従業員へのメッセージとなり、組織と個人を結ぶ絆を深めていきます。
3コストと効果のバランスを意識する
福利厚生の導入には当然コストがかかるため、導入する際には費用対効果を考えることも大切です。予算内でできる工夫をしつつ、利用率や満足度を定期的に評価し、効果が薄い制度は見直す柔軟性も必要です。外部サービスの活用やパッケージ型の福利厚生代行サービスを利用するのも、コストを抑えながら幅広い制度を提供する手段になるでしょう。
まとめ
自身の働き方やライフスタイルに合った福利厚生の重要性
福利厚生は、企業が提供する「働く人への思いやり」の形です。自分のライフスタイルや働き方に合った福利厚生があることで、日々の仕事の充実度や生活の安定感が大きく変わります。仕事だけでなく、生活全体の質を上げるためにも、福利厚生の内容はしっかり確認しておきたいポイントです。