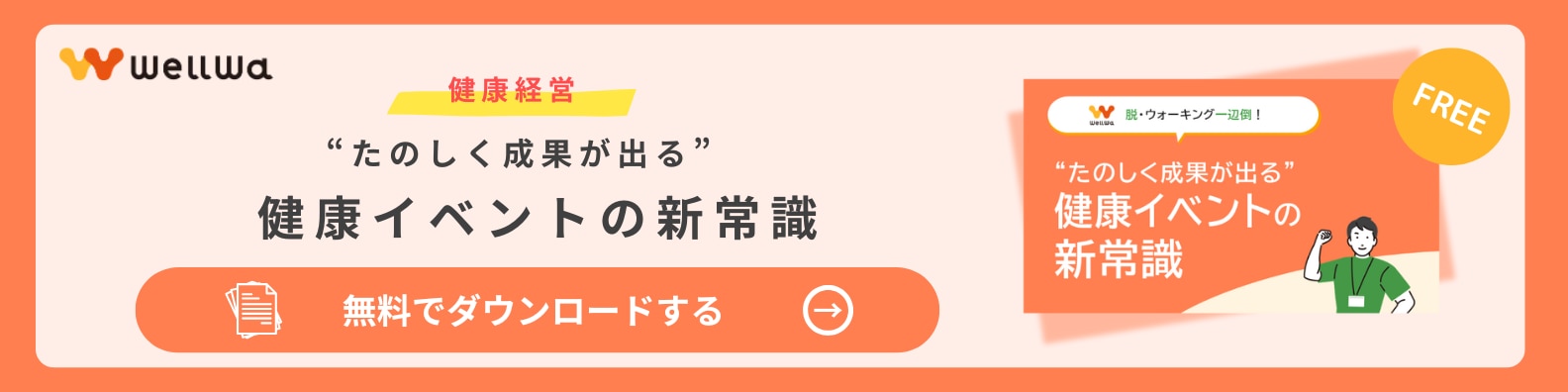福利厚生として運動施策を導入するメリットとは?おすすめ施策と注意点を解説!
働き方改革や健康経営の流れの中で、従業員の健康づくりに取り組む企業が増えています。特に注目されているのが、福利厚生としての「運動施策」です。この記事では、企業が運動施策を導入するメリットや実施方法、注意点について、担当者の視点でわかりやすく解説します。
目次[非表示]
なぜ福利厚生として運動施策が注目されているのか?
健康経営の実現には、従業員の健康促進が欠かせません。その一環として、企業による「運動施策」が注目を集めています。背景には、運動不足による健康リスクや生産性低下といった課題があり、それを解決する手段として、福利厚生を活用する動きが広がっています。
運動不足が健康や生産性に与える影響
デスクワーク中心の働き方による運動不足の増加
現代のオフィスワーカーの多くは、デスクワーク中心の業務スタイルです。リモートワークの普及により通勤や移動も減り、運動量はますます減少傾向にあります。こうした働き方は、筋力低下や体力の低下、さらには血行不良などの健康問題を引き起こす要因となっています。
健康リスク(生活習慣病・メンタル不調)の高まり
運動不足が続くと、肥満や高血圧、糖尿病といった生活習慣病のリスクが高まります。また、適度な運動にはストレス解消や気分の安定といったメンタルヘルスへの効果もあるため、運動をしない生活はうつ病や不安障害などのリスクを増加させる要因にもなります。
労働生産性の低下や医療費負担の増加につながる
健康状態が悪化すれば、体調不良による欠勤や休職のリスクが高まり、企業の業務効率や生産性にも影響します。さらに、企業が負担する医療費や健康保険料も増加することから、従業員の健康管理は企業の経営課題としても重要視されています。
健康経営の一環としての運動施策
企業の「健康経営優良法人」認定にもつながる
経済産業省が推進する「健康経営優良法人認定制度」では、従業員の健康管理に積極的に取り組む企業が認定されます。運動施策の導入はその評価項目のひとつであり、社内外への信頼性向上や企業ブランディングにも寄与します。
従業員の健康維持・向上が、企業全体の成長につながる
従業員の健康が維持されることで、欠勤や離職の減少、業務パフォーマンスの向上が期待できます。結果として企業の生産性やチームの活力が向上し、健全な組織づくりの土台となります。運動施策はその中心的な取り組みとして、ますます重要性を増しています。
福利厚生として運動施策を導入するメリット
運動施策は、単なる健康対策にとどまらず、業績向上や人材戦略にも寄与します。ここでは、企業が得られる主な4つのメリットを解説します。
1従業員の健康増進と医療費削減
運動習慣を促進することで、生活習慣病(肥満・糖尿病・高血圧など)を予防
定期的な運動には、肥満防止や血糖値・血圧のコントロール、筋力維持など、生活習慣病の予防に効果があることが多くの研究で証明されています。企業が運動施策を導入することで、運動習慣が身に付きやすくなり、健康リスクを大幅に減少させることができます。
企業の医療費負担の軽減につながる
従業員の健康状態が改善されると、病院受診や治療にかかるコストが減少し、結果として企業が負担する健康保険料や医療費補助も削減されます。中長期的には経済的メリットが大きく、経営面から見ても非常に合理的な施策といえるでしょう。
2業務パフォーマンスの向上
運動によるリフレッシュ効果で集中力・生産性アップ
軽い運動でも、脳内に「幸せホルモン」と呼ばれるエンドルフィンやセロトニンが分泌され、気分のリフレッシュにつながります。これにより、業務中のマンネリ化や疲労感が解消され、再び高い集中力をもって仕事に取り組める状態をつくり出します。運動の時間を「生産性の敵」と捉えるのではなく、「集中力を回復させる戦略的休憩」として設計することが鍵です。
ストレス軽減でメンタルヘルス向上 → 休職や離職の防止
運動には、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を抑える作用があります。継続的な運動習慣をサポートすることで、従業員の不安や抑うつリスクを下げ、メンタル不調による休職・離職の予防につながります。特に、メンタル不調が「見えにくい」オフィス環境では、運動を通じて自律神経を整えることが効果的なセルフケアとなります。
3社員のモチベーション・エンゲージメント向上
運動を通じた社内コミュニケーションの活性化
チームでのウォーキングチャレンジや、ヨガ・ストレッチのオンラインクラスなど、運動をきっかけにした「ゆるいつながり」が、部署を越えたコミュニケーションの促進につながります。特にリモートワーク下では、偶発的な会話の機会が減るため、こうした非業務的な交流は、組織の一体感を保つうえで非常に有効です。
福利厚生が充実することで、企業への満足度・帰属意識が高まる
福利厚生としての運動施策は、単なる健康支援を超えて、「この会社にいて良かった」と思える要素になります。従業員のライフスタイルや価値観に寄り添った施策を設計することで、企業への愛着や帰属意識が醸成され、優秀な人材の定着率向上にもつながります。また、採用時のアピールポイントとしても有効です。
福利厚生としての運動施策の種類と選び方
運動施策を導入する際には、企業文化や社員のニーズに合った形を選ぶことが重要です。ここでは代表的な施策の例と、導入する際のポイントを紹介します。
1 企業負担型(無料・補助型)
スポーツジム・フィットネスクラブの法人契約
企業がスポーツジムと法人契約を結び、従業員が無料または割引料金で利用できる制度です。全国展開のフィットネスチェーンと提携すれば、出張時や自宅近くでも利用可能で利便性が高まります。通いやすい環境を整えることで、継続的な運動習慣の促進につながります。
オフィス内運動設備の設置
オフィスに簡易的なジムスペースやストレッチコーナー、バランスボールなどを設置する方法もあります。昼休みや就業前後に気軽に利用でき、運動へのハードルを下げる効果があります。省スペースでも導入可能で、社員のリフレッシュにも効果的です。
ヨガ・ピラティス・ストレッチ講座の実施
インストラクターを招いて、オフィス内やオンラインで定期的にレッスンを実施する方法です。初心者でも取り組みやすく、運動が苦手な社員にも反響が良いのが特徴です。メンタル面にも効果があり、ストレス緩和や集中力向上が期待できます。
2インセンティブ型(ポイント・報酬制度)
歩数・運動量に応じたポイント付与制度
スマートフォンや活動量計で日々の歩数や運動量を記録し、それに応じてポイントを付与する制度です。獲得したポイントは、社内通貨や商品と交換できるようにすることで、モチベーション向上につながります。
健康管理アプリと連携し、目標達成でインセンティブ(社内ポイント・クーポンなど)を提供
専用の健康管理アプリと連動させ、運動や健康目標の達成に応じて、社内ポイントやクーポンなどの特典を提供する仕組みです。可視化・評価されることで、従業員の行動変容を促しやすくなります。データを蓄積することで、健康経営の効果測定にも活用できます。
健康チャレンジイベントの開催
部署対抗のウォーキングイベントや運動チャレンジを定期的に実施することで、チームの一体感や参加意識が高まります。イベント形式にすることで、普段運動しない社員も楽しみながら参加しやすくなり、健康への関心を広げるきっかけにもなります。
3社員の自主性を尊重した選択型
カフェテリアプランで運動系サービスを選択可能にする
ポイント制のカフェテリアプランに運動関連サービスを含めることで、従業員が自分に合った運動施策を選択できます。フィットネスだけでなく、スポーツ観戦やアウトドア体験など、広義の「アクティブ」な選択肢も含めることで、満足度を高めることができます。
ヨガ・ジム・ランニングクラブなど、個人に合った運動施策を自由に選べる
運動習慣やライフスタイルに応じて、従業員が利用したいサービスを自由に選べるようにすることで、参加率や継続率が高まります。特にランニングや自転車など、趣味と健康を兼ねる活動は、導入の選択肢が広がります。
福利厚生アプリを活用し、運動プログラムを提供
オンラインで参加できるストレッチ・筋トレ・ダンスなどの動画コンテンツを、福利厚生アプリを通じて提供する方法も人気です。出勤・在宅に関わらず、いつでも好きな時間に取り組める利便性があり、運動が苦手な社員にもハードルが低くなります。
従業員の健康行動でポイントがたまる健康特化型の福利厚生アプリとは?

最近では、従業員の健康行動を可視化し、報酬やインセンティブを通じて促進する「健康特化型の福利厚生サービス」が注目を集めています。これらは健康管理アプリやウェアラブルデバイスと連携し、日々の歩数や運動習慣をスコア化。その結果に応じて社内ポイントがたまる仕組みを提供します。
従業員はゲーム感覚で取り組め、健康への意識を自然に高めることができ、企業としても参加率や成果をリアルタイムで把握できるメリットが得られます。一部のサービスでは、健康診断結果と連動したリスク評価機能や、産業医との連携機能もあり、健康経営全体の効率化と高度化が図れます。従来の施策では補完できなかった「行動変容」へのアプローチが可能な点で、今後ますます導入が進むと考えられます。
〈キリンビバレッジが提供している福利厚生ソリューションとは〉
まとめ
運動施策は、従業員の健康増進にとどまらず、生産性の向上、医療費削減、企業ブランディングなど、さまざまな面で企業に利益をもたらします。導入の際には、企業の規模や文化に応じて適切な方法を選び、従業員が無理なく継続できる環境を整えることが重要です。今後も、運動を軸とした福利厚生は、健康経営の中核としてその役割を拡大していくでしょう。