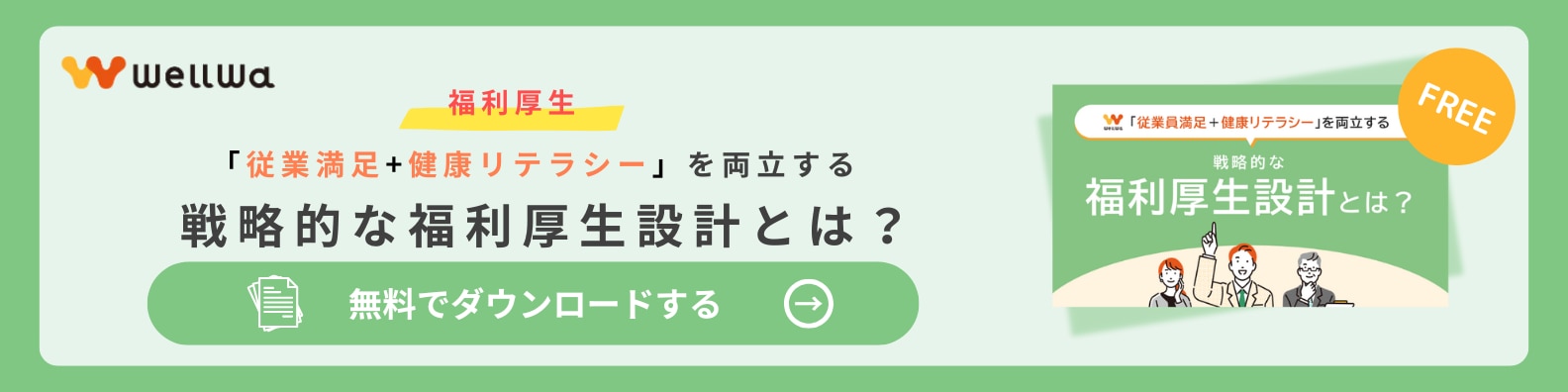ウェルビーイングとは?人事が知るべき意味・企業メリット・推進ポイントをわかりやすく解説
企業の人事・経営戦略において、従業員のウェルビーイングは生産性向上や離職率低下に直結します。本記事では、ウェルビーイングの構成要素や推進ポイントを解説します。
目次[非表示]
- 1.ウェルビーイングとは?その本質と注目される背景
- 1.1.ウェルビーイングの基本的な意味と定義(WHO・OECDなど)
- 1.2.「幸福」や「健康」との違いとは
- 1.3.今なぜ企業でウェルビーイングが注目されているのか(人的資本経営・SDGsとの関連)
- 2.人事・経営にとっての「ウェルビーイング」の重要性と実践方法
- 3.ウェルビーイングの構成要素とは?
- 4.人事主導でウェルビーイングを推進するためのポイント
- 4.1.推進していく上での社内基盤とマインドセット
- 4.2.実践施策の例(柔軟な働き方、メンタルサポート、キャリア支援など)
- 4.3.測定と改善の仕組み(KPI/ROI・従業員サーベイ・ストレスチェック)
- 5.自社にあったウェルビーイング戦略を設計するには?
- 5.1.ペルソナ分析と従業員の声の活かし方
- 5.2.経営層・現場の巻き込み方
- 5.3.自社らしい「ウェルビーイングのかたち」とは
- 6.まとめ|人事担当者が今からできること
ウェルビーイングとは?その本質と注目される背景
企業の人事・経営戦略において、従業員のウェルビーイングは生産性向上や離職率低下に直結します。本記事では、ウェルビーイングの構成要素や推進ポイントを解説します。
ウェルビーイングの基本的な意味と定義(WHO・OECDなど)
「ウェルビーイング(Well-being)」とは、直訳で「良好な状態」「幸福」などを意味しますが、単なる感情的な幸福感を超えた包括的な概念です。世界保健機関(WHO)は、ウェルビーイングを「肉体的、精神的、社会的に完全に良好な状態」と定義しており、単なる「病気でないこと」以上の積極的な健康を含んでいます。また、経済協力開発機構(OECD)も、個人および社会の両面から、生活の質や満足度を重視する指標としてウェルビーイングを位置づけています。
「幸福」や「健康」との違いとは
「健康」や「幸福」との違いは、ウェルビーイングが心身の状態のみならず社会的な良好さを同時に含んでいる点にあります。例えば、健康診断の数値が良好でも、職場で強いストレスを感じている場合はウェルビーイングが実現されているとは言えません。また、一時的な喜び(例:ご褒美スイーツでの一時的な幸福感)とは異なり、ウェルビーイングは人生全体を通じて持続的に良好な状態を志向します。
今なぜ企業でウェルビーイングが注目されているのか(人的資本経営・SDGsとの関連)
昨今、企業がウェルビーイングに取り組むべき理由は大きく二つあります。一つは、人的資本経営の加速です。従業員の健康・働きがいを「資本」と捉え、持続的な企業価値向上を図る流れが強まっています。もう一つは、SDGs(持続可能な開発目標)との接続です。特に目標3「すべての人に健康と福祉を」や目標8「働きがいも経済成長も」と深くリンクし、社会的要請が高まっています。
人事・経営にとっての「ウェルビーイング」の重要性と実践方法
従業員の幸福と企業業績の相関関係(生産性・離職率・エンゲージメント)
近年の研究では、ウェルビーイングの高い従業員ほど生産性が高く、離職率が低いことが明らかになっています。たとえばギャラップ社の調査によれば、ウェルビーイングが高い従業員はエンゲージメントが高く、業績向上に直結する行動(顧客対応・イノベーション提案など)を多くとる傾向があります。ウェルビーイングは福利厚生の充実のみならず、戦略的な投資対象として注目されているのです。
出典:ギャラップ社「Japan's Workplace Wellbeing Woes Continue」
経営戦略とウェルビーイングの接続点(ESG・人的資本開示対応)
日本でも人的資本の情報開示が義務化されつつあり、ウェルビーイング推進はESG投資家や採用市場において重要な評価指標となっています。
従業員の持続的な成長・健康を支援することは、企業ブランドの向上にもつながります。
中小企業にとってのメリットと推進意義
大企業のみならず、中小企業にとっても、ウェルビーイング推進は従業員の定着率向上や採用力アップに直結します。特にリソースの限られた中小企業では、「一人ひとりの健康・モチベーション」がそのまま組織力に直結するため、費用対効果の高い投資対象となるでしょう。
ウェルビーイングの構成要素とは?
PERMAモデル(ポジティブ心理学の視点)
ウェルビーイングの構成要素を体系的に示した理論の一つが、マーティン・セリグマン博士によるPERMAモデルです。PERMAは以下の5つで構成されます。
- P:Positive Emotion(前向きな感情)
- E:Engagement(没頭・積極的な関与)
- R:Relationships(良好な人間関係)
- M:Meaning(意味・意義)
- A:Accomplishment(達成感)
企業施策では、これらを意識してウェルビーイング推進を図ることが効果的です。
ギャラップ社の5つのウェルビーイング要素
ギャラップ社は、さらに実務的な観点からウェルビーイングを5要素で定義しています。
- キャリアウェルビーイング(仕事に満足している)
- ソーシャルウェルビーイング(良好な人間関係がある)
- フィナンシャルウェルビーイング(経済的安定がある)
- フィジカルウェルビーイング(身体的健康を維持している)
- コミュニティウェルビーイング(安全で満足のいく環境での生活、地域社会への貢献)
これら5つをバランスよく高めることが、個人の持続的なウェルビーイングに繋がります。詳細は、ウェルビーイング5つの要素で確認できます。
日本企業で注目される独自要素(働き方・人間関係・キャリア視点)
日本企業においては、さらに働き方の柔軟性(リモート・副業推奨)、職場の心理的安全性、キャリア自律支援なども独自要素として重視されています。特に、上司との信頼関係やキャリアパスの見通しは、ウェルビーイング推進に強い影響を与えることがわかっています。こうした特性を踏まえた取り組みが、今後さらに求められるでしょう。
人事主導でウェルビーイングを推進するためのポイント
推進していく上での社内基盤とマインドセット
ウェルビーイング施策を成功させるには、施策開始前に社内基盤とマインドセットを醸成することが重要です。まず、経営層と人事部門で「なぜ今ウェルビーイングに取り組むのか」というビジョン・目的を明確化しましょう。施策の対象が「健康意識が高い一部の社員」にならないよう、全従業員を対象とする意識を持つことが欠かせません。 これにより、施策のブレや一過性を防ぐことができます。
実践施策の例(柔軟な働き方、メンタルサポート、キャリア支援など)
具体的な施策例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 柔軟な働き方:リモートワークやフレックスタイム制度の導入
- メンタルサポート:産業医面談、EAP(従業員支援プログラム)提供
- キャリア支援:キャリア面談制度、副業容認、社内公募制の拡充
これらは、従業員の身体・心・社会的な健康すべてを支えるものであり、ウェルビーイング推進に直結します。
測定と改善の仕組み(KPI/ROI・従業員サーベイ・ストレスチェック)
施策の持続性を高めるには、目標値の設定や改善の仕組みが不可欠です。 たとえば、
- KPI設定(例:エンゲージメントスコア向上率、離職率低下率)
- ROI可視化(健康投資効果の定量評価)
- 従業員サーベイ(四半期ごとの意識調査)
- ストレスチェック結果活用(部署別フィードバック)
を組み合わせ、PDCAサイクルを回す体制を整えましょう。
自社にあったウェルビーイング戦略を設計するには?
ペルソナ分析と従業員の声の活かし方
効果的な施策設計には、自社の従業員のリアルな実態把握が不可欠です。従業員アンケートやインタビューから年齢層、家族構成、キャリア志向などの傾向を把握し、それを基にペルソナ設計を行います。その上で、ニーズ・課題をより明確にしていくことが重要です。 これにより、施策の「押しつけ感」をなくし、当事者意識を醸成できます。
経営層・現場の巻き込み方
ウェルビーイング推進は、人事部門だけで完結しません。経営層には「企業価値向上」「人的資本開示対応」を、現場には「働きやすさ」「チーム力向上」に重点を置き、巻き込むアプローチが効果的です。それぞれに応じたメリット訴求で、施策を「みんなごと」にしていきましょう。
自社らしい「ウェルビーイングのかたち」とは
実情を考慮したうえで、最適な仕組みを構築することが成功への近道です。 たとえば、
- 製造業なら「体力づくり支援」が重要かもしれません。
- クリエイティブ職なら「心理的安全性の確保」が第一になるかもしれません。
自社の文化・事業特性に合った「ウェルビーイングのかたち」を設計することが成功への近道です。
まとめ|人事担当者が今からできること
この記事で解決した疑問と学びの振り返り
この記事では、「ウェルビーイングとは何か」という基本から、企業が取り組む意義・設計のポイントまで体系的に解説しました。ウェルビーイングは単なる健康施策ではなく、経営戦略の一部であることを再確認し、体系的に実践していくことが求められます。
まず最初に取り組むべき3つのアクション
- 社内ビジョンの明確化(なぜ取り組むのかを言語化)
- 従業員実態の可視化(アンケート・ペルソナ分析)
- スモールスタート施策の実行(できることから始める)
この3ステップで、着実なウェルビーイング推進が期待できます。
信頼されるウェルビーイング推進者になるために
最後に、重要なのは現場と対話を重ね、信頼を得る姿勢です。数値目標だけにとらわれず、「従業員一人ひとりの幸せ」を心から願うことが、ウェルビーイング推進者として不可欠です。