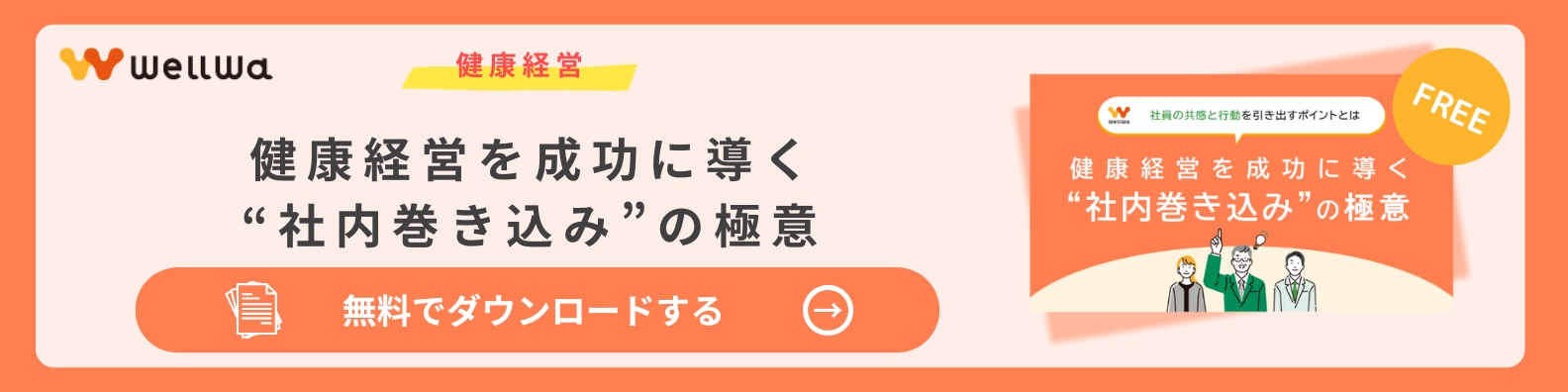「健康無関心層」への効果的アプローチとは?人事が抑えるべき戦略と実践ステップ
「健康施策に関心を示さない社員」へのアプローチに悩んでいませんか?本記事では、無関心層の心理と行動特性をふまえた戦略的なアプローチ方法、職場でできる実践ステップ、効果測定までをわかりやすく解説します。
目次[非表示]
なぜ健康に「無関心な層」が存在するのか?
企業が健康施策を推進する中で必ず直面する壁のひとつが、「健康無関心層」の存在です。どれだけ健康診断や運動促進プログラムを用意しても、一定数の社員が参加しない、関心を示さない現象は珍しくありません。この「届かなさ」は、一体どこから生まれるのでしょう。
厚生労働省が実施した「令和元年国民健康・栄養調査」によると、20歳以上の国民の約4人に1人が、食習慣または運動習慣の改善に「関心はあるが改善するつもりはない」と回答しています。
出典:厚生労働省「令和元年国民健康・栄養調査」
人事担当者にとって盲点になりやすいのが、無関心層の「本当の理由」です。単なる怠慢ではなく、健康施策への心理的ハードルや職場文化、過去の挫折経験など、根深い背景が影響していることが多いのです。この深層を理解することが、効果的アプローチの第一歩となります。
健康無関心層に共通する特徴と心理
無関心層の行動パターンを見ると、単なる「情報不足」だけでは説明できないケースが多く存在します。厚生労働省の調査では、健康行動の妨げになる理由として「仕事(家事・育児等)が忙しくて時間がない」(38.1%)という回答が最も多く、次いで「面倒くさい」(27.6%)が続いています。
出典:厚生労働省「令和元年国民健康・栄養調査」
また、職場環境そのものが健康を「義務」として押し付けてしまっている場合もあります。健診受診を義務化するだけで、なぜ健康が重要なのかを伝えない、運動イベントを「強制参加」にしてしまうといった施策の設計ミスが、かえって無関心層の反発や諦めを招いていることも少なくありません。
自己効力感ーーつまり「自分にもできる」という感覚が低いと、どんなに小さな健康行動でも「自分には無理だ」と感じてしまい、行動変容のチャンスを逃してしまいます。無関心層へのアプローチには、この心理的ハードルをどう下げるかが重要な鍵となります。
健康意識のセグメント分けとは?
無関心層への戦略を考えるうえで効果的なのが、社員を「健康意識レベル」でセグメント分けするアプローチです。ここで参考になるのが、厚生労働省の「e-ヘルスネット」でも紹介されている行動変容理論「トランスセオレティカルモデル(TTM)」です。このモデルでは、行動変容は「無関心期」「関心期」「準備期」「実行期」「維持期」というステージに分けられ、それぞれに適した支援が必要とされています。
企業で実践する場合、簡易的に「無関心層/意識低め層/関心層」に分類するのがおすすめです。健康診断受診状況、ストレスチェック受検率、簡易アンケート結果などを組み合わせて、社員の健康意識レベルを可視化してみましょう。
セグメントごとの特徴を把握したうえで、アプローチ方法を設計していくことが、効果的な健康施策推進のための重要な準備段階となります。無関心層に無理に「関心を持て」と迫るのではなく、それぞれの今いる場所に寄り添うアプローチが求められるのです。
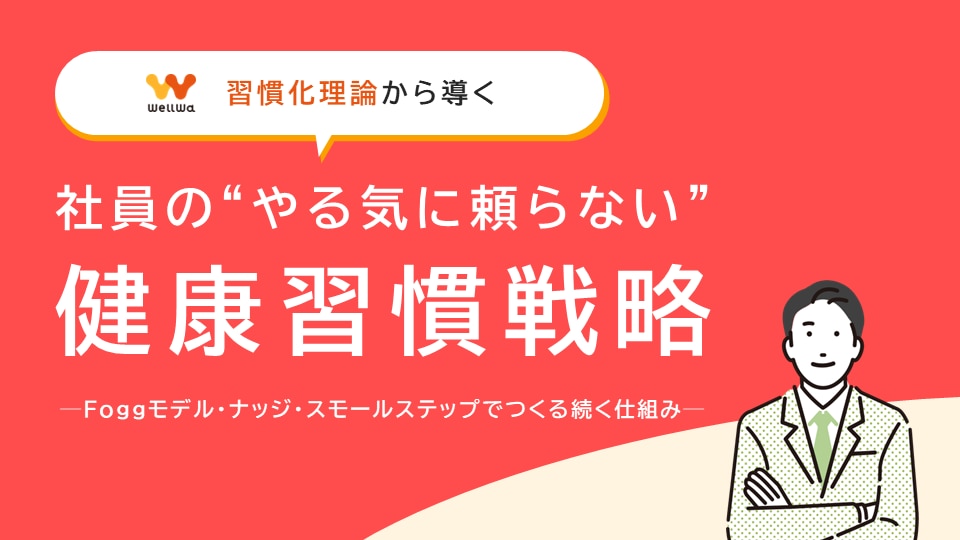
習慣化理論から導く、社員の「やる気に頼らない」健康習慣戦略
~ Foggモデル・ナッジ・スモールステップでつくる続く仕組み ~
【ダウンロードはこちらから】
健康無関心層を動かす5つのアプローチ戦略
無関心層に対して行動変容を促すには、単なる「啓発」ではなく、心理に寄り添った戦略的なアプローチが必要です。
1.ナッジ理論を活用した自然な誘導
「健康診断を受けた人には社食クーポンをプレゼント」といった設計により、強制ではなく自然な選択を促すことができます。意思決定のハードルを下げる仕掛けが鍵です。
2.効果的なインセンティブの設計
健康活動に応じたポイント付与、あるいは人事評価の加点項目として設定するなど、行動に対して小さなリターンを用意することで、参加のモチベーションを高めます。
3.関係性ベースのアプローチ
「みんなで歩数チャレンジ」や「チーム対抗健康イベント」など、個人ではなく「仲間と一緒に」取り組む設計にすると、無関心層も自然と巻き込まれやすくなります。
4.デジタルツールによるパーソナライズ
健康アプリなどで自分に合った目標設定や日々の小さな成功体験をサポートする仕組みを取り入れると、自己効力感向上にもつながります。無関心層に対しては「自然に、寄り添い、簡単に」できるツールが有効です。
5.環境から変えるアプローチ
オフィスに健康自販機を設置する、階段利用を促すポスターを掲示するなど、無意識のうちに健康行動を促す職場デザインを工夫することで、抵抗感なく行動変容を促せます。
成果を可視化する評価と報告
無関心層アプローチの成果を社内外に示す際は、「数字+ストーリー」で伝えることがポイントです。健康施策前後での健診受診率向上、歩数平均の増加率といった定量データに加え、参加した社員の声や変化した行動エピソードなどの定性情報も併せて報告すると説得力が高まります。
特に、社外への開示を意識する場合は、社員の健康増進が生産性向上や離職率低下につながったといった経営インパクトを整理し、エビデンスベースで提示することが重要です。健康施策が「自己満足」ではなく、「経営投資」であることを数字で語れるかどうかが、信頼獲得の分かれ目になります。
無関心層も楽しめるウェルビーイングアプリ「WellWa」

無関心層へのアプローチには、楽しみながら取り組める仕掛けが欠かせません。その点で、キリンが提供するアプリ「WellWa」は非常に効果的です。
WellWaでは、個人でもチームでも楽しめるプログラムが豊富に用意されています。歩数ランキングや部署対抗チャレンジなど、ゲーム感覚で健康行動を続けられる仕組みがあり、無関心層も自然に巻き込まれていきます。
さらに、健康活動に応じてポイントが貯まり、人気の「食の福利厚生」(スムージーといった飲料など)と交換できるシステムも魅力的です。「健康は義務」ではなく「ちょっと嬉しいこと」に変換する設計が、無関心層攻略の強い味方になります。
まとめ
健康に無関心な社員は、「無関心」なのではなく、「まだ可能性に気づいていない」だけかもしれません。適切なきっかけとサポートがあれば、誰もが小さな行動変容を起こすことができるのです。
焦らず、責めず、楽しみながら寄り添うこと。健康施策は、すべての社員の未来を支える投資であり、組織の持続的成長を支える力となります。
明日から小さな一歩を、一緒に始めてみましょう。