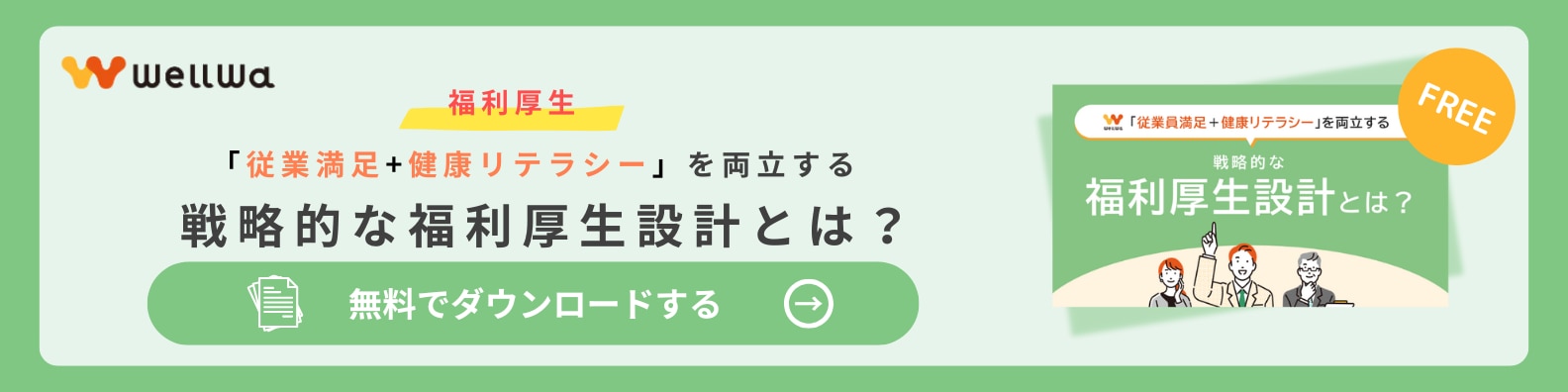今こそ見直す!ウェルビーイングを高める福利厚生とは?導入・改善・成功事例を徹底解説
ウェルビーイングを高めるために有効な福利厚生の導入・改善方法を企業の成功事例を交えながら5つのカテゴリに分けて紹介し、自社の制度を見直す際の留意点を解説します。
目次[非表示]
- 1.福利厚生とウェルビーイングの関係性|企業が果たす役割とは
- 2.ウェルビーイング経営に効く!5つの福利厚生施策
- 2.1.1.身体的ウェルビーイング施策(健康診断、フィットネス、食事補助)
- 2.2.2.精神的ウェルビーイング施策(メンタルヘルス支援、カウンセリング、ストレス対策)
- 2.3.3.社会的ウェルビーイング施策(社内コミュニケーション施策、ピアボーナス)
- 2.4.4.経済的ウェルビーイング施策(給与の最適化、家賃・通勤補助)
- 2.5.5.キャリア・自己実現に関する施策(リスキリング支援、副業解禁、キャリア相談)
- 3.自社に最適な福利厚生の選び方と導入のための3つのプロセス
- 4.ユニークで効果的なウェルビーイング施策
- 5.ウェルビーイングに関するよくある疑問とその解消法
- 6.ウェルビーイングを高める「WellWa」とは
- 7.まとめ|人事が取り組むべきウェルビーイング施策の重要性
福利厚生とウェルビーイングの関係性|企業が果たす役割とは
従来型福利厚生とウェルビーイング型福利厚生の違い
従来の福利厚生(住宅手当や通勤補助といった生活支援)は、主に金銭的支援が主流でした。しかし、現代に求められるのは、単なる経済的支援を超え、心理的安全性やワークライフバランス、ストレスマネジメントにまで踏み込んだウェルビーイング型福利厚生です。身体的、精神的、社会的側面すべてを網羅し、社員が主体的かつ前向きに働き続けられる環境をつくることが、企業に求められています。
ウェルビーイング施策が従業員定着率・エンゲージメントに与える影響
福利厚生をウェルビーイング視点で再設計することで、社員の定着率やエンゲージメント向上にも直結します。昇給や昇進だけでは、社員が求める価値や満足感をすべてカバーすることは困難です。働きがいや組織への愛着を醸成する仕組みとして、福利厚生の役割はますます重要性を増しています。特に若年層やZ世代は、企業選びにおいて「自分を大切にしてくれる会社か」を重視する傾向が強く、福利厚生の質が採用競争力にも影響を与えるようになりました。
人的資本開示におけるウェルビーイングの位置づけ
人的資本開示が求められる時代背景の中で、ウェルビーイングに関する取り組みは、開示対象項目として注目を集めています。健康支援やエンゲージメント向上施策の有無が、投資家や求職者からの評価に影響を与えるようになりました。福利厚生は単なるコストではなく、戦略的な投資と捉える視点が不可欠になっています。
ウェルビーイング経営に効く!5つの福利厚生施策
ウェルビーイングを高める福利厚生施策は、大きく5つのカテゴリに分類できます。基本的な特徴や概念を押さえておきましょう。
1.身体的ウェルビーイング施策(健康診断、フィットネス、食事補助)
定期健康診断やフィットネス補助、オフィス内のヘルシーランチ提供などが含まれます。社員の健康意識を高め、生活習慣病リスクを低減する基盤を整える施策です。
2.精神的ウェルビーイング施策(メンタルヘルス支援、カウンセリング、ストレス対策)
ストレスチェックの実施に加え、外部カウンセラーとの連携による相談窓口の設置、マインドフルネスプログラムの導入などが挙げられます。心の健康を守る施策を推進することは、エンゲージメントや生産性に直結するため、重要な投資となります。
3.社会的ウェルビーイング施策(社内コミュニケーション施策、ピアボーナス)
部門横断型の交流イベントや、社員同士を称え合うピアボーナス制度などが代表的な事例です。仕事上のつながりだけでなく、心理的な絆を深める仕組みが、組織全体の活性化を促します。
4.経済的ウェルビーイング施策(給与の最適化、家賃・通勤補助)
給与制度の透明化や最適化、家賃補助や通勤手当の拡充など、金銭面で生活の安定を支える施策も不可欠です。安心して働き続けることができる基盤を整えることで、離職防止にも寄与します。
5.キャリア・自己実現に関する施策(リスキリング支援、副業解禁、キャリア相談)
リスキリング支援制度や副業推奨制度、キャリア相談窓口の設置などもウェルビーイング施策の促進につながります。社員一人ひとりが長期的に成長できる環境を整えることは、組織全体の競争力向上に直結します。
自社に最適な福利厚生の選び方と導入のための3つのプロセス
1.現状分析と課題抽出(従業員アンケート・ヒアリング)
福利厚生施策を検討する際は、まず現状分析と課題抽出から始めることが基本です。社員アンケートやヒアリングを通じて、既存施策に対する満足度や利用実態、さらに潜在的なニーズを把握していきます。このプロセスを怠ると、ニーズと施策がかみ合わず、制度が形骸化し、期待した効果が得られないリスクがあります。
2.ペルソナ設計と世代別ニーズの可視化
次に、アンケート結果などを基にターゲットとする社員像(ペルソナ)を設計し、世代別・ライフステージ別に求められるサポート内容を可視化します。若手層とミドル層、子育て世代とシニア世代では、必要とする福利厚生の中身が大きく異なるため、細やかな設計が求められます。
3.施策の優先順位と経営層との合意形成(提案資料作成のコツ)
そして、施策を絞り込む際には、インパクト(効果の大きさ)と実現可能性(コスト・リソース)を軸に優先順位を整理します。経営層への提案資料には、具体的な数値やデータを用いながら施策の目的、期待できる効果、投資対効果(ROI)を明示し、経営の視点から納得感を得られるようなストーリーを構築することが成功のポイントとなります。
ユニークで効果的なウェルビーイング施策
導入事例(大企業・中小企業・スタートアップ企業での工夫)
ウェルビーイングを高める取り組みは、企業規模を問わずさまざまな形で進化しています。大企業では、専用アプリを活用して社員の運動習慣を促進したり、社内ポイントを貯めて健康関連グッズと交換できるプログラムを導入するケースが見られます。一方で、中小企業では、社員同士で感謝を伝え合うピアボーナス制度や、月1回のオンラインヨガセッションを実施するなど、コストを抑えながら効果的な施策を展開しています。スタートアップ企業では、フルリモート環境下でもつながりを感じられるよう、バーチャルウォーキングイベントや、雑談専用チャットチャンネルを活用するなどの取り組みが増えています。
コストを抑えるための工夫(補助金制度の活用など)
自治体の補助金制度など助成金を活用することで、低予算でも成果を得ることは可能です。例えば、健康経営推進のための助成金を利用して、ストレスチェックツールの導入や、オンラインフィットネスサービスとの提携費用を補填する企業もあります。小規模な取り組みでも、社員のウェルビーイング向上に大きく寄与します。
従業員から高評価を得た施策の3つの共通項
従業員から高評価を得た施策に共通するのは、押し付けにならず、社員自身が主体的に関わることができる仕掛けがあることです。「選択肢を提供する」「楽しさを演出する」「成果を可視化する」。この3つを意識するだけで、施策の受け入れ度は大きく変わります。
ウェルビーイングに関するよくある疑問とその解消法
どこまでやればいいの?|リソース別施策の考え方
ウェルビーイング施策に取り組もうとすると、「どこまでやればいいのか」と悩む声もありますが、すべてを一気に実現する必要はありません。自社のリソースに応じて、取り組むべき領域と施策を選び、段階的に導入・拡大することが成功への近道です。最初はできる範囲から始め、成功体験を積み重ねていきましょう。
使われないのでは?|利用率を高める方法
「せっかく制度を設けても使われないのでは」と懸念を抱く担当者も見られます。その原因は、多くの場合、施策内容と社員ニーズのズレ、または周知・浸透不足にあります。制度設計の段階から社員の声を吸い上げ、導入後もこまめなリマインドや体験共有を行うことで、利用率を確実に高めることができます。
費用がかさむのでは?|福利厚生を“投資”と捉える視点
さらに、「コストがかさむのでは」と心配されることもありますが、ウェルビーイング施策はコストではなく「投資」と捉えるべきです。生産性向上、離職率低下、採用力強化といったリターンを考慮すれば、中長期的には費用対効果が十分に期待できます。
ウェルビーイングを高める「WellWa」とは

全社員・個人で楽しめるプログラム設計
キリンが提供する「WellWa」は、ウェルビーイング施策をより身近に、楽しく推進するためのサービスです。特徴の一つは、全社員が個人でもチームでも楽しめるプログラム設計にあります。たとえば、部署対抗チャレンジや歩数ランキング機能を活用することで、日々の健康行動の促進につながり、社内コミュニケーションの活性化にも寄与します。
人気の「食の福利厚生」でポイント交換
さらに、WellWaでは健康行動によって貯まったポイントを、キリンの商品と交換できる「食の福利厚生」も提供しています。美味しく楽しく健康を意識できる仕組みが、社員のモチベーション向上に直結しています。
初期コストを抑えることができる置き型健康食品サービス「WellStock」

加えて、初期コストを抑えて導入できる置き型健康食品サービス「WellStock」もラインアップ。オフィスに手軽に健康食品を設置できるこのサービスは、従業員の食習慣改善を後押ししつつ、企業負担を最小限に抑えることが可能です。
まとめ|人事が取り組むべきウェルビーイング施策の重要性
企業と従業員をともに支える福利厚生の効果
ウェルビーイング施策は、社員の健康や幸福感を高めるだけでなく、組織全体のエンゲージメント向上、生産性改善、企業ブランディング強化という多方面のメリットをもたらします。人事が率先して取り組むことで、企業と従業員双方にとって持続可能な成長の基盤を築くことが可能です。
ウェルビーイング施策の最初のステップは?
最初の一歩としては、現場の声を吸い上げ、実現可能な範囲で施策を試してみることが重要です。初期段階で大規模な改革を目指すのではなく、小さな成功体験を積み重ねながら、徐々にウェルビーイング文化を育てていきましょう。
社内巻き込みのための効果的な提案方法
社内巻き込みを図る際には、経営層へのロジカルな提案と、現場社員への共感的なアプローチの両方が重要になります。人事がそのハブとなり、未来志向の組織づくりをリードしていきましょう。