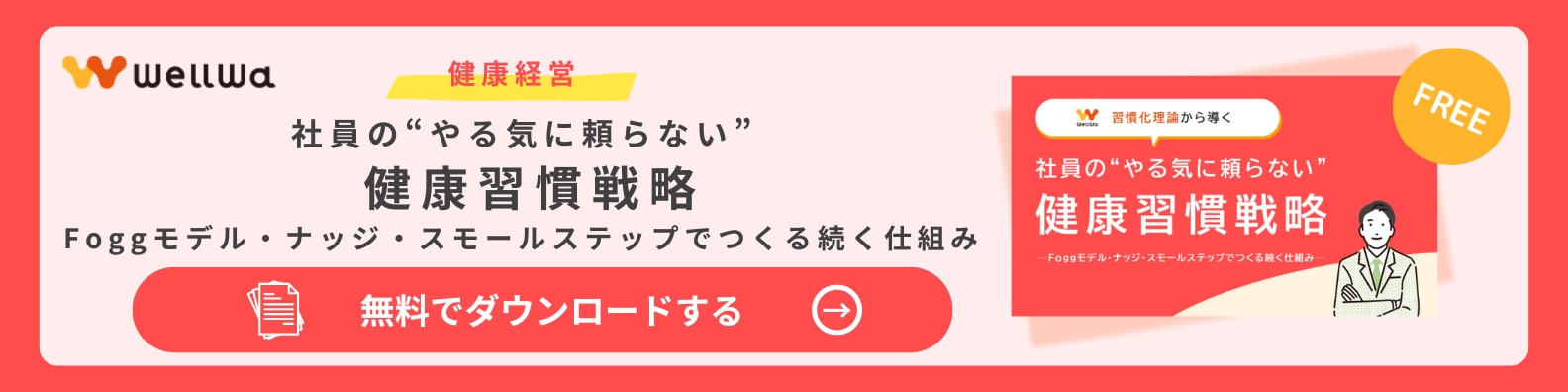ウェルビーイングと働き方の最前線:エンゲージメント・心理的安全性・企業文化まで徹底解説
企業の成長に不可欠なウェルビーイングに着目し、働き方改革、健康経営、心理的安全性など、現代企業が進めるべき施策について解説します。未来に向けた組織づくりに役立つポイントも併せて紹介します。
目次[非表示]
ウェルビーイングの定義と働き方改革との関係
近年、働き方改革や人的資本経営の流れの中で、ウェルビーイングという概念が急速に注目を集めています。ウェルビーイングとは、単なる健康維持に留まらず、身体的・精神的・社会的に良好な状態を目指す考え方です。この視点を働き方に取り入れることによって、社員一人ひとりのパフォーマンスを最大化し、組織の持続的成長に結びつける動きが加速しています。
働き方におけるウェルビーイングの重要性が高まる理由
各企業がウェルビーイングに注目する背景には、リモートワークの普及、ライフステージの多様化、そしてキャリア観の変化があります。働き方が柔軟になる一方で、社員が孤立したり、働きがいを見失ったりするリスクも増えました。そのため、企業は、「働く」という行為に幸福感を組み込む視点を持つことが求められています。
ウェルビーイングと福利厚生・健康経営との違いとは?
ウェルビーイングは福利厚生や健康経営とは似て非なるものです。福利厚生が「制度提供」に重点を置くのに対し、ウェルビーイングは、「社員自身が自律的かつ持続的に活躍できる健康・心理的に良好な状態」をゴールとしています。また、健康経営が主に健康リスク低減を目指すのに対し、ウェルビーイングは、仕事を通じた自己実現や社会的なつながりまで視野に入れた、より広範な概念です。この違いを正しく理解することが、これからの施策設計において極めて重要になります。
ウェルビーイングが社員と組織に与える影響と効果
従業員エンゲージメント・定着率に与える効果
社員のウェルビーイングが向上すると、まず最初に現れる効果は、エンゲージメントの向上です。仕事に対する前向きな気持ちや、組織への貢献意欲が高まり、定着率も向上します。特に若年層は、給与や福利厚生より「働きがい」を重視する傾向が強まっており、ウェルビーイング施策は優秀な人財の確保・維持にも直結します。
チームの生産性・創造性が向上する仕組み
チーム単位での生産性や創造性にも大きな好影響があります。ウェルビーイングが高い組織では、社員同士のコミュニケーションが活発になり、「心理的安全性」が高まります。その結果、アイデア出しや意見交換が促進され、新しい価値の創造が生まれやすくなります。Googleが行った「プロジェクト・アリストテレス」でも、チームの成功要因として最も重視されたのは、スキルではなく心理的安全性であったことが示されています。
メンタルヘルスや職場の心理的安全性の改善
メンタルヘルスの改善もウェルビーイング推進のための重要な要素となります。過度なストレスや孤立感が低減されることで、長期的な心身の健康維持につながり、その結果、プレゼンティーズム(出勤しているがパフォーマンスが低下している状態)やアブセンティーズム(欠勤)の削減にもつながります。組織全体にとっても、大きな経済的メリットが期待できます。
未来型組織に必要なウェルビーイング視点の働き方設計
「人を中心に据える」組織設計の重要性
これからの未来型組織には、「人を中心に据える」視点が不可欠です。単に効率性や業績向上を追求するのではなく、社員一人ひとりのウェルビーイングを基盤とした働き方設計が求められます。社員の意欲や幸福感を高めることが、結果としてイノベーションや企業競争力の源泉になるためです。
ハイブリッドワークとジョブクラフティングがウェルビーイングに与える影響
この文脈で注目されるのが、ハイブリッドワークとジョブクラフティングです。ハイブリッドワークは、リモートワークとオフィス勤務を柔軟に組み合わせることで、個々のライフスタイルやコンディションに合わせた働き方を可能にします。一方、ジョブクラフティングとは、社員自身が自らの仕事のやり方や意義を主体的に再定義していく取り組みです。これらの実践を通じて、ウェルビーイングを高めることができます。
「やりがい」や「意味ある仕事」が幸福度にどう関係するか
また、単に仕事をこなすだけでなく、「やりがい」や「意味ある仕事」を実感できるかも、ウェルビーイングに直結します。ギャラップ社の調査によれば、自分の仕事に意味を感じられる社員は、感じられない社員に比べてエンゲージメントが3倍以上高いというデータもあります。企業側には、社員が仕事の意義を見出せるような仕掛けを設計する責任が問われています。
出典:ギャラップ社「Japan's Workplace Wellbeing Woes Continue」
ウェルビーイングを支える企業文化とリーダーシップ
トップダウンとボトムアップを両立させるための方法
ウェルビーイングな働き方を定着させるには、制度や施策だけでは不十分です。明暗を分けるのは、企業文化とリーダーシップの在り方です。トップダウンとボトムアップ、どちらか一方に偏るのではなく、両者をうまく組み合わせることが重要になります。経営層が理念と方向性を明確に示しつつ、現場の社員一人ひとりが自ら考え、行動できる環境を整えること。この相互作用こそが、組織変革の原動力となります。
管理職が変わると組織が変わる:ミドルマネジメントの役割
現場を束ねるミドルマネジメント層は極めて重要な役割を担っています。管理職の意識と行動が変化することで、現場の雰囲気やチームの在り方にも大きな影響が生じます。したがって、単なる業務管理者ではなく、チームメンバーのウェルビーイングを支える存在へと意識を変革していくことが求められます。そのためには、管理職自身に対するサポートや、ウェルビーイング・マネジメントスキルの育成も不可欠です。
「心理的安全性」を育てる組織文化とは?
心理的安全性を育てる組織文化づくりも重要です。ミスを許容し、意見を歓迎する空気がなければ、社員は本音を語れず、エンゲージメントも低下してしまいます。小さな失敗も前向きに捉え、学びに変える文化が、ウェルビーイング経営の基盤になります。
社員の声を活かした共創型ウェルビーイング施策のすすめ
サーベイや対話によるニーズを可視化する方法
ウェルビーイング施策を形骸化させないためには、現場の声を施策に反映させることが重要です。サーベイや1on1、対話型ワークショップなどを活用し、社員のニーズや課題感を可視化するところから始めましょう。
施策の「押し付け感」を防ぐための共創のプロセス
施策を設計する際には、押し付けにならないよう注意が必要です。企業が一方的に指示するのではなく、社員と共に考え、共に作り上げるプロセスを重視することがポイントです。この共創型のアプローチによって、社員の自律的な行動変容を促進することが可能となります。
ボトムアップ型ウェルビーイングの成功事例
実際にボトムアップ型でウェルビーイング推進を成功させた企業では、現場発案による健康イベントや、社員が自らアイデアを持ち寄るウェルビーイング委員会などを組織しています。社員の提案や取り組みに細かく目配りをし、制度化していくことが、実効性のある企業文化の構築につながります。
ウェルビーイングな働き方を促進するアプリ「WellWa」とは

全社員・個人で楽しめるプログラム設計
こうした組織変革を支えるツールとして注目されているのが、キリンの「WellWa」です。WellWaは、全社員が個人でもチームでも楽しめる仕組みを備えています。たとえば、部署対抗で歩数を競い合うチャレンジイベントや、日々の健康行動を可視化するランキング機能など、自主的な健康行動を促進する工夫が満載です。
人気の「食の福利厚生」でポイント交換
また、WellWaでは健康行動によって貯まったポイントを、キリンの人気商品と交換できる「食の福利厚生」サービスも提供しています。単なる健康管理ではなく、社員にとって嬉しい体験を通じて、無理なくウェルビーイングが文化として定着する仕掛けになっている点が大きな特徴です。
よくある落とし穴と導入失敗を防ぐポイント
「形だけ」施策になってしまう理由
ウェルビーイング施策が失敗してしまう典型的なパターンの一つは、「形だけ」の取り組みになってしまうことです。制度を作った段階で満足し、運用が形骸化すると、社員の不信感を招きかねません。施策導入後も、定期的な振り返りと改善を怠らないことが大切です。
社員の反応が鈍いときに試すべきウェルビーイング施策の改善方法
施策に対する社員の反応が鈍いときは、焦らず、柔軟に対応していきましょう。社員の声を吸い上げ、施策をアップデートしていくことで、少しずつ共感と納得感を積み上げ、組織全体に浸透させることができます。
成果を出し続けるための工夫とは
ウェルビーイング施策は、短期間で成果が得られるものではありません。成果が見え始めるまで一定の時間がかかることを前提に、焦らず、継続しましょう。小さな変化もポジティブに捉え、施策を推進していくことが、成功への近道です。
まとめ|共創型の取り組みで未来型組織を築く
ウェルビーイングな働き方は、単なる制度整備ではなく、組織文化と社員一人ひとりの行動変容によって初めて実現します。そのためには、人事部門のリーダーシップはもとより、経営層、マネジメント層、そして社員自身を巻き込んだ共創型の取り組みが不可欠です。小さな一歩を踏み出し、対話を重ね、成功体験を増やしながら、少しずつ組織全体を変えていく。この地道な積み重ねこそが、未来型組織への確かな道筋となるでしょう。