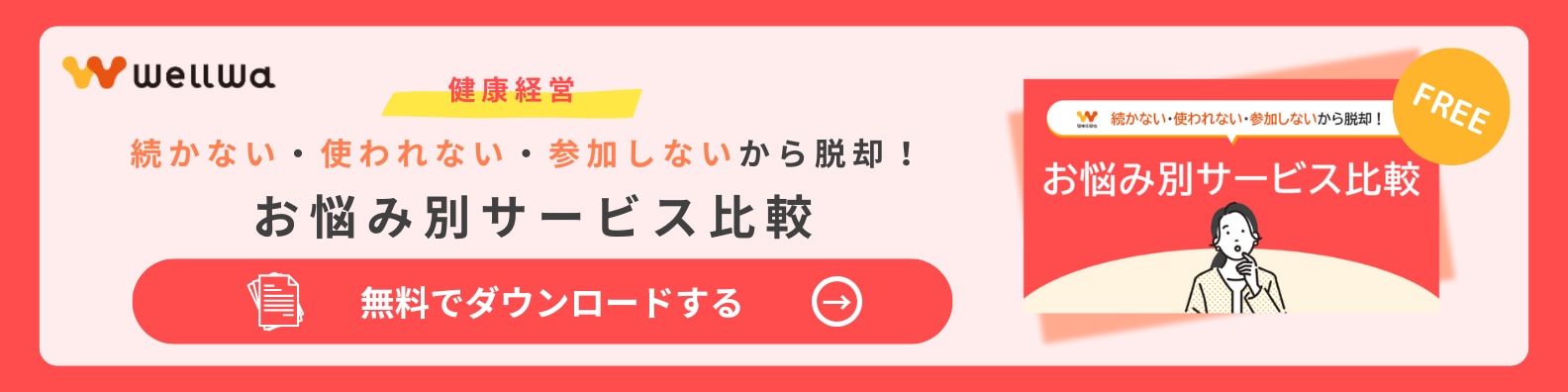健康経営・ウェルビーイング施策が社内に浸透しない理由とは?人事が知っておくべき導入・定着の成功ステップ
人事担当者に向け、ウェルビーイング施策を定着させるためのステップやプレゼンティーズムや離職リスクを防ぐ方法、KPIを設計する際の考え方を紹介します。
目次[非表示]
- 1.ウェルビーイングと健康経営の定義と関係性
- 2.人事担当者が向き合うべき健康課題とメンタルヘルス対策の重要性
- 2.1.従業員が抱える健康課題の多様化(身体・精神・社会的側面の具体例)
- 2.2.メンタル不調やプレゼンティーズムが離職を招く理由とは?
- 2.3.健康施策が生産性・エンゲージメント・企業価値に与える影響とは
- 3.ウェルビーイング施策の始め方:導入前にやるべき3ステップ
- 4.成果が出る健康経営・ウェルビーイング施策の成功パターンとは
- 5.導入後の「制度倒れ」を防ぐ運用と効果測定における3つのポイント
- 6.KIRINの「WellWa」とは?健康経営に活用できる可視化アプリの機能と効果
- 7.よくある質問|人事の悩みへの対応策
- 8.まとめ|企業の未来を支える健康とウェルビーイング施策の始め方
ウェルビーイングと健康経営の定義と関係性
「健康経営」とは、従業員の健康増進を経営課題と位置づけ、戦略的に取り組む考え方を指します。一方で「ウェルビーイング」は、単に疾患がない状態ではなく、身体・精神・社会的に良好な状態を目指す、より包括的な概念です。両者に共通するのは、従業員の健康と働きやすさを重視し、最終的には組織力や企業価値の向上を目指す点ですが、ウェルビーイングの方が「働く意義」や「人間関係」「自己成長支援」など、より広い視野を持つアプローチが求められます。
人事担当者が向き合うべき健康課題とメンタルヘルス対策の重要性
従業員が抱える健康課題の多様化(身体・精神・社会的側面の具体例)
現代の職場では、運動不足や生活習慣病リスクといった身体的課題に加え、ストレスや不安感、燃え尽き症候群など精神的な問題、さらには孤立感やチームのつながり希薄化といった社会的な問題まで、従業員の健康課題が多様化しています。身体面だけを支援しても、十分とは言えません。心身および社会的側面を含む包括的な支援が必要とされています。
メンタル不調やプレゼンティーズムが離職を招く理由とは?
メンタル不調が表面化する前段階では、漠然とした体調不良や意欲の低下といったプレゼンティーズム(出勤はしているがパフォーマンスが低下している状態)が見られます。この兆候を放置すれば、やがて高い離職リスクへとつながります。初期段階で兆候を把握し、組織全体で支援できる体制が必要です。
健康施策が生産性・エンゲージメント・企業価値に与える影響とは
従業員の健康施策は、単なる福利厚生ではありません。「働きやすさ」を向上させ、エンゲージメントを高め、生産性向上や離職率低下につながり、結果的には企業価値を高めます。このロジックを社内で共有し、人事施策ではなく経営戦略の一環として位置づけることが、これからの時代には不可欠です。
ウェルビーイング施策の始め方:導入前にやるべき3ステップ
1.まず何から始める?社内ヒアリングと課題の棚卸し
ウェルビーイング施策を成功させるためには、まず現場の声を集めることが重要です。健康診断やストレスチェック、エンゲージメントサーベイなどのデータを活用しつつ、部署別や役職別にヒアリングを行い、健康課題や働き方の悩みを棚卸ししていきます。
2.予算・リソースを見極めた現実的な施策の設計
施策設計にあたっては、あらかじめ年間予算枠を設定し、実際に運用できるリソース(担当者数、協力部署など)を見極め、無理のない小規模な施策から段階的に導入することが求められます。完璧な施策を目指すよりも、施策を継続的に実施・改善することが重要です。
3.推進体制とステークホルダーの巻き込み方
推進体制の整備も重要です。経営層には目的と得られる効果やロジックを具体的に説明して支援を得る一方、現場管理職を巻き込んで推進役を育成し、さらに社員代表(アンバサダー制度など)によるボトムアップ推進も同時に進めることが求められます。一方的な指示ではなく、現場に共感される施策設計が、成功を左右します。
成果が出る健康経営・ウェルビーイング施策の成功パターンとは
中小企業でも導入可能なコストを抑えた施策例
中小企業でも始められる低コスト施策として、ウォーキングチャレンジやオンラインでのマインドフルネス講座、月1回の健康ニュースレター配信などがあります。小規模であっても、継続的かつ一貫性のある実施により大きな効果が期待できます。
働き方・人間関係・メンタルケアに寄与するアイデア
働き方や人間関係、メンタルケアにも寄与する施策としては、部署対抗型の健康イベントや、1on1ミーティングの活用、オンライン雑談タイムの導入などが効果的です。心理的安全性の向上は、ウェルビーイングの改善と強く関連しています。
デジタルヘルスツール・ウェアラブル活用事例
デジタルヘルスツールやウェアラブル端末を活用した歩数・睡眠ログ管理や、アプリを用いたチーム対抗チャレンジ(例:WellWa活用)なども、自発的な健康行動を促す有効な手段となります。これらを組み合わせることで、単発イベントではない、「文化」としてのウェルビーイング推進が可能になります。
導入後の「制度倒れ」を防ぐ運用と効果測定における3つのポイント
ウェルビーイング施策を導入した後、よくある悩みが「最初は活気があったが、早期に形骸化した」というものです。この失敗を防ぐには、社員が自発的に継続したくなる工夫が不可欠です。以下の3つのポイントを念頭に置くことで成功に一歩近づくことができます。
1.社員が継続的に参加したくなる運用設計(ナッジ)
たとえば、施策に参加するだけでポイントがたまり、景品と交換できる制度を設けたり、健康行動を見える化して、部署ごとのランキングや個人スタンプ機能を活用するのも効果的です。こうした小さな成功体験を積み重ねることで、義務感の強い印象を払拭し、自然と継続を促すナッジ(無理なく行動変容を促す仕組み)として機能します。
2.事前のKPI設定と効果測定
施策導入時には、あらかじめ明確なKPI(重要業績評価指標)を設計しておくことが重要です。たとえば、「初期参加率70%以上」「3か月後の継続利用率50%以上」「ウォーキング習慣者を15%増やす」など、具体的なゴールを設定し、数値で振り返りましょう。施策を続けるモチベーションにもなります。
3.経営層と現場の共感を生む報告資料
社内報告資料を作成する際には、実施概要や参加人数だけでなく、KPI進捗や社員の自由記述による具体的な声もあわせて紹介しましょう。単なる数値だけではなく、「社員の声」を届けることで、経営層・現場双方に納得感と共感を生み出すことができます。
KIRINの「WellWa」とは?健康経営に活用できる可視化アプリの機能と効果

投資対効果を示すサーベイ・分析モデル
健康施策の成果を数値で示すことに苦戦している人事担当者にとって、WellWaは有効な支援ツールになります。WellWaでは、25問の設問に社員が回答するだけで、健康施策の投資対効果(ROI)、同業他社との比較(ベンチマーク)、経年比較による改善傾向を、データとして可視化できる独自の統計分析モデルを提供しています。これにより、曖昧で情緒的な判断ではなく、「数値で効果を説明できる」運用へと大幅な改善が可能となります。経営層への説得力も飛躍的に高まるでしょう。
豊富な健康イベント、社内巻き込みに特化したプログラム設計
WellWaはサーベイツールのみならず、部署対抗型ウォーキングチャレンジや睡眠改善キャンペーン、飲酒習慣ケアプログラムなど、多彩な健康イベントプログラムも用意されており、ランキング機能やスタンプ機能によって、チーム内外での自発的な参加を促進します。この自然な社内コミュニケーションの活性化が、ウェルビーイング文化の定着を後押しします。
よくある質問|人事の悩みへの対応策
効果が見えにくいのでは?|ROIをどう示すか
WellWaのようなサーベイ・分析ツールを活用し、プレゼンティーズム改善額やエンゲージメント向上を金額換算できる仕組みを導入することで、効果を明確に数値化できるようになります。
現場からの反発が心配|理解促進と意識変革のコツ
健康施策は、目的や意義をしっかりと伝えることが重要です。単なる「健康管理」ではなく、社員自身の幸福や働きやすさを高める取り組みであることを具体的に伝えましょう。さらに、ゲーム性やチーム制など、楽しめる要素を盛り込むことで自発的な参加促進につながります。
小規模でも実施できる?|スモールスタートの工夫
小規模だからこそ、柔軟なスモールスタートが可能です。たとえば、部署や希望者を限定してパイロット運用を行い、オンライン完結型のイベントから着手すれば、リスクも回避しやすくなります。最初に得た成功データをもとに、徐々に社内展開を拡大していきましょう。
まとめ|企業の未来を支える健康とウェルビーイング施策の始め方
ウェルビーイング施策は、企業文化を変え、人的資本価値を高め、未来の企業競争力をつくるための戦略的な取り組みです。
まずはスモールスタートで取り組みを始めましょう。デジタルツールやサーベイを活用すれば、効果の可視化も無理なく実現できます。特に、WellWaのようなアプリを活用すれば、自発的な健康習慣が定着し、組織の一体感と活力を育むことも可能です。