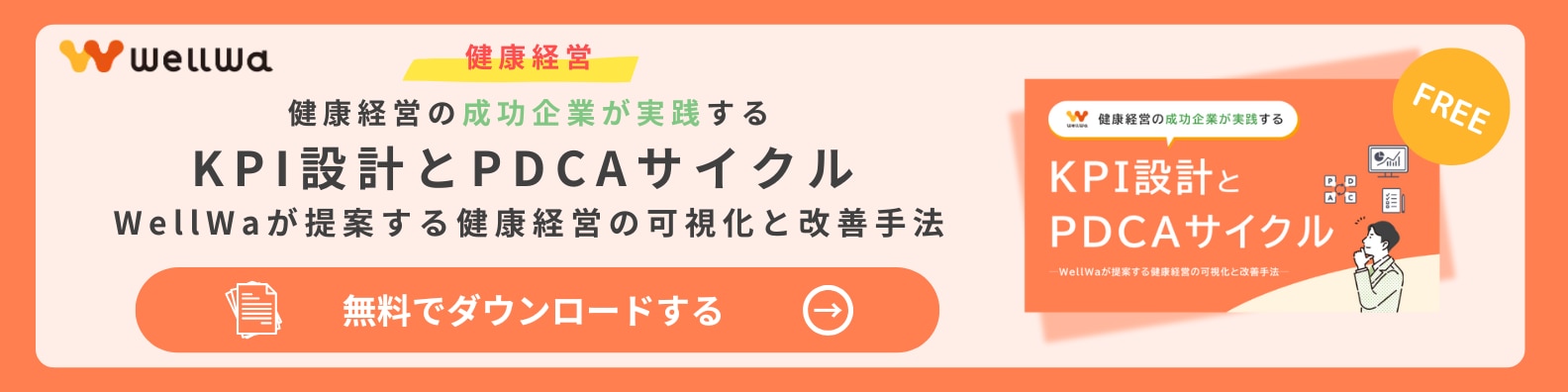エンゲージメントが人的資本経営の鍵!成功事例に学ぶ戦略とは
人口減少や価値観の多様化が進む中、人的資本経営の成否を分けるのは従業員エンゲージメントです。
本記事では、その重要性やモチベーションとの違い、心理的安全性・双方向コミュニケーション・ウェルビーイング施策など成功の3戦略と実践例を解説します。
目次[非表示]
人的資本経営とは何か?注目される背景と企業の課題
なぜ今「人的資本経営」が求められているのか
人的資本経営とは、従業員を単なる「労働力」ではなく、「企業価値を生み出す資本」として捉える経営手法です。これまでの経営では、財務や設備への投資に重点が置かれてきましたが、今は“人”への投資が企業の競争優位を左右すると考えられています。
その背景には、人口減少、価値観の多様化、テクノロジーの進化といった構造的な変化があります。機械やAIには代替できない「創造性」や「共感力」といった人間らしい価値が、今後の企業成長の鍵となっているのです。
情報開示義務の強化と経営インパクト
2023年3月期以降、上場企業約4,000社には「人的資本情報の開示」が義務化されました。企業は有価証券報告書に、女性管理職比率、男性の育児休業取得率、男女間賃金格差など、従業員の状態や組織施策に関するデータを記載する必要があります。
これは単なる報告義務ではなく、企業の透明性や信頼性、さらには投資判断にも直結する重大な経営要素です。人的資本経営が企業価値の一部として評価される時代が到来しているのです。
組織現場で起きている「やらされ感・無関心」の正体
人的資本経営を導入しても、現場で思うように定着しないという悩みは多くの企業に共通します。その主因が、「やらされ感」と「無関心」です。
現場の従業員が、自分の業務や働き方と人的資本経営とのつながりを実感できなければ、「また何か始まった」「負担が増えるだけ」とネガティブに捉えてしまいます。人的資本経営を成功させるには、従業員が当事者として関わり、納得して動ける仕組みが不可欠です。そのカギこそが、“エンゲージメント”なのです。
なぜ「従業員エンゲージメント」が人的資本経営の中核なのか
エンゲージメントが経営成果に直結する理由
従業員エンゲージメントとは、「自社への信頼」や「仕事への情熱」を持って、自発的に貢献しようとする心理的なつながりを指します。エンゲージメントが高い社員は、生産性・創造性・定着率が高く、離職リスクやプレゼンティーズムが低いとされています。
経済産業省の人材版伊藤レポート2.0においても、エンゲージメントは人的資本経営の重要な指標として位置づけられています。多くの研究により、エンゲージメントの高い組織は業績指標でも優れた成果を出すことが証明されており、人的資本経営において「最も重要な成果指標の一つ」といっても過言ではありません。
出典:経済産業省「人材版 伊藤レポート2.0」
モチベーションとの違いと誤解されがちなポイント
エンゲージメントとよく似た言葉に「モチベーション」がありますが、両者は異なる概念です。モチベーションは「一時的なやる気」であり、報酬や外的要因によって上がったり下がったりします。
一方、エンゲージメントはもっと深い“内発的な結びつき”です。会社のビジョンや職場の人間関係、仕事のやりがいなど、長期的な関係性の中で育まれる感情であり、持続性において大きな違いがあります。
測定指標と定量化の壁
エンゲージメントの重要性は理解されていても、定量化の難しさから評価や改善が難しいと感じる企業は少なくありません。従来の従業員満足度調査だけでは、組織への「愛着」や「貢献意欲」といったエンゲージメントの本質が見えてこないこともあります。
そこで注目されているのが、エンゲージメントサーベイの導入です。「WellWa(ウェルワ)」のようなアプリでは、従業員の健康状態・生活習慣・コミュニケーション・ストレスなどを総合的に可視化し、エンゲージメント指標と生産性向上をひも付けて分析する仕組みが整っています。
エンゲージメント向上に向けた実践戦略:3つの柱
【戦略1】心理的安全性を育むリーダーシップと仕組み
エンゲージメントを高める土台となるのが「心理的安全性」です。これは、従業員が「自分らしく意見を言える」「失敗しても責められない」と感じられる環境のことです。
心理的安全性がある職場では、挑戦が生まれ、学びが深まり、結果としてエンゲージメントが育ちます。そのためには、リーダー層の関わり方が極めて重要です。フィードバック文化の醸成や、対話の場づくりなどを通じて、信頼関係を築いていくことが求められます。
【戦略2】双方向コミュニケーションの仕掛けづくり
エンゲージメントの醸成には、トップダウンだけでなくボトムアップの声が生かされる環境が必要です。一方通行の発信だけでは従業員の当事者意識は高まりません。
アンケート、1on1、社内SNS、ミニイベントなどを通じて、従業員の声を拾い、行動につなげる設計が欠かせません。
「聞かれた意見が実際に反映された」「フィードバックがすぐに返ってきた」といった体験が、組織への信頼を高め、心理的な“つながり”としてのエンゲージメントを育てていきます。
【戦略3】ウェルビーイング施策で健康と働きがいをつなぐ
身体と心の健康は、仕事への意欲や集中力、創造性と密接に関わります。そこで注目されているのが、ウェルビーイング施策を通じてエンゲージメントを高める戦略です。健康支援、フレキシブルな働き方、社内イベントといった施策は、従業員の「働きがい」に直結します。
Well-being(よく生きる)を大切にする企業文化は、単なる満足度向上にとどまらず、持続的な人的資本の活性化にも貢献します。健康と働きがいは両輪であり、どちらも欠かすことはできません。
WellWaに学ぶ、エンゲージメント起点の健康経営モデル
WellWaとは?“たのしい健康”によるチームビルディング
WellWaは、キリンビバレッジが開発した健康×エンゲージメントの統合支援アプリです。従業員の健康習慣を「個人の努力」で終わらせず、「チームで楽しく取り組む」文化へと進化させることを目的としています。
ウォーキング、睡眠、野菜摂取などの習慣を競い合いながら記録することで、部署横断のつながりやポジティブな会話が自然と生まれます。これは単なる健康支援ではなく、組織のエンゲージメントを高める仕掛けでもあります。
「スタンプ」「ランキング」機能が生む組織内交流
WellWaの特徴は、数値の記録だけでなく、感情のやりとりを重視している点です。スタンプ機能では「ありがとう」「がんばったね」といった気持ちをチーム内で送り合うことができ、心理的報酬が得られます。
また、部署別や個人別のランキング表示は、目標意識と健全な競争心を刺激します。業務とは関係のない活動を通じて、組織全体のつながりが深まり、心理的安全性のある文化が形成されていきます。
健康施策のROIを25問で可視化する独自サーベイモデル
WellWaの強みの一つは、25問の簡易サーベイでエンゲージメント、健康、ストレス、会話量、プレゼンティーズムといった指標を可視化できる点です。しかも、これらの数値を生産性や金額効果に換算することで、経営層にも納得されやすいROIが提示できます。
この“見える化”の仕組みが、人的資本経営の実行性と継続性を後押ししています。
まとめ:エンゲージメント経営の第一歩を踏み出そう
人的資本経営は「共感と継続」が成功のカギ
人的資本経営を成功させるには、従業員が共感し、自ら関わり続けられる仕組みが欠かせません。エンゲージメントは、健康経営や評価制度などの取り組みすべてをつなぐ“ハブ”のような役割を果たします。
制度をつくるだけではなく、人が動きたくなる仕組みをどう設計するか。それがこれからの人事や健康経営担当者に求められる視点です。
WellWaの導入で得られる短期・中長期の成果
WellWaは、すぐに始められるスモールスタートが可能でありながら、組織風土や生産性といった中長期的な成果へもつながる仕掛けが組み込まれています。
「やらされ感のない健康施策」「見える化されたエンゲージメント」「心理的報酬による参加率向上」。これらを一つの仕組みで実現できることは、人的資本経営に取り組む企業にとって大きな武器になるでしょう。