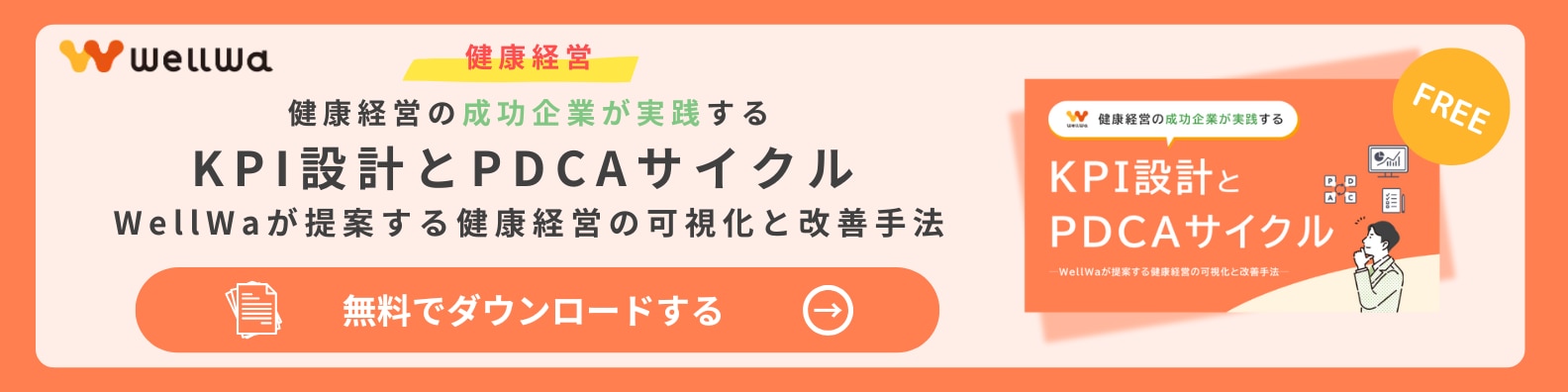働くことで生じる健康問題と、企業が取るべき対策
働くことで生じる健康問題(長時間労働のストレス・メンタル不調、運動不足による生活習慣病リスク、コミュニケーション不足による孤立)は、生産性低下や離職につながる重大な経営課題です。本記事では、プレゼンティーズム/アブセンティーズムの損失、制度の形骸化を防ぐ行動変容設計、健康経営戦略マップとPDCA、部署横断の巻き込み施策など、企業が今すぐ実装できる実践対策をわかりやすく解説します。
働くことで起こる主な健康問題とは?
長時間労働によるストレス・メンタルヘルス不調
現代の働き手にとって、最も身近な健康問題の一つが「ストレス」です。長時間労働や過度なプレッシャー、人間関係の摩擦、これらは日々の業務環境から生じます。特に慢性的な残業や業務量の過多は、疲労の蓄積だけでなく、うつ病や不眠症といった深刻なメンタル不調にもつながります。
ストレスを放置すると、心身のパフォーマンスが低下するだけでなく、職場の人間関係や私生活にも悪影響を及ぼします。企業が健康経営を掲げる以上、「働きすぎない働き方」の設計は、業績向上と不可分の課題といえるでしょう。
デスクワークによる運動不足・生活習慣病リスク
オフィスワーク中心の働き方は、一見すると身体への負担が少ないように見えます。しかし、長時間の座りっぱなしは運動不足を招き、肥満・高血圧・糖尿病といった生活習慣病のリスクを高めます。さらに、肩こりや腰痛などの不調も生じやすく、生産性に影響するケースも少なくありません。
職場にいながら健康を維持するという視点から見ると、企業が積極的に介入できる施策には、まだ取り組む余地があります。ストレッチタイムの導入や、歩数計やアプリを使った祖活動促進など、小さな習慣でも、継続すれば大きな効果を生みます。
コミュニケーション不足による孤立・エンゲージメント低下
テレワークやフリーアドレスの普及により、柔軟な働き方が進む一方で、1日誰とも深く関わらずに仕事を終えるケースが増えています。こうした状況は社員の孤立感を強め、心理的安全性やチーム連携を損ないます。
また、職場内での共感や感謝の機会が減ることで、「この会社で働いている意味」や「一体感」が感じられず、エンゲージメントの低下につながるリスクもあります。仕事における「つながり」は、単なる感情論ではなく、健康にも直結する重要なファクターであることを、企業は改めて認識する必要があります。
健康問題が企業に及ぼす影響
見えない生産性損失:プレゼンティーズムとアブセンティーズム
出社していても心身の不調で本来の力が出せない「プレゼンティーズム」と、病欠や休職により不在となる「アブセンティーズム」。どちらも業務の質を下げ、コスト増に直結します。
経済産業省の調査によれば、プレゼンティーズムによる損失額はアブセンティーズムの数倍にのぼるといわれており、これは企業の利益を静かに削る「見えない赤字」です。社員の健康維持は、単なる人事部門の課題ではなく、経営課題として捉える必要があります。
離職率の上昇と採用難
健康不調が原因となり、やむを得ず離職する社員が増えれば、それは組織全体の持続可能性にも影響を及ぼします。特に採用競争が激しい現在、一度優秀な人財を失えば代替コストも高くつきます。
また、健康に配慮しない職場環境は、企業の評判やブランドイメージにも直結します。SNSや口コミを通じて職場の実態が可視化される時代において、「この会社は人を大切にしていない」と思われてしまえば、新たな人財の確保すら難しくなります。健康経営とは、採用力の強化にもつながる戦略的施策なのです。
健康経営度調査と競争力
近年注目が高まっている「健康経営度調査」では、制度の有無だけではなく、実際の利用状況や課題に沿った設計が評価されます。形だけの制度ではスコアは伸びません。日常的な行動変容を促すような施策があれば、評価は大きく向上します。
健康経営優良法人の認定や人的資本の情報開示を目指す企業にとって、健康問題への本質的なアプローチは、今や「やるべきこと」から「やらなければならないこと」へと変わりつつあります。
健康課題の背景:職場が与える影響
働き方の多様化に制度が追いつかない
フルリモートと現場勤務者間で健康支援の格差がないか、ライフステージに応じた柔軟な対応ができているか、これらを検証しないと課題は深刻化します。
健康支援が個人任せになっている
制度やツールはあっても、それが日常に組み込まれていなければ意味がありません。運動アプリを導入したとしても、それが使われなければ単なるコストに終わってしまいます。支援が使われる仕組みになるためには、行動変容を促す設計が不可欠です。
共感・つながりの欠如
職場の健康課題を見過ごしてしまう最大の理由は、「他人ごと」で終わってしまうことです。「自分には関係ない」という空気が広がると、施策は形骸化します。
共感やつながりを土台に持つことで、健康を自然に話題にできる風土づくりが重要です。
企業が取るべきアプローチ
「評価」だけでなく「行動変容」まで支援する施策を
健康経営の実現において、施策の有無や制度の整備だけでは不十分です。重要なのは、従業員が実際に行動を変え、それが習慣として定着するところまで支援できているかどうかです。
定期健診やストレスチェックといった評価制度は広く導入されていますが、それを基に「具体的に何をすればいいのか」が明確に提示されなければ、社員にとっては単なる形式的な確認作業にとどまってしまいます。行動変容を後押しするためには、日常に溶け込むような継続支援型の設計が不可欠です。
健康経営戦略マップとPDCAの導入
行き当たりばったりの施策では、効果があっても長続きせず、組織全体への波及も限定的になります。そこで有効なのが、「健康経営戦略マップ」の作成と、PDCA(計画・実行・評価・改善)による運用体制の構築です。
マップは、企業が目指す健康経営のゴールを可視化し、その実現のために必要な活動やKPI、関係部門との連携を体系的に整理するものです。これにより、施策ごとの目的や優先順位が明確になり、経営層・人事部門・現場の足並みをそろえる基盤が整います。
部署横断・巻き込み型の社内風土づくり
健康経営は人事部門だけが担うものではありません。各部署、さらには役職者やリーダー層を巻き込んだ全社的な動きにしてこそ、実効性が高まります。
部署間の連携を促すためには、共通の目標やイベント、ミッションを設けることが有効です。また、「健康=自己責任」という意識を乗り越え、互いに気にかけ、応援し合える風土を育てることで、自然と健康行動が浸透していきます。
WellWaを活用した健康課題解決の仕組みづくり
楽しみながら参加できる「チャレ活」で運動・食事習慣を定着化
WellWa(ウェルワ)の「チャレ活」は、チーム単位で楽しみながら運動や食事改善に取り組める仕掛けです。例えば「毎日5,000歩チャレンジ」や「野菜を一品プラス」など、日常に取り入れやすいミッションが用意され、達成状況がリアルタイムで可視化されるようになっています。
こうした工夫により、「やらされ感」ではなく「やってみたくなる」動機が生まれ、行動のきっかけが自然に生まれます。ゲーム感覚で健康を身近にする工夫は、特に運動習慣の定着に大きな効果を発揮しています。
ポイント機能で健康行動をインセンティブ化
健康行動がポイントとして蓄積され、そのポイントが食の福利厚生(WellStore)で使える商品や特典と交換できるという循環は、WellWaの大きな魅力です。企業は、制度としての報酬を明確に提示しながら、行動変容を促すインセンティブを提供できます。
また、社内でオリジナルの特典を設定する「WellStock」では、自社らしいユニークなリワード設計も可能です。これにより、健康行動を楽しく・継続しやすい文化へと昇華できます。
部署横断のイベント設計で孤立を防ぎ、会話を促す職場へ
WellWaは、今後さらに家族向け機能の拡充が予定されており、働く人の周囲も巻き込む開かれた健康支援を目指しています。部署対抗のイベント通じて、職場内外の「つながり」が強化され、孤立感の解消や会話の活性化が自然に促されます。
職場で健康が話題になることは、メンタルヘルス対策の第一歩でもあり、コミュニケーションの質そのものを高める起点にもなり得ます。
継続できる施策のポイント
データ分析で効果検証まで可視化
どれほど優れた施策でも、継続には「手応え」が必要です。WellWaでは、行動ログやアンケート結果などを自動で集計し、分析できる機能が用意されています。これにより、参加率の変化や習慣化の進行度、満足度などを数値で把握でき、次の一手が見えやすくなります。
単にやったかどうかではなく、どれだけ変化したかという視点を持つことで、健康経営に対する経営陣の納得感も高まるはずです。
経営層・現場の巻き込みが継続性を左右する
制度が継続するかどうかは、導入時の熱量だけでは決まりません。経営層が健康経営を本気で推進しているか、現場リーダーが巻き込まれているか。この2点が大きく影響します。
役員が自らチャレ活に参加したり、部署単位で取り組みを発信したりすることで、社員の参加意識も高まるでしょう。WellWaではこうした見える化やシェアの仕組みが充実しているため、トップダウン・ボトムアップの両面から施策を支えることが可能です。
小さく始めて改善を重ねるステップ型実践法
すべてを一度に変えようとするのではなく、まずはスモールスタートで始めることも大切です。限られた部署や対象者でのテスト運用を経て、フィードバックを取り入れながら徐々に展開範囲を広げていく。このような素早い導入が、実態に即した制度設計を支えます。
WellWaは、小規模導入から本格展開まで段階的な運用に適しており、組織の変化に合わせた柔軟なカスタマイズも可能です。
まとめ
職場起因の健康問題は、個人だけでなく、企業の生産性やブランドにまで大きな影響を及ぼします。「働くことで健康になれる職場」を実現することが、これからの企業の競争力です。
テータとテクノロジー、人と人とのつながりを組み合わせ、まずは一歩を踏み出しましょう。