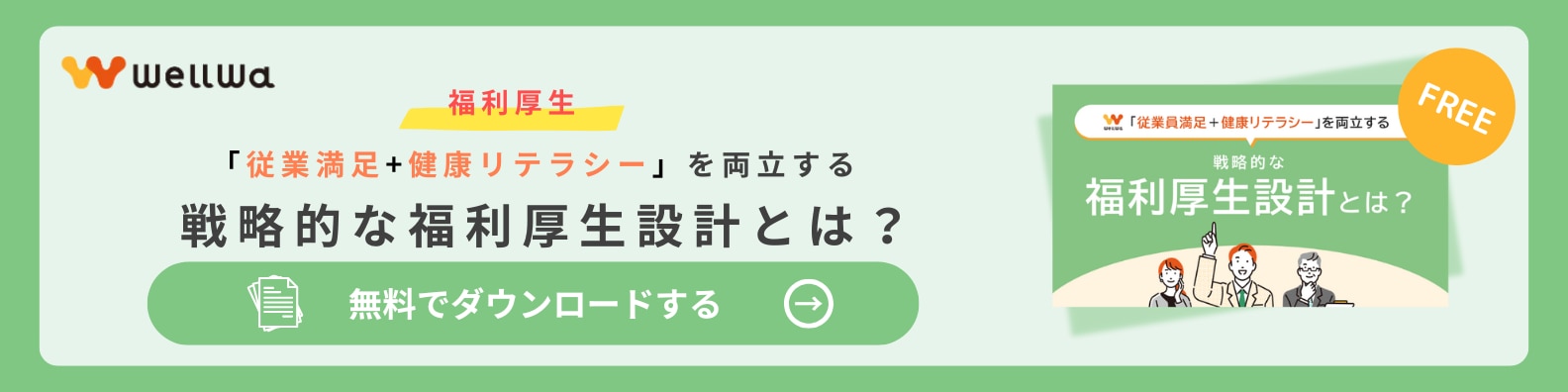福利厚生の活用課題を解決する方法|響かない原因と実践的解決法
企業が従業員満足度の向上や人材定着のために力を入れている「福利厚生」。しかし、せっかく導入した制度が社員に使われていないという悩みを抱える企業も少なくありません。本記事では、福利厚生が活用されない根本的な原因と、その課題を解決するための具体策を詳しく解説します。
目次[非表示]
- 1.福利厚生の活用課題と現状
- 2.社員に響かない福利厚生の主な課題と原因
- 2.1.ニーズとのミスマッチ
- 2.2.制度の認知度不足課題
- 2.3.煩雑な利用手続き
- 2.4.心理的ハードル
- 2.5.公平性の欠如
- 3.福利厚生の活用課題を解決するための実践的方法
- 3.1.1. 社員ニーズの的確な把握と最適な制度設計
- 3.2.2. 効果的な情報発信による認知度向上
- 3.3.3. 利用ハードルの引き下げ
- 3.4.4. 心理的安全性の確保
- 3.5.5. 公平性を重視した制度設計
- 4.健康促進を支援する福利厚生サービス「WellWa」
- 5.まとめ
福利厚生の活用課題と現状
福利厚生は企業が従業員の満足度を高め、優秀な人材を確保・定着させることを目的に導入されています。住宅手当や育児支援、リフレッシュ休暇などを整備することで、働きやすい環境を提供し、社員のモチベーションを向上させる効果が期待できます。また、充実した福利厚生は企業の魅力として外部にアピールでき、採用活動においても強力な武器となります。
しかし、多くの企業では制度を導入しているにもかかわらず、実際には社員にほとんど利用されていないという課題を抱えています。その背景には、制度の魅力不足や利用しづらさ、認知不足などの問題が潜んでいます。企業としては制度に投資しているにもかかわらず、期待した効果が得られていないのが現状です。
社員に響かない福利厚生の主な課題と原因
ニーズとのミスマッチ
福利厚生が活用されない最大の原因の一つが、従業員のニーズとのミスマッチです。企業側が「これなら喜ばれるだろう」と導入した制度が、実際の社員にとっては必要性を感じない内容であることも少なくありません。
例えば、スポーツジムの補助制度は運動習慣のない社員にとっては魅力的に映らず、社宅制度も独身で賃貸派の社員には無関係な制度となります。従業員の多様なライフスタイルや価値観に合った制度設計がされていないと、福利厚生は形骸化してしまいます。
制度の認知度不足課題
せっかく福利厚生を導入しても、その存在や利用方法が社員に十分に伝わっていなければ意味がありません。特に入社時のオリエンテーションでの説明が不十分だったり、制度の詳細が社内ポータルサイトの深い階層に埋もれていたりすることで、多くの社員が制度を知らずにスルーしてしまう状況が発生します。
制度が存在しているだけではなく、それが「どんな時に、どう使えるのか」を明確に伝える仕組みが不可欠です。
煩雑な利用手続き
福利厚生を利用する際の申請手続きが煩雑であると、社員は利用をためらってしまいます。例えば、補助金を申請するために紙の領収書や詳細な報告書を提出しなければならない場合、それだけで心理的負担が大きくなります。
さらに、上司の承認が必要な場合や、複雑な手続きフローを踏まなければならない状況では、忙しい社員ほど「使うのが面倒」と感じ、制度を敬遠するようになります。
心理的ハードル
メンタルヘルス相談や育児支援など、センシティブな内容の福利厚生制度については、周囲の目を気にして利用を避ける社員もいます。例えば、「ストレスチェックを受けたことが上司に知られ、評価に影響するのでは?」といった不安を感じるケースが少なくありません。
こうした心理的な壁は、制度の存在自体を無意味にしてしまうリスクがあります。社員が安心して利用できるような仕組みや風土づくりが求められます。
公平性の欠如
福利厚生が特定の属性の社員に偏っている場合、他の社員は制度に関心を持てなくなります。例えば、子育て支援制度は育児中の社員にはありがたい一方で、独身や子どもがいない社員には無関係な制度となりがちです。
これでは、社内に不公平感が生まれ、制度全体への関心や信頼を損ねる結果につながります。全社員が公平に恩恵を受けられる制度設計が必要です。
福利厚生の活用課題を解決するための実践的方法
1. 社員ニーズの的確な把握と最適な制度設計
福利厚生制度は「導入すること」自体が目的ではなく、「社員にとって価値ある制度」であることが重要です。まず社員のニーズをしっかり把握するために、年に1回以上のアンケート調査を行い、社員が何を望んでいるかを定期的に確認しましょう。
また、多様なライフスタイルに対応できる「カフェテリアプラン」などの選択制福利厚生を導入することで、社員一人ひとりが自分に合ったサービスを選べる環境を整えることができます。
2. 効果的な情報発信による認知度向上
福利厚生制度の認知度を高めるには、定期的かつ多様な方法で情報を発信することが鍵です。月1回の福利厚生ニュースをメールで配信したり、社内ポータルのトップページに専用バナーを設置したりするなど、社員の目に触れる機会を増やしましょう。
新入社員にはオンボーディング時に専用のガイドブックを配布し、制度の概要や活用方法を丁寧に説明することも効果的です。利用事例を紹介するなど、具体的なイメージを持ってもらう工夫も大切です。
3. 利用ハードルの引き下げ
福利厚生制度の利用を促すためには、手続きの簡素化とアクセスのしやすさが重要です。申請フローの見直しを行い、必要書類の削減や承認プロセスの簡略化を図ることから始めましょう。
デジタル化やアプリ化を進めることで、スマートフォンやPCからいつでも手軽に申請・利用できる仕組みを整えることも効果的です。オフィス内の動線上に福利厚生サービスを設置するなど、利用しやすい環境を作ることで、社員の目に触れやすく、使いやすい設計になります。
4. 心理的安全性の確保
福利厚生制度を安心して利用してもらうためには、心理的なハードルを取り除く施策も欠かせません。メンタルヘルス相談やストレスチェックなどは匿名で利用できるようにし、個人情報が他者に知られるリスクをなくすことが大切です。
経営陣や管理職が制度を率先して活用することで、制度の利用を自然なものとする社内文化を醸成できます。制度を「使っても評価に影響しない」というメッセージを明確に伝えることも、安心感につながります。
5. 公平性を重視した制度設計
公平性のある福利厚生を実現するためには、多様な社員のニーズに対応する制度設計が求められます。育児支援だけでなく、独身者向けの余暇支援や学習補助、健康促進サービスなど、年齢・家族構成・働き方に関係なく活用できる福利厚生を導入することが重要です。
制度利用状況を定期的に分析し、偏りがないかをチェックすることで、より公平な福利厚生の運用が可能になります。全ての社員が「自分にとっても有益な制度がある」と感じられる環境を目指しましょう。
健康促進を支援する福利厚生サービス「WellWa」
キリンビバレッジが提供するウェルビーイングサービス「WellWa」は、社内の健康イベント参加やミッション達成によるポイント付与など「楽しい健康」を体験できる健康支援を提供しています。
貯まったポイントはキリンが提供している健康ドリンクなどと交換可能で、さらに、管理者側は社員の健康状態やアクティビティ状況を可視化できるため、健康施策の効果測定や改善にも役立ちます。
〈詳細はこちら〉
「WellWa」は、従業員の食習慣をサポートする置き型健康飲料サービス「WellStock」を提供しています。手軽に取り入れられる健康支援として注目されており、オフィスに簡易冷蔵庫を設置し、野菜不足を補えるスムージーや、プラズマ乳酸菌入り飲料などを常備する形式が人気です。「WellStock」は初期費用0円から導入できる点も大きな特徴です。コストを抑えて始められるため、中小企業でも導入しやすく、福利厚生制度の第一歩としても最適です。導入から運用までをサポートする体制が整っており、社内に専任担当がいなくてもスムーズに利用を開始できます。
単なる社内設置にとどまらず、社内イベントとの連携や利用促進キャンペーンなど、継続的に活用される工夫を取り入れることで効果が高まります。
まとめ
福利厚生は単に「導入するだけ」で満足していては意味がありません。社員にとって「本当に使いたい」と思える制度であることが重要です。
社員の声を聞くことから始まり、制度の告知や利用のしやすさ、公平性に配慮した内容の充実など、包括的な見直しを行いましょう。
福利厚生は社員の生活の質を向上させるだけでなく、企業全体の魅力を高める重要な要素です。「使われない福利厚生」の現状を打破し、社員と企業の双方にとって価値ある制度へと進化させるチャンスです。